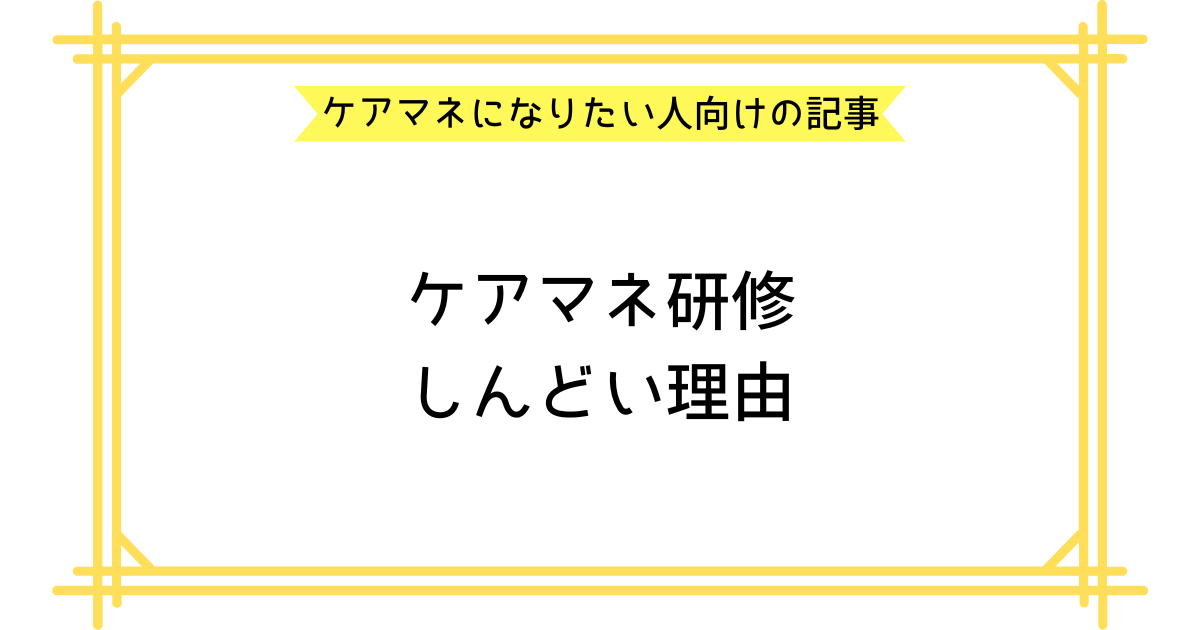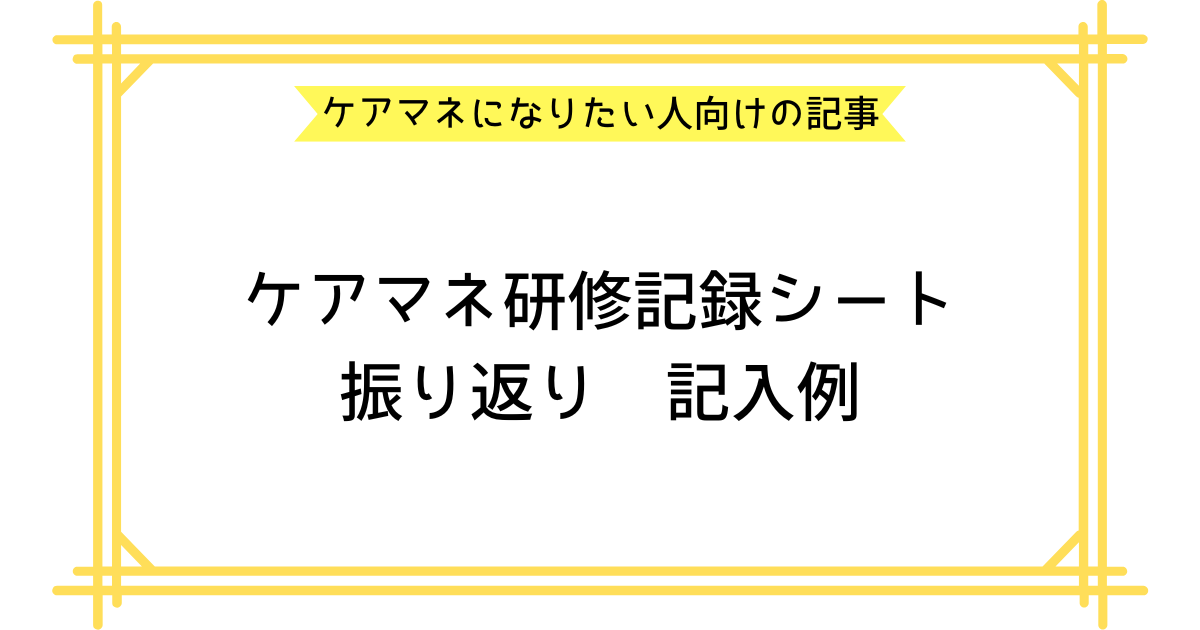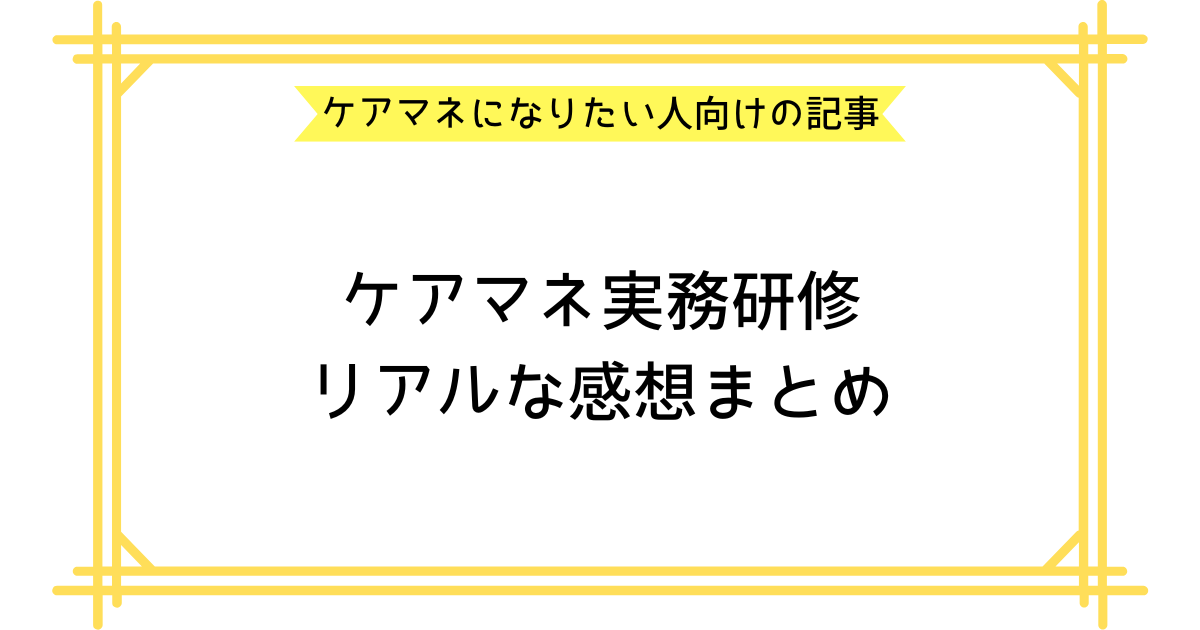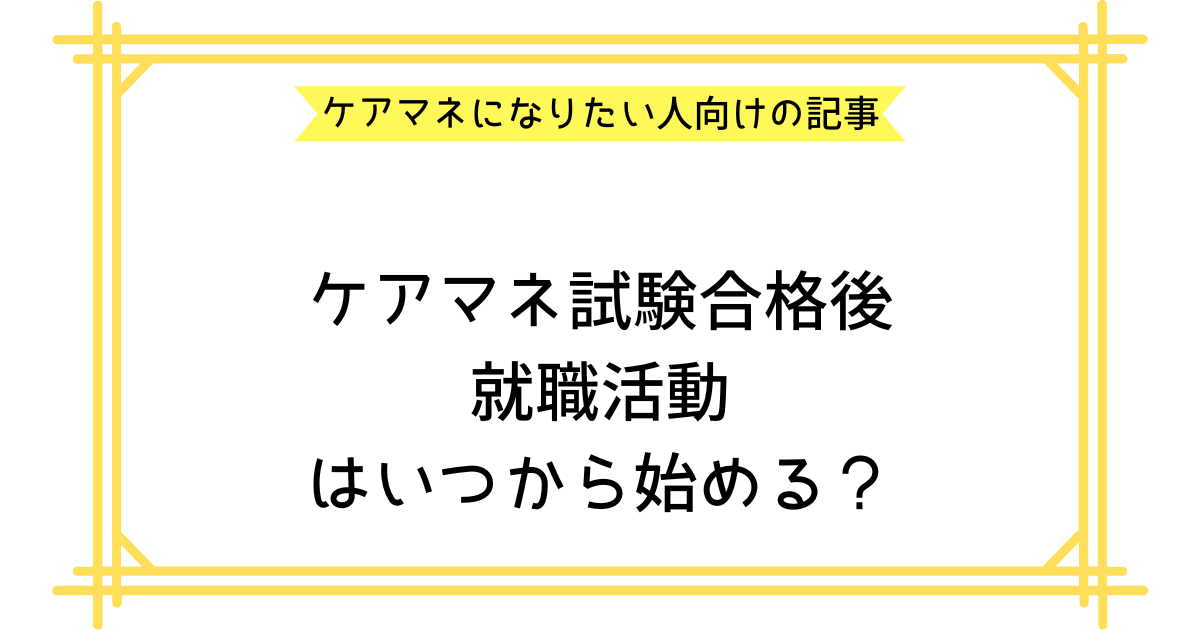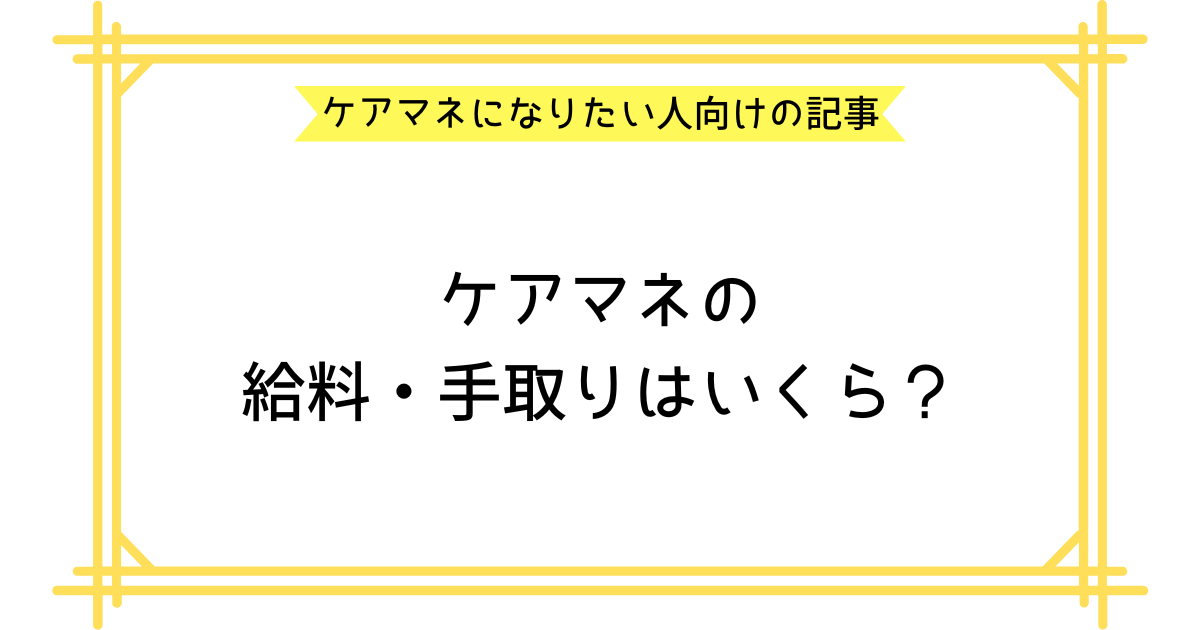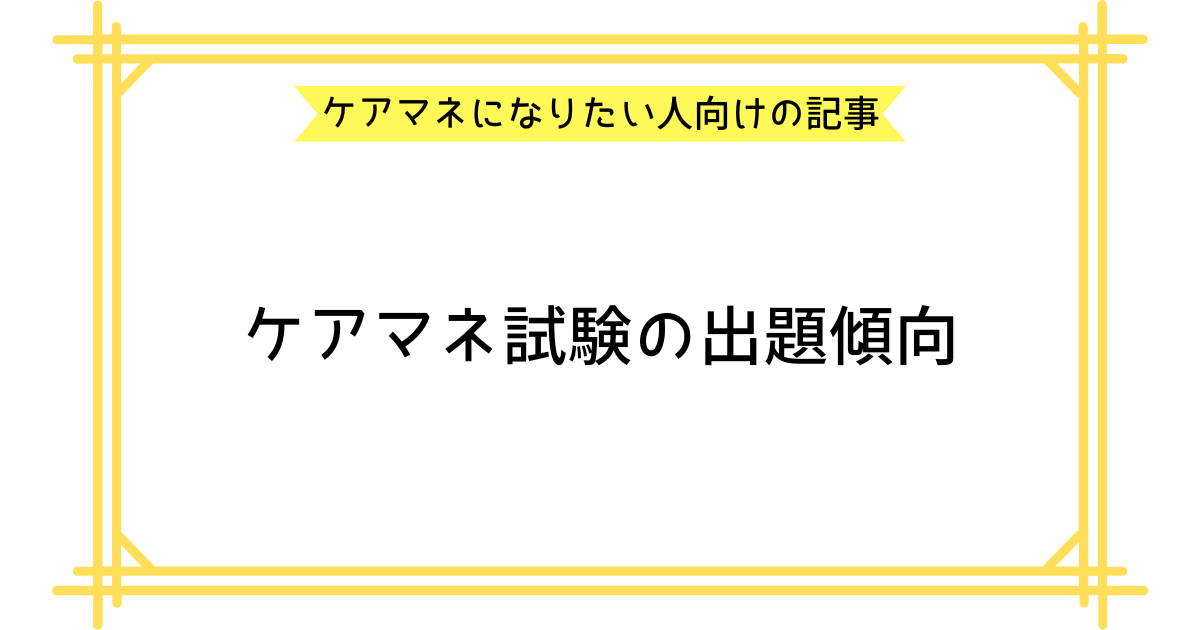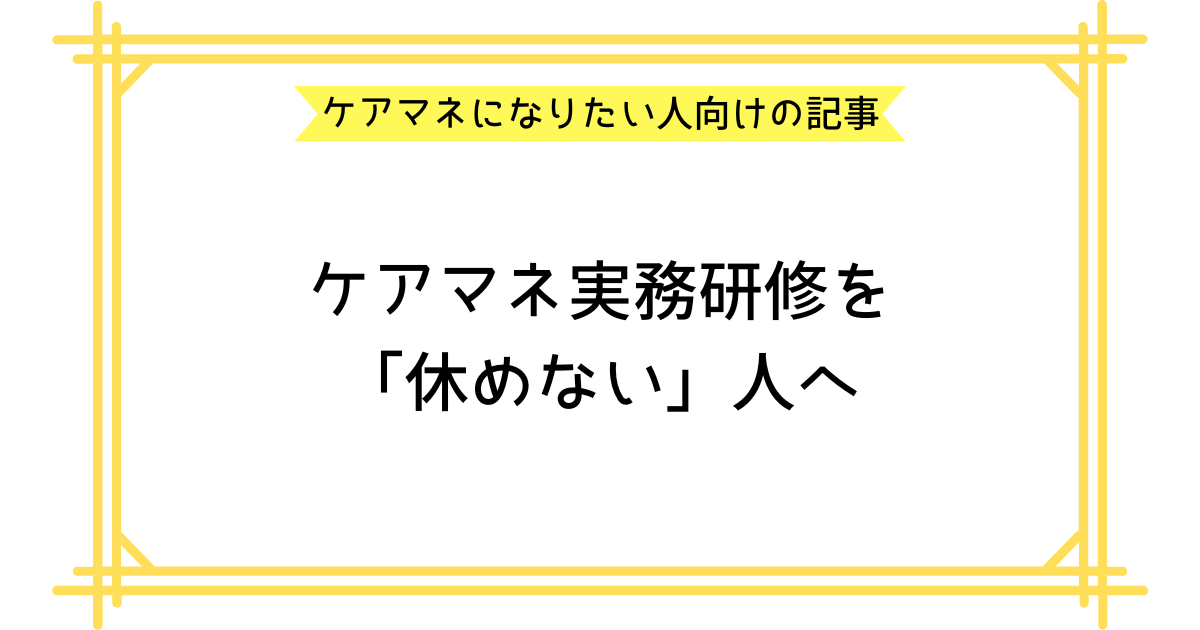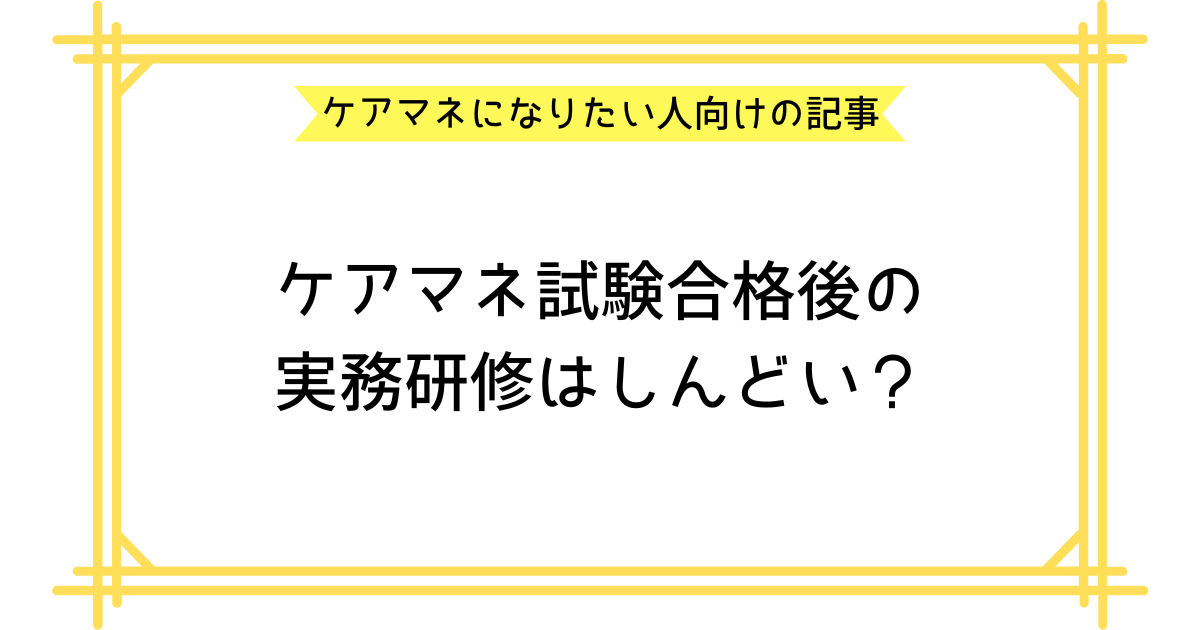【ケアマネ試験対策】スーパービジョンとは?覚えておくべきことを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
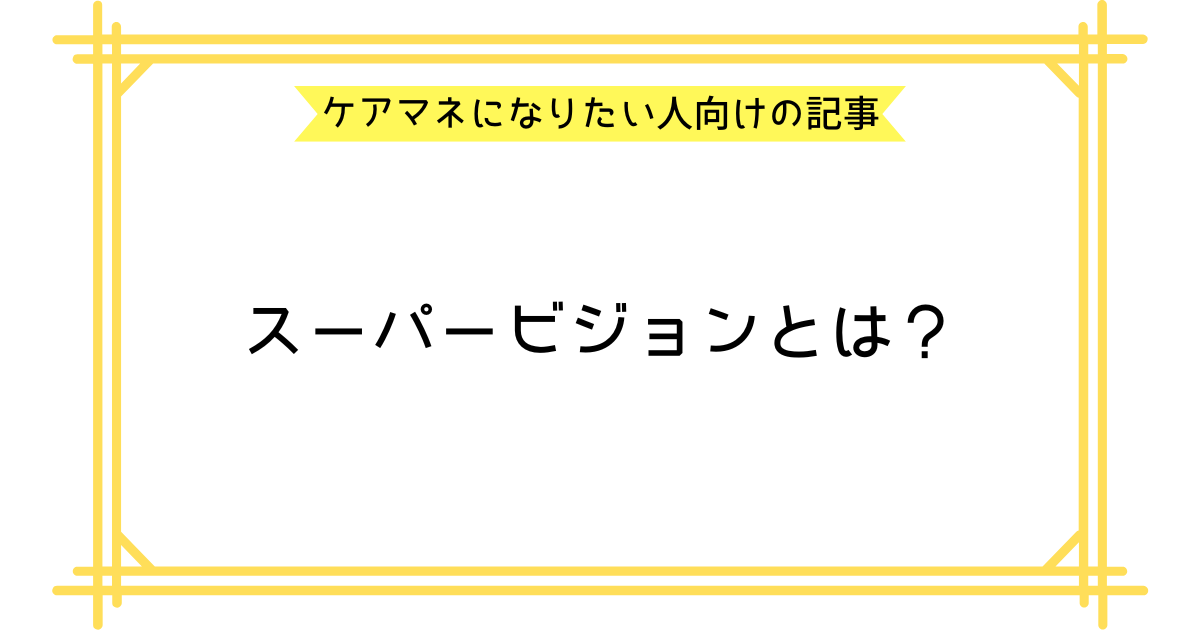
ケアマネ試験の勉強をしていると「スーパービジョン」という用語が必ず登場します。
しかし、普段の実務であまり耳にしない方も多く、「どんな意味?」「試験ではどう出題されるの?」と疑問に思うのではないでしょうか。
この記事では、スーパービジョンの基本的な定義や目的、種類、そしてケアマネ試験で覚えておくべき重要ポイントを整理して解説します。
目次
スーパービジョンとは?
スーパービジョンとは、経験の浅い専門職が、より経験豊富な専門職(スーパーバイザー)から指導・助言を受け、専門性を高めていくプロセス のことを指します。
介護や福祉の領域では、ケアマネジャーやソーシャルワーカーが成長していくために欠かせない支援の仕組みです。
スーパーバイザー(指導者)が、スーパーバイジー(指導を受ける者)に対して、事例検討や面接を通してアドバイスし、専門職としての成長を促します。
スーパービジョンの目的
スーパービジョンには大きく3つの目的があります。
- 教育的機能
専門職として必要な知識・技術を指導する役割。実務経験の浅い職員の育成に直結します。 - 支持的機能
スーパーバイジーの心理的な負担を和らげ、安心して業務に取り組めるよう支える役割。 - 管理的機能
組織やサービスの質を担保するため、業務の進め方や倫理的側面を確認・指導する役割。
この3つを総合して、スーパービジョンは「専門職育成とサービス質向上のための重要な仕組み」とされています。
スーパービジョンの種類
ケアマネ試験対策として、スーパービジョンの種類を覚えておくことが大切です。
- 個別スーパービジョン
1対1で指導を行う形式。事例検討や面接を通じて行われる。 - 集団スーパービジョン
複数のスーパーバイジーが集まり、グループで事例や課題を共有し、指導を受ける。 - 直接的スーパービジョン
スーパーバイザーが実際の面接や援助場面に立ち会い、その場で指導・助言する。 - 間接的スーパービジョン
記録や報告書、面接内容をもとにして後から助言を行う。
これらの分類は、試験で「〇〇型スーパービジョンの説明として正しいものはどれか」といった形で出題されやすいです。
ケアマネ試験で問われやすいポイント
ケアマネ試験では、スーパービジョンに関して次の点がよく出題されます。
- スーパービジョンの 3つの機能(教育的・支持的・管理的)
- スーパービジョンの 種類(個別・集団、直接・間接など)
- スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係性
- スーパービジョンの目的は「職員の育成」と「サービスの質向上」であること
特に「教育的支援だけでなく、心理的支援や組織的管理も含む」という点は重要です。
試験対策としての覚え方
- 「教える・支える・管理する」=教育・支持・管理の3機能
- 「個別・集団」「直接・間接」=場の違いと方法の違い
- 「スーパーバイザー=指導者」「スーパーバイジー=指導を受ける人」
語呂合わせや図表で整理すると記憶に残りやすいでしょう。
まとめ
スーパービジョンとは、経験豊富な専門職が指導・助言を行い、職員の成長とサービスの質向上を図る仕組みです。
ケアマネ試験では、
- 3つの機能(教育・支持・管理)
- 種類(個別・集団、直接・間接)
- スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係
といった基礎知識がよく出題されます。
「なぜ必要なのか」「どんな種類があるのか」を押さえれば、試験対策だけでなく実務にも役立ちます。