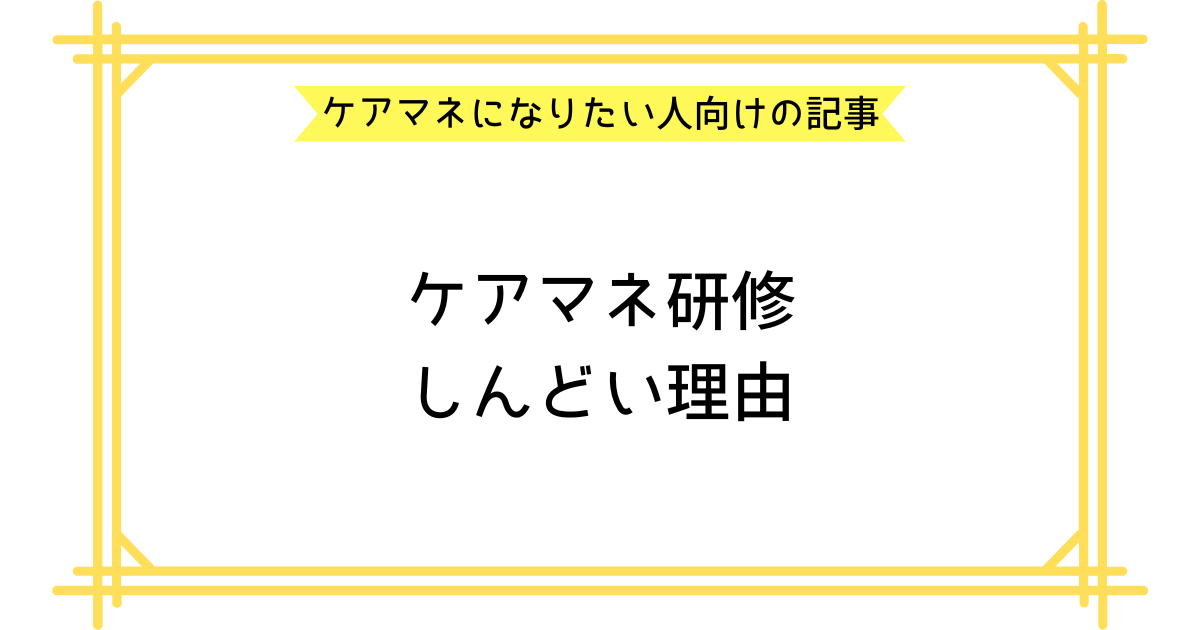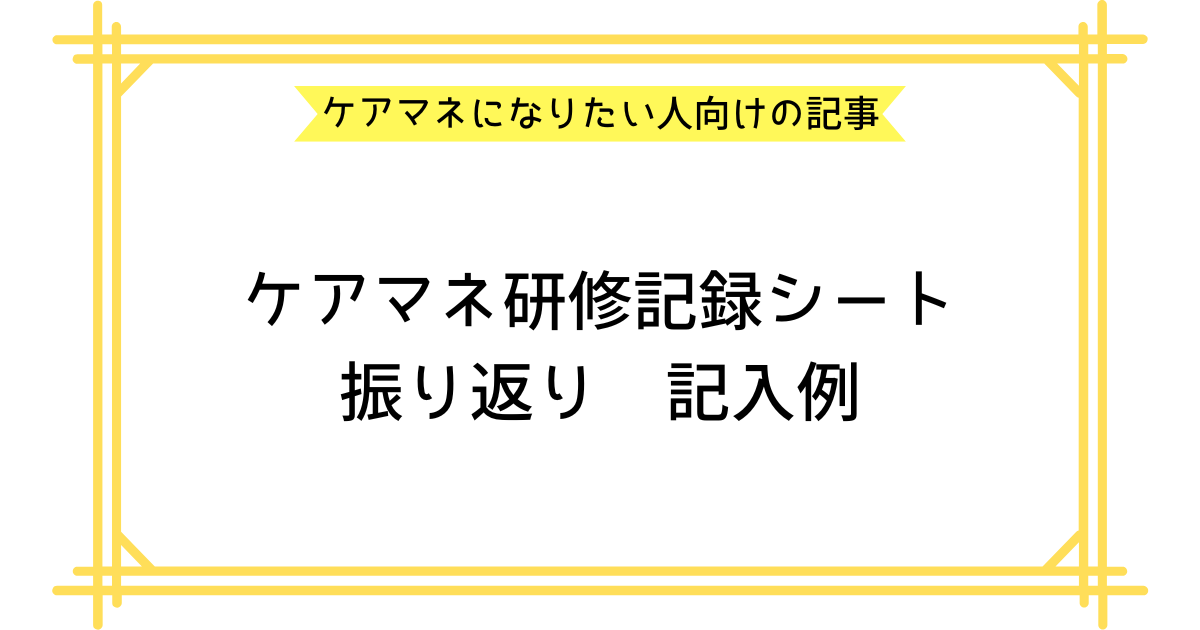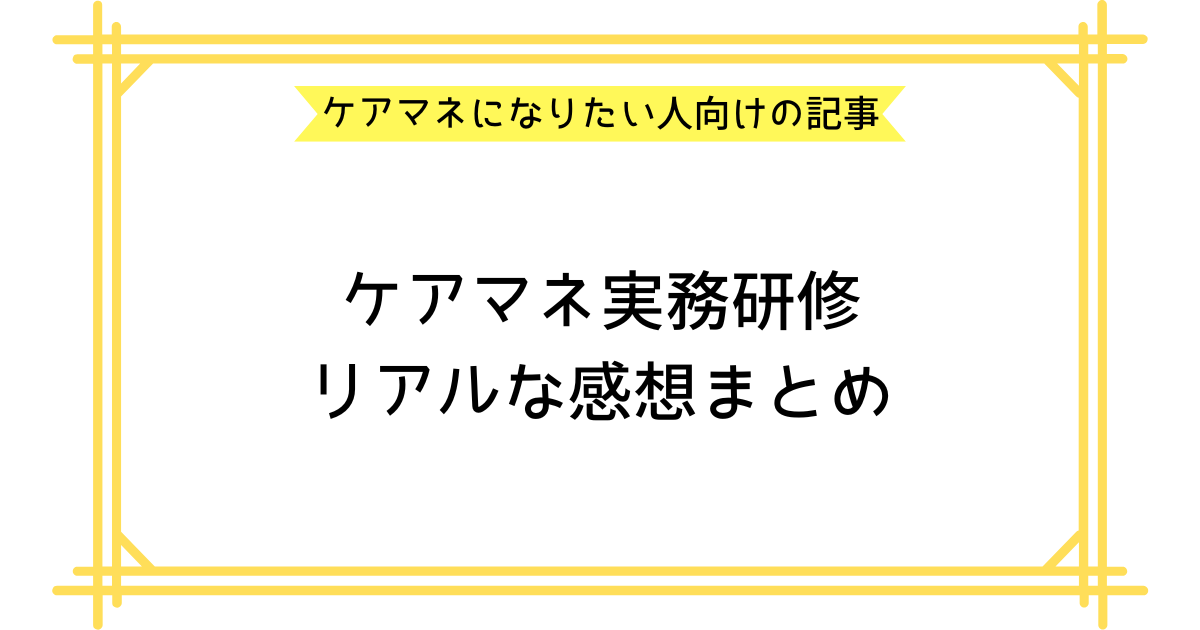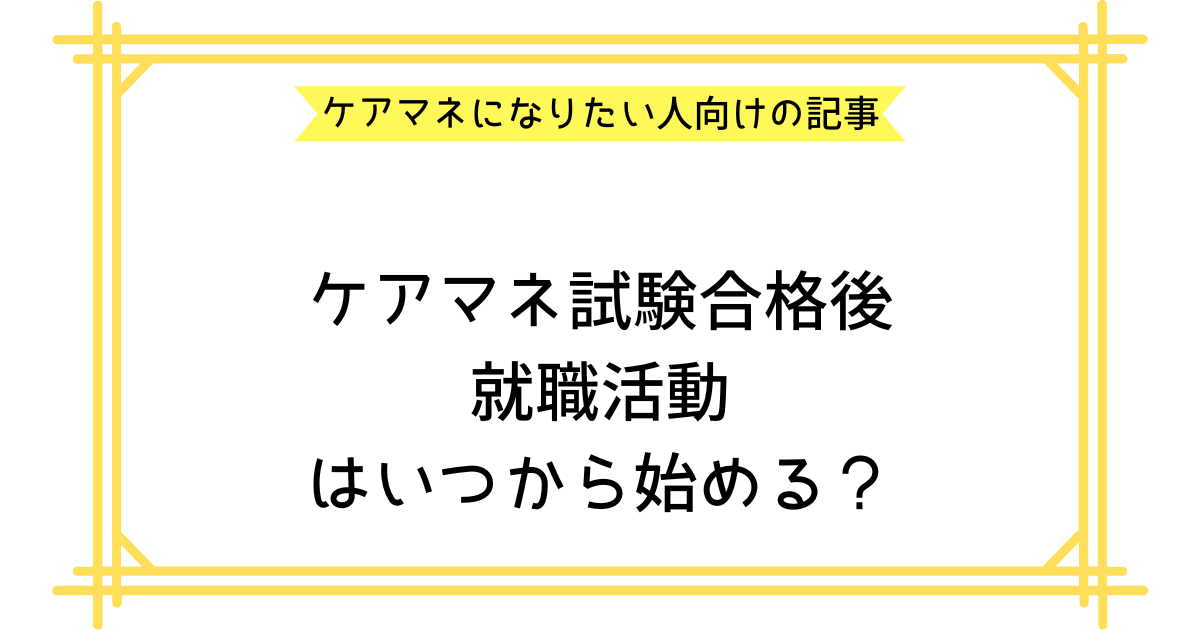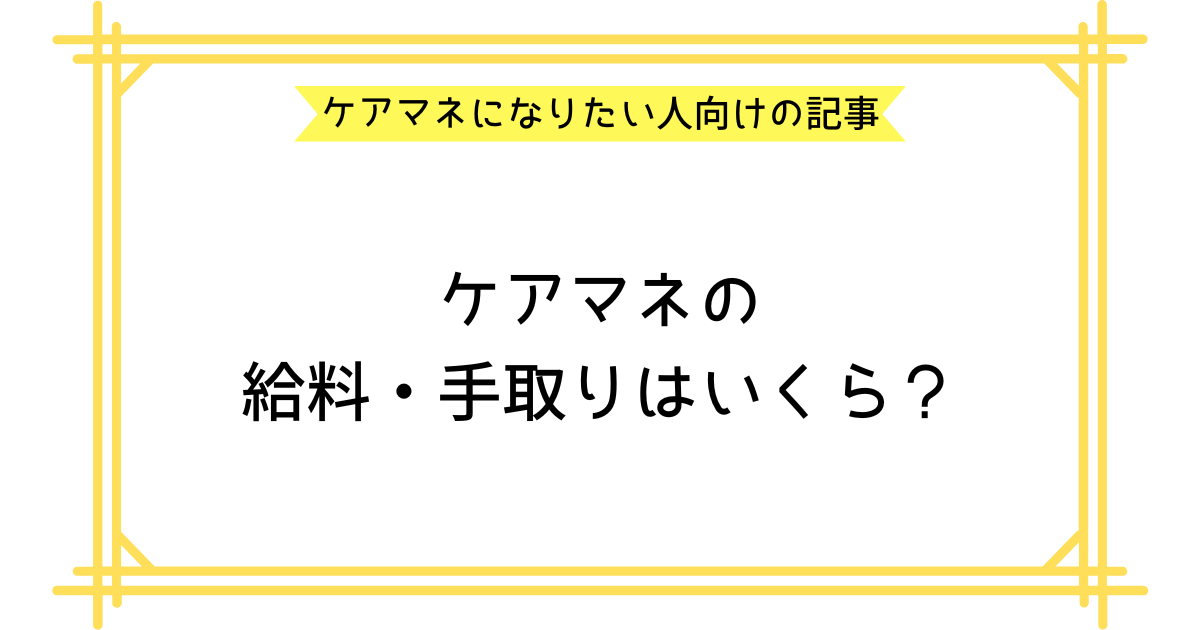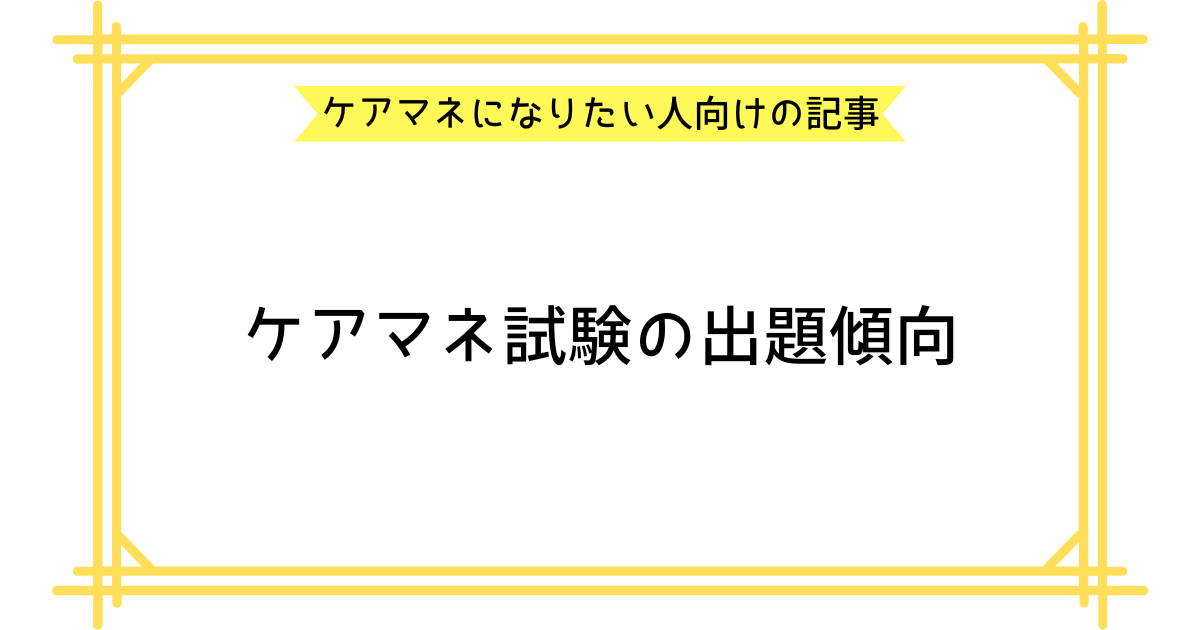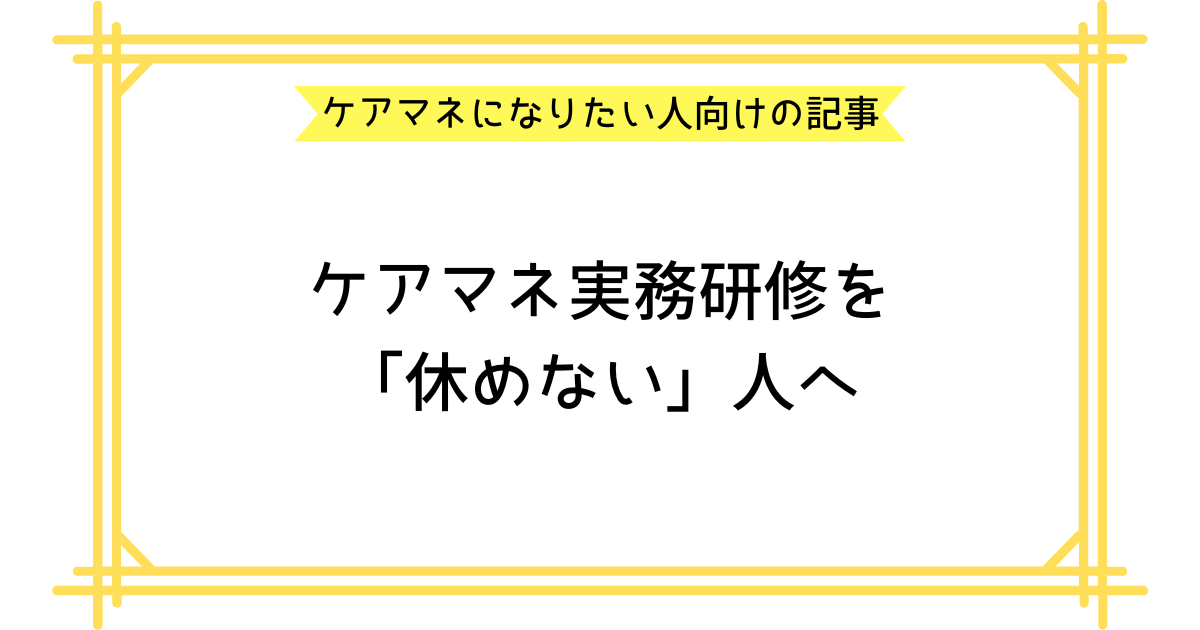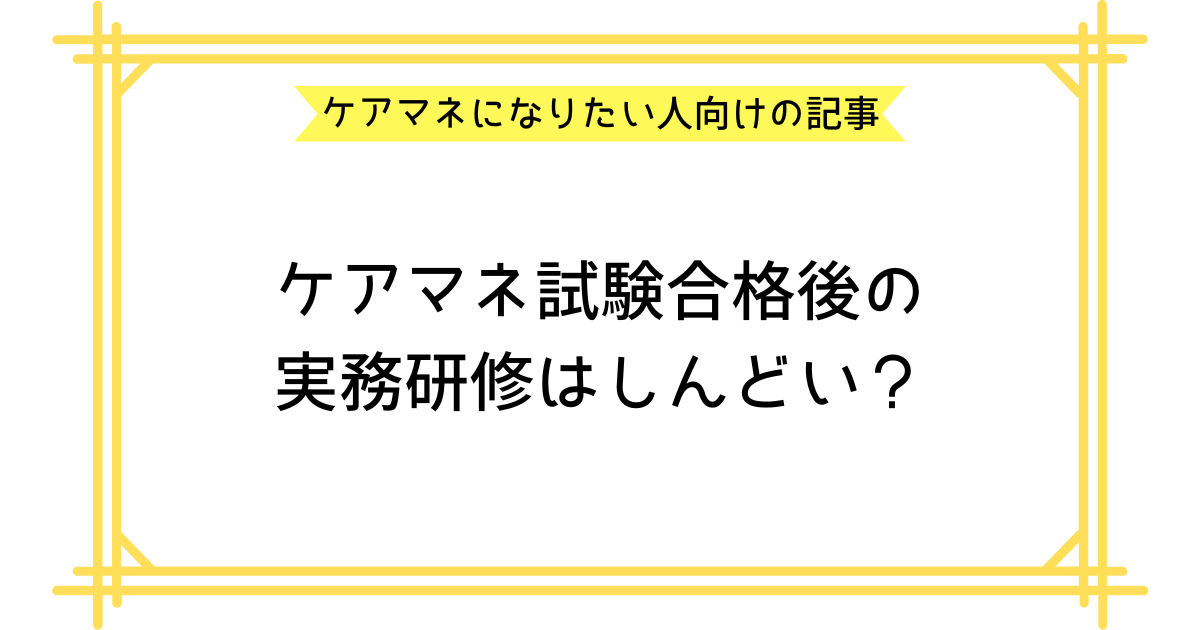ケアマネ試験対策|第1号被保険者を徹底解説!覚え方・試験の出題ポイントも紹介
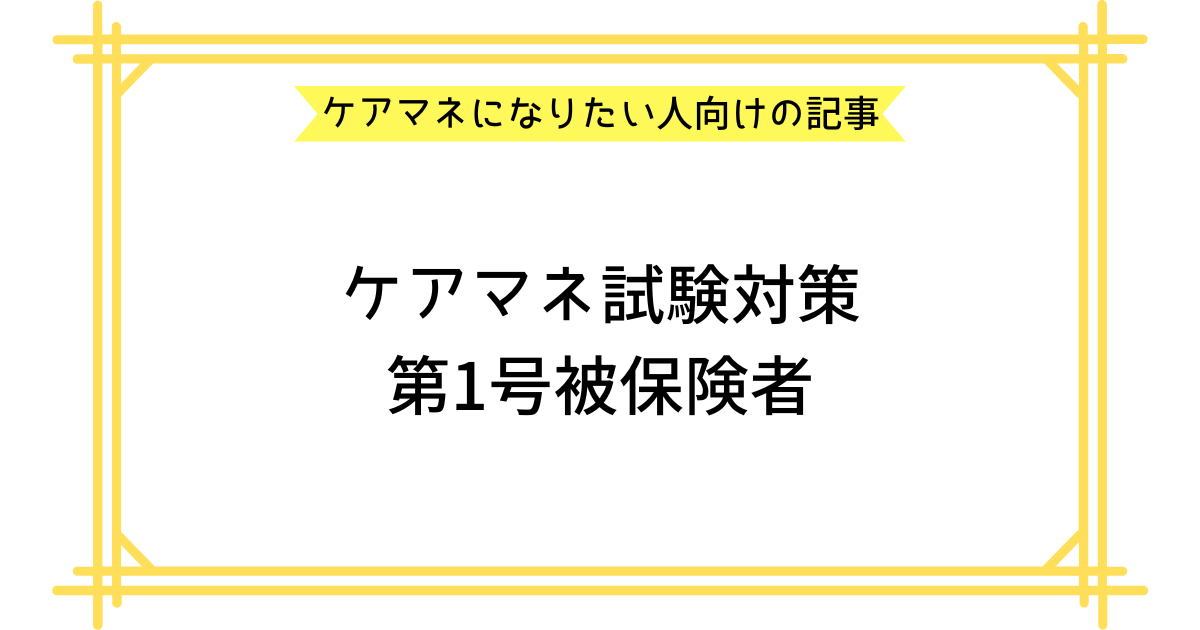
ケアマネ試験の「介護保険制度」分野で毎年出題されるのが、第1号被保険者に関する問題です。
介護保険の対象年齢や保険料の負担、サービス利用の条件などを問う問題は、数字や用語が多く混乱しやすい部分でもあります。しかし、ここを正しく理解しておくと、制度全体の構造がスッキリ整理でき、他の分野の理解にもつながります。
この記事では、第1号被保険者の定義から、第2号との違い、試験に頻出する出題傾向、暗記のコツまで、ケアマネ試験合格を目指す方のために図表を使わず言葉でわかりやすく徹底解説します。
第1号被保険者とは?基本の定義を正確に覚えよう
第1号被保険者とは、65歳以上のすべての人で、介護保険制度の対象者のうち「高齢者層」にあたるグループです。
この定義を間違えると他の問題にも影響するため、まず最初にしっかり押さえましょう。
- 対象年齢:65歳以上
- 被保険者資格:日本国内に住所を有する人(住民票のある人)
- 保険者:市町村(介護保険制度の運営主体)
つまり、日本国内に住所を持つ65歳以上の人は全員、自動的に第1号被保険者になります。国籍や職業、所得の有無は問いません。
ケアマネ試験では、「介護保険に加入するために申請が必要か?」という問題が出ることがありますが、第1号の場合は申請不要です。
住民登録に基づいて自動的に被保険者資格が付与されます。
第2号被保険者との違いを明確に整理
第1号被保険者とよく比較されるのが、第2号被保険者(40〜64歳)です。
試験ではこの「違い」を問う問題が多く出ます。
| 区分 | 年齢 | 加入方法 | 保険料の徴収方法 | サービス利用条件 |
|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 自動加入(市町村) | 市町村が直接徴収 | 要介護・要支援認定を受けたすべての人が対象 |
| 第2号被保険者 | 40~64歳 | 医療保険加入により自動的に介護保険にも加入 | 医療保険と一括徴収 | 介護保険法に定められた16種類の特定疾病により要介護・要支援状態になった場合のみ対象 |
このように、第1号と第2号では「対象年齢」「徴収方法」「サービス利用条件」が異なります。
特に、第1号被保険者は加齢による要介護状態であっても介護サービスを受けられるのに対し、第2号は特定疾病が原因の場合のみ利用できる点が重要です。
第1号被保険者の保険料の決まり方
第1号被保険者の保険料は、市町村ごとに異なります。
介護保険の保険者である市町村が、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」に基づいて保険料率を決定します。
このとき、所得に応じた所得段階別保険料が採用されているのが特徴です。
保険料は原則として12段階に区分されており、所得の高い人ほど保険料が高く設定されます。
これは「応能負担」の考え方に基づいており、制度の公平性を保つための仕組みです。
保険料の徴収方法には以下の2通りがあります。
- 特別徴収:年金からの天引き(原則)
- 普通徴収:納付書や口座振替による支払い(年金受給額が少ない場合など)
試験では「原則として年金からの特別徴収である」という点が頻出します。
保険料の使われ方と財源における割合
第1号被保険者が支払う保険料は、介護給付費(介護サービスの費用)や地域支援事業の財源として使われます。
介護保険全体の財源構成は以下の通りです。
- 保険料:全体の50%(第1号22%、第2号28%)
- 公費(税金):全体の50%(国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%)
つまり、第1号被保険者の保険料は介護保険財源全体の約22%を占めるということです。
また、地域支援事業(介護予防や包括的支援)に使われる財源のうち、保険料部分は第1号被保険者のみが負担します。
第2号被保険者の保険料は地域支援事業には使われません。
第1号被保険者が介護サービスを利用できる条件
第1号被保険者が介護サービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は、介護の必要性の度合いを判断する仕組みで、以下の7段階に区分されます。
- 要支援1・2
- 要介護1〜5
申請は市町村の窓口で行い、主治医意見書や訪問調査結果に基づいて認定が決定されます。
この認定結果によって、利用できるサービス内容や介護給付費の支給額が変わります。
試験では「65歳以上であれば誰でも介護サービスを受けられる」といった誤りの選択肢が出ることがありますが、認定を受けてはじめて利用できる点を忘れないようにしましょう。
要介護・要支援認定の流れ(第1号被保険者)
第1号被保険者が介護サービスを利用するまでの基本的な流れは以下のとおりです。
- 市町村の介護保険窓口で申請
- 調査員による訪問調査
- 主治医による意見書の作成
- コンピュータによる一次判定
- 介護認定審査会による二次判定
- 要支援・要介護認定の決定
- ケアマネジャーによるケアプラン作成
試験では「要介護認定を行うのはどこか?」「一次判定と二次判定の違い」など、手続きの流れそのものを問う問題が多く見られます。第1号被保険者に限らず、この流れを丸ごと理解しておくことが重要です。
ケアマネ試験で狙われやすい「第1号被保険者」問題パターン
ケアマネ試験では、「第1号被保険者」に関して次のような出題パターンがあります。
- 定義・年齢・資格
→ 65歳以上で、日本に住所を有する人。申請不要で自動的に資格取得。 - 第2号との比較問題
→ 特定疾病の有無、徴収方法、保険料の使途などの違いを選ぶ。 - 保険料の徴収方法
→ 原則は年金からの特別徴収である。 - 財源における割合
→ 全体の約22%を負担している。 - 地域支援事業との関係
→ 地域支援事業に使われる保険料は第1号のみ。 - 介護認定の流れ
→ 申請は市町村、認定は介護認定審査会。
過去問を見ると、ほぼ毎年どこかで「第1号被保険者」関連の設問が出題されています。
試験で差がつくポイント①:住所要件と資格の自動付与
第1号被保険者になる条件のうち、見落としがちなのが「住所要件」です。
介護保険法では、「日本国内に住所を有する65歳以上の者」と明記されています。
したがって、海外在住の日本人は原則として対象外です。
また、第1号被保険者の資格は申請不要で自動付与される点も重要です。
一方、第2号被保険者は医療保険への加入を通じて介護保険にも自動加入します。
この違いを混同しやすいため、整理して覚えましょう。
試験で差がつくポイント②:特別徴収と普通徴収の違い
保険料の徴収方法に関する出題も頻出です。
第1号被保険者の保険料は原則として特別徴収(年金からの天引き)ですが、以下の場合は普通徴収となります。
- 年金受給額が年18万円未満の場合
- 新たに65歳になり、まだ年金からの徴収に切り替わっていない期間
- 介護保険料の滞納や未納がある場合
この区分を覚えておくと、「どちらの徴収方法が適用されるか」を問う問題に対応できます。
試験で差がつくポイント③:滞納者に対する給付制限
第1号被保険者が介護保険料を滞納した場合、以下のような給付制限を受けることがあります。
- 一時的に介護保険サービスの利用を制限される
- 受けたサービス費用を全額自己負担とされる場合がある
- 高額介護サービス費などの支給が一時的に停止される
この「滞納による給付制限」は、制度の実務面を理解していないと見落としがちな部分ですが、試験では「保険料を滞納しても介護サービスを受けられる」といった誤答を混ぜてくることがあります。
正しくは、「滞納期間や理由により給付制限を受ける場合がある」です。
第1号被保険者と介護予防支援(地域支援事業)の関係
第1号被保険者は、要介護認定を受けていなくても、地域支援事業による介護予防支援を受けられる場合があります。
たとえば、要支援状態やそのリスクがある高齢者に対し、地域包括支援センターが中心となって介護予防ケアマネジメントを行います。
この仕組みは「介護予防・日常生活支援総合事業」と呼ばれ、65歳以上のすべての高齢者が対象です。
つまり、第1号被保険者は介護が必要になってからの支援(要介護認定後)だけでなく、予防段階でも支援を受けられるという点が重要です。
暗記のコツ:「第1=高齢者・自動加入・予防も対象」
第1号被保険者の特徴を短い語呂で覚えると、試験中でも思い出しやすくなります。
- 「いちばん上の65歳(第1号)」
- 「自動加入・自動認定じゃない(認定は別)」
- 「予防も対象」
数字だけでなく、「誰が・どこで・どのように」関わるかをストーリーで覚えるのが合格のコツです。
まとめ:第1号被保険者はケアマネ試験の得点源!
第1号被保険者に関する出題は、数字さえ覚えれば正答できるものが多く、ケアマネ試験の中でも最も安定して得点できる分野です。
最後に、要点をまとめましょう。
- 対象:65歳以上、日本国内に住所を有する人(自動加入)
- 保険料:市町村が徴収、原則年金からの特別徴収
- 保険料の割合:介護保険財源全体の22%
- サービス利用:要介護認定を受けたすべての人が対象
- 地域支援事業:第1号のみが保険料を負担
- 滞納時:給付制限あり
- 覚え方:「第1=高齢者・自動加入・予防も対象」
これらを確実に押さえておけば、介護保険制度全体の構造が理解しやすくなり、他の関連分野(第2号被保険者、財務構造、地域支援事業など)にもつながります。
試験本番では、「数字」よりも「構造」を意識して学ぶことが合格への近道です。