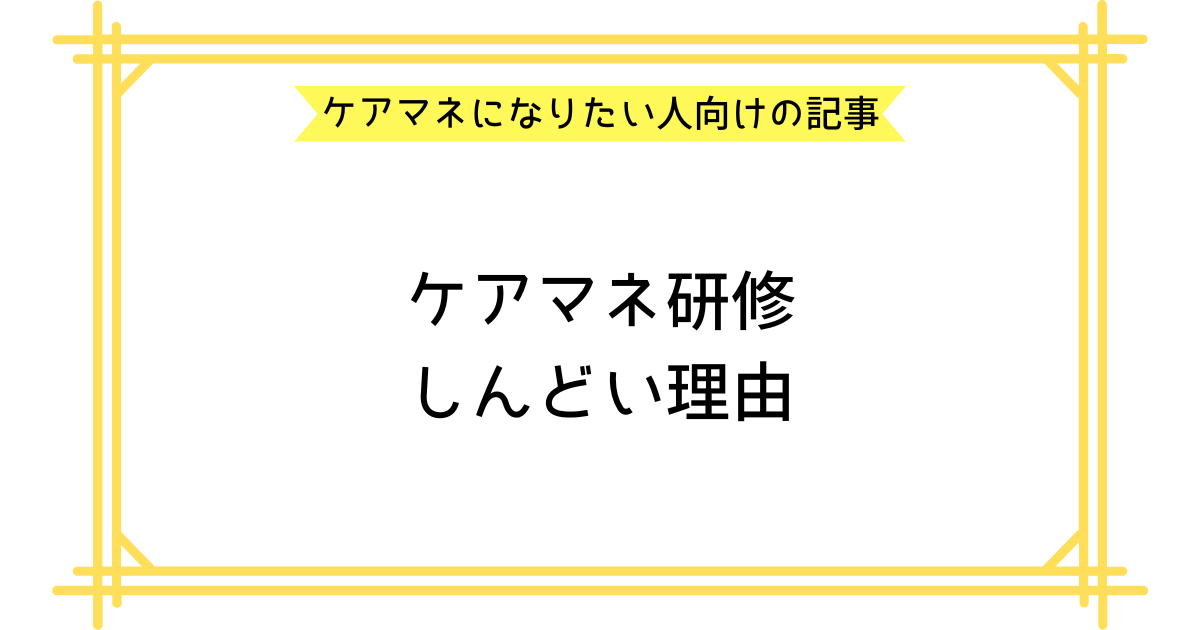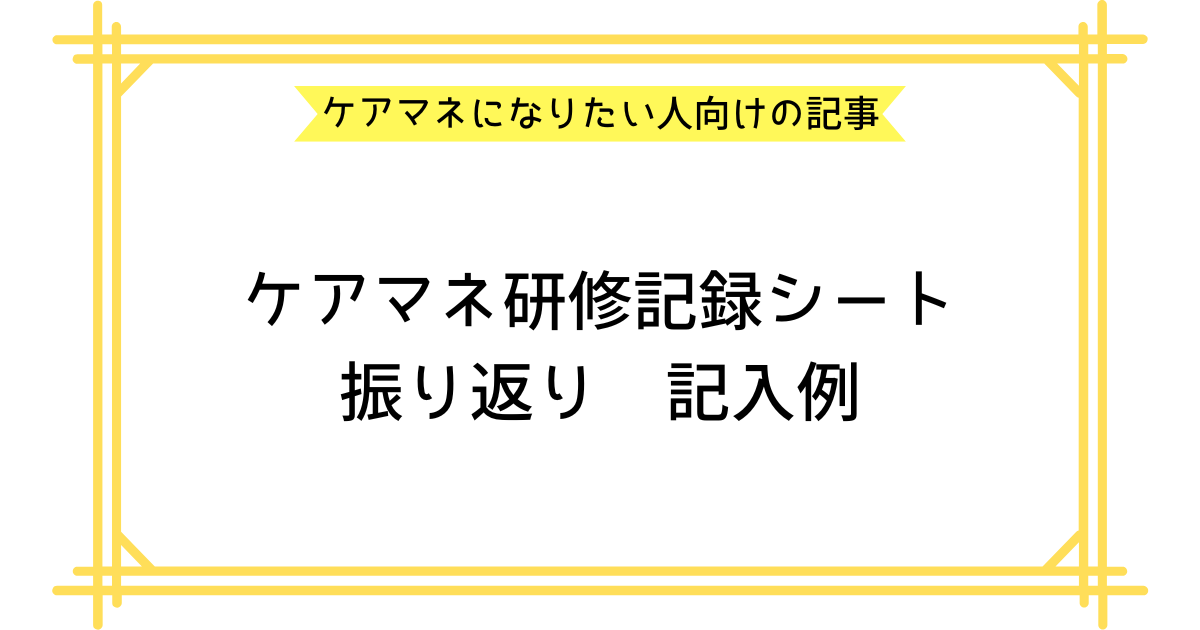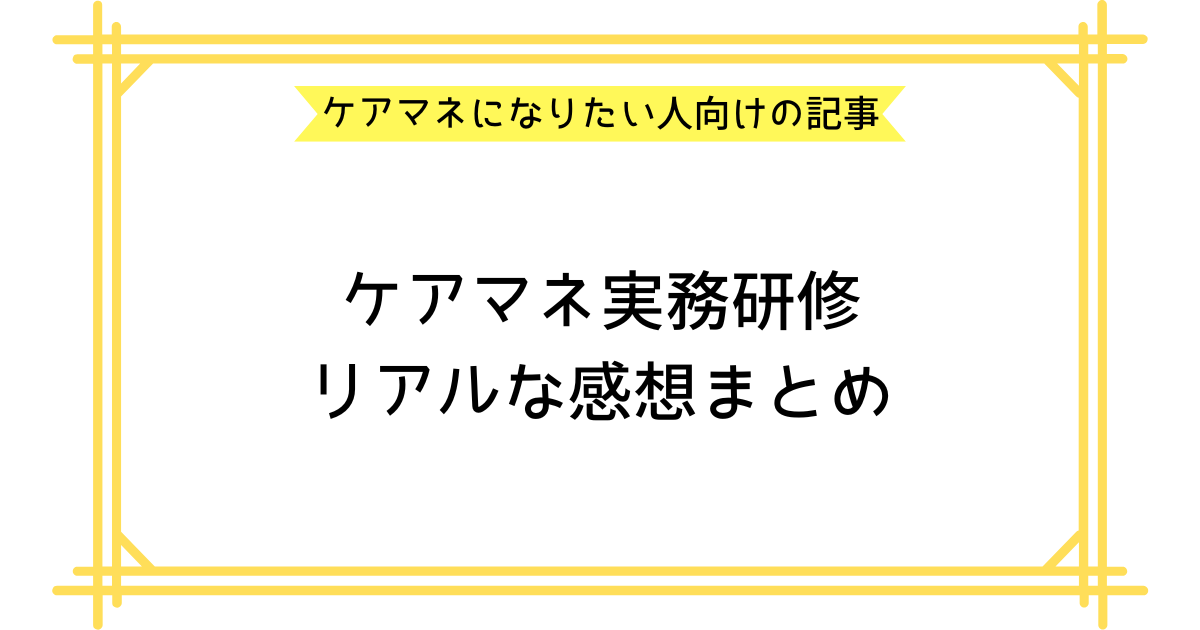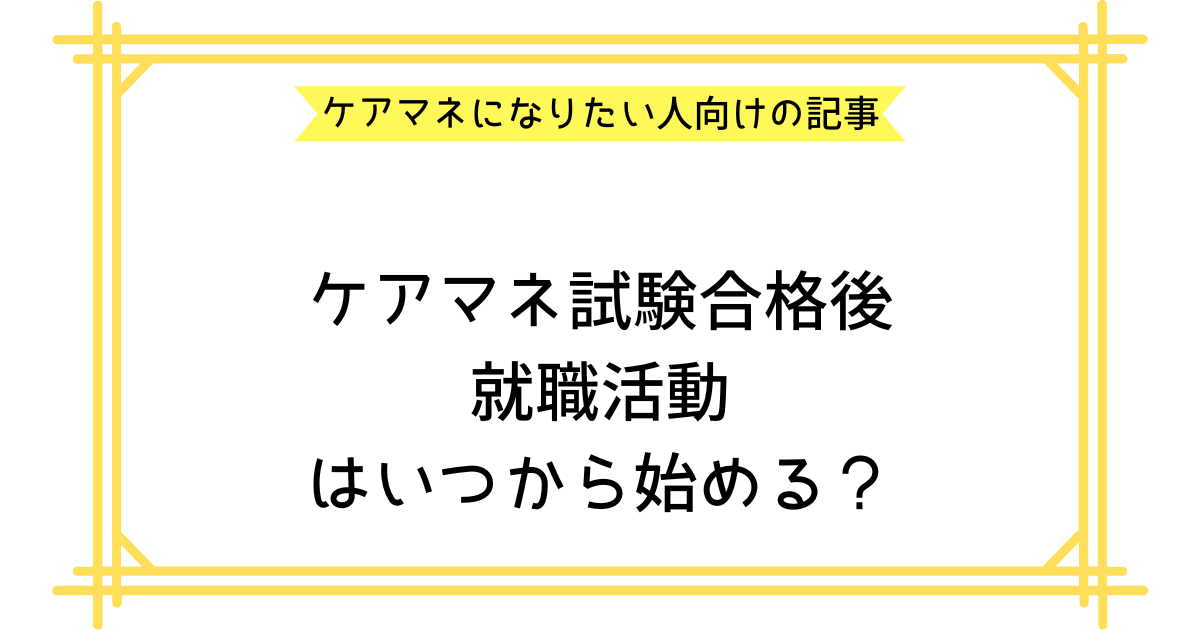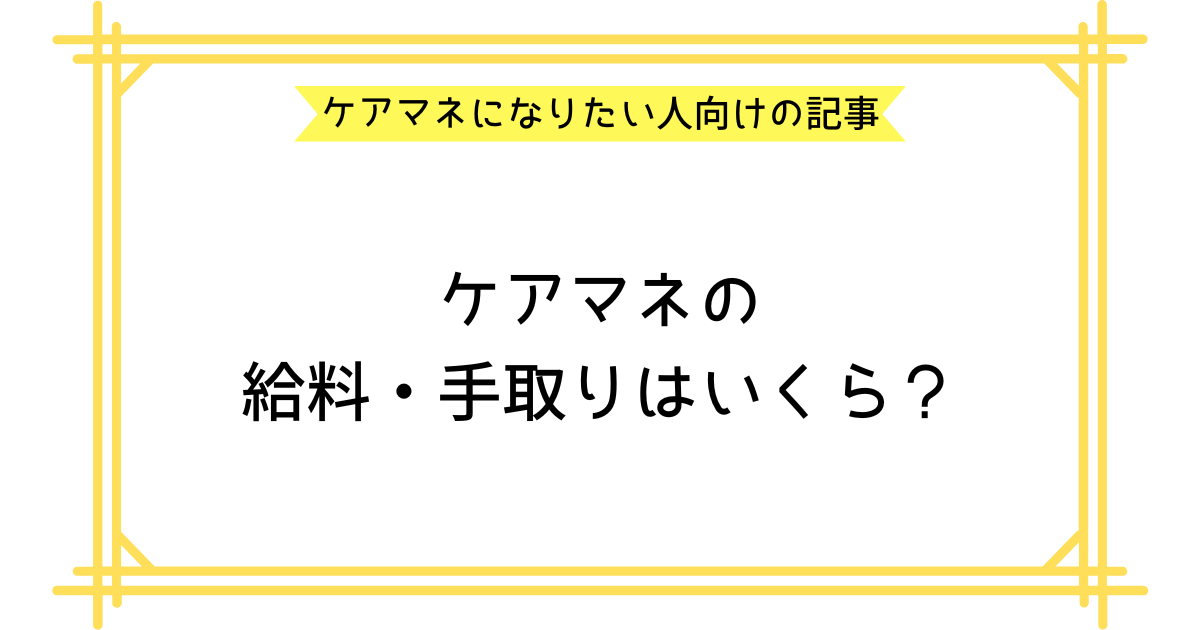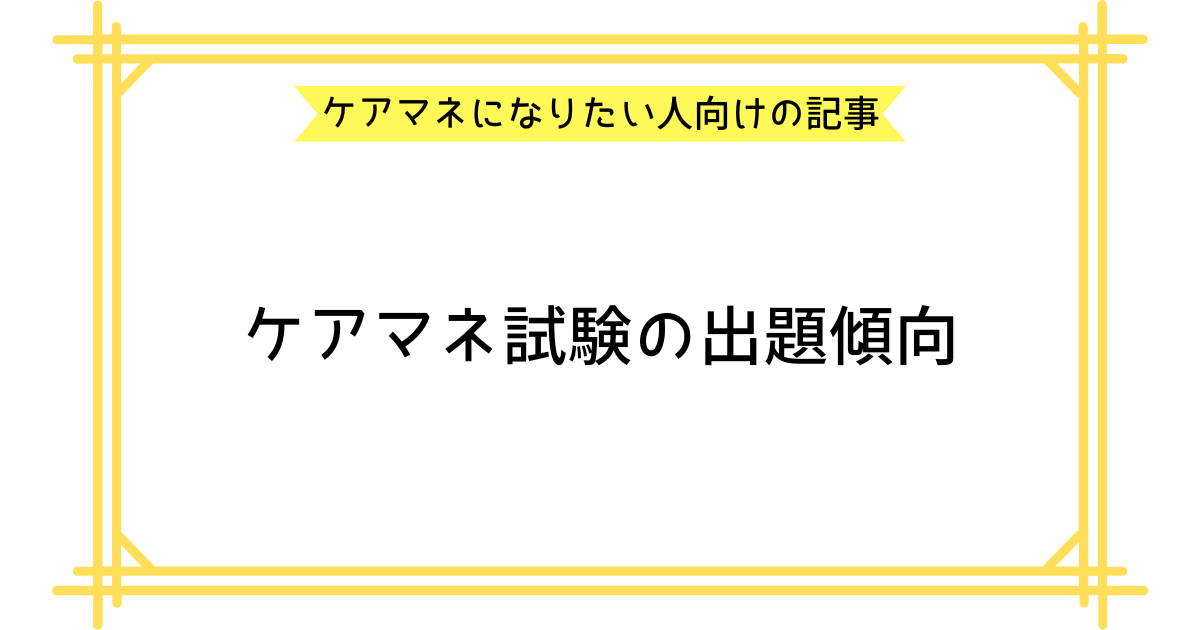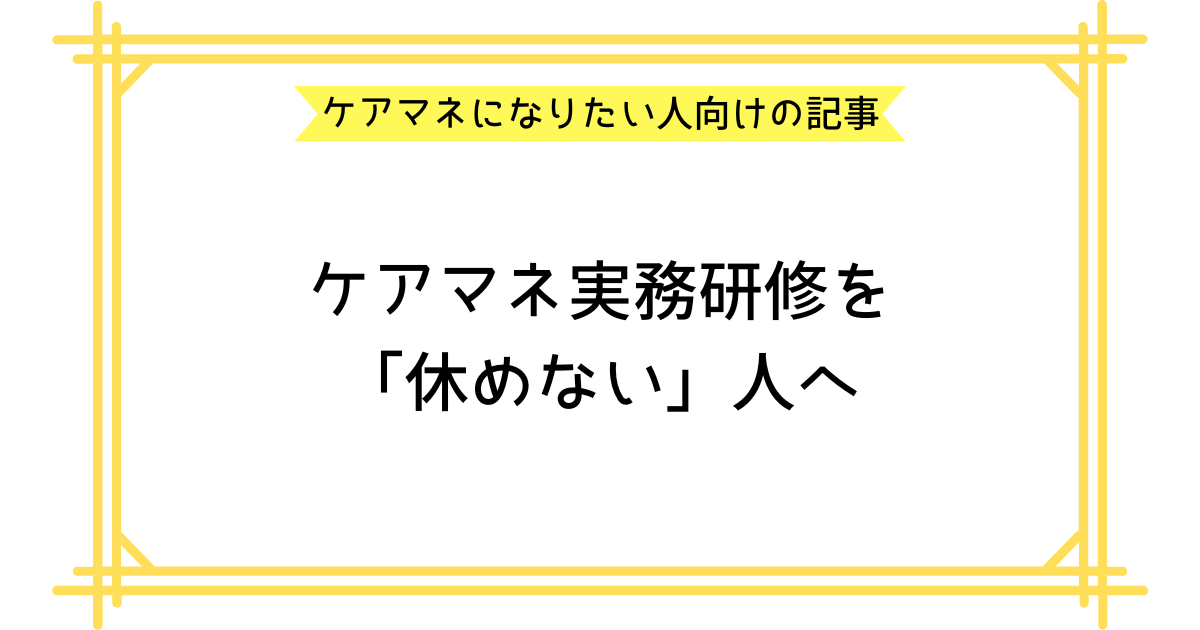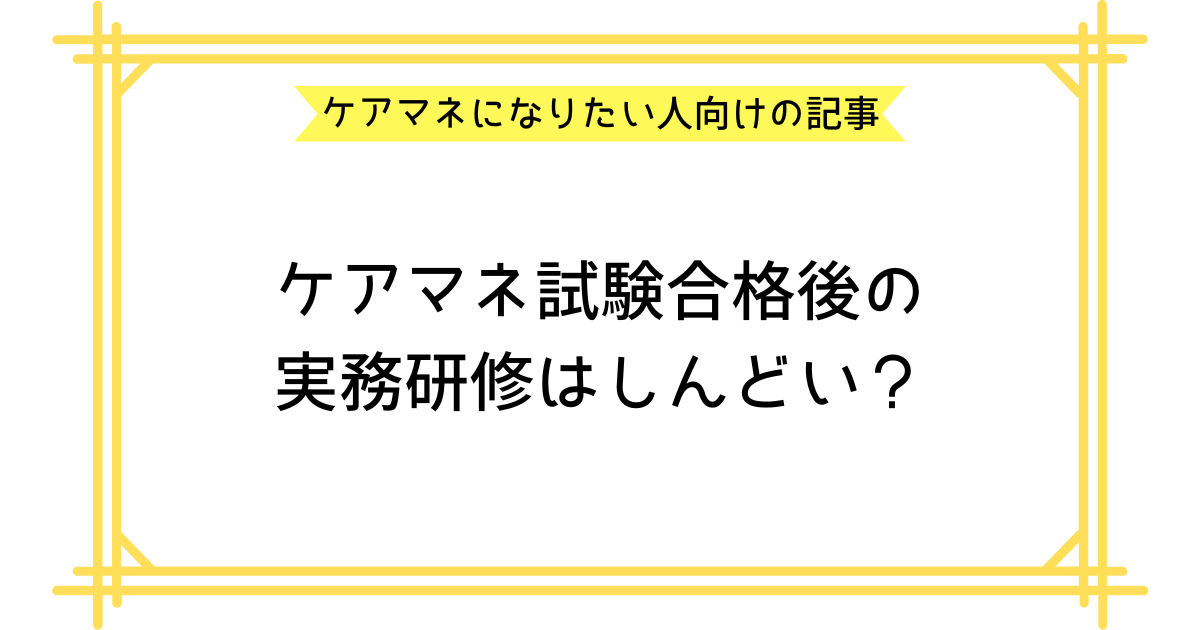ケアマネ試験を諦めそうなあなたへ|諦める前に知ってほしい現実と突破のコツ
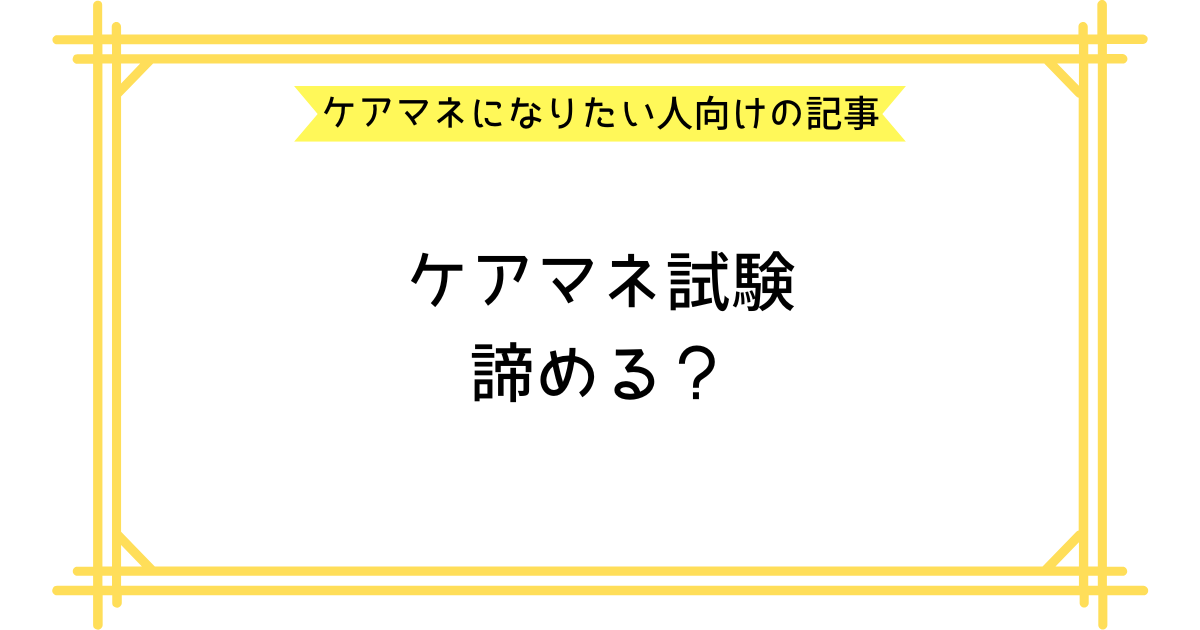
「ケアマネ試験、もう無理かもしれない…」「勉強しても全然頭に入らない」「今年も落ちたらもう諦めようかな」
そう感じている人は決して少なくありません。実際、ケアマネ試験は合格率が約20%前後と難関で、途中で心が折れそうになる受験者が多いのが現実です。
しかし、ここで諦めてしまうのはもったいないこと。この記事では、ケアマネ試験を「諦めたくなる理由」から、「再挑戦するための考え方」「効率的な勉強法」まで、経験者の実例を交えながら解説します。
この記事を読み終えるころには、「まだできることがある」と前向きに感じられるはずです。
ケアマネ試験を諦めたくなる理由
合格率の低さに心が折れる
ケアマネ試験の合格率は例年20%前後で推移しています。つまり、5人に1人しか合格できない厳しい試験です。
受験者の多くは仕事や家事の合間に勉強しており、「頑張っても受からないかもしれない」という不安が常につきまといます。特に2回・3回と不合格が続くと、自信を失って「もう自分には無理だ」と感じる人が増えてしまうのです。
勉強時間が確保できない
ケアマネ試験は範囲が広く、介護支援分野・保健医療サービス・福祉サービスと3科目をバランスよく学ぶ必要があります。
仕事で残業が多い人や、家族の介護・育児をしている人にとって、毎日勉強時間を確保するのは至難の業です。「勉強したいのにできない」ことがストレスになり、諦める引き金になるケースも多くあります。
勉強しても成果が見えない
参考書を読み込んでも模試で点が取れない、過去問を解いても理解が追いつかない…。
努力しても結果が出ないと、「自分は向いていないのかも」と感じてしまいます。特に勉強を始めたばかりの時期は、知識が定着しにくいため、焦りと不安が強まる時期でもあります。
ケアマネ試験を諦めないための考え方
合格は「才能」ではなく「継続力」で決まる
ケアマネ試験は記憶力や理解力よりも、「継続力」が結果を左右します。1日30分でも勉強を続けた人と、途中で諦めた人の差は大きく、1年後には確実に結果に表れます。
「毎日コツコツやる人が最終的に勝つ」──これがケアマネ試験の本質です。
落ちることは「失敗」ではなく「準備期間」
1回で受かる人もいれば、3年目でようやく合格する人もいます。
不合格という結果は「ダメだった証拠」ではなく、「次に合格するためのデータ収集期間」だと捉えるべきです。
何が苦手だったのか、どの分野で点数が取れなかったのかを分析すれば、次回に確実に活かせます。
合格者の多くは「諦めかけた経験者」
合格者へのアンケートでは、「途中で諦めようと思ったことがある」と答えた人が7割以上にのぼります。
つまり、「諦めたい」と思うのは当たり前であり、むしろそれを乗り越えた人こそが最終的に合格しているのです。
実際に諦めずに合格した人の特徴
特徴①:小さな成功体験を積み重ねていた
いきなり「全範囲を完璧に」と思うと挫折します。
合格した人の多くは、1日1単元、1問ずつでも理解を深める「小さな成功体験」を積んでいました。
「今日はここまで進めた」と記録することで、自己肯定感を維持していたのです。
特徴②:勉強法を見直しながら柔軟に対応
同じ方法で結果が出ないなら、やり方を変える勇気も大切です。
例えば、テキスト中心から「過去問アプリ+動画講義」に切り替えたり、ノートまとめをやめて音声学習に変えたりするだけでも、効率は大きく変わります。
特徴③:孤独に戦わなかった
勉強仲間やSNSの学習アカウントを活用し、他の受験者と情報交換していた人が多いです。
「自分だけじゃない」と感じることでモチベーションが維持でき、継続の原動力になります。最近ではLINEオープンチャットやX(旧Twitter)でケアマネ受験グループを作る人も増えています。
諦めそうな時に試してほしいこと
1. 「なぜケアマネになりたいのか」を書き出す
原点を思い出すことで、再びやる気が戻ることがあります。
「利用者の人生を支えたい」「在宅介護の知識を仕事に活かしたい」など、動機を紙に書き出してみましょう。目に見える形にすることで、初心を再確認できます。
2. 1日10分だけ勉強する
やる気が出ないときほど、「ハードルを下げる」ことが大切です。
「10分だけ」と決めて始めると、意外と集中でき、そのまま1時間勉強していたというケースもあります。まずは机に向かうことが最初の一歩です。
3. 勉強する環境を変える
いつもと同じ場所では集中できなくなることも。図書館、カフェ、車の中など、勉強場所を変えるだけでリフレッシュできます。
また、周囲の雑音を遮断するノイズキャンセリングイヤホンも効果的です。
勉強を続けるための具体的な工夫
スケジュールを「見える化」する
目標までの道のりが見えないと、モチベーションは下がります。
カレンダーアプリや手帳で「今日は過去問10問」「明日は動画視聴30分」など、細かくスケジュール化することで、達成感を得やすくなります。
苦手分野を「後回し」にしない
苦手分野を避けると、いつまでも不安が残ります。
特に「保健医療サービス分野」や「福祉サービス分野」は出題範囲が広いため、早めに取りかかるのがコツです。得意分野でモチベーションを上げ、苦手分野に挑戦するリズムを作りましょう。
模試を活用して「実力を可視化」
本番形式の模試を受けることで、自分の弱点が明確になります。
点数が低くても落ち込む必要はありません。むしろ「あと何点で合格ラインか」を数値で把握できることが重要です。
それでも迷ったら、一度「休む勇気」も大切
「もう無理」と感じたときは、思い切って1週間勉強を休むのも効果的です。
無理に詰め込んでも頭に入りません。短期間リセットすることで、冷静に「今の自分に必要なこと」を見つめ直せます。
勉強を止めることは「諦める」ことではありません。むしろ、再スタートの準備期間なのです。
ケアマネ試験を諦めなかった人の声(体験談)
・「2回落ちて心が折れかけたけど、3年目にやっと合格。過去問を繰り返す勉強法に変えてから一気に点が伸びた。」
・「夜勤明けでも毎日1時間勉強。周りから“無理だよ”と言われても、自分を信じてよかった。」
・「子育てと両立で大変だったけど、家族に支えられて合格できた。今は居宅でケアマネとして働いています。」
このように、ほとんどの合格者が「諦めそうになった経験」を持っています。
彼らに共通するのは、「完全に辞めなかった」こと。それが合格への一番の近道です。
まとめ|諦める前に、あと一歩だけ進んでみよう
ケアマネ試験は確かに難しいですが、「難しい=不可能」ではありません。
合格する人は、最初から完璧な人ではなく、何度も失敗しながらも「もう一度やってみよう」と立ち上がった人たちです。
もし今、「もう諦めようかな」と感じているなら、今日だけはテキストを開いてみてください。
その小さな一歩が、来年の合格通知につながるはずです。