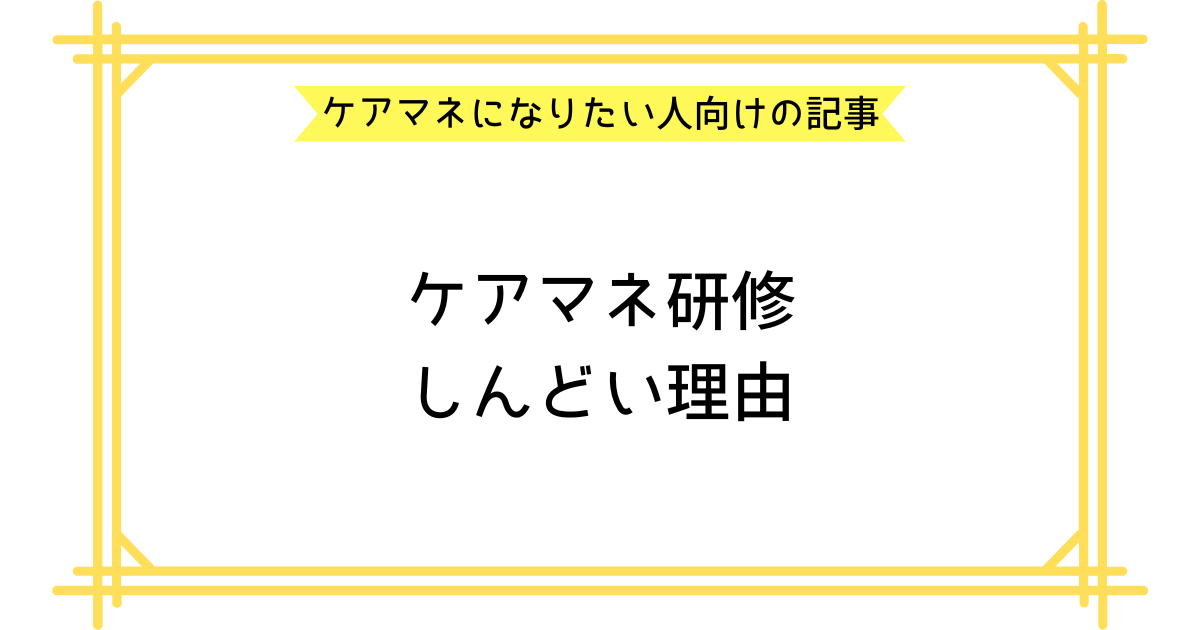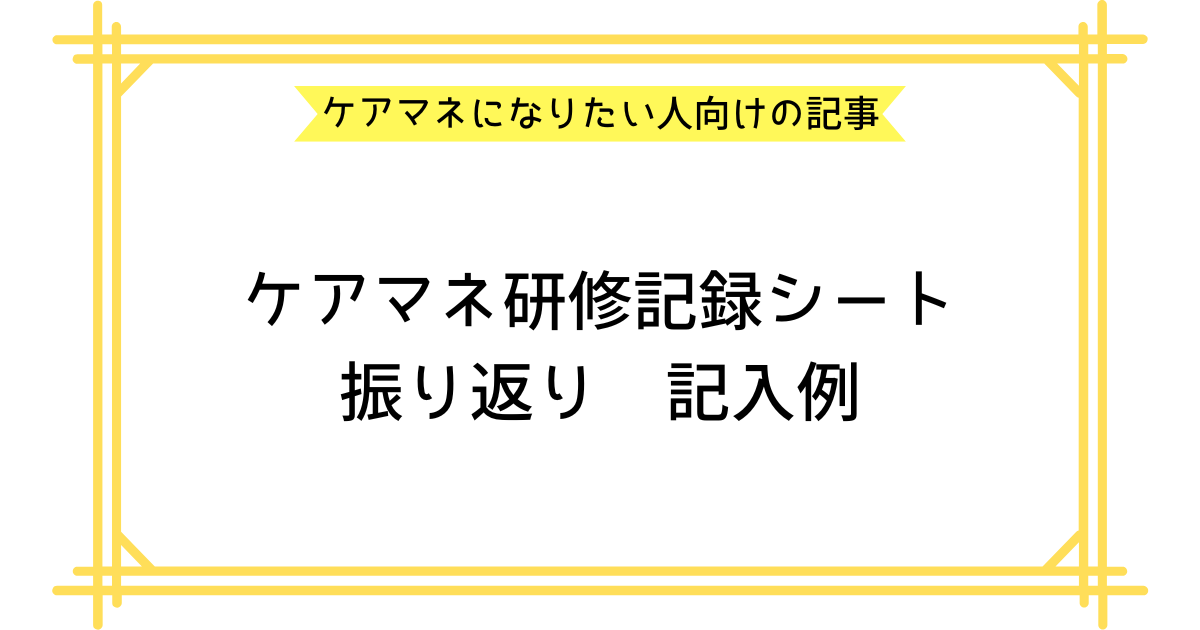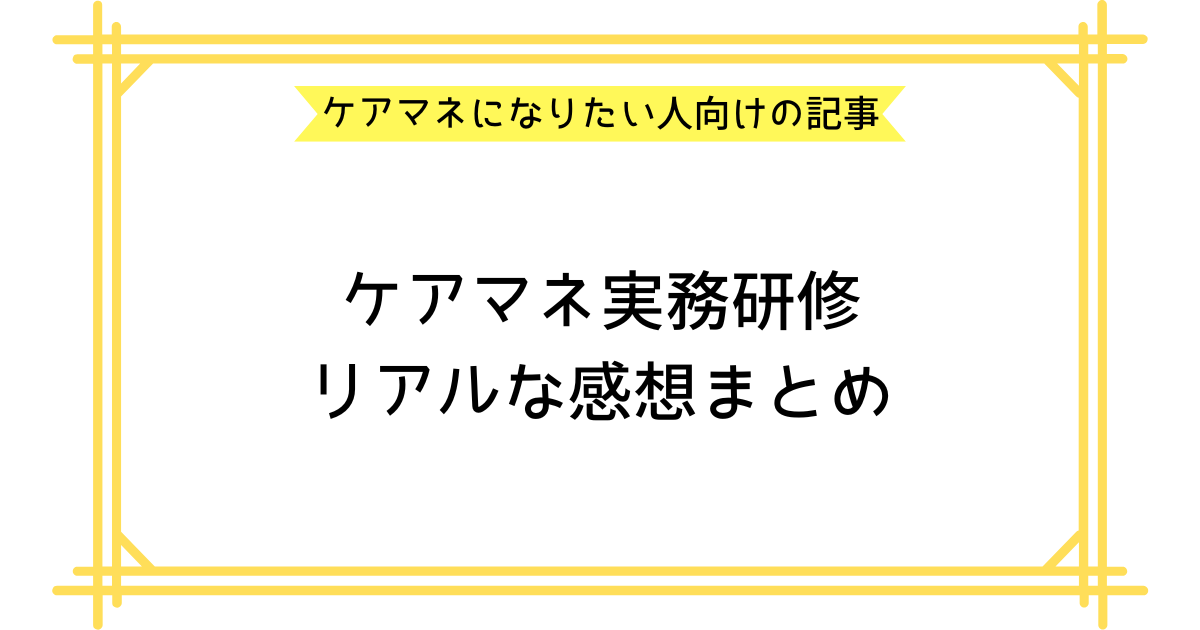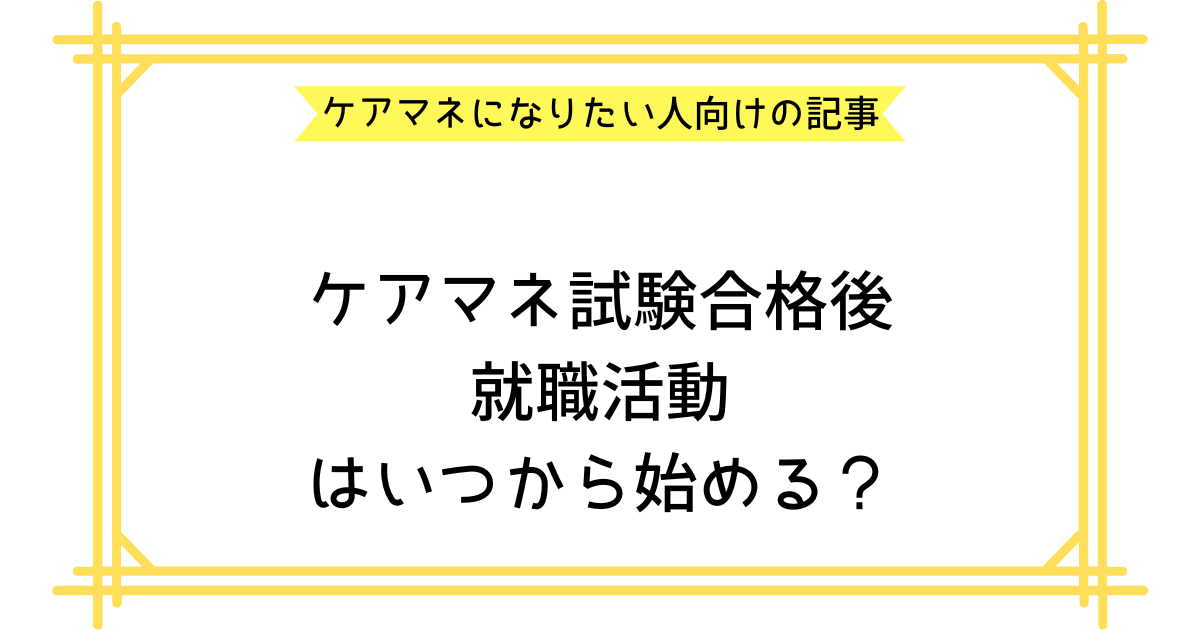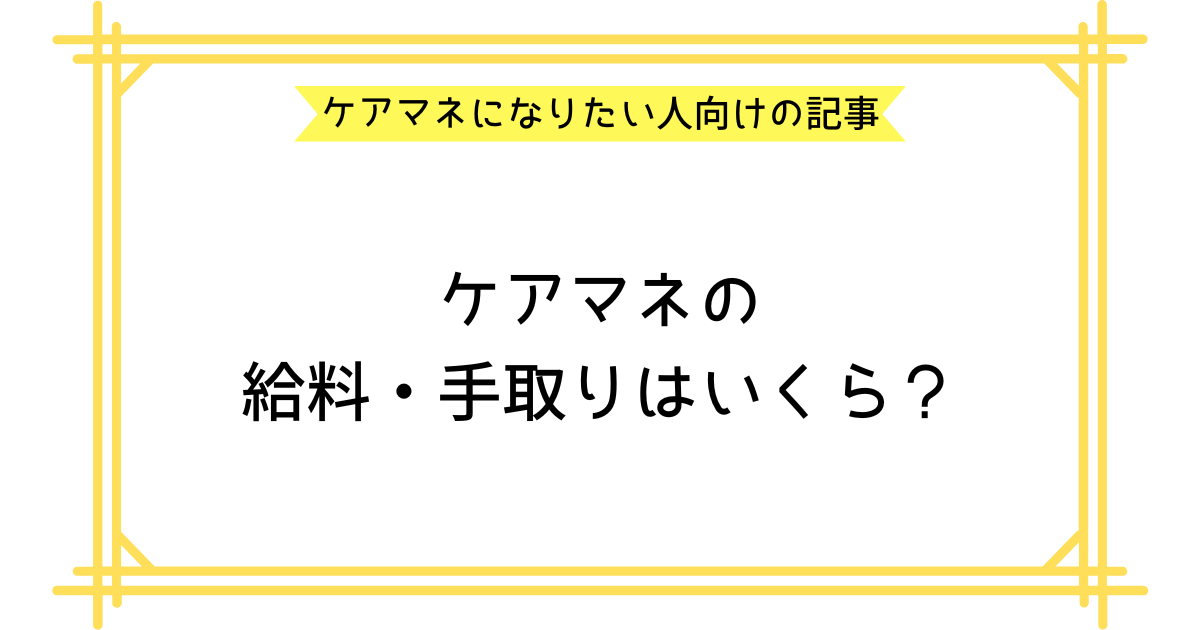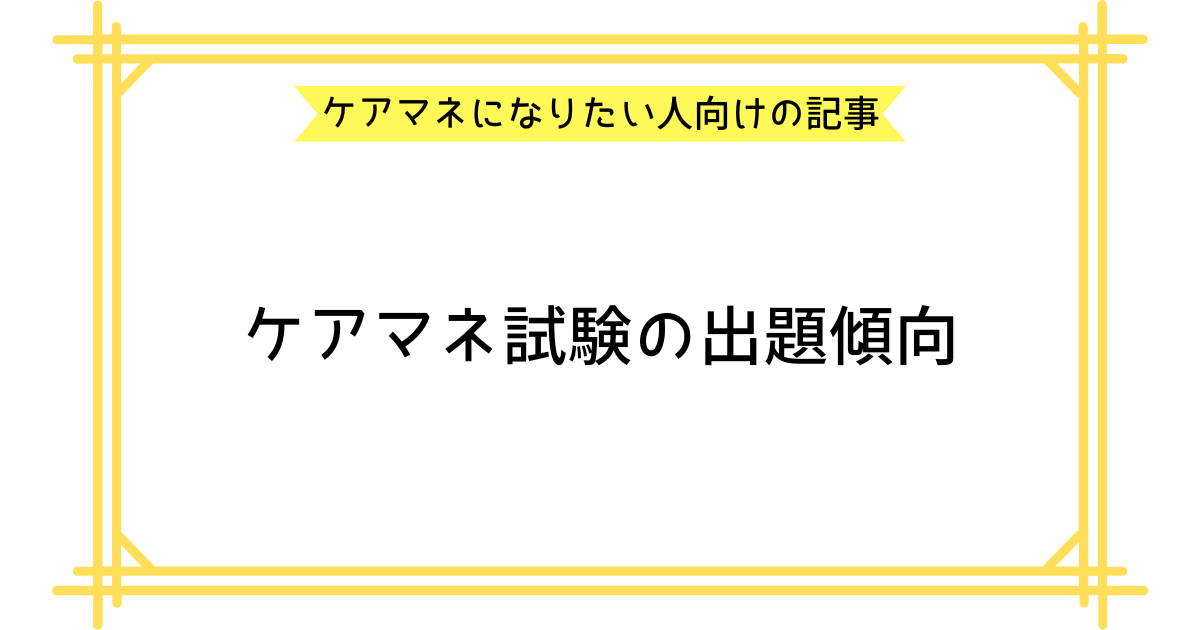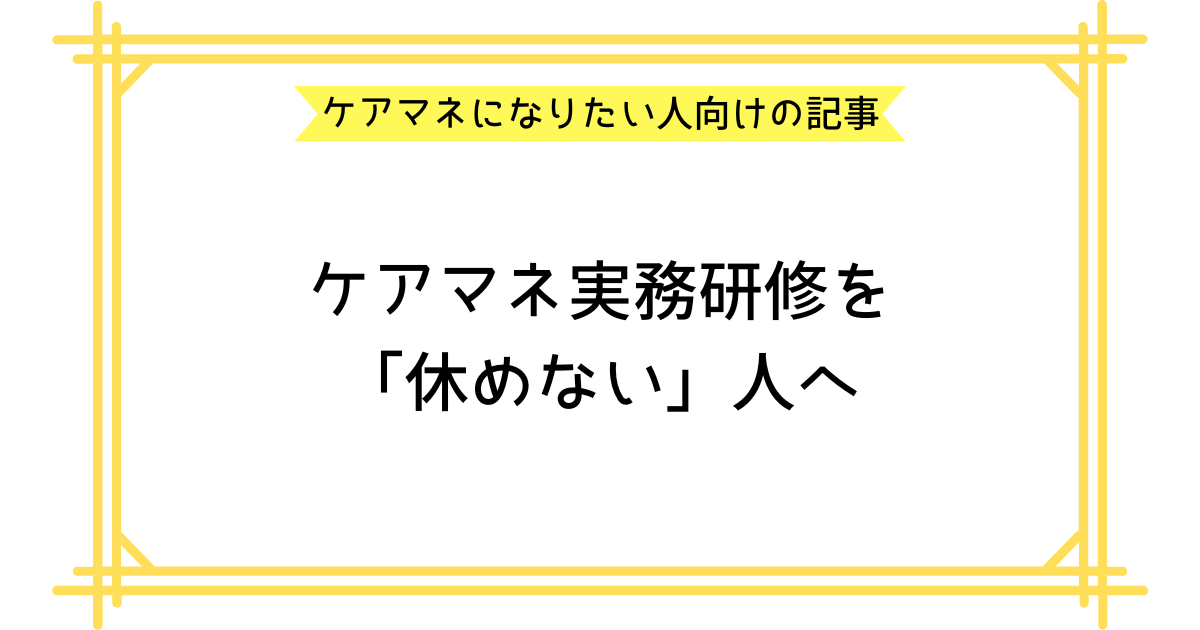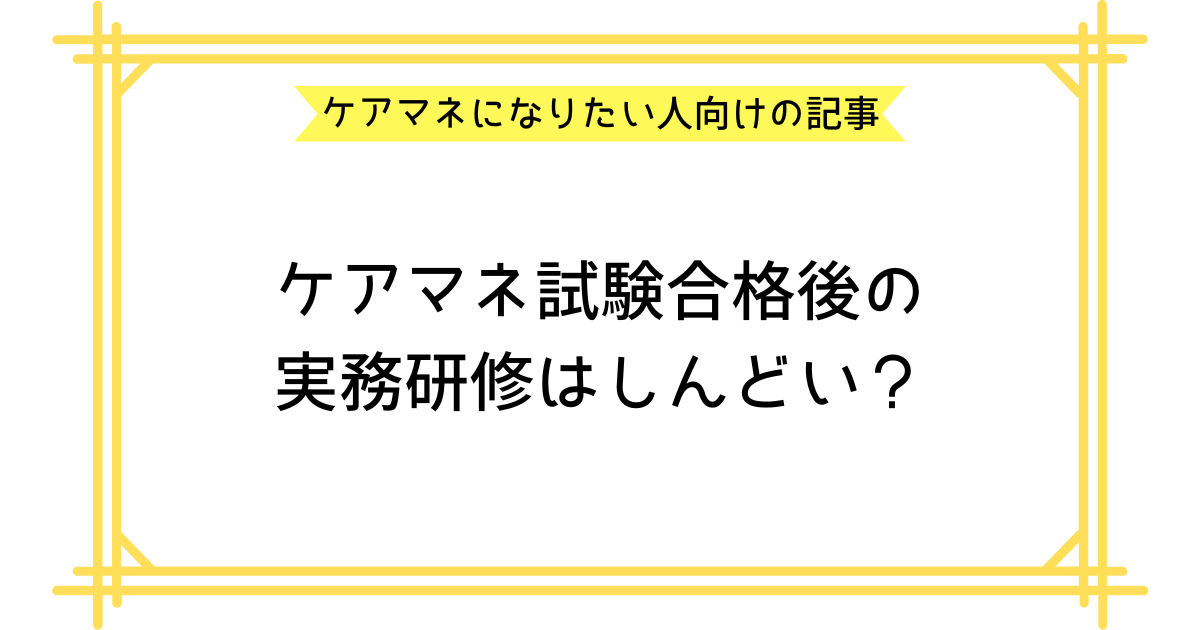【ケアマネ試験対策】ソーシャルワークとは?覚えておくべきことを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
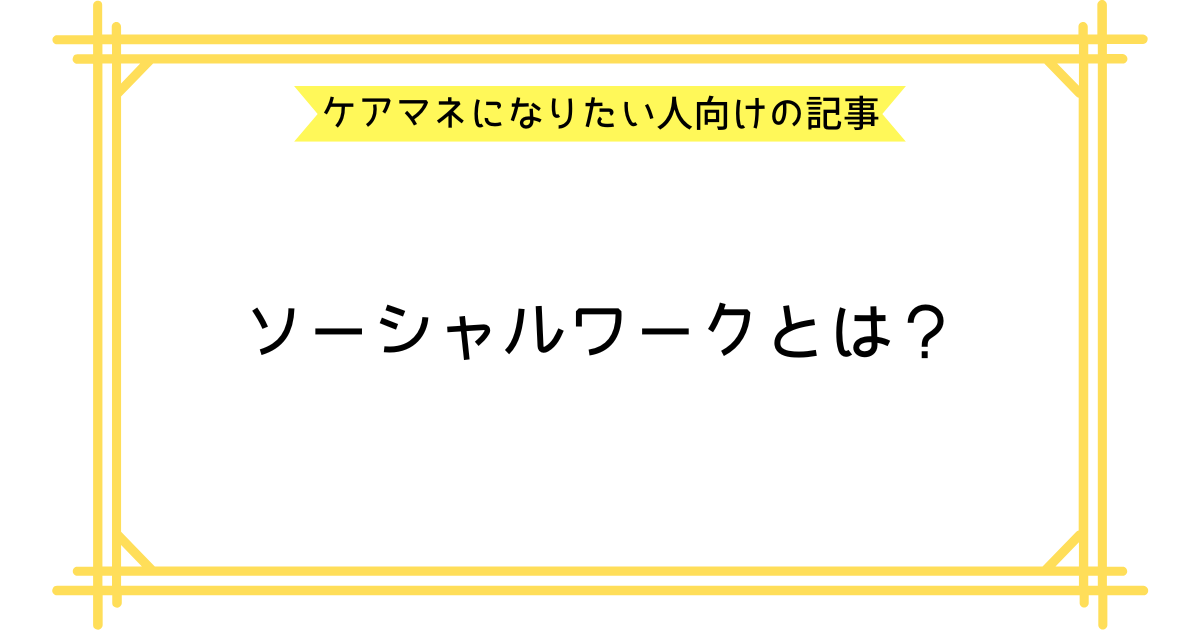
ケアマネ試験の勉強を進める中で「ソーシャルワーク」という言葉は必ず出てきます。
しかし、漠然と「福祉の支援方法」とイメージしているだけでは試験に対応できません。
ソーシャルワークは介護・福祉の基盤となる考え方であり、ケアマネジャーとして利用者支援を行う上でも欠かせない知識です。
この記事では、ソーシャルワークの定義・目的・原則、そして試験で問われやすいポイントをわかりやすく解説します。
目次
ソーシャルワークとは?
ソーシャルワークとは、個人・家族・地域社会が抱える課題に対して、生活の質(QOL)の向上や自立支援を目的に行われる援助活動 のことを指します。
国際ソーシャルワーカー連盟(IFSW)の定義によれば、ソーシャルワークは「社会正義、人権の尊重、集団的責任、多様性の尊重に基づき、福祉や発展を促進する専門職」とされています。
ケアマネにとっては、利用者や家族が直面する生活課題を整理し、必要な資源につなげる「支援の基盤的視点」として理解しておく必要があります。
ソーシャルワークの目的
ソーシャルワークの主な目的は以下の通りです。
- 利用者の自立支援:生活機能を回復・維持し、自分らしく暮らせるようにする
- 社会的資源の活用:介護サービスや地域資源をつなぎ、生活課題を解決する
- 権利擁護:高齢者や障害者など社会的に弱い立場にある人の権利を守る
- 生活の質(QOL)の向上:身体・精神・社会的側面から総合的に支援する
ソーシャルワークの基本原則
ケアマネ試験では「ソーシャルワークの原則」がよく問われます。
- 受容:利用者を一人の人間として尊重し、そのまま受け止める
- 自己決定:利用者自身が選択・決定する権利を尊重する
- 個別化:利用者ごとの状況や背景に応じて支援を行う
- 意図的感情表出:利用者が感情を安心して表出できるよう支援する
- 秘密保持:支援の中で知り得た個人情報を守る
- 統制された情緒的関与:専門職としての冷静さを持ちながら感情的に寄り添う
- 利用者の全体性の尊重:身体・精神・社会的側面を含めた全人的な存在として支援する
これらは 「ソーシャルワークの7原則」 として試験対策で必ず覚えておくべきポイントです。
ケアマネ試験で問われやすいポイント
- ソーシャルワークの定義(人権・社会正義・自立支援がキーワード)
- ソーシャルワークの目的(生活の質向上、社会資源活用、権利擁護)
- ソーシャルワークの7原則(受容・自己決定・個別化・意図的感情表出・秘密保持・統制された情緒的関与・全体性の尊重)
- ケアマネ業務にどう活かされるか(ケアプラン作成、アセスメント、サービス調整の基本姿勢)
試験対策の覚え方
- 受容・自己決定・個別化 → 利用者中心の基本姿勢
- 意図的感情表出・秘密保持 → 面接場面で重要
- 統制された情緒的関与・全体性の尊重 → 専門職としての態度
「利用者を尊重し、自立を支えるための支援原則」とまとめて覚えると理解しやすいです。
まとめ
ソーシャルワークとは、利用者の自立支援や生活の質向上を目的とし、人権や社会正義を基盤に行われる援助活動のことです。
ケアマネ試験対策としては、
- ソーシャルワークの定義と目的
- ソーシャルワークの7原則
- ケアマネ業務との関わり
を押さえておくことが重要です。
「ソーシャルワークは利用者支援の基本姿勢」として理解すれば、試験にも実務にも役立ちます。