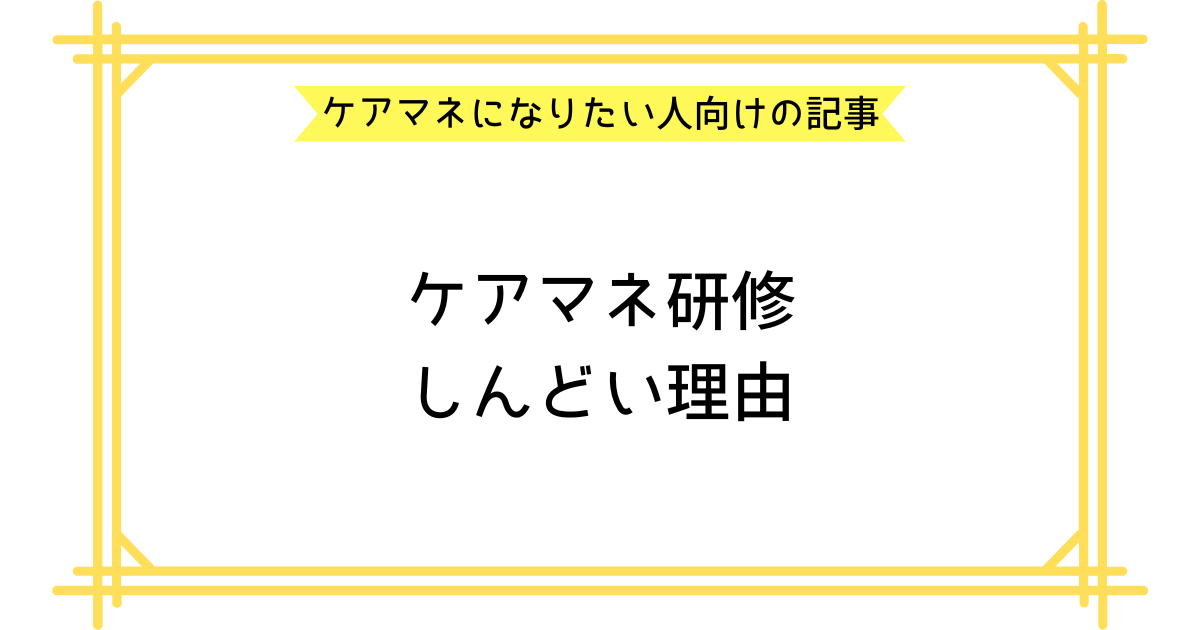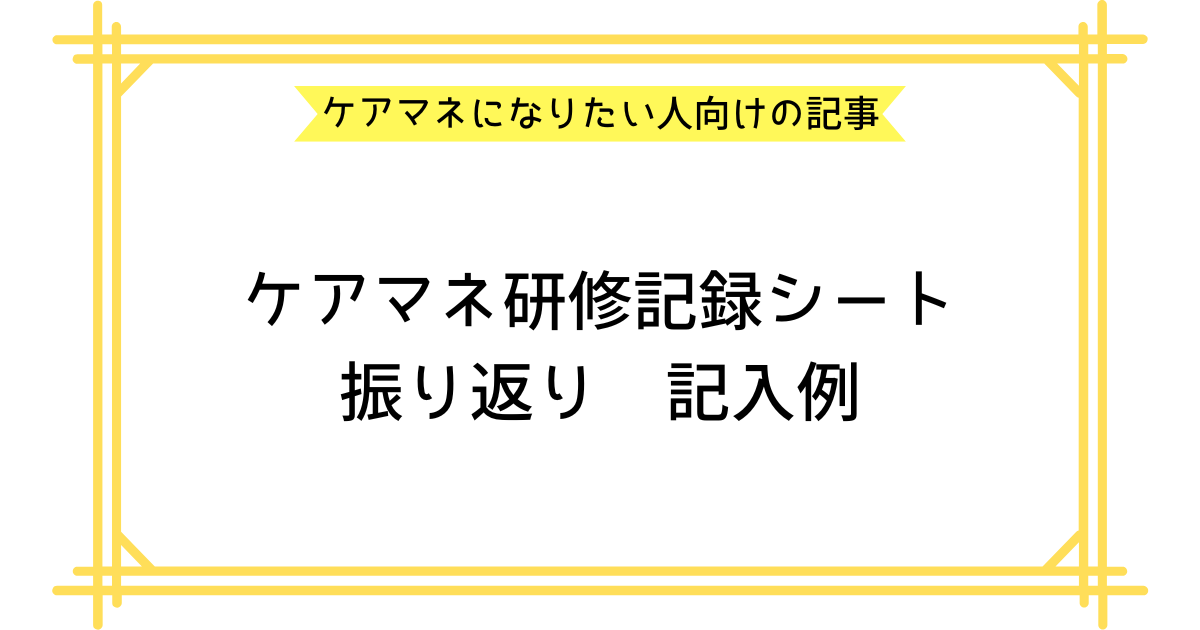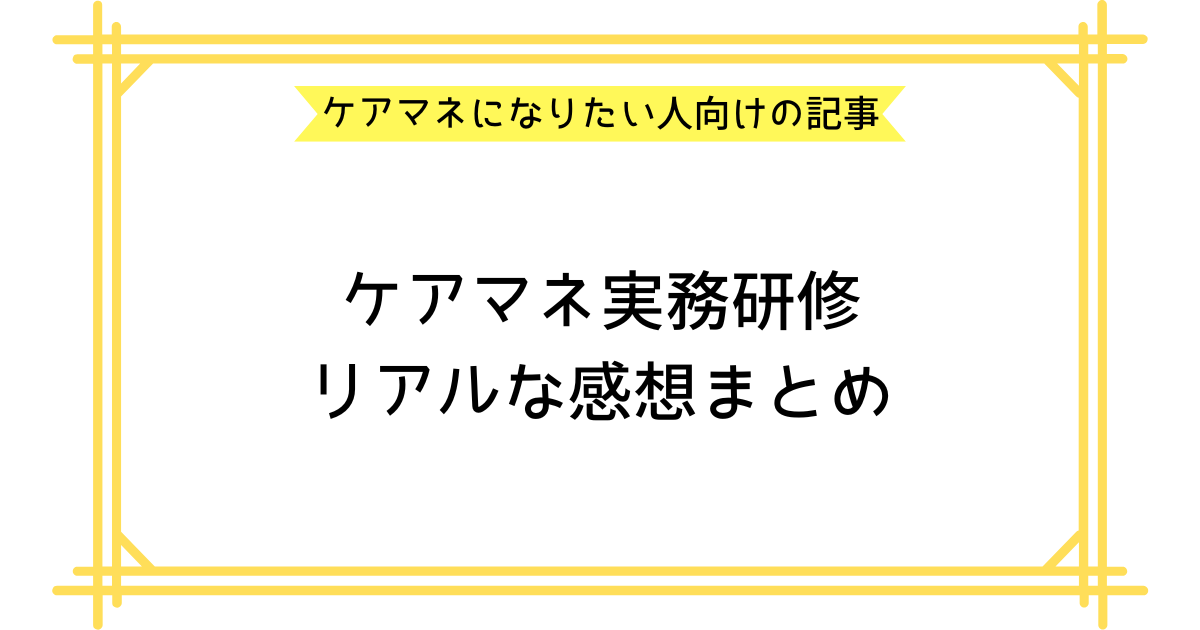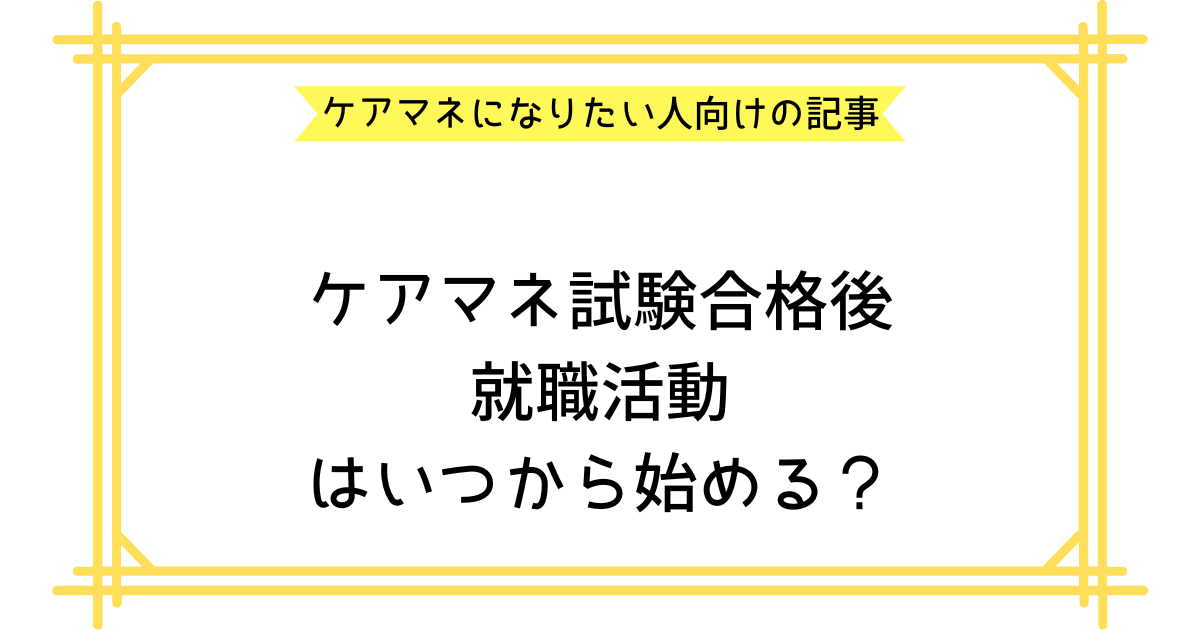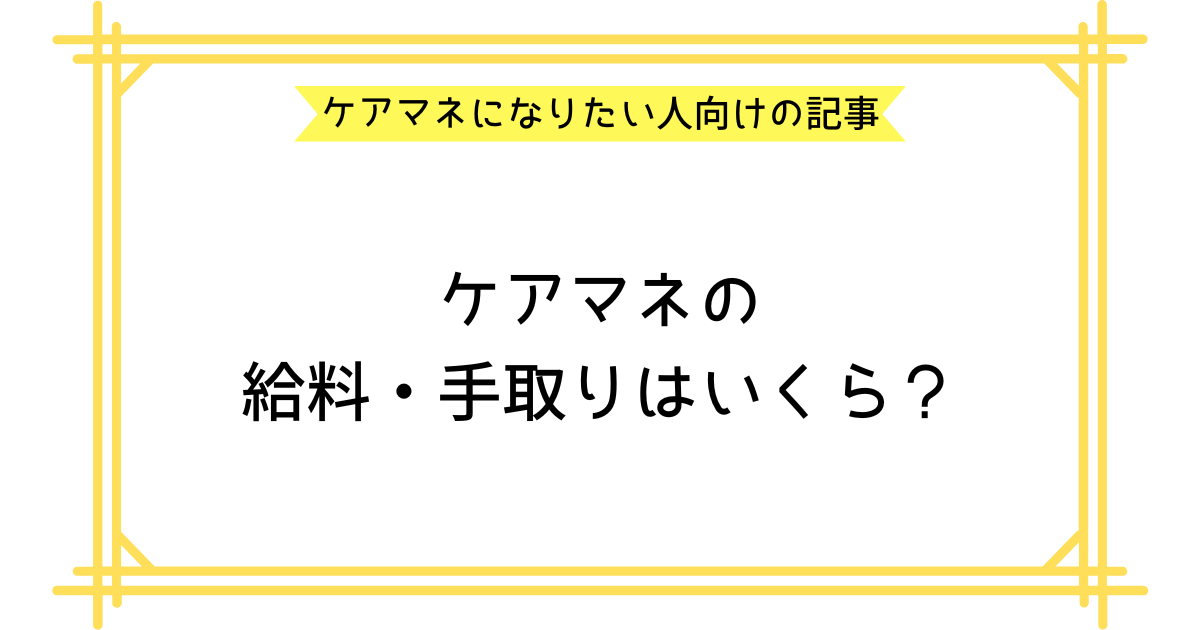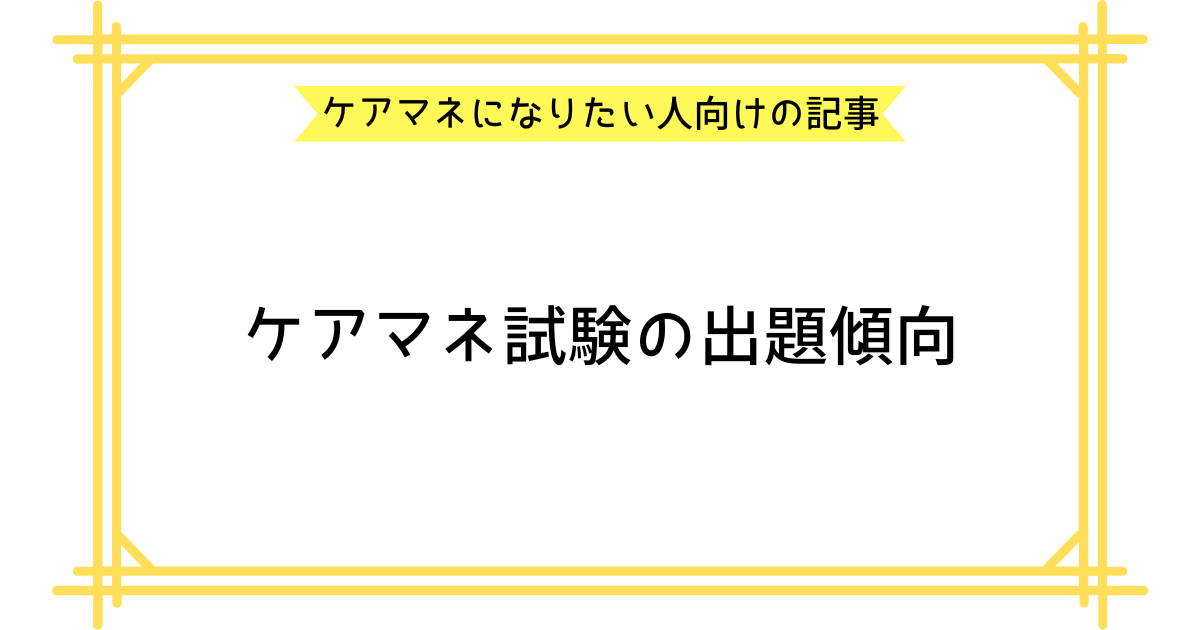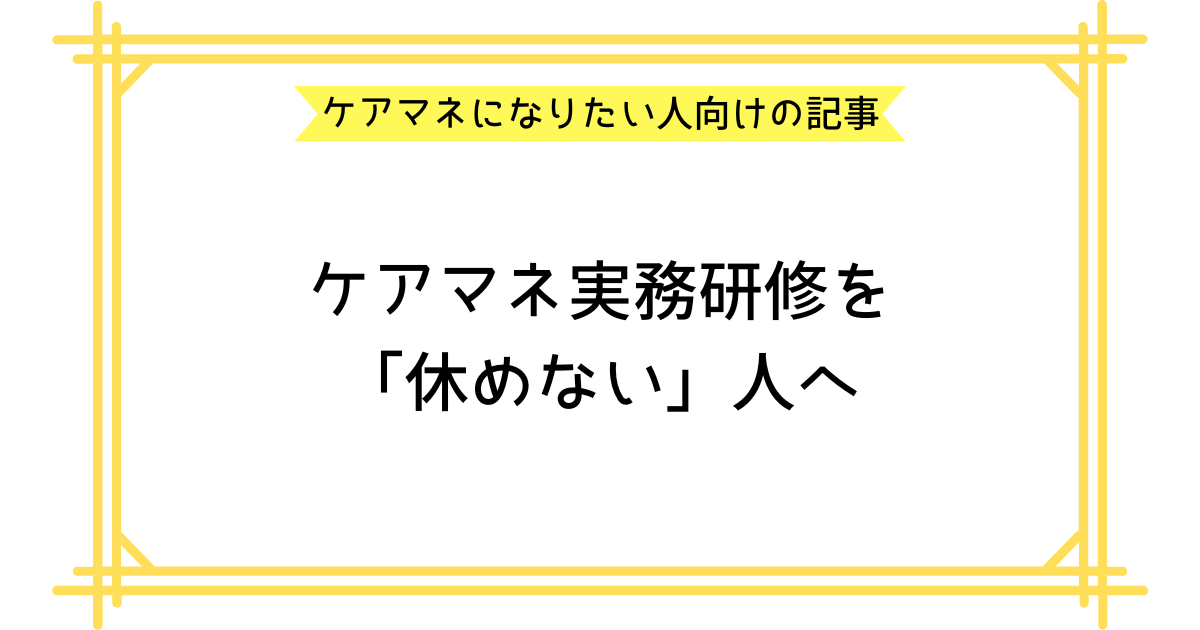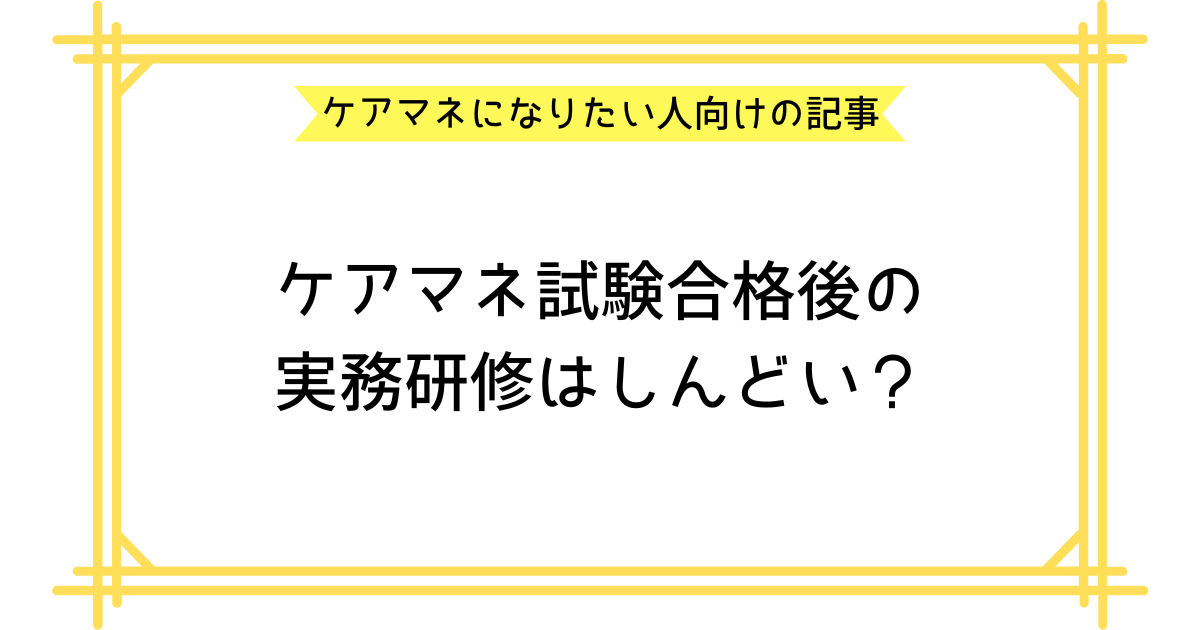社会福祉士とケアマネはどちらが難しい?試験の違いや合格率を徹底比較
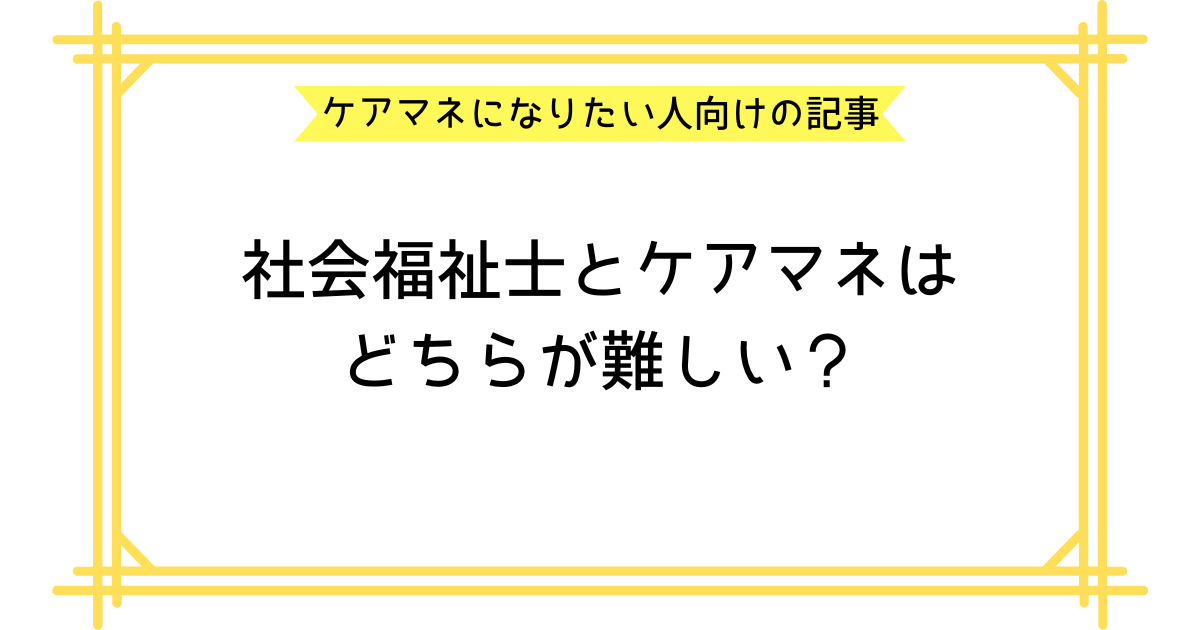
福祉や介護の専門資格としてよく比較される「社会福祉士」と「ケアマネ(介護支援専門員)」。
どちらも専門性が高く、将来性のある資格ですが「実際にはどちらが難しいの?」「取得を目指すならどちらを優先すべき?」と悩む人も多いでしょう。
この記事では、社会福祉士とケアマネそれぞれの試験制度や合格率、必要な勉強量を比較しながら、どちらが難しいのかをわかりやすく解説します。
社会福祉士とケアマネの資格制度の違い
社会福祉士とは
社会福祉士は、ソーシャルワーカーとして福祉に関する相談援助を専門に行う国家資格です。高齢者や障害者、生活困窮者など幅広い対象に対し、相談支援や権利擁護を行います。受験資格として大学・養成校で所定の科目を修了する必要があり、取得のハードルは学歴・履修要件に左右されます。
ケアマネ(介護支援専門員)とは
ケアマネは、介護保険制度の下で利用者のケアプランを作成し、多職種と連携しながら介護サービスを調整する専門職です。国家資格ではなく都道府県実施の公的資格ですが、介護保険制度を支える要となる存在です。受験資格は、介護福祉士や看護師などの国家資格を持ち、かつ実務経験が5年以上必要となります。
試験の難易度を比較
受験資格の難しさ
- 社会福祉士:大学や養成施設での履修要件が必要。誰でも受けられるわけではなく、学歴要件を満たす必要がある。
- ケアマネ:受験資格に5年以上の実務経験が必要。資格を持っていても経験が浅いと受験できない。
試験の範囲と科目数
- 社会福祉士:19科目にまたがる幅広い知識が必要(人権、福祉制度、相談援助技術、医学知識など)。暗記量が多く、勉強時間の確保が必須。
- ケアマネ:出題範囲は介護保険制度、ケアマネジメント過程、医療・介護の基礎知識など。範囲は社会福祉士より狭いが、実務的な内容が多く、経験を知識に結びつける力が必要。
合格率の比較
- 社会福祉士試験:合格率はおよそ 25〜30%前後。合格率は安定しているが、出題範囲が広いため勉強量が多い。
- ケアマネ試験:近年は合格率が 10〜20%前後 と低め。特に2018年度以降は合格率が一桁台になった年もあり、「狭き門」と言われる。
どちらが難しいのか?
結論としては、
- 勉強量の多さでは社会福祉士が難しい
- 合格率の低さではケアマネが難しい
社会福祉士は膨大な科目を理解しなければならず、学生時代から体系的に学習する必要があります。一方、ケアマネは受験資格のハードルが高く、試験範囲は絞られているものの、合格率は低いため「実務経験を積んだ上でさらに学習が必要」という難しさがあります。
どちらを目指すべきか?
- 福祉分野で幅広く相談援助をしたい人 → 社会福祉士
- 介護分野で実務経験を活かし、ケアプラン作成や多職種連携に携わりたい人 → ケアマネ
両方を取得することでキャリアの幅はさらに広がります。特に社会福祉士資格を持つ人がケアマネを取得すると、相談援助スキルとケアマネジメント力の両方を発揮でき、地域包括支援センターや行政でも重宝されます。
まとめ
社会福祉士とケアマネはどちらも専門性が高く、介護・福祉の現場で欠かせない資格です。
- 学習範囲の広さでは社会福祉士が難しい
- 合格率の低さや受験資格の厳しさではケアマネが難しい
どちらが難しいかは一概に言えませんが、自分が目指すキャリアや働きたい現場に合わせて選ぶことが大切です。
将来的に両方を取得することで、さらに専門性を高め、活躍の場を広げることができるでしょう。