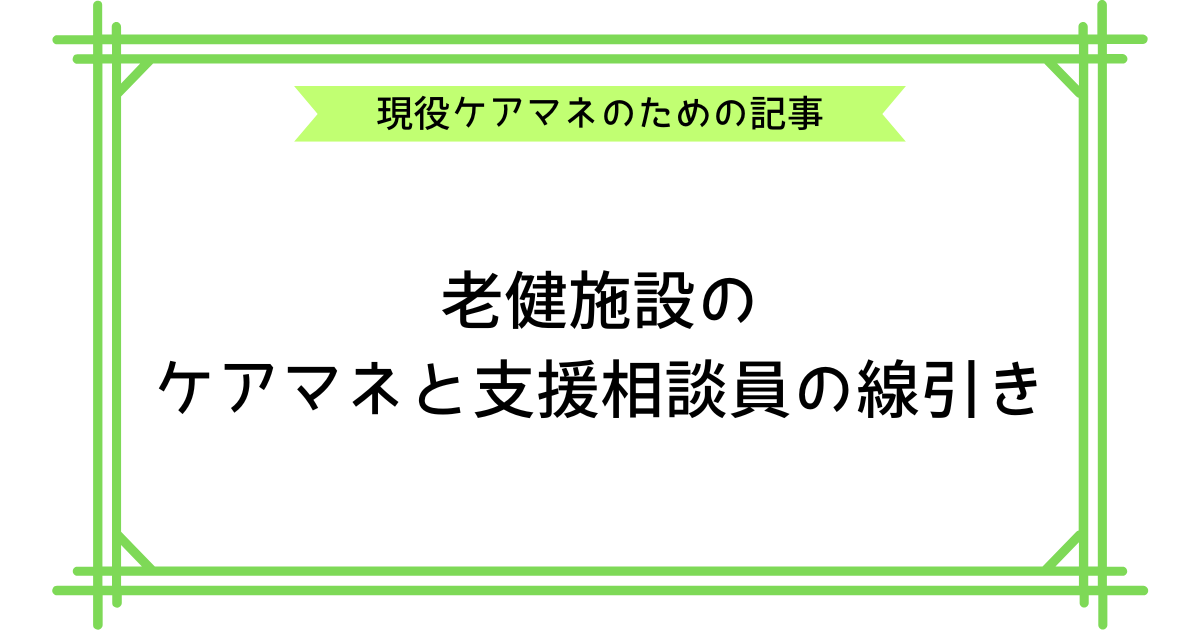施設ケアマネと居宅ケアマネ、どちらが大変?仕事内容と負担を徹底比較

「施設ケアマネと居宅ケアマネ、どちらが大変なの?」
ケアマネジャーとして働く上で、勤務先によって仕事内容や求められるスキルは大きく異なります。
施設ケアマネは利用者が同じ施設内にいる一方、居宅ケアマネは訪問・調整が多く、どちらにもメリットと大変さがあります。
この記事では、両者の違い・負担の度合い・やりがい・向いている人の特徴をわかりやすく解説します。
施設ケアマネと居宅ケアマネの違いとは
まずは、両者の基本的な働き方と業務範囲を整理してみましょう。
| 項目 | 施設ケアマネ | 居宅ケアマネ |
|---|---|---|
| 勤務場所 | 介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・グループホームなど | 居宅介護支援事業所 |
| 担当利用者数 | 約50〜100人(施設規模による) | 約35人が上限(法定人数) |
| 主な業務 | 施設入所者のケアプラン作成・モニタリング・多職種連携 | 在宅利用者のケアプラン作成・訪問・サービス調整 |
| 関わる職種 | 看護師・介護職・相談員・医師・PT/OT/STなど同施設内スタッフ | 訪問介護・デイサービス・福祉用具・病院など外部事業所 |
| 1日の業務スタイル | 施設内で完結 | 外出・訪問・電話連絡が多い |
一見すると「施設の方が楽そう」「居宅は大変そう」と思われがちですが、実際はどちらも別の意味で大変です。
施設ケアマネの大変なところ
1. 利用者数が多く、事務処理が膨大
施設ケアマネは、入所者全員(数十〜百人)のケアプランを一括で管理します。
月ごとのモニタリングや会議、記録業務だけでも膨大で、デスクワークの量が非常に多いです。
・入退所の調整や家族対応も発生
・一人のケアマネが複数フロアを担当することも
・加算算定や書類期限の管理も大変
特に、加算要件や介護報酬の改定対応では、細かいチェック作業が多く、**「パソコンとにらめっこが続く日々」**という声も。
2. 現場業務と兼務になりやすい
施設ケアマネは、人手不足の施設では介護職を兼務するケースが多いです。
ケアマネ業務に加えて、入浴介助・食事介助・夜勤のサポートを求められることもあります。
「ケアマネなのに現場に呼ばれる」「書類が進まない」という悩みを抱える人も多く、純粋にケアマネ業務に集中できない環境がストレスになることもあります。
3. 家族対応が難しい
入所者の家族からは、介護方針・サービス内容・医療対応など、細かい要望が寄せられます。
トラブル時には真っ先にケアマネが対応するため、精神的なプレッシャーが大きい職場でもあります。
居宅ケアマネの大変なところ
1. 担当利用者の多様性
居宅ケアマネは、年齢・疾患・家族状況が全く異なる利用者を35人前後担当します。
「認知症高齢者」「独居」「ターミナル期」「生活保護世帯」など、支援内容が多岐にわたり、一人ひとりに合わせた調整力が求められます。
2. 外部調整・電話対応の多さ
デイサービス・訪問介護・訪問看護・病院・包括支援センターなど、多数の関係機関と連絡を取る必要があります。
1日中、電話とメールで調整を行い、“つねに誰かと連絡を取っている”状態です。
さらに、モニタリング訪問・サービス担当者会議・更新手続きなど外出業務も多く、1日のスケジュール管理が難しいのも特徴です。
3. 責任の重さと孤独感
居宅ケアマネは、利用者1人ひとりの生活を支える“司令塔”です。
一つの判断ミスが支援全体に影響することもあり、責任の重さを感じやすい仕事です。
また、事業所によってはケアマネが1人しかいない場合もあり、孤独感や相談相手の少なさに悩むこともあります。
どちらが大変か?実際の声を比較
| 比較項目 | 施設ケアマネ | 居宅ケアマネ |
|---|---|---|
| 体力的な負担 | 介護兼務があると重い | 外回りが多く移動が大変 |
| 精神的な負担 | 職員・家族間の調整が多い | 利用者・事業所・家族との板挟み |
| 事務処理量 | 多い(特に加算関係) | 多い(給付管理・報告書) |
| 人間関係の難しさ | 同僚との連携が密、摩擦も | 外部調整が多くストレスも分散 |
| 仕事のやりがい | チームで支援が完結する達成感 | 在宅生活を支える実感が得られる |
| 休みの取りやすさ | 施設シフトに左右される | 比較的調整しやすい(事業所による) |
結論としては、**どちらも「大変な方向性が違う」**と言えます。
施設は「人数・書類・組織調整」が大変で、居宅は「個別対応・外部調整・責任の重さ」が負担になります。
向いている人の特徴
施設ケアマネに向いている人
・チームで仕事をするのが好き
・現場を近くで見ながら支援したい
・ルーティン業務や記録作業が得意
・人間関係を安定的に築けるタイプ
施設ケアマネは、日々の変化が比較的少なく、同じ利用者を長く支援できます。
一方で、チーム内での調整力が求められます。
居宅ケアマネに向いている人
・外回りや訪問が苦にならない
・自分でスケジュールを組みたい
・多様なケースを柔軟に考えられる
・個人の判断力と責任感を持てるタイプ
居宅ケアマネは、自由度が高い分、自己管理力と判断力が不可欠です。
一人ひとりに寄り添う支援をしたい人には向いています。
「大変さ」よりも「やりがい」で選ぶのが正解
どちらの職場でも、共通しているのは「利用者の生活を支える」という使命感です。
施設ではチームで、居宅では地域全体で、それぞれの形で“生活を支える”やりがいがあります。
【選ぶポイント】
・安定した環境で長く働きたい → 施設ケアマネ
・自分の裁量で動きたい・在宅支援が好き → 居宅ケアマネ
自分の性格・働き方・ライフスタイルに合った方を選ぶことが、長く続ける上で最も大切です。
まとめ:どちらも大変。でも方向性が違う
| まとめポイント |
|---|
| 施設ケアマネ:人数・書類・組織調整の大変さ |
| 居宅ケアマネ:外部連携・責任の重さ・スケジュール管理の大変さ |
| どちらも大変だが、「働き方の方向性」が違う |
| 自分に合う職場環境を選ぶことで、やりがいを実感できる |
ケアマネとして働く道は一つではありません。
自分に合った環境を見極めれば、「大変さ」を超えてやりがいを感じられる仕事です。