ケアマネは親族や同居家族・親の担当はできるのか?
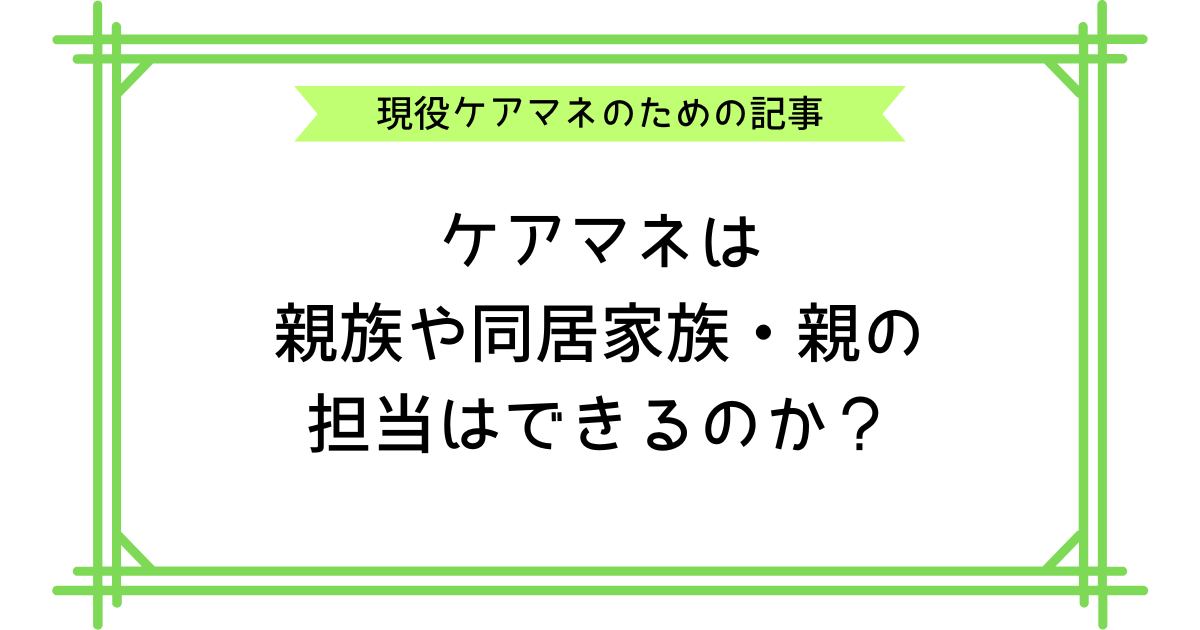
介護サービスを利用する際に中心となるのがケアマネジャー(介護支援専門員)です。
では、もし自分自身がケアマネジャーだった場合に「親の担当になれるのか?」「同居している家族のケアプランを作成できるのか?」と疑問に思う方もいるでしょう。
実際には、介護保険制度には一定のルールや制限が設けられており、親族や同居家族を担当することには注意点があります。
この記事では、ケアマネジャーが親族や同居家族を担当できるのかどうか、制度上の取り扱いや実務での留意点をわかりやすく解説します。
ケアマネは親族や同居家族の担当になれるのか?
結論から言うと、親族や同居家族を担当ケアマネジャーとして引き受けることは可能ですが、強く推奨されていません。
介護保険制度上で絶対に禁止されているわけではありませんが、厚生労働省のガイドラインや運営基準では「公正・中立性」が重視されており、家族を担当すると利益相反や公平性の問題が生じやすいためです。
制度上の根拠と考え方
利用者本位の原則
介護保険制度では「利用者本位」が基本原則です。ケアマネジャーは利用者や家族の意向を尊重しつつ、公平な立場で最適なサービスを調整しなければなりません。
利益相反の懸念
親族や同居家族を担当すると、サービス内容を客観的に判断できなくなる恐れがあります。たとえば「家族の介護負担を軽くするために必要以上のサービスを入れる」「逆にサービスを抑えてしまう」といったバイアスが働きやすくなるのです。
行政監査の対象になりやすい
居宅介護支援事業所は定期的に行政の指導監査を受けますが、親族を担当しているケースは「適切なケアマネジメントができているか」特に厳しくチェックされます。
実務上の取り扱い
1. 親の担当ケアマネになるケース
現実的には「自分がケアマネだから親のケアプランも自分で作りたい」という状況はあり得ます。その場合、制度上は可能ですが、事業所の運営規程や管理者判断で断られることもあるのが実情です。
2. 同居家族の担当になる場合
同居している家族を担当すると、客観的判断が難しくなりやすいです。そのため、包括支援センターや事業所から「できるだけ他のケアマネに変更してください」と指導される場合があります。
3. 特別な事情があるとき
地方や離島などケアマネの数が限られている地域では、やむを得ず親族が担当することが容認されることもあります。この場合でも、公正中立性を確保するために他職種との連携や第三者チェックを強化することが求められます。
ケアマネが親族を担当することのメリットとデメリット
メリット
- 本人や家族の希望をよく理解している
- 状況を把握しやすく連絡もスムーズ
- サービス利用に至るまでの調整が早い
デメリット
- 客観性が失われる可能性が高い
- 行政監査で問題視されるリスクがある
- 利用者本人の声より「家族の都合」を優先しやすい
- 利用者とケアマネの立場が混同しやすい
利用者・家族が知っておくべきこと
もし「担当ケアマネが親族」という状況になった場合、利用者や家族としては以下の点を確認しましょう。
- ケアプランが本人の希望に沿っているか
- サービス内容に偏りがないか
- 他職種(医師・看護師・事業所職員)と連携できているか
- 定期的なモニタリングや評価が形骸化していないか
ケアマネ自身が注意すべきポイント
親族を担当する場合、ケアマネ自身にも強い自覚が求められます。
- 利用者本人の意思を最優先する
- 家族の介護負担と本人の希望を混同しない
- 事業所内での第三者チェックを受ける
- サービス担当者会議を形式的にせず、多職種の意見を取り入れる
まとめ
ケアマネジャーが親族や同居家族・親の担当になることは、介護保険制度上は可能です。しかし 「利益相反」「客観性の欠如」「監査リスク」 などの問題があるため、実務上は推奨されません。
もし担当となる場合は、
- 利用者本位の姿勢を徹底する
- 第三者の意見や多職種連携を取り入れる
- 家族もケアプランの内容をしっかり確認する
といった工夫が欠かせません。介護サービスは利用者の人生に直結するものです。親族を担当する場合も「中立性」を忘れず、適切なケアマネジメントを行うことが求められます。















