【コピペOK】ケアプラン 1表(課題分析の結果)の文例70例
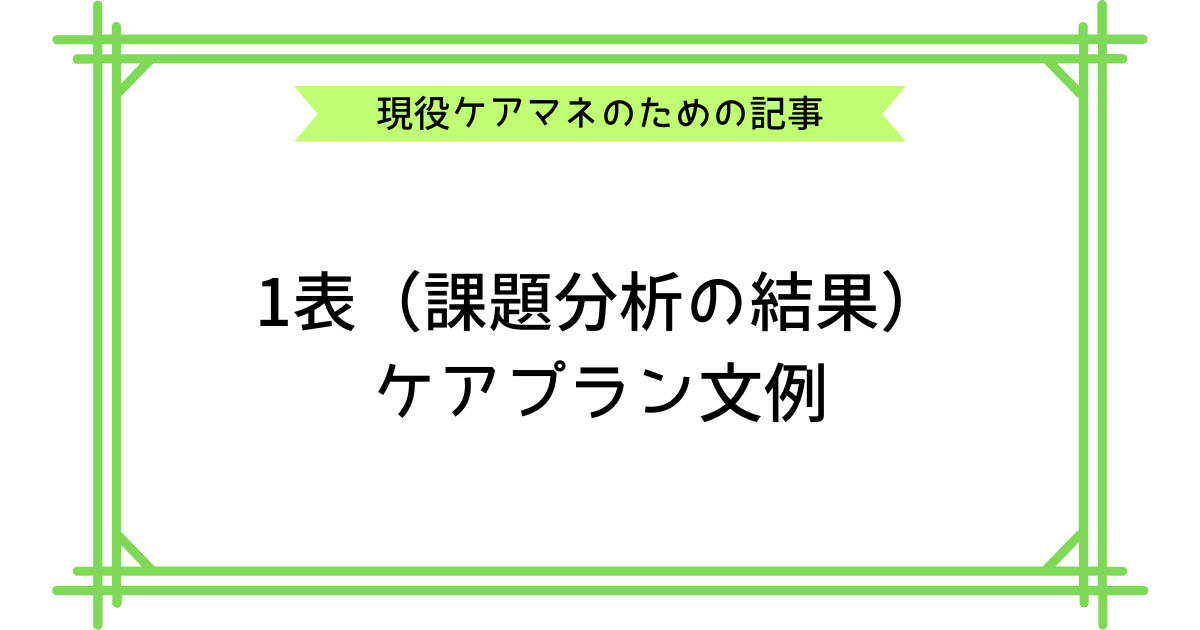
ケアプランの1表「課題分析の結果」は、利用者や家族の意向を踏まえながら、生活全般の課題を整理し、支援の方向性を明確にする重要な部分です。
しかし「どのように文章化すればよいのか迷う」「いつも似たような表現になってしまう」と悩むケアマネジャーも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、運営指導対応にも安心な【コピペOK】の文例を 70例 用意しました。
生活全般・身体面・精神面・環境面など幅広く網羅しているため、そのまま活用していただけます。
ケアプラン 1表(課題分析の結果)の文例
文例1
本人は独居で日中ひとりで過ごす時間が長く、体調変化時の対応に不安がある。定期的な見守りや緊急時の連絡体制を整え、安心して在宅生活を継続できるよう支援が必要である。
文例2
歩行時にふらつきが見られ、転倒の危険がある。家屋環境の工夫や福祉用具の導入、見守りの体制を強化することで、安全な移動を確保することが課題である。
文例3
認知機能の低下により、服薬管理が困難となっている。飲み忘れや重複服薬のリスクがあるため、家族や訪問サービスと連携し、確実な服薬支援を行うことが必要である。
文例4
食欲が低下し体重減少がみられる。低栄養の進行を防ぐために、栄養バランスの取れた食事内容の工夫や補助食品の活用を検討することが課題である。
文例5
入浴動作に不安があり、転倒リスクから自宅での入浴を控える傾向がある。清潔保持を目的に、デイサービスや訪問介護での入浴支援を導入することが望まれる。
文例6
本人は家事全般を自力で行うことが困難であり、特に掃除や買い物に負担を感じている。生活環境を清潔に維持し、安心して暮らせるよう外部支援の活用が必要である。
文例7
家族介護者の負担が大きく、心身の疲労が強い。介護負担軽減を目的としたサービス利用やレスパイト支援を導入し、継続的な在宅介護が可能となるよう支援することが課題である。
文例8
夜間せん妄や徘徊があり、家族の見守りに大きな負担がかかっている。安全確保と家族の安眠を守るために、福祉用具の利用や夜間対応サービスの導入を検討する必要がある。
文例9
本人は趣味や交流の機会が減少し、閉じこもり傾向がある。生活に張り合いを持ち、意欲を高めるために、通所サービスや地域活動への参加を促すことが課題である。
文例10
慢性的な腰痛により、立位や歩行に支障をきたしている。疼痛緩和や適切なリハビリを取り入れ、日常生活動作の維持・改善を図ることが必要である。
文例11
高血圧や糖尿病などの慢性疾患があり、自己管理が不十分なため健康状態が不安定である。医師や看護師との連携を図り、生活習慣の改善や服薬管理を徹底することが課題である。
文例12
視力の低下により、日常生活での危険が増している。転倒や事故を防ぐため、住環境の整備や福祉用具の活用、家族の見守り強化が必要である。
文例13
本人はトイレ動作に時間がかかり、失禁が見られるようになった。排泄の自立を促しつつ、羞恥心に配慮した支援を行い、尊厳を保ちながら生活できるよう整えることが課題である。
文例14
独居での生活が長く、近隣との交流がほとんどないため孤立感が強い。社会的孤立を予防するため、地域の交流の場や通所サービスの活用が必要である。
文例15
認知症の進行により、金銭管理や買い物が困難になっている。経済的なトラブルを防ぐために家族や成年後見制度の活用を検討し、安心して生活を続けられるよう支援することが必要である。
文例16
本人は退院直後で体力が低下しており、日常生活動作に不安がある。リハビリテーションを取り入れ、体力の回復と在宅生活の安定を図ることが課題である。
文例17
服薬に対する理解が乏しく、自己判断で中断してしまうことがある。服薬管理を徹底し、必要に応じて服薬支援を導入することで病状の安定を図ることが課題である。
文例18
本人は趣味活動や役割を失い、無気力な様子が目立つ。生活に楽しみを持てるよう、本人の関心を引き出す活動を取り入れ、意欲の向上を支援することが課題である。
文例19
下肢筋力の低下があり、屋内でも歩行器を使用している。今後も転倒リスクを軽減しながら、自立した移動を維持できるようリハビリと環境整備を進めることが必要である。
文例20
家族は仕事と介護の両立で疲弊しており、介護負担が限界に近い。レスパイトサービスの導入や訪問介護の利用を増やし、家族の介護継続を支援することが課題である。
文例21
食事摂取に時間がかかり、誤嚥のリスクがある。栄養士やST(言語聴覚士)と連携し、嚥下機能に配慮した食形態や摂取方法を導入することが課題である。
文例22
本人は入浴を拒否する傾向があり、清潔保持が難しい状況にある。本人の気持ちを尊重しつつ、安心して入浴できる環境や支援を工夫することが必要である。
文例23
排便コントロールが不安定で便秘や下痢を繰り返している。食事内容の調整や水分摂取の支援、排便日誌の活用で安定を図ることが課題である。
文例24
本人は自宅での転倒経験があり、家族の不安が大きい。再発防止のため住環境を整え、転倒予防体操や見守りサービスを導入することが必要である。
文例25
独居で日常の買い物が困難になり、栄養バランスが偏っている。配食サービスや訪問介護による買い物支援を取り入れ、栄養状態を安定させることが課題である。
文例26
本人は夜間の不眠が強く、昼間の活動量が減少している。生活リズムの改善や医師との連携を図り、安定した睡眠を確保することが課題である。
文例27
家族内で介護方針の意見が分かれており、ケア方針の共有が不足している。サービス担当者会議や話し合いを通じて、家族間で統一した支援方針を持てるよう支援する必要がある。
文例28
本人は認知症による物忘れで調理や火の管理が危険になっている。火災事故を予防するためにガス使用の制限やIHコンロの導入を検討する必要がある。
文例29
本人は服装や整容に関心が薄くなり、身だしなみに乱れが見られる。自己肯定感を保つために、整容動作の支援や声かけを行い、清潔感のある生活を継続することが課題である。
文例30
高齢による筋力低下で、ベッドからの起き上がりや立ち上がりに介助を要する。リハビリや福祉用具の活用で自立度を高め、日常生活動作の維持を目指すことが課題である。
文例31
本人は物忘れが強く、同じことを繰り返し尋ねることが増えている。認知症の進行による不安を軽減するため、安心できる環境作りと定期的な声かけが必要である。
文例32
関節痛が強く歩行距離が短くなっている。疼痛コントロールと適度な運動を取り入れ、活動範囲を広げていくことが課題である。
文例33
家族は介護方法に不安を感じており、介助の仕方が統一されていない。介護職員や医療職からの指導を受け、適切な介護方法を身につけられるよう支援が必要である。
文例34
本人は日中臥床時間が長く、活動量が減少している。廃用症候群を予防するため、デイサービスやリハビリを通じて活動的な生活習慣を取り入れることが課題である。
文例35
嚥下機能が低下しており、むせ込みが増えている。誤嚥性肺炎を予防するために食事形態の調整や嚥下訓練を導入することが必要である。
文例36
本人は生活意欲が低下し、食事や整容への関心が薄れている。小さな達成感を積み重ねる活動を取り入れ、自己肯定感を高めていく支援が求められる。
文例37
転倒に対する本人と家族の不安が強く、外出を控える傾向にある。転倒予防のためのリハビリや環境整備を行い、安全に外出できるよう支援することが課題である。
文例38
独居で見守りが不十分なため、服薬や食事の管理に漏れがある。安否確認を兼ねたサービス導入により、生活リズムの安定を図ることが必要である。
文例39
本人はデイサービス利用に抵抗を示している。安心して利用できるよう説明や体験利用を通じて信頼関係を築き、外部サービスを受け入れられるよう支援することが課題である。
文例40
本人は下肢の浮腫が強く、歩行に影響を及ぼしている。医師との連携を図りながら、弾性ストッキングや運動療法を取り入れて症状の軽減を目指すことが必要である。
文例41
本人は失語症があり、意思疎通に時間を要する。コミュニケーション方法を工夫し、本人の思いを汲み取れるような支援が課題である。
文例42
食事中に集中力が続かず、摂取量が不足する傾向がある。見守りや声かけを行い、必要に応じて一口量を調整するなどして十分な栄養摂取を確保することが必要である。
文例43
本人は排尿に不安があり、外出を控えるようになっている。排泄リズムを整え、トイレ環境を整備することで安心して外出できるよう支援することが課題である。
文例44
家族が本人の介護に対して否定的な発言を繰り返し、関係が悪化している。介護に関する理解を深めるために、相談支援やカウンセリングを導入することが望まれる。
文例45
本人は独居で服薬を自己管理しているが、誤薬の危険がある。服薬カレンダーや服薬支援サービスを活用し、適切な服薬を維持することが課題である。
文例46
認知症により昼夜逆転の生活リズムが見られる。日中の活動量を増やし、規則正しい生活を取り戻すことが必要である。
文例47
本人は嚥下障害により水分摂取を控える傾向がある。脱水や便秘を防ぐため、ゼリーやスープなど代替手段を活用し、安全に水分補給できるよう支援することが課題である。
文例48
加齢により聴力が低下し、会話が成立しにくい。補聴器の使用や大きな声での対応を工夫し、本人が孤立感を抱かないよう支援することが必要である。
文例49
本人は退院後の生活に不安が強く、自信を失っている。安心して在宅生活を続けられるように医療職や家族と連携し、支援体制を整えることが課題である。
文例50
本人は趣味活動を中断してから生活に張り合いがなくなった。再び趣味や役割を持つことで生活意欲を取り戻せるよう支援することが必要である。
文例51
本人は便秘が続いており、排便に強い不安を抱えている。食事や水分の工夫、排便コントロールの支援を行い、快適な生活を維持することが課題である。
文例52
糖尿病の管理が不十分で、血糖コントロールが不安定である。栄養指導や服薬管理を徹底し、合併症を予防することが必要である。
文例53
本人は失禁を恥ずかしく思い、外出を控えるようになっている。羞恥心に配慮しつつ排泄支援を行い、安心して外出できるよう整えることが課題である。
文例54
本人は転倒経験から外出への恐怖心が強く、活動範囲が狭まっている。安全に移動できるようリハビリや環境整備を行い、自立性を取り戻すことが必要である。
文例55
本人は服薬を忘れることが多く、持病の症状が悪化するリスクがある。服薬支援や家族との連携を図り、安定した健康管理を行うことが課題である。
文例56
本人は長時間座っていることが多く、褥瘡のリスクが高い。体位変換やクッションの使用を取り入れ、皮膚トラブルを予防することが必要である。
文例57
本人は家族に気を遣い、要望を伝えることができない。本人の気持ちを尊重し、意思を引き出す支援を行うことが課題である。
文例58
認知症の影響で物盗られ妄想が出ており、家族関係が悪化している。専門職と連携し、心理的支援と環境調整を行い、安心できる生活を整えることが必要である。
文例59
本人は関節のこわばりで着替えが困難となっている。衣類の工夫や介助方法を導入し、できる限り自立的に整容を行えるよう支援することが課題である。
文例60
本人は嚥下機能低下により誤嚥のリスクが高い。STや看護師と連携し、誤嚥性肺炎を予防する食事形態や姿勢を工夫することが必要である。
文例61
本人は日中の活動量が減少し、生活リズムが乱れている。デイサービスや運動プログラムを取り入れ、規則正しい生活習慣を確立することが課題である。
文例62
本人は不安が強く、介護サービスに抵抗を示す。信頼関係を築きながら少しずつサービス導入を進め、安心して利用できる体制を整えることが必要である。
文例63
本人は家事の一部を自力で行うことが難しくなっているが、自立への意欲は強い。残存機能を活かしながら生活支援を行い、自立を促進することが課題である。
文例64
本人は歩行器を使用しているが、段差でのつまずきが多い。住環境を整備し、外出や室内移動の安全を確保することが必要である。
文例65
本人は認知症により金銭の管理が困難になっている。経済的なトラブルを防ぐため、家族や後見制度と連携した支援を行うことが課題である。
文例66
本人は介護に対して依存傾向が強く、自分でできることもしなくなっている。過介護を防ぎ、自立を維持できるよう支援方法を工夫することが必要である。
文例67
本人は持病による息切れがあり、移動に制限がかかっている。医師の指示に基づいたリハビリや休息の工夫を行い、安全に生活できるよう支援することが課題である。
文例68
本人は家族との関係が希薄で、孤立感が強い。地域資源の活用や相談支援を通じて、孤独感の軽減を図ることが必要である。
文例69
本人は視覚障害により調理や掃除が危険になっている。生活環境の工夫や訪問サービスを導入し、安全に生活を続けられるよう支援することが課題である。
文例70
本人は介護サービスに対する理解が十分でなく、不安を抱えている。制度やサービス内容を丁寧に説明し、本人と家族の納得を得ながら導入を進めることが必要である。
まとめ
ケアプラン1表「課題分析の結果」は、利用者の生活全般を把握し、支援の方向性を明確に示す大切な部分です。しかし、いざ文章化しようとすると「表現が単調になる」「監査対応を意識すると書きづらい」といった悩みも多いのが実情です。
今回紹介した【コピペOK】の文例70は、身体面・認知面・生活環境・家族支援・心理的側面 など幅広い視点をカバーしています。これらをそのまま使うだけでなく、利用者一人ひとりの生活状況に合わせてアレンジすれば、より説得力のあるケアプランに仕上げることができます。
ケアプランは「利用者の生活を守る設計図」です。文例をうまく活用しながら、利用者と家族が安心して暮らせる支援計画を作成していきましょう。















