居宅介護支援事業所の管理者になれる要件とは?
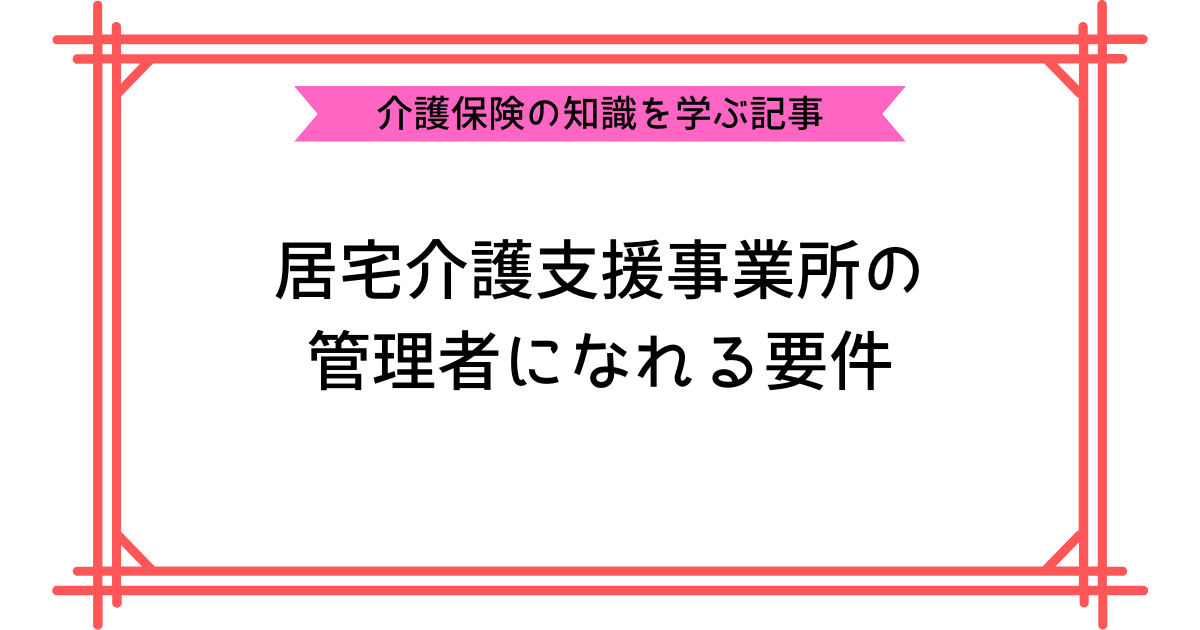
居宅介護支援事業所を運営する上で欠かせない存在が「管理者」です。
管理者は事業所の運営責任を担い、職員体制の整備や業務管理を行います。
しかし「誰が管理者になれるのか」「どんな資格や経験が必要か」「ケアマネでなければいけないのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
本記事では、居宅介護支援事業所の管理者になれる要件について、法律上の基準を踏まえながら分かりやすく解説します。
併せて、兼務の可否や注意点についても紹介します。
居宅介護支援事業所とは?
居宅介護支援事業所は、介護保険制度の中で「ケアマネジャー(介護支援専門員)」が配置され、利用者のケアプランを作成しサービス調整を行う機関です。
利用者と介護サービス事業者をつなぐハブとして機能し、在宅介護を支える重要な役割を担っています。
その中で「管理者」は事業所全体をまとめる責任者として位置づけられており、事業所の質や運営の安定性を左右する存在です。
管理者になれる要件とは?
厚生労働省の基準によると、居宅介護支援事業所の管理者には以下の要件があります。
介護支援専門員(ケアマネジャー)であること
基本的に、管理者は 介護支援専門員(ケアマネジャー)の有資格者であること が求められます。ケアプラン作成やサービス調整の専門性を理解していなければ、事業所全体を統括するのは難しいためです。
実務経験が求められる場合がある
法律上明確に「○年以上」とは規定されていませんが、実際にはケアマネ経験が浅い人が管理者を務めるのは難しく、一定の実務経験があることが望ましいとされています。法人によっては「ケアマネ経験3年以上」を条件とするケースもあります。
常勤であること
管理者は原則として 常勤職員 でなければなりません。非常勤や兼務での形だけの配置は認められず、実際に事業所運営に関わる必要があります。
兼務は可能なのか?
居宅介護支援事業所の管理者は、同時に「介護支援専門員」として利用者を担当することも可能です。
ただし、管理業務とケアマネ業務をバランスよくこなせる体制でなければ、現場に負担がかかりすぎる恐れがあります。
また、法人内で他の事業所の管理者を兼務することは基本的に認められていません。
1つの事業所に専任で配置されるのが原則です。
管理者の主な役割
管理者は単なる肩書きではなく、事業所の運営全体を支える役割を果たします。
具体的には以下のような業務があります。
- 職員の勤務管理や指導
- 介護サービスの質の管理
- 行政への報告や監査対応
- 利用者や家族からの苦情対応
- ケアマネ業務と事業所運営のバランス調整
つまり、管理者は「現場のリーダー」と「経営責任者」の両方の顔を持つ存在だといえます。
管理者に求められる資質
法律上の要件を満たすだけでなく、以下のようなスキルや姿勢も重要です。
- ケアマネ業務に関する高い知識と経験
- 職員をまとめるリーダーシップ
- 行政や他事業者と調整できるコミュニケーション力
- 経営感覚とコンプライアンス意識
こうした資質を持った人が管理者を務めることで、事業所は安定して運営され、利用者にとっても安心できる支援体制が整います。
管理者を選任する際の注意点
事業所が管理者を任命する際には以下の点に注意が必要です。
- 名義貸しなど形式的な管理者は認められない
- 常勤要件を満たす必要がある
- ケアマネ資格を持たない職員を管理者にすることはできない
- 法人全体の経営戦略を考慮して適任者を選ぶ
特に監査では「実際に管理者が業務を行っているか」がチェックされるため、形だけの配置はリスクが高いです。
まとめ
居宅介護支援事業所の管理者になるには、基本的に 介護支援専門員(ケアマネジャー)の資格を持ち、常勤で配置されること が要件となります。
実務経験やリーダーシップも重要な要素であり、単に資格を持っているだけでは務まりません。
- 管理者はケアマネ資格必須
- 常勤であることが条件
- 実務経験やリーダーシップが求められる
- 名義貸しや兼務は原則不可
管理者は事業所運営の要であり、その力量が利用者支援の質や法人の信頼性に直結します。
適任者を選び、安定した事業所運営を目指すことが大切です。















