【コピペOK】ALS(筋萎縮性側索硬化症)のケアプラン文例200事例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
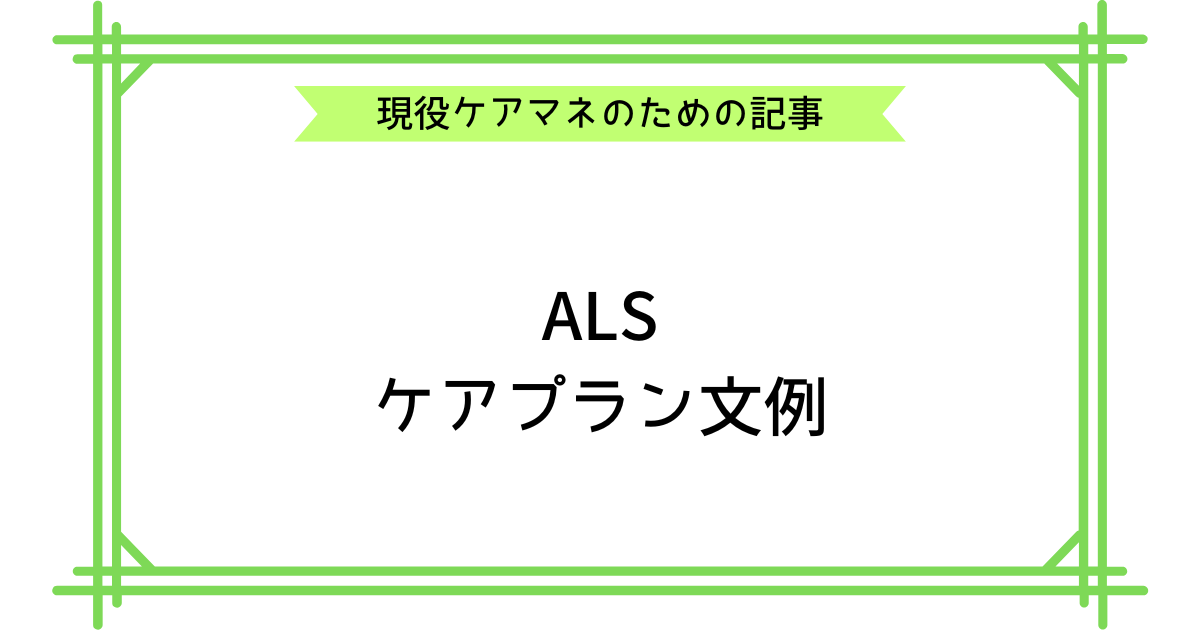
ALS(筋萎縮性側索硬化症)の利用者に対するケアプラン作成は、進行性の症状に応じて柔軟に対応していくことが求められます。
呼吸器管理、嚥下障害への対応、コミュニケーション支援、そして家族の介護負担軽減など、多面的な視点が必要です。
しかし、いざケアプランを書くとなると「どのような文例を書けばよいか迷う」というケアマネジャーも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、ALSのケアプランにそのまま活用できる【コピペOK】文例200事例を紹介します。
居宅サービス計画(ケアプラン)の長期目標・短期目標、サービス内容の具体的な記載例としてご活用ください。
目次
ALSケアプラン文例【1〜50事例】
- 進行性の筋力低下によりADLが制限されているが、必要な福祉用具を導入し、安全に生活できるよう支援する。
- 呼吸機能の低下に備え、訪問看護が定期的にSpO₂を測定し、主治医へ報告する。
- 嚥下障害により誤嚥リスクがあるため、STの指導に基づき食事形態を調整する。
- 食事摂取量が減少しているため、栄養士と連携し高カロリー補助食品を取り入れる。
- 筋力低下により歩行困難となったため、電動車椅子を導入し自立移動を支援する。
- 言語機能の低下に備え、コミュニケーションボードやICT機器を導入する。
- 家族の介護負担を軽減するため、訪問介護で入浴介助を導入する。
- 呼吸困難時に備えて、人工呼吸器導入の検討を進める。
- 痰の喀出困難があるため、吸引器を設置し、家族へ操作方法を指導する。
- 将来的な気管切開に備え、医師・看護師・家族間で意思決定支援を行う。
- 夜間の呼吸苦を軽減するため、在宅酸素療法を導入する。
- 嚥下困難が進行した場合に備え、胃ろう造設について医師と相談する。
- 言語が出にくくなっているため、タブレット端末で文字入力を活用する。
- 家族が安心して介護できるよう、訪問看護が日常的に指導を行う。
- 四肢筋力低下により更衣が困難なため、訪問介護で着替えを支援する。
- 排泄動作が難しくなっているため、ポータブルトイレやオムツを活用する。
- 介護者の休養を目的に、ショートステイを定期利用する。
- 進行予測に基づき、サービス担当者会議で支援方針を定期的に見直す。
- 痛みやこわばりがある場合は、訪問リハでストレッチを行う。
- 精神的な不安が強いため、心理的サポートを取り入れる。
- 呼吸リハビリを取り入れ、呼吸筋の維持を図る。
- 家族が吸引対応に習熟できるよう、訪問看護が継続的に指導する。
- 外出困難となっても社会参加を継続できるよう、オンライン交流を支援する。
- 嚥下機能が低下しても口腔ケアを徹底し、誤嚥性肺炎を予防する。
- 発話困難が進んでも意思伝達装置を活用し、意思を尊重する。
- 自宅改修を行い、介護ベッドやスロープを設置して安全性を高める。
- 嚥下体操を日課として取り入れ、摂食嚥下機能の維持を図る。
- 身体機能の低下に応じて介護サービス量を増やす。
- 緊急時に備えて、救急搬送時の連絡体制を整備する。
- 家族が孤立しないよう、地域包括支援センターと連携する。
- 夜間の吸引に対応するため、家族と訪問看護で当番体制を整える。
- 服薬管理を徹底し、副作用や体調変化を早期に発見する。
- ベッド上での褥瘡予防にエアマットを導入する。
- 意思決定支援会議を定期的に行い、本人の希望を尊重する。
- 医師・看護師・ケアマネ・家族が連携し、在宅療養を継続する。
- 入浴が困難となった場合は、訪問入浴を導入する。
- 嚥下障害が進行した際は、栄養補助食品を主食に切り替える。
- 身体拘縮を予防するため、関節可動域訓練を継続する。
- 訪問歯科を導入し、口腔内の清潔保持を支援する。
- 利用者と家族が将来に備えた介護方針を話し合える場をつくる。
- 呼吸器使用に伴う医療処置を訪問看護が支援する。
- 家族が24時間介護を担えるよう、定期的に介護技術を指導する。
- コミュニケーション困難を補うため、視線入力装置を導入する。
- 栄養状態を維持するため、医師・栄養士・看護師と連携する。
- 心理的安定を図るため、本人の希望する趣味活動を取り入れる。
- 呼吸器の設定確認を訪問看護が定期的に実施する。
- 在宅での療養を継続するため、介護ベッドを配置する。
- 服薬アラームを使用し、服薬忘れを防止する。
- ケアマネが定期的にサービスの調整を行い、過不足を防ぐ。
- 家族の負担軽減を目的に、レスパイトケアを定期導入する。
- 排痰困難時には吸引器を使用し、呼吸状態を安定させる。
- 進行に応じて、訪問看護の回数を柔軟に調整する。
- 終末期を見据え、本人・家族とACP(人生会議)を行う。
- 嚥下困難が増した場合には、食事姿勢を工夫して誤嚥を防ぐ。
- 家族が吸引や呼吸器操作を習得できるよう、繰り返し指導する。
- 在宅での生活継続を目指し、定期的に主治医とカンファレンスを行う。
- 進行に合わせ、移乗動作にリフトを導入する。
- 意思伝達装置を早期に導入し、意思疎通を保障する。
- 家族の介護負担を軽減するため、ヘルパーを追加配置する。
- 疲労が強い日は、活動量を調整し休養を優先する。
- 呼吸苦の症状を訴えた際は、訪問看護が即時対応できる体制を作る。
- 病状の進行に応じて、訪問リハビリを縮小または終了する。
- 嚥下障害により水分摂取が困難な場合は、とろみ剤を活用する。
- 家族が安心して介護を続けられるよう、定期的に心理的サポートを行う。
- 自宅療養を継続するため、地域の在宅医療体制を活用する。
- 介護ベッドを電動タイプに変更し、体位変換を容易にする。
- 医療処置が増える時期に備え、訪問看護ステーションと契約を強化する。
- 家族の不安軽減のため、24時間連絡体制を整える。
- 呼吸リハビリで呼吸筋の柔軟性を維持する。
- 意思決定の場に本人を必ず参加させ、尊厳を守る。
- 症状進行に合わせ、在宅から施設への移行も選択肢として共有する。
- 痰が多く苦しい場合は、体位ドレナージを取り入れる。
- 栄養状態を確認し、必要に応じて栄養補給食品を導入する。
- 排泄管理を強化し、便秘や失禁に適切に対応する。
- 家族が介護方法を実践できるよう、実技を交えて指導する。
- 意思疎通が困難な場合は、Yes/Noカードで対応する。
- ALSの進行状況を家族に随時説明し、不安軽減を図る。
- 定期的に呼吸器機器の動作確認を行い、トラブルを防ぐ。
- ケアマネが定期的にプランを見直し、最新の状態に対応する。
- 医師・訪問看護・リハ職と連携し、多職種チームで支援する。
- 精神的負担を軽減するため、カウンセリングを導入する。
- 家族の休養確保のため、定期的にショートステイを利用する。
- 外出困難でも生活に張りを持てるよう、趣味活動を取り入れる。
- 声が出にくくなった場合は、ボイスアンプを活用する。
- 呼吸苦の際には、吸引・体位調整で速やかに対応する。
- 意思決定が困難になる前に、終末期ケアについて話し合う。
- 服薬管理を徹底し、症状緩和に努める。
- 呼吸器装着後も在宅生活を継続できるよう支援する。
- 介護者が孤立しないよう、家族会や支援団体に参加を促す。
- 訪問歯科を導入し、口腔内を清潔に保つ。
- 栄養摂取が困難な場合は、胃ろう造設を検討する。
- 進行に備え、緊急連絡網を整える。
- 主治医の方針を家族と共有し、安心して療養できるようにする。
- 意思伝達が困難でも表情や目線を活用し、希望を尊重する。
- 在宅療養を支えるため、訪問介護の回数を増やす。
- 精神的安定のため、本人の好きな音楽を日常に取り入れる。
- 体位変換を定期的に行い、褥瘡を予防する。
- 呼吸器のトラブル時には、早急に医師へ連絡できる体制を整える。
- 医療機器導入後も家族が安心して対応できるよう指導する。
- 最期まで本人の意思を尊重し、在宅療養を支える。
- 身体機能の変化を定期的に評価し、ケアプランを更新する。
- ALSの進行に応じ、必要なサービス量を柔軟に調整する。
- 呼吸困難が強まった場合には、緊急往診体制を整える。
- 服薬後の副作用を観察し、医師へ報告する。
- 嚥下リハを継続し、少しでも摂食機能を維持する。
- 吸引が頻回になった際は、訪問看護の回数を増やす。
- 福祉用具貸与で身体負担を軽減する。
- 呼吸筋が弱まった際は、体位調整で呼吸を楽にする。
- 意思伝達装置を家族も操作できるよう練習する。
- 介護サービス導入により、家族の身体的負担を軽減する。
- 栄養補給を適切に行い、体重減少を予防する。
- 医師と連携し、進行予測を踏まえて介護計画を立てる。
- 嚥下困難が強い場合は、経管栄養への移行を検討する。
- 家族が不安を感じた際に、ケアマネが相談対応する。
- 医療処置を伴う介護に対応できるよう、訪問看護と協働する。
- 睡眠障害がある場合、生活環境を整備する。
- 呼吸器導入に備えて、家族に緊急対応を指導する。
- 地域の難病相談支援センターと連携する。
- コミュニケーション機器を複数導入し、環境に応じて使い分ける。
- 定期的に家族会議を開き、介護方針を共有する。
- 精神的サポートを受け、本人の不安を軽減する。
- 福祉用具導入により、入浴動作を安全に行う。
- 在宅酸素を導入し、呼吸の安定を図る。
- 摂食困難時には、主治医と栄養士が連携して対応する。
- ケアマネが月1回以上のモニタリングを実施する。
- 家族が体調を崩さないよう、介護サービスを適切に組み合わせる。
- 夜間の吸引に対応できるよう、訪問看護の夜勤体制を利用する。
- 呼吸状態に応じ、早期に呼吸器を導入する。
- 訪問介護で清潔保持を継続する。
- 意思決定を支えるため、情報を分かりやすく提供する。
- 栄養補助食品を利用し、摂食困難時でも栄養を確保する。
- 家族が吸引の技術を習得し、安心して在宅生活を続ける。
- ケアマネが関係機関と連携し、サービスを調整する。
- 医師との情報共有を密にし、急変時に迅速に対応する。
- 看取り期に向けた準備を家族と共有する。
- 医療処置が増えても家族の負担を軽減できるよう支援する。
- 嚥下障害に合わせて食事内容を随時変更する。
- 呼吸状態に応じて訪問看護の時間を調整する。
- 介護者の心身の疲労を軽減するため、レスパイトを活用する。
- 最期まで尊厳を守るケアを実施する。
- コミュニケーション困難な状態でも意思を尊重する。
- 医療依存度が高まっても在宅療養を継続する。
- 呼吸器導入後も生活の質を高める工夫を行う。
- ケアマネが常に最新情報を家族に提供する。
- 入浴困難時は清拭や部分浴で対応する。
- 家族に介護知識を提供し、安心感を高める。
- 嚥下訓練で少しでも自分で摂取できるよう支援する。
- 栄養状態を定期的に評価する。
- 医師との診察情報を家族と共有する。
- 看取り期の介護方法を事前に家族と確認する。
- 呼吸苦を軽減するため、体位を工夫する。
- 病状の進行を見越し、施設入所の可能性も含めて検討する。
- 意思伝達方法を早期に確立する。
- 訪問看護が中心となり医療処置を支援する。
- 服薬スケジュールを家族と共有する。
- 呼吸リハを継続し、少しでも呼吸筋を維持する。
- 嚥下困難が進んでも経口摂取を楽しめる工夫をする。
- 家族が孤立しないよう、地域の支援団体につなげる。
- 夜間の呼吸管理を強化する。
- 家族の介護力を評価し、必要なサービスを追加する。
- 医師・看護師と連携し、進行に応じた方針を決定する。
- 意思決定支援を繰り返し行い、本人の希望を反映する。
- 呼吸器トラブル時に迅速に対応できるよう家族に指導する。
- 終末期に備えて在宅医療と連携する。
- 家族の介護負担を評価し、定期的に調整する。
- コミュニケーション機器を更新し、使いやすい環境を整える。
- 栄養補給が困難になった場合は、点滴や経管栄養を導入する。
- 精神的サポートを受け、本人・家族の不安を軽減する。
- 呼吸状態が悪化した場合、酸素療法を強化する。
- 在宅で看取りを希望する場合、その準備を進める。
- ALSの進行を家族に丁寧に説明する。
- 家族の希望を尊重し、介護方針を一緒に考える。
- 呼吸苦があるときは早めに吸引を行う。
- 在宅生活を続けられるよう、ケアマネが全体調整を担う。
- 褥瘡予防を徹底し、清潔な環境を保つ。
- コミュニケーションの工夫で本人の意思を反映する。
- 緊急搬送時の対応を事前に確認しておく。
- 医療と介護が連携し、安心して暮らせる体制を整える。
- 家族の精神的支えになるよう、定期的に相談に応じる。
- 終末期ケアを本人の希望に沿って実施する。
- 呼吸器使用に伴う生活の変化を支援する。
- 嚥下機能の低下に応じて適切な介護方法を導入する。
- 意思疎通が難しい場合でも傾聴姿勢を大切にする。
- 家族に対してレスパイトケアを提供する。
- 緊急時の対応方法をマニュアル化して家族に渡す。
- ALSの進行を前提にした長期的な支援計画を作成する。
- 医師の診察を定期的に受け、ケア内容を調整する。
- 呼吸器導入に伴う生活費用を事前に説明する。
- 本人の尊厳を守り、希望を大切にしたケアを行う。
- 家族の体調管理にも配慮する。
- 福祉用具の導入を随時見直す。
- 訪問看護師と家族が情報を共有する仕組みを作る。
- 服薬の副作用を確認し、主治医に報告する。
- 呼吸器の安全確認を定期的に行う。
- 看取りの時期が近づいた場合は、家族に十分な説明を行う。
- 終末期に向けて痛みや不安を軽減するケアを優先する。
- 本人の希望を最優先にしたサービス調整を行う。
- 医療・介護チームで看取りケアを支援する。
- 最期まで尊厳ある生活を支え、本人と家族をサポートする。
- 在宅看取りを実現するため、24時間支援体制を整備する。
まとめ
ALS(筋萎縮性側索硬化症)のケアプランは、進行性疾患の特性上、呼吸管理・嚥下対応・意思疎通支援・家族支援・看取り支援 が必ず求められます。
今回紹介した200の文例は、そのまま活用できる【コピペOK】形式です。利用者一人ひとりの症状や希望に合わせてアレンジし、実際のケアプランに役立ててください。















