【おすすめ】ケアマネが読むべき小説を10冊紹介
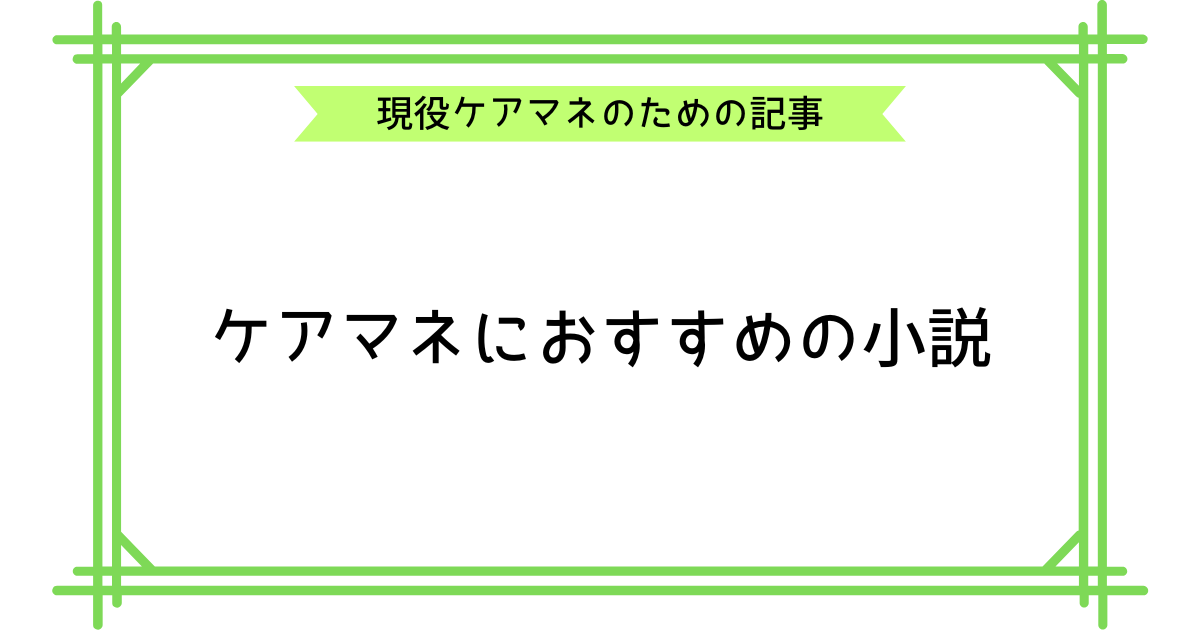
ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事は、制度や書類の知識だけでなく、利用者や家族の心情に寄り添うコミュニケーション力が求められます。
小説を読むことは、他人の人生や価値観を疑似体験できる貴重な学びの時間です。
物語を通じて「人の気持ちを理解する力」や「想像力」「共感力」を養うことができるため、日々のケアマネ業務にも大いに役立ちます。
本記事では、ケアマネに特におすすめしたい小説を10冊厳選して紹介します。
ケアマネが読むべきおすすめの小説
『1リットルの涙』 木藤亜也
難病に立ち向かう少女とその家族の姿を綴った実話。ケアマネとして関わる利用者の中には、病気や障害と向き合う方が多くいます。この作品を読むことで、本人や家族の「日常の小さな希望」や「絶望と再生の心情」をリアルに理解でき、支援における視点の幅が広がります。
『余命1ヶ月の花嫁』 武藤将吾
若くして病と向き合い、限られた時間をどう生きるかを描いた感動作。ケアマネは人生の終末期に関わることも多く、この小説を通じて「人は最後までどう生きたいか」というテーマを深く考えることができます。ターミナルケアの重要性を改めて実感できる一冊です。
『風が強く吹いている』 三浦しをん
駅伝を目指す学生たちの成長を描いた青春小説。介護の現場でも「チームワーク」が重要であり、この作品からは仲間と支え合う姿勢や、利用者・家族・多職種が協働するためのヒントを得ることができます。前向きな気持ちを取り戻せる作品です。
『ノルウェイの森』 村上春樹
人間の孤独や喪失感をテーマにした文学作品。ケアマネ業務では、利用者や家族の「心の孤独」と向き合う場面が少なくありません。この作品を読むことで「人はなぜ孤独を抱えるのか」という普遍的な問いに向き合い、より深い共感力を育むことができます。
『博士の愛した数式』 小川洋子
記憶が80分しかもたない数学者と、その周囲の人々の交流を描いた物語。認知症支援に関わるケアマネにとって、この小説は「記憶の消失に寄り添う」という視点を学ぶ機会となります。優しさと温かさに満ちた作品は、日常業務における関わり方のヒントになります。
『そして、バトンは渡された』 瀬尾まいこ
親が何度も変わる中で育った少女が、周囲の人々の愛情を受けながら成長する物語。家族の多様性や「血縁を超えた絆」がテーマであり、介護現場で多様な家族背景に対応するケアマネにとって大切な示唆を与えてくれます。
『ビタミンF』 重松清
家族の絆や葛藤をテーマにした短編集。利用者の家族関係に悩むことはケアマネ業務でもよくあることです。この作品は「家族の不完全さ」を優しく描いており、家族支援における柔軟な視点を養うことができます。
『ツナグ』 辻村深月
死者と生者をつなぐ「使者」を描いた物語。ケアマネは「人生の最期」に関わることも多く、死に対する価値観を考えるきっかけになります。人の想いに寄り添うことの大切さを再認識できる一冊です。
『流星ワゴン』 重松清
家族関係の修復や人生の再生をテーマにした感動作。介護現場でも「過去の後悔」や「家族との確執」に悩む利用者や家族に接することがあります。この小説は「許すこと」「受け入れること」の大切さを教えてくれます。
『火花』 又吉直樹
お笑い芸人の世界を舞台にした友情と葛藤の物語。ケアマネ業務はシビアな側面もありますが、この作品からは「人が夢を追いかける姿」「不器用でも生きる誠実さ」に触れることができます。利用者の「その人らしさ」に寄り添う視点を養える一冊です。
まとめ
ケアマネが読むべき小説は、単なる娯楽ではなく「利用者や家族に寄り添う力」を育む教材にもなります。
感動作から文学作品まで幅広いジャンルを読むことで、利用者の心情をより深く理解でき、ケアマネとしての成長につながります。
日々の業務に追われる中でも、ぜひ本記事で紹介した小説を手に取り、ケアマネとしての視野を広げてみてください。
























