【コピペOK】食事のケアプラン文例を100紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
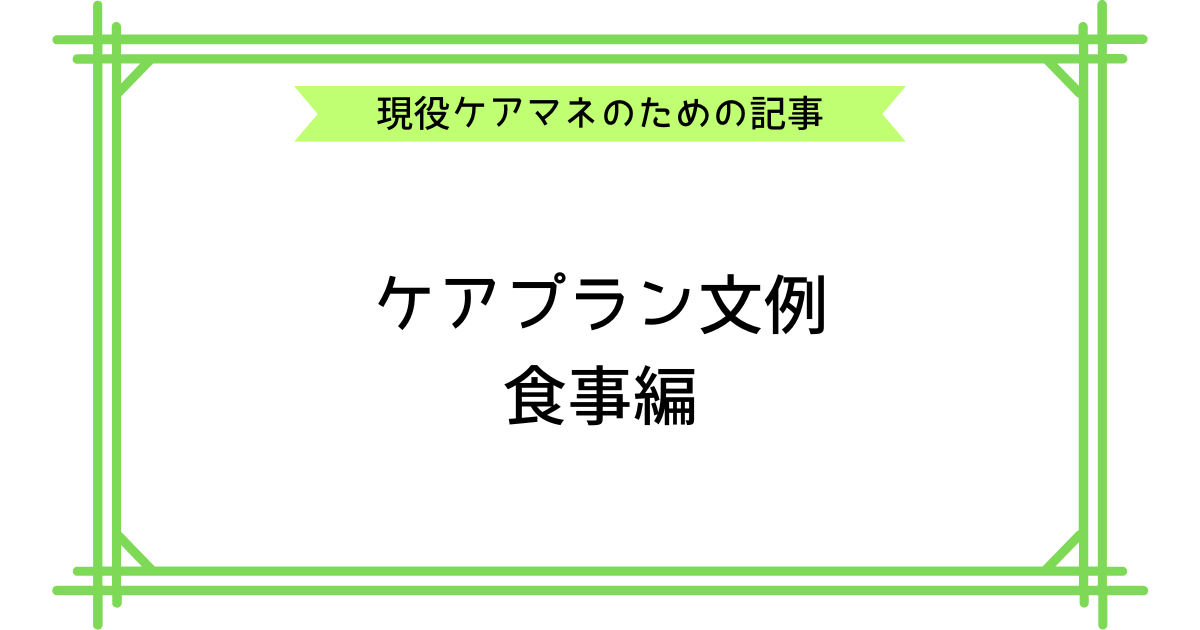
介護サービスを利用する高齢者にとって、食事は「栄養をとる」だけでなく「生活の楽しみ」の一つです。
しかし、嚥下障害や食欲低下、栄養バランスの乱れなど、さまざまな課題が発生しやすい領域でもあります。
そのためケアプランでは、栄養面・安全面・心理面のバランスを取りながら、食事支援の内容を具体的に記載する必要があります。
この記事では、食事に関するケアプラン文例を100事例 用意しました。
コピーしてすぐに使える文例集ですので、居宅・施設・通所などの場面でご活用ください。
目次
食事のケアプラン文例100
【基本的な食事支援】
- 毎食時に安全に食事がとれるよう見守りを行う。
- 食事前に手洗いを支援し、衛生面を保つ。
- 食事の前後に口腔ケアを行い、誤嚥性肺炎を予防する。
- 食事中は落ち着いた環境を整え、集中できるようにする。
- 本人の食事スピードに合わせて介助する。
- 食欲が低下している際は、少量から提供する。
- 本人が自分で食べられるよう、自立支援を優先する。
- 食事中に声かけを行い、楽しく摂取できるようにする。
- 食事の準備を一緒に行い、参加意欲を高める。
- 食後はゆっくり休養できるよう配慮する。
【姿勢保持・誤嚥予防】
- 食事中は30〜45度の角度で座位を保持する。
- 誤嚥防止のため、顎を引いた姿勢で食事をとれるよう支援する。
- 車椅子使用時はフットレストを調整し、安定した姿勢を確保する。
- 食事中は背もたれやクッションで体幹を支える。
- 食後30分は座位を保持し、逆流を防ぐ。
- 嚥下障害がある場合は、とろみをつけた飲み物を提供する。
- 誤嚥のリスクが高い食品は避けるよう調整する。
- 一口ごとに嚥下を確認しながら介助する。
- 咳き込みがあった際は一時中止し、落ち着いてから再開する。
- 食事時には吸引器を準備し、緊急対応できるようにする。
【嚥下訓練・リハビリ】
- 言語聴覚士の指導に基づき嚥下訓練を行う。
- 食前に口腔体操を実施し、嚥下機能を高める。
- 嚥下時の喉頭挙上を促す声かけを行う。
- 舌の運動を促すリハビリを取り入れる。
- 嚥下困難時は専門職と連携して食形態を調整する。
- 食事中に嚥下確認のため「ごっくん」声かけを行う。
- 飲水はストローを使用せず、コップから直接飲む練習を行う。
- 嚥下障害が重度の場合はペースト食を提供する。
- 食事姿勢や咀嚼方法を職員が指導する。
- 食後に声のかすれがある場合は嚥下評価を依頼する。
【栄養管理】
- 栄養士が献立を作成し、バランスの取れた食事を提供する。
- 低栄養予防のため、栄養補助食品を併用する。
- BMIを定期的に測定し、栄養状態を評価する。
- 血糖管理が必要なため、糖質量を調整する。
- 高血圧予防のため減塩食を提供する。
- 腎疾患に配慮し、タンパク質量を調整する。
- 脂質異常症に対応した献立を取り入れる。
- 食欲が低下している場合は嗜好を取り入れた食事を準備する。
- 水分補給をこまめに促し、脱水を予防する。
- 栄養評価を定期的に行い、必要に応じて医師に報告する。
【心理的支援・楽しみとしての食事】
- 食事を一緒に楽しむ雰囲気を作る。
- 食事中は肯定的な声かけを行い、意欲を高める。
- 本人の好きな料理を取り入れ、食欲を促す。
- 行事食や季節の料理を提供し、楽しみを増やす。
- 家族と一緒に食事を楽しむ機会を設ける。
- 食事に関する本人の希望を尊重する。
- 盛り付けを工夫し、食欲を刺激する。
- 食事の時間を本人の生活リズムに合わせる。
- 食器を本人が使いやすいものに変更する。
- 「美味しいね」と共感し、食事の喜びを共有する。
【自立支援】
- 自分でスプーンを持てるよう支援する。
- 箸が使いにくい場合はスプーン・フォークを提供する。
- 自助具を活用し、食事動作を支援する。
- 手の動きに合わせて食器の配置を工夫する。
- 食事の一部だけでも自立できるよう見守る。
- 本人が得意な動作を尊重し、できる範囲で自立を促す。
- 配膳の際に本人に選んでもらう。
- 食べやすい形態にカットして提供する。
- 飲み物は持ちやすいカップで提供する。
- 食事動作が成功したときは積極的に褒める。
【認知症対応】
- 食事の時間を繰り返し伝える。
- 迷っているときは食器を手渡しして促す。
- 食事の途中で中断しないよう、静かな環境にする。
- 食べ物を認識できるよう説明を行う。
- 食べる順番を一緒に確認する。
- 本人が安心できる位置に座席を配置する。
- 好きな料理から提供し、食欲を高める。
- 食事を忘れた場合はさりげなく促す。
- 「一緒に食べましょう」と声をかける。
- 食事を拒否した場合は無理強いせず時間をおく。
【安全・事故予防】
- 誤嚥のリスクをアセスメントし、対応を記録する。
- 食事中の窒息リスクを職員間で共有する。
- 飲み込みが不十分な場合は再度嚥下を確認する。
- 入れ歯の装着を確認してから食事を開始する。
- 食器の破損や誤飲を防ぐよう注意する。
- 食事中に急変した際の対応手順を職員間で統一する。
- 食後の嘔吐に備えて清潔物品を準備する。
- 水分摂取時には特に誤嚥に注意する。
- 食事中に姿勢が崩れたら直ちに修正する。
- 食事拒否が続いた場合は医師へ相談する。
【家族支援】
- 家族に食事中の介助方法を説明する。
- 家族に嚥下体操を一緒に行ってもらう。
- 家族と一緒に好物を持ち寄る機会を作る。
- 家族に水分補給の大切さを伝える。
- 家族に栄養バランスを考えた献立例を紹介する。
- 食事中の観察ポイントを家族に伝える。
- 家族に食事中のポジショニングを説明する。
- 家族に調理の工夫を提案する。
- 食事の様子を家族に報告し、安心してもらう。
- 家族と共に目標を共有し、一体的に支援する。
【将来を見据えた支援】
- 定期的に嚥下機能を評価する。
- 栄養状態を継続的にモニタリングする。
- 状況に応じて食形態を変更する。
- 食事の楽しみを維持できるよう工夫を続ける。
- 本人の希望に応じた食事内容を取り入れる。
- 栄養補助食品や経口補水液を必要時に導入する。
- 医師・栄養士・言語聴覚士と連携し対応する。
- 食事に関する本人・家族の意向を尊重する。
- 定期的にケアプランを見直す。
- 食事を通じて生活の質を高めることを目標とする。
まとめ
食事のケアプランでは、安全性・栄養管理・嚥下支援・心理的支援・家族連携 をバランスよく盛り込むことが重要です。
今回紹介した100文例は、そのままコピーしても、利用者の状況に応じてアレンジしても活用できます。
ケアプラン作成に悩んだときの参考にしていただき、利用者が安心して食事を楽しめる環境づくりにつなげてください。















