【ケアマネ必見】個別避難計画の作成事例とケアマネの役割を徹底解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
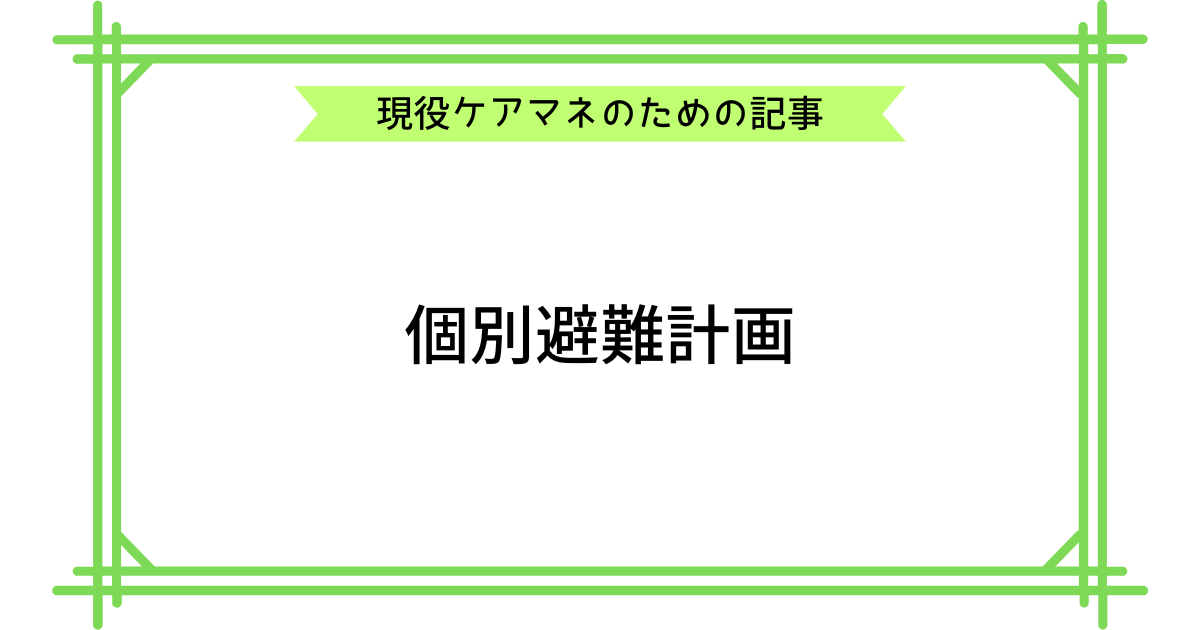
災害時に要配慮者の安全を確保するために重要なのが「個別避難計画」です。
特に高齢者や障害を抱える方の生活を支援するケアマネジャーにとって、計画の作成と活用は大きな役割となります。
しかし「具体的にどのように作成すればよいのか」「事例をどうプランに反映するのか」と悩むケアマネも多いでしょう。
この記事では、【個別避難計画の事例】と【ケアマネの実務での関わり方】を分かりやすく解説します。
実際のケアプラン作成にも活用できる事例を紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
個別避難計画とは?ケアマネに求められる役割
個別避難計画とは、災害時に自力避難が困難な要配慮者(高齢者、障害者、難病患者など)が、安全かつ迅速に避難できるように事前に作成される計画のことです。
市町村が主体となって推進していますが、日常的に本人の生活支援に関わるケアマネジャーが中心的な役割を担うことが多くなっています。
ケアマネの役割としては、
- 本人の心身状態・居住環境の把握
- 家族や地域住民、サービス事業者との連携
- 避難経路や避難方法の具体化
- ケアプランとの整合性確認
などが挙げられます。特に災害時は「誰が支援を行い、どのルートで避難し、どこに避難するか」を明確にしておくことが必須です。
個別避難計画をケアマネが関わる流れ
- 対象者の選定:市町村や地域包括支援センターから要支援者名簿が提供される。
- アセスメント:ケアマネが心身状態、移動手段、医療的ケアの有無を把握。
- 支援者の決定:家族・隣人・ボランティアなど、誰が避難を支援するかを明確化。
- 避難経路の確認:自宅から避難所までのルートを実際に確認。
- 計画書への反映:支援者・ルート・連絡体制を記録。
- ケアプランとの整合性:介護サービスと矛盾がないか確認。
- 訓練・見直し:防災訓練に参加し、定期的に更新。
個別避難計画の事例(ケアマネ視点)
事例1:独居高齢者で歩行困難
- 状況:80代女性、要介護2。杖歩行。家族は遠方。
- 個別避難計画:近隣住民2名が避難支援者として登録。避難時は車椅子を使用し、最寄りの小学校に避難。
- ケアマネの関与:平時から住民との顔合わせを行い、避難器具の設置を市に依頼。
事例2:認知症のある利用者
- 状況:70代男性、要介護3。徘徊傾向あり。
- 個別避難計画:家族と訪問介護員が協力。避難所では徘徊予防のために区画を分けてもらうよう事前に調整。
- ケアマネの関与:本人が混乱しないよう、日常的に避難ルートを散歩の経路に組み込み習慣化。
事例3:在宅酸素を利用する利用者
- 状況:60代男性、要介護2。COPDで在宅酸素療法中。
- 個別避難計画:避難先に電源が確保できるか確認。発電機が利用可能な福祉避難所を指定。
- ケアマネの関与:医師と市役所に情報提供を依頼し、電源確保手段を記録。
事例4:集合住宅で車いす生活
- 状況:要介護4女性。集合住宅の3階に居住。
- 個別避難計画:マンション管理組合と連携し、災害時は管理人と住民2名が介助。
- ケアマネの関与:管理組合会議に参加し、エレベーター停止時の避難方法を検討。
ケアマネが注意すべきポイント
- 本人の同意と尊厳の尊重:計画は本人の意思を反映することが重要。
- 関係機関との連携:地域包括、消防、自治会との連携を強化。
- ケアプランとの統一性:介護サービスと矛盾しない計画にする。
- 定期的な見直し:状態変化や災害対策の更新に合わせて修正。
まとめ
「個別避難計画」は、要介護者や要支援者の命を守る大切な仕組みです。
ケアマネジャーは、普段のケアプランとあわせて計画作成を進めることで、災害時のリスクを大幅に軽減できます。
本記事で紹介した事例を参考に、地域や本人の状況に合わせて活用してください。















