介護保険の訪問リハビリは複数事業所で利用できる?制度上のルールを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
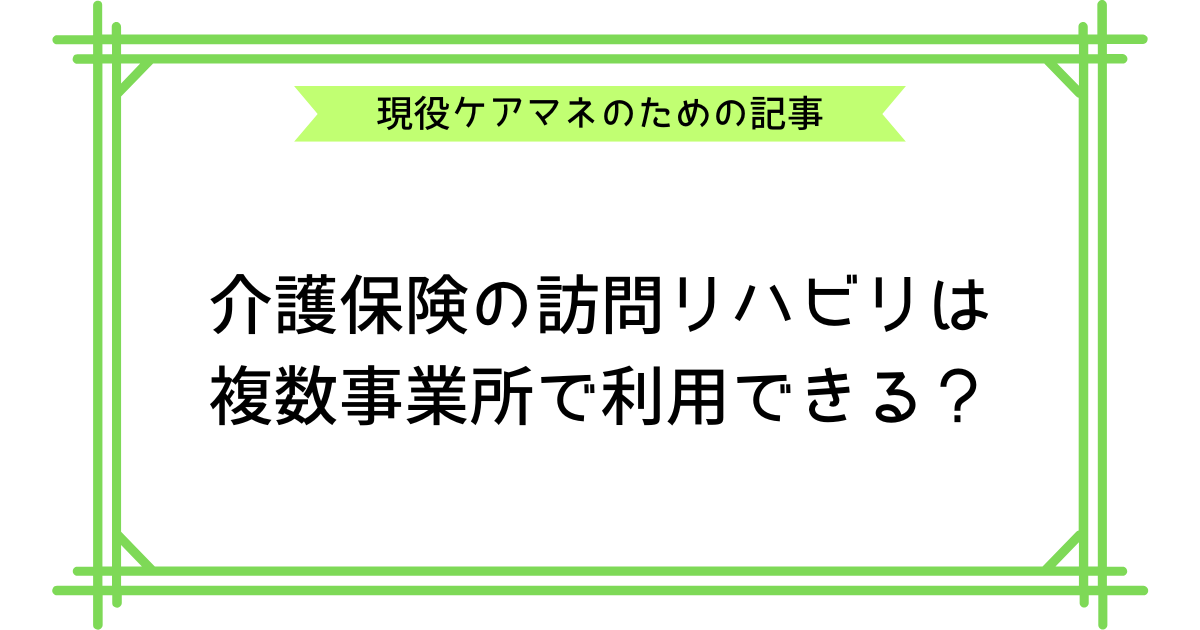
自宅での生活機能の維持・向上を目的に利用できる「訪問リハビリテーション」。
医師の指示のもと、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)が自宅を訪問し、心身の機能訓練や日常生活動作の指導を行います。
しかし利用者や家族からよく質問されるのが、「訪問リハビリを複数の事業所から利用できるのか?」 という点です。実際には、制度上のルールやケアプランの位置づけにより利用可否が決まります。
本記事では、介護保険における訪問リハビリの複数事業所利用について、制度の根拠を踏まえて詳しく解説します。
目次
訪問リハビリの基本ルール
- 介護保険の居宅サービスに位置づけられる
- 事業所の医師の指示書(場合によって診療情報提供書)が必要
- 週の利用回数や単位数には上限あり(地域区分・状態により異なる)
- ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいて利用する
つまり「医師の指示」と「ケアプラン上の必要性」が利用条件になります。
訪問リハビリは複数事業所で利用できるのか?
結論としては、特別な理由がある場合のみ、複数の事業所から訪問リハビリを利用することが可能です。
原則
- 訪問リハビリは基本的には1事業所のみでの利用が前提。
例外的に認められるケース
- 専門性が異なるリハビリが必要な場合
(例:言語聴覚士による嚥下訓練と、理学療法士による歩行訓練を並行して受けたい) - 医療機関と在宅リハ事業所の両方を組み合わせる必要がある場合
(例:退院直後は病院併設の訪問リハを継続し、在宅生活が安定したら地域の訪問リハを追加) - 地理的・訪問上の制限があり、一つの事業所だけでは対応が難しい場合
これらの場合には、主治医・ケアマネジャー・事業所間の調整が必要になります。
制度上の留意点
ケアプランの位置づけ
複数事業所を利用する場合、ケアマネジャーはケアプランに「なぜ複数必要なのか」を明確に記載する必要があります。単に「利用者が希望したから」では認められません。
医師の指示書
訪問リハは医療系サービスのため、医師の指示が必須です。複数利用の場合でも、主治医がその必要性を認め、指示書を発行する必要があります。
給付管理
介護給付費請求では、同一利用者に複数の訪問リハを算定する場合、重複や単位超過がないか厳格にチェックされます。ケアマネジャーは給付管理業務を慎重に行う必要があります。
複数利用のメリットとデメリット
メリット
- 複数の専門職から多角的にリハビリを受けられる
- 病院併設リハと在宅リハを組み合わせることで切れ目ない支援が可能
- 利用者の希望に柔軟に対応できる
デメリット
- サービス調整が複雑になる
- ケアマネジャーや事業所間の連携不足で重複や抜け漏れが起こりやすい
- 主治医の指示書や給付管理に手間がかかる
併用が難しいケース
- 同じ内容のリハビリを複数事業所で受けたい場合
- 単に利用枠を増やすための併用(制度上認められない)
- ケアプランに合理的な理由を示せない場合
まとめ
- 訪問リハビリは介護保険で利用できるサービスだが、原則は1事業所のみ
- ただし「専門性が異なるリハビリが必要」「医療機関と在宅リハを組み合わせる必要がある」などの場合は、複数事業所の利用も可能
- 利用には 主治医の指示・ケアプランへの明記・事業所間の連携 が不可欠
- ケアマネジャーは給付管理と説明責任を果たす必要がある
利用者や家族が「もっとリハビリを受けたい」と希望した場合には、まずは主治医とケアマネジャーに相談し、複数利用の必要性を検討することが大切です。















