【ケアマネがコピペで使える】腎疾患のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
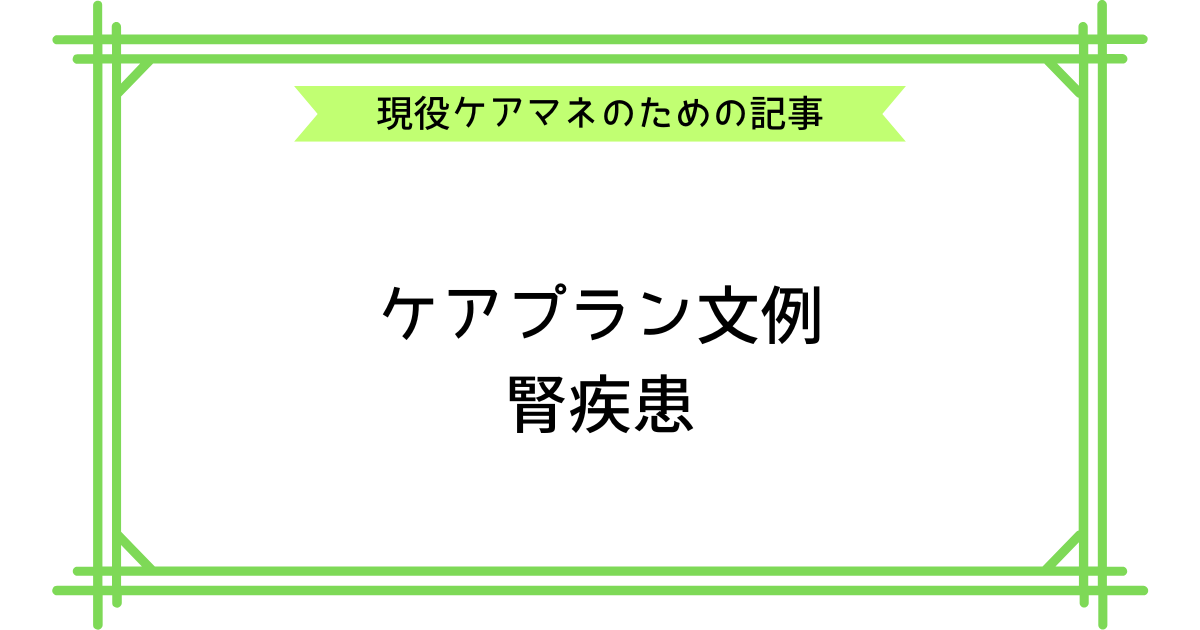
腎疾患(慢性腎不全、腎炎、人工透析導入前後など)は、食事・水分制限や服薬管理、通院支援が欠かせず、在宅生活の維持には多角的なケアが必要です。症状が安定していても急変リスクが高いため、ケアマネジャーは 医療・介護・家族の連携 を重視したケアプランを作成することが求められます。
本記事では、腎疾患を持つ方へのケアプラン文例を 100事例 紹介します。コピペできる形式でまとめていますので、そのまま使えるのはもちろん、利用者の状態に応じてアレンジしてご活用ください。
目次
症状・体調管理に関する文例
- 毎日の血圧・体重測定を行い、変化を記録する。
- 浮腫の有無を観察し、異常があれば医師に報告する。
- 倦怠感や息切れなどの自覚症状を確認する。
- 血液検査の結果を医師と共有し、療養に反映する。
- 排尿状態を観察し、変化を記録する。
- 呼吸苦が出現した場合は安静を保ち、主治医へ連絡する。
- 夜間の尿量やトイレ回数を確認し、日常生活に反映する。
- バイタル測定を定期的に行い、訪問看護師と共有する。
- 体重増加が急激な場合は受診を促す。
- 疲労感が強いときは活動を控え、休養を優先する。
- 不眠が続く場合は医師へ相談する。
- 貧血症状が出ていないか観察する。
- 嘔気・嘔吐があれば速やかに対応する。
- 食欲の変化を確認し、栄養管理に反映する。
- 下肢のむくみを観察し、写真で記録する。
- 呼吸状態を毎日確認し、異常があれば家族に報告する。
- 血圧上昇時は食塩摂取量を確認する。
- 日々の症状を日記に残し、通院時に医師へ伝える。
- 定期的な健診を受け、合併症の早期発見を図る。
- 体調変化に応じて介護サービスを柔軟に調整する。
食事・水分管理に関する文例
- 栄養士の指導をもとに、腎疾患に適した食事を準備する。
- 塩分制限を守れるよう、減塩調味料を使用する。
- タンパク質摂取量を調整し、腎機能に配慮する。
- カリウム制限に合わせた食材を選ぶ。
- リンを抑えた食事を意識する。
- 外食時も制限を考慮したメニューを選ぶ。
- 水分制限を守るため、家族と協力して管理する。
- 水分量を記録し、制限値を超えないようにする。
- 果物や野菜の摂取に注意し、カリウム値を管理する。
- 食事量を日誌に記録し、栄養士と共有する。
- 少量でも満足できるよう、見た目を工夫した料理を提供する。
- 間食を制限し、栄養バランスを保つ。
- 甘い飲料を控え、無糖の水分を選ぶ。
- 水分を氷片などで工夫して摂取する。
- 料理に出汁や香辛料を使い、減塩でも満足感を得られるようにする。
- 家族も一緒に減塩食を実践する。
- 栄養補助食品を取り入れ、栄養不足を補う。
- 調理方法を工夫し、油分を減らす。
- 制限食を本人が無理なく続けられるよう支援する。
- 食事制限を本人と家族で共有し、継続を図る。
服薬・通院支援に関する文例
- 医師の指示に従い、毎日の服薬を継続する。
- 服薬カレンダーを使用し、飲み忘れを防止する。
- 薬の残量を確認し、切らさないよう管理する。
- 家族と連携し、服薬を見守る。
- 医師から処方変更があった場合はすぐに反映する。
- 副作用の有無を観察し、医師に報告する。
- 通院日をカレンダーに記録し、忘れずに受診する。
- 通院時は家族が付き添い、説明内容を共有する。
- 血液検査結果を整理し、次回受診時に持参する。
- 薬剤師の服薬指導を受け、正しい服薬を習慣化する。
- 訪問看護師が服薬管理を確認する。
- 自己管理が困難な場合は家族が代行する。
- 通院負担を軽減するため、送迎支援を導入する。
- 医師の指示に従い、エリスロポエチン注射を適切に実施する。
- 腎代替療法について説明を受け、今後に備える。
- 受診前に体調や症状をまとめて医師に伝える。
- 訪問診療を導入し、通院負担を軽減する。
- 医療者と連携し、服薬管理を徹底する。
- 家族も服薬内容を理解できるよう説明を受ける。
- 定期通院を継続し、病状安定を図る。
日常生活支援に関する文例
- 活動と休養のバランスを取り、疲労をためないようにする。
- 睡眠環境を整え、夜間の安眠を確保する。
- 入浴は体調に応じて清拭に切り替える。
- 排泄時の負担を軽減するため、動線を整備する。
- 家事負担を軽減するため、訪問介護を導入する。
- 外出時は体調を確認し、短時間で行う。
- 屋内移動を安全に行えるよう、手すりを設置する。
- 転倒を防ぐため、動線上の障害物を整理する。
- 服薬・食事制限を含めた生活習慣を支援する。
- 疲労が強い日は介助を増やす。
- 趣味や余暇活動を通じて生活意欲を高める。
- 気分転換の外出を家族と一緒に行う。
- デイサービスを利用し、社会交流を維持する。
- 訪問リハビリを導入し、体力維持を図る。
- 季節に応じた温度管理を徹底する。
- 感染症予防のため、日常生活に衛生習慣を取り入れる。
- 日々の生活動作を無理なく継続できるよう工夫する。
- 疲れやすい体質に合わせ、日課を柔軟に調整する。
- 本人の希望を尊重した生活スタイルを支援する。
- 在宅生活を継続できるよう、多職種で支援する。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に腎疾患の特徴を説明し、理解を深める。
- 家族に食事・水分制限の重要性を説明する。
- 家族が調理方法を学び、減塩食を準備できるよう支援する。
- 家族に水分制限の工夫を伝える。
- 家族が服薬管理を見守れるようにする。
- 緊急時の対応方法を家族に説明する。
- 家族に腎代替療法の選択肢を説明する。
- 家族会議を開き、介護方針を共有する。
- 家族の介護負担を軽減するため、訪問介護を導入する。
- 家族の休養を確保するため、ショートステイを活用する。
- 家族が安心して介護できるよう、医療職と連携する。
- 家族に相談窓口を紹介する。
- 家族に腎疾患の再発予防について説明する。
- 家族の心理的支援を行い、不安を軽減する。
- 介護知識を家族に提供し、支援体制を整える。
- 緊急連絡体制を整備し、家族と共有する。
- 家族と共に生活リズムを整える。
- 家族に透析の見学を勧め、理解を深める。
- 医療・介護サービスを組み合わせ、在宅療養を継続する。
- 本人と家族が安心して生活できるよう、環境を整備する。
まとめ
腎疾患のケアプランは、 症状管理・食事制限・服薬管理・生活支援・家族支援 を組み合わせることが不可欠です。今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーがそのままコピーして活用できるよう整理しました。
利用者の体調や生活環境に応じて文例を選び、最適なケアプランを作成してください。















