【ケアマネがコピペで使える】進行性核上性麻痺のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
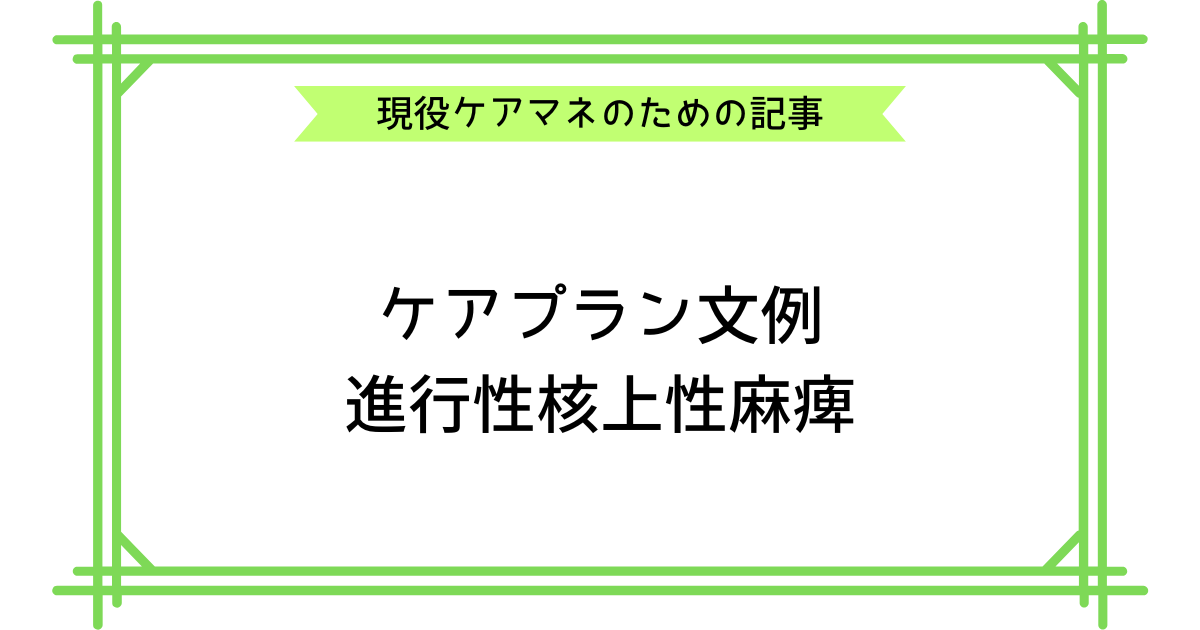
進行性核上性麻痺(PSP)は、進行性の神経変性疾患であり、特徴的な症状として 歩行障害・転倒・眼球運動障害・嚥下障害・認知機能低下 などが見られます。症状は徐々に進行するため、利用者本人と家族が安心して暮らせるよう、早期からの環境整備や多職種連携が欠かせません。
ケアマネジャーは、転倒リスクの高い生活動線の工夫や、嚥下障害への配慮、家族の介護負担軽減などを考慮したプランを立案することが重要です。
本記事では、進行性核上性麻痺の利用者に対応できるケアプラン文例を 100事例 紹介します。コピペでそのまま活用できるよう整理しました。
目次
運動機能・転倒予防に関する文例
- 理学療法士の指導に基づき、歩行訓練を継続する。
- 転倒リスクを軽減するため、室内の段差を解消する。
- 歩行補助具(シルバーカー、歩行器)を使用する。
- ベッドからの立ち上がり時に声かけを行う。
- 急な方向転換を避け、動作をゆっくり行うよう支援する。
- バランス練習を取り入れ、体幹機能を維持する。
- 転倒予防のため、床に滑り止めマットを敷く。
- 夜間トイレ時には家族が付き添う。
- 外出時は必ず介助者が同伴する。
- 歩行困難時は車椅子を導入する。
- 繰り返しの転倒歴を記録し、原因を分析する。
- 動線上の家具を減らし、移動を安全にする。
- 居室に手すりを設置する。
- 体調に合わせて活動量を調整する。
- リハビリを通じて関節拘縮を予防する。
- 移動時は必ず声かけを行い、注意を促す。
- 転倒による骨折リスクを軽減するため、転倒検知センサーを導入する。
- 座位保持の訓練を継続する。
- 車椅子のブレーキを確実に確認する習慣をつける。
- 安全を最優先にし、介助を増やして転倒を防ぐ。
日常生活動作の工夫に関する文例
- 食事動作を補助し、自助具を活用する。
- 入浴はシャワーチェアを用いて安全に行う。
- 排泄時はポータブルトイレを活用する。
- 就寝時にナースコールを手元に置く。
- 更衣動作を小分けにし、疲労を軽減する。
- 衣類は着脱しやすいものを選ぶ。
- 体力に合わせて清拭を行い、清潔保持を支援する。
- ベッド周囲を整理整頓し、起居動作を容易にする。
- 食器を工夫し、握力が弱くても使用できるものを準備する。
- 入浴介助を受けながら本人の自立を尊重する。
- 日常生活動作の習慣を繰り返し支援する。
- トイレまでの動線を短縮し、安全性を高める。
- 日中の活動を短時間で区切り、休養を取り入れる。
- 電動ベッドを活用し、起き上がりを容易にする。
- 室温・湿度を一定に保ち、体調を整える。
- 食事・排泄・更衣などは同じ時間に行い、生活リズムを安定させる。
- 移乗介助は安全第一で行う。
- 生活動作の記録をつけ、改善点を見直す。
- 自立できる部分は本人に任せ、達成感を得られるようにする。
- 介助量を柔軟に調整し、負担を最小限にする。
嚥下・言語支援に関する文例
- 言語療法士の指導に基づき、発声訓練を行う。
- 会話時は本人の正面に座り、ゆっくり話す。
- 筆談やコミュニケーションボードを活用する。
- 会話内容を短く区切り、理解を助ける。
- 食事は誤嚥防止のためソフト食にする。
- 水分にはトロミをつけて提供する。
- 食事中は姿勢を正し、30分間座位を保持する。
- 嚥下体操を日課とする。
- 食事中は会話を控え、誤嚥を予防する。
- 咳やむせ込みが頻繁にあれば医師へ報告する。
- 胃瘻造設について医師と家族で検討する。
- 言語訓練の成果を家族と共有する。
- 吐き気や食欲不振がある場合は栄養補助食品を活用する。
- 食事は少量ずつ、時間をかけて行う。
- 嚥下機能の変化を定期的に評価する。
- 言語表出が困難な場合は代替コミュニケーション手段を導入する。
- 声が出にくい時は、家族が繰り返し確認する。
- 食事中の環境を静かにし、集中できるようにする。
- 本人の希望に沿った食事形態を検討する。
- 嚥下支援を通じて誤嚥性肺炎を予防する。
心理・社会参加支援に関する文例
- 趣味活動を継続し、生活の張りを持つ。
- デイサービスに参加し、社会的交流を維持する。
- 孫や家族との交流時間を増やす。
- 不安や抑うつに対して傾聴を行う。
- 必要に応じて心理士によるカウンセリングを導入する。
- 気分転換のため、屋外活動を計画する。
- 季節ごとの行事に参加できるよう支援する。
- 同じ疾患を持つ人との交流機会を提供する。
- 本人が望む活動を可能な範囲で実現する。
- 生活意欲を高めるため、役割を与える。
- 音楽や読書などの余暇活動を取り入れる。
- デイケアで仲間との交流を促進する。
- 家族と一緒に外食や買い物を計画する。
- 精神的ストレスを軽減するため、環境を整える。
- 家族との会話時間を意識的に増やす。
- ビデオ通話を活用し、遠方の家族と交流する。
- 季節のイベントに参加し、楽しみを持つ。
- 社会参加の機会を確保する。
- 日常生活の中で達成感を得られる活動を取り入れる。
- 精神的支援を通じて安心感を提供する。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に進行性核上性麻痺の特徴を説明する。
- 家族が介助方法を学べるように指導する。
- 家族会議を開き、介護方針を共有する。
- 家族の介護負担を軽減するため、訪問介護を導入する。
- 家族の休養を確保するため、ショートステイを活用する。
- 緊急時の対応方法を家族に伝える。
- 家族の心理的支援を行う。
- 医療者・介護者と家族の連携を強化する。
- 家族に嚥下・言語障害への対応方法を伝える。
- 家族の介護負担を定期的に確認する。
- 居室に手すりを設置し、安全を確保する。
- 照明を明るくし、転倒リスクを軽減する。
- 車椅子が使用できるよう、段差を解消する。
- 浴室環境を整え、介助しやすいようにする。
- ベッド周囲を整理し、安全に起居できるようにする。
- 医療・介護サービスを組み合わせ、在宅生活を継続する。
- 家族に相談窓口を紹介する。
- 家族にレスパイトケアを提供する。
- 本人と家族が安心して暮らせるよう、環境調整を行う。
- 利用者と家族が尊厳を持って生活できるよう包括的に支援する。
まとめ
進行性核上性麻痺は、転倒や嚥下障害などにより生活が大きく制限される疾患です。ケアプランでは 転倒予防・日常生活動作の工夫・嚥下と言語支援・心理的ケア・家族支援 を多面的に取り入れることが大切です。
今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーがそのまま活用できる形で整理しています。利用者の病状や希望に合わせて組み合わせ、実効性のあるケアプランを作成してください。















