ソーシャルワーカーとケアマネジャーの連携とは?役割と協働の重要性を解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
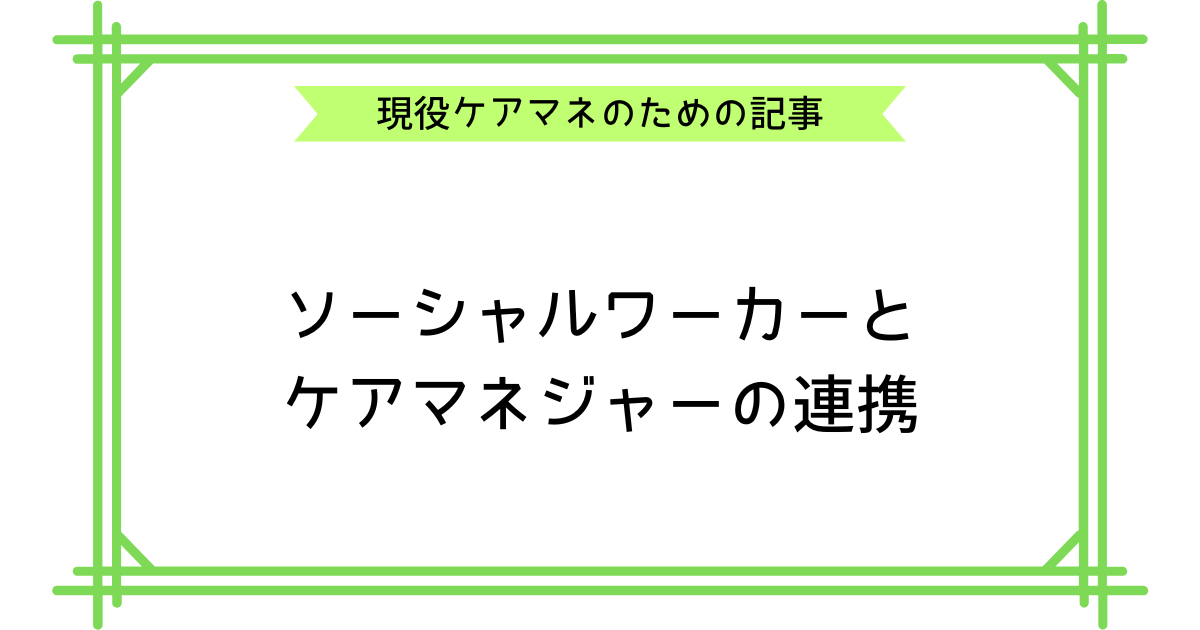
介護や医療の現場では、ソーシャルワーカー と ケアマネジャー(介護支援専門員) が連携して利用者・家族を支援する場面が多くあります。
両者の専門性は異なりますが、協力することでより包括的で質の高い支援が可能になります。
この記事では、それぞれの役割の違いと連携の具体的な方法、実際の場面での活用例、そして課題と今後の展望について解説します。
目次
ソーシャルワーカーとケアマネジャーの役割の違い
ソーシャルワーカー
- 医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士、社会福祉士などを含む
- 社会的課題の解決 を専門とする
- 医療費、生活費、就労、住宅、福祉制度の利用など、生活全般を支援
- 病院や地域包括支援センター、行政機関などで活躍
ケアマネジャー
- 介護保険制度に基づき、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成
- 介護サービスの調整役 として、介護事業所や医療機関と連携
- 利用者の自立支援・QOL向上を目的に、介護サービスの利用をコーディネート
👉 ソーシャルワーカー=「社会資源の専門家」
👉 ケアマネジャー=「介護サービスの調整役」
ソーシャルワーカーとケアマネジャーの連携が必要な理由
- 包括的な支援の実現
ケアマネは介護サービス中心、ソーシャルワーカーは生活全般中心。両者の視点を組み合わせることで、利用者支援がより充実する。 - 制度横断的な支援
介護保険だけでなく、医療保険、生活保護、障害福祉などの制度を活用できるようになる。 - 家族支援の強化
介護負担や経済問題など、ケアマネだけでは対応しきれない課題にソーシャルワーカーが対応できる。 - 在宅生活の継続を支える
医療・介護・福祉を横断的に支えることで、入退院や在宅療養がスムーズになる。
具体的な連携の場面
1. 退院支援
- 医療ソーシャルワーカーが病院で退院調整を行い、ケアマネに情報を共有
- ケアマネが在宅での介護サービスを調整し、スムーズな在宅生活へつなげる
2. 経済的・制度的課題
- 利用者が介護サービス利用料の支払いに困難を抱えている場合
- ソーシャルワーカーが生活保護・高額介護サービス費・助成制度などを紹介
- ケアマネが制度を反映したケアプランを作成
3. 虐待や権利擁護
- ケアマネが虐待や不適切な介護に気づいた際、ソーシャルワーカーと連携して対応
- 行政機関や地域包括へのつなぎを強化
4. 家族支援・レスパイトケア
- ケアマネが介護者の負担を把握し、ソーシャルワーカーが心理的・社会的サポートにつなげる
連携のメリットと課題
メリット
- 利用者の 生活全般に対応できる
- 制度の狭間に落ちにくくなる
- 家族の安心感が増す
- 支援者の負担分散につながる
課題
- 情報共有が不十分になりやすい
- 役割分担が曖昧になる場合がある
- 連携体制が事業所や地域によって差がある
まとめ
ソーシャルワーカーとケアマネジャーの連携は、利用者・家族にとって大きなメリットがあります。
- ソーシャルワーカー=生活全般を支える専門職
- ケアマネジャー=介護サービスを調整する専門職
- 両者が連携することで「包括的で切れ目のない支援」が可能になる
現場では、退院支援や経済的支援、権利擁護などでの連携が特に重要です。課題もありますが、情報共有や役割分担を意識することで、より質の高いケアマネジメントにつながります。















