入院中のアセスメントをケアマネはどう行う?退院後につなげるポイントを解説
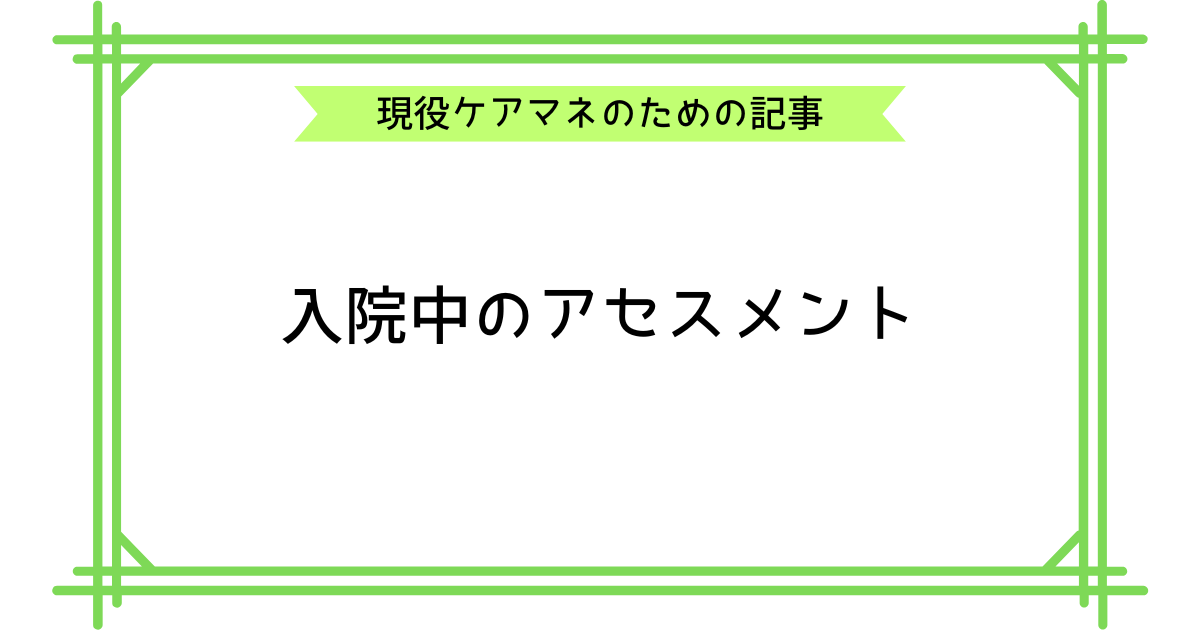
利用者が入院したとき、ケアマネジャー(介護支援専門員)はどのように関わり、どのようなアセスメントを行うのでしょうか?
「入院中は病院に任せるだけ」と思われがちですが、退院後の生活を支えるためにケアマネが関与することは非常に重要です。
この記事では、入院中にケアマネが行うアセスメントの内容や、その後のケアプラン作成へのつなげ方を詳しく解説します。
ケアマネが入院中に関わる意義
入院は、利用者の生活や心身状態が大きく変化するタイミングです。
入院前の状態に戻るとは限らず、退院後は新たな介護ニーズが生じることもあります。
ケアマネは入院中から情報収集やアセスメントを行うことで、退院後の在宅生活や施設生活へスムーズにつなげることができます。
特に高齢者の場合、入院をきっかけにADL(日常生活動作)が低下し、以前の生活に戻れないことも少なくありません。
早期から関与し、医療職や家族と情報を共有することが、退院後の生活を支える大きなポイントになります。
入院中にケアマネが行うアセスメントの流れ
1. 入院時の情報収集
- 入院の経緯(病名、手術や治療の有無)
- 入院前のADL・生活状況(歩行、排泄、食事、入浴など)
- 服薬内容や既往歴
- 家族の介護力、在宅環境(住宅改修の有無、福祉用具の利用状況など)
これらの情報を把握することで、退院後に必要となる介護サービスの方向性が見えてきます。
2. 医療職との連携
病棟看護師やMSW(医療ソーシャルワーカー)、リハビリ職などと連携し、入院中の回復見込みや医療的ケアの継続の有無を確認します。経管栄養や在宅酸素、褥瘡ケアなどが必要になる場合は、在宅で対応できるかどうかを早めに調整する必要があります。
3. 家族への聞き取り
退院後の生活場所(自宅か施設か)、家族の介護体制、希望する生活の形などを確認します。介護力の不足が予想される場合は、入院中からサービス調整を検討しておくことが大切です。
4. 退院支援カンファレンスへの参加
病院で開かれる退院前カンファレンスに参加し、本人・家族・医療職と一緒に退院後の生活について話し合います。ケアマネは介護の専門家として、在宅介護や施設入所の選択肢を示し、ケアプランの方向性を提案します。
入院中のアセスメントで重視すべき視点
- 心身機能の変化:入院前と比べてどの程度ADLが低下しているか
- 医療的ニーズ:退院後も続く医療処置があるかどうか
- 生活環境:自宅での生活が可能か、住宅改修や福祉用具は必要か
- 介護力:家族の介護力や協力体制に変化はないか
- 本人・家族の意向:どのような生活を望んでいるのか
これらを整理することで、退院後の介護サービス導入や施設選択がスムーズになります。
入院中のアセスメントが退院後にどうつながるか
ケアマネが入院中から積極的にアセスメントを行うことで、次のようなメリットがあります。
- 退院直後にサービスが途切れず開始できる
- 自宅退院か施設退院かを早めに判断できる
- 医療と介護の連携不足によるトラブルを防げる
- 家族の不安を軽減できる
例えば、退院後に自宅での生活を希望する場合、訪問看護や訪問介護、福祉用具レンタルなどを事前に手配できます。施設入所を希望する場合も、入院中から情報収集と調整を始めることでスムーズに移行できます。
ケアマネが入院中にできないこと
ケアマネは介護支援専門員であり、医療行為を直接行うことはできません。
点滴や吸引、処置などは医師や看護師の役割です。また、病院内でのケア方針を決定するのも主治医であり、ケアマネはその情報を基に退院後の生活支援を整える立場にあります。
まとめ
ケアマネは入院中からアセスメントを行い、退院後の生活に必要な介護サービスを調整する重要な役割を担っています。
入院中の情報収集や多職種連携、退院支援カンファレンスへの参加を通じて、退院後のケアプランがスムーズに進むように支援します。
「入院中のアセスメントなんて必要なの?」と思う方もいますが、退院後の生活の質を大きく左右する大切なプロセスです。
介護に不安を感じたら、ケアマネに早めに相談することが安心につながります。















