ケアマネの担当利用者が少ない!新規獲得方法を教えます!
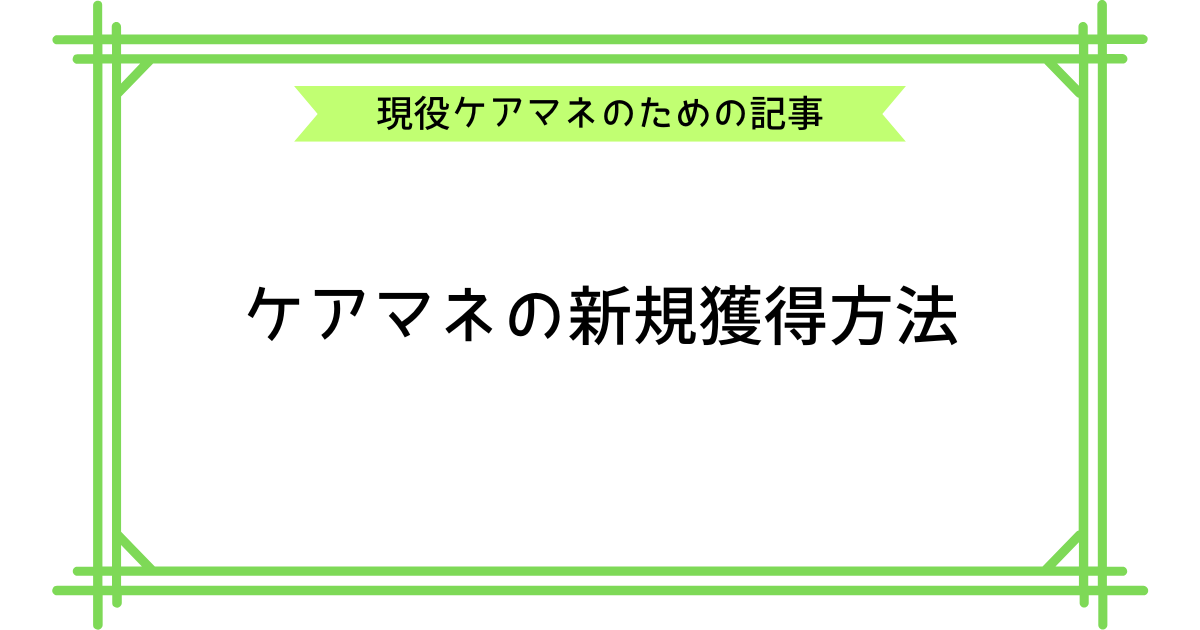
「担当利用者がなかなか増えない」「加算取得が厳しい」とお悩みのケアマネジャーや管理者の方は多いのではないでしょうか?
地域によっては競合事業所も多く、新規利用者を獲得するのが難しい状況になっています。
しかし、正しいアプローチと継続的な関係づくりを行うことで、新規利用者の獲得は十分に可能です。
本記事では、居宅介護支援事業所が意識すべき集客のポイントと、具体的な新規獲得の方法について、実例を交えながらわかりやすく解説します。
担当利用者が少ない理由とは?まずは現状を分析しよう
地域の高齢者数や競合の多さも影響
まず、事業所周辺の高齢者人口や要介護認定者の数を確認しましょう。需要があるかどうかを把握せずに「利用者が来ない」と悩んでいても対策は立てづらくなります。また、近隣に居宅介護支援事業所が多数ある場合は、競合対策も必要になります。
地域包括支援センターや医療機関との連携が不十分
新規利用者の多くは、地域包括支援センター、病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)、訪問看護師などから紹介されてくるケースが大半です。これらの関係機関との連携ができていないと、自然と紹介件数も減ってしまいます。
利用者や家族への「見え方」に課題があることも
事業所の印象や評判も、利用者数に大きく影響します。ホームページが古い、対応が遅い、柔軟な対応ができていないなど、知らぬ間に選ばれにくい存在になっている可能性もあります。
新規利用者を獲得するための具体的な方法をご紹介
1. 地域包括支援センターとの関係を深める
地域包括支援センターは、要支援者・軽度者の支援から要介護認定につながる相談までを担う機関です。ここからの紹介は非常に多いため、関係性の強化がカギとなります。
実践ポイント:
- 月1回程度、包括支援センターへあいさつ訪問
- 困難事例の相談を受けた際は積極的に対応する
- 情報交換会や地域ケア会議に積極的に出席する
「顔の見える関係」を築くことで、紹介の機会が増えていきます。
2. 退院支援部門(MSW)との連携を強化する
病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)は、在宅復帰を支援する役割を担っており、ケアマネ紹介の重要な窓口です。特に急性期病院や回復期リハビリ病棟などにアプローチするのが効果的です。
実践ポイント:
- 事業所のリーフレットを持って病院を定期訪問
- 「すぐ動けるケアマネがいます」と伝える
- 退院調整会議への参加を申し出る
スピード感と対応力が評価されれば、継続的に紹介をもらえるようになります。
3. 医療・介護事業所との関係を広げる
訪問看護、訪問介護、福祉用具事業所、デイサービスなど、在宅系サービスの各事業所と情報交換を行うことで、利用者紹介につながる可能性があります。
関係づくりのコツ:
- お互いの得意分野を理解して紹介し合える関係を築く
- サービス担当者会議での積極的な発言
- 「空き状況表」を共有する
同じ利用者を支える仲間としての信頼関係を築くことで、情報が自然と集まってきます。
4. ホームページやSNSなどで存在を発信する
現代ではインターネットを使ってケアマネ事業所を探す利用者・家族も増えています。ホームページが古い、更新されていないと「ここはやっていないのでは?」と思われかねません。
簡単に始められる工夫:
- Googleマイビジネスで事業所情報を登録
- ホームページに「空き状況」「対応エリア」「連絡先」を明記
- 月1回でもブログやお知らせを更新する
「どんなケアマネがいるのか」「連絡したらすぐ動いてくれそうか」が伝わる発信が効果的です。
ケアマネの担当利用者が増えやすい事業所の共通点とは?
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| 迅速な対応 | 紹介後すぐに訪問・契約が可能 |
| 情報発信 | HPや紹介状などの資料が整備されている |
| 信頼関係 | 包括・医療機関との関係性が深い |
| 安定感 | ケアマネの対応が丁寧で、離職率が低い |
| 柔軟性 | 緊急対応や夜間対応に応じられる体制がある |
利用者はもちろん、紹介する側(包括・MSWなど)にとっても「安心して紹介できる事業所」であることが、最も重要なポイントです。
注意すべき落とし穴にも気をつけよう
無理に人数を増やすと業務が回らなくなる
件数ばかりに目が行くと、ケアの質が下がり、既存利用者の不満が増えたり、苦情につながったりします。業務量・対応力を見ながら、計画的に受け入れを進めましょう。
自事業所の強みを把握していないと訴求できない
「どんな利用者に強いか」「どういう支援が得意か」を把握していないと、紹介元にも選んでもらえません。一度、自分たちの強みを言語化して整理することが重要です。
まとめ
ケアマネの担当利用者が少ない状況に悩んでいる場合、まずは地域包括支援センターや病院、介護事業者との関係づくりから始めることが効果的です。
顔の見える関係を築き、迅速かつ丁寧な対応を積み重ねていくことで、自然と紹介件数が増えていきます。
また、インターネットや紙媒体での情報発信も、今後ますます重要になります。
ただし、無理な受け入れで業務がひっ迫しないよう、質の高い支援を継続できる体制づくりも忘れずに進めましょう。
継続的な努力が新規獲得につながります。















