ケアマネ退職引き継ぎ期間の目安ってどのくらい?
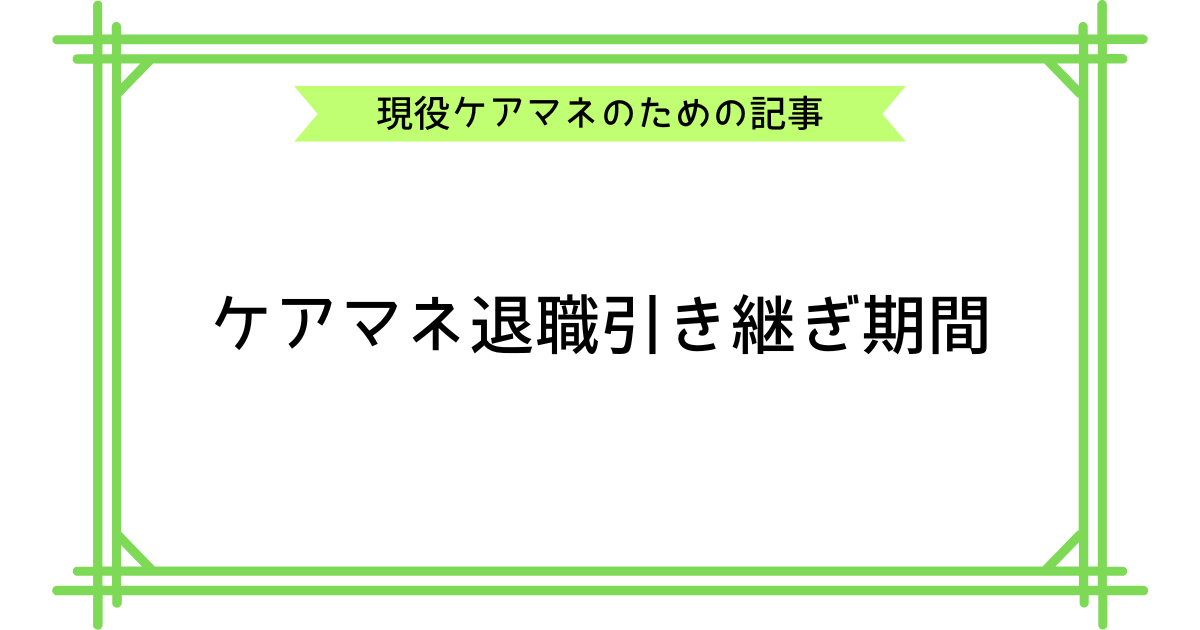
ケアマネジャーとして退職を考えたときに悩むのが「引き継ぎはどのくらいの期間必要なのか?」という問題です。
ケアマネの業務は単に事務的なものではなく、利用者との関係性やサービス事業所との調整など、多岐にわたるため、引き継ぎが不十分だと支援に支障をきたす可能性があります。
本記事では、ケアマネが退職する際の引き継ぎ期間の目安、スムーズに引き継ぐためのポイント、実務で注意すべき点などをわかりやすく解説します。
引き継ぎ期間の一般的な目安は「1か月前」
法的には2週間前の申し出で退職可能
民法上では、「労働者は2週間前に退職の意思を示せば辞められる」とされています。とはいえ、ケアマネの業務は複雑で担当利用者との関係性も深いため、実務上は1か月程度前に退職の意思を伝えるのが一般的なマナーです。
- 就業規則に「30日前までの申し出」とある場合も多い
- 事業所の規模や後任の有無によっても異なる
- 長く勤めた場合や主任ケアマネの場合はもう少し長めに設定することも
急な退職は避けるのがベスト
「体調不良」や「家庭の事情」などやむを得ない事情がない限りは、引き継ぎに十分な時間を確保し、利用者や関係事業所に混乱を与えないようにすることが重要です。
担当件数別に見る!必要な引き継ぎ期間の目安
1人あたりの引き継ぎに必要な時間は?
1人の利用者に対する引き継ぎには、最低でも30分〜1時間程度の情報共有が必要とされています。担当者が20〜35人前後いると仮定すると、業務の合間を縫って2〜3週間は必要となるのが一般的です。
| 担当件数 | 引き継ぎ期間の目安 |
|---|---|
| ~20件 | 約2週間 |
| 20~30件 | 約3週間 |
| 30件以上 | 約4週間以上 |
※上記は目安であり、後任の経験や事業所体制によって変動します
こんな場合は長めに確保するのが安心
- 担当利用者に医療依存度が高い人が多い
- 後任が新人ケアマネ、または他職種からの異動である
- 主任ケアマネとして多職種連携や地域活動を担っていた
このような場合は、1か月以上前に退職の意思を示すのが理想的です。
スムーズな引き継ぎのための実務ポイント
1. 引き継ぎシートを活用する
利用者ごとに以下のような内容をまとめた「引き継ぎシート」を作成しておくと、後任への情報共有がスムーズになります。
記載すべき項目:
- 基本情報(要介護度・家族構成・連絡先など)
- 介護保険サービスの内容・回数
- 医療機関・主治医情報
- 利用者の性格や生活リズム、注意点
- 特記事項(家族との関係性・トラブル履歴など)
2. サービス事業所にも事前に情報共有
ケアマネ交代の連絡をできるだけ早めに事業所に伝え、後任の顔合わせ日程や調整の連絡を行っておくと、事業所側もスムーズに対応しやすくなります。
- サービス担当者会議の日程も含めて調整
- 電話だけでなく、文書やメールでの共有も有効
- 書類の更新タイミング(モニタリング・プラン更新)も考慮
3. 利用者・家族には直接説明を
利用者・家族への「ケアマネ交代」の説明は非常に重要です。信頼関係を築いていた場合ほど、丁寧な説明が必要になります。
- 面談または電話で交代の理由と今後の対応を伝える
- 不安を感じさせないよう、後任の紹介も丁寧に
- サービスに支障が出ないことを明言する
退職時にやってはいけないNG行動とは?
引き継ぎ内容を口頭だけで済ませる
忙しさのあまり「口頭でざっくり伝えただけ」では、後任が困るだけでなく、支援の質にも悪影響が出る可能性があります。書面と対面での引き継ぎをセットにすることが基本です。
引き継ぎせずに有給休暇を一気に取る
有給休暇の取得は労働者の権利ですが、引き継ぎをせずに全日程を休むような使い方はトラブルの元です。管理者と相談しながら、業務への影響を最小限にする配慮が求められます。
後任や関係者への不満を利用者に伝える
たとえ不満があっての退職であっても、それを利用者や家族に伝えるのは絶対にNGです。信頼関係を損なうだけでなく、事業所や後任者への悪影響も出てしまいます。
引き継ぎ後の確認とフォロー
自分が退職した後も最低限の連絡先を残す配慮を
退職後に緊急で確認されることもあります。連絡が必要な場合は◯◯を通してください、と伝えておくと、安心して職場を離れることができます。
退職後の証明書類(離職票・源泉徴収票)も忘れずに
手続き関連の書類が必要になる場合もあるため、人事・事務とのやりとりも計画的に進めておきましょう。
まとめ
ケアマネの退職にあたっての引き継ぎ期間は、一般的に「1か月程度」が目安とされています。
担当利用者数や業務内容、後任の経験によって必要な期間は異なりますが、できる限り余裕を持って引き継ぎ準備を進めることが大切です。
丁寧な引き継ぎは、後任者・利用者・事業所すべての信頼につながり、自分自身が気持ちよく退職するためにも重要です。
無理のないスケジュールで、しっかりと業務を終え、新たなスタートを切りましょう。















