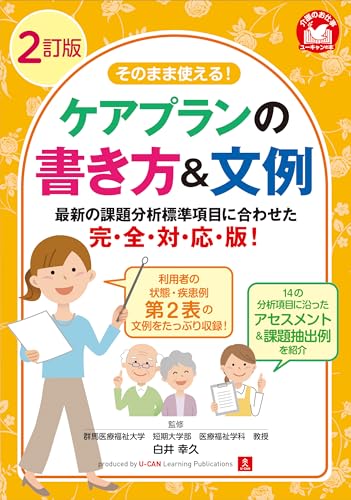【ケアマネが仕事で使える】訪問看護のケアプランの文例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
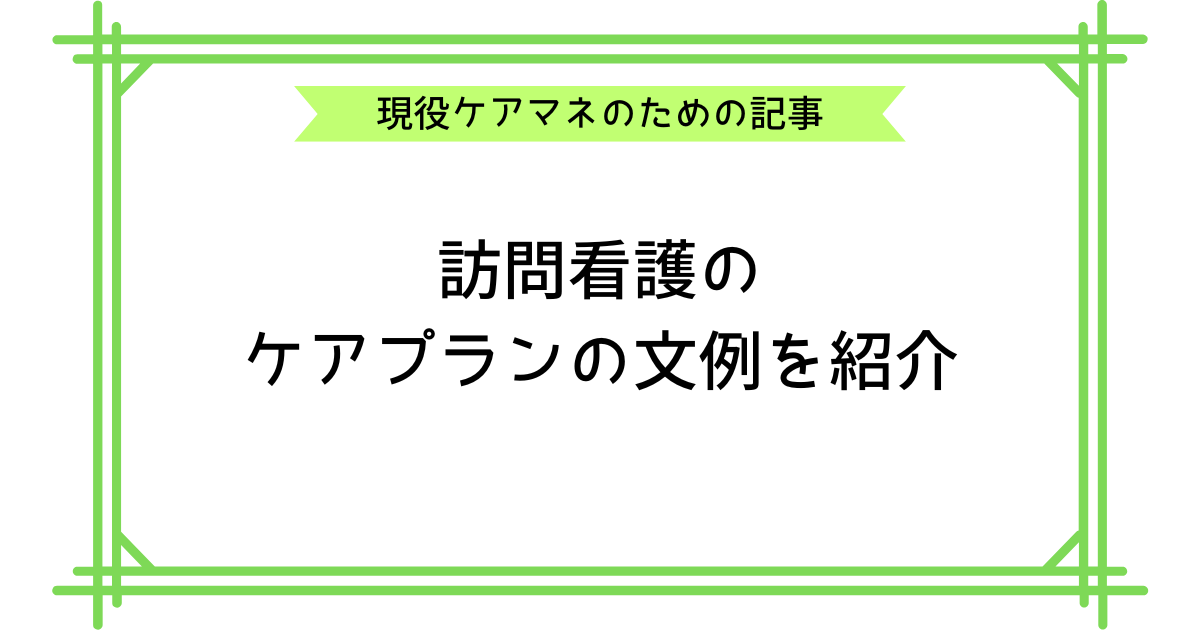
ケアマネジャーの皆さん、訪問看護を導入する際のケアプラン作成で「適切な表現が思いつかない」「医療的視点をどう反映すればよいかわからない」と感じたことはありませんか?
訪問看護は、医療職が在宅療養者を支援する重要なサービスであり、疾患管理・予後の安定化・家族支援など多様な目的をもって活用されます。
今回は、訪問看護の導入時に実務でそのまま使えるケアプラン文例を、第1表・第2表に分けて多数ご紹介。
目的別にわかりやすくまとめていますので、ぜひご活用ください。

ケアマネはこの本を持っておくと便利だよ!
目次
訪問看護の位置づけとケアプラン作成のポイント


医療ニーズ+生活支援の視点が必要
訪問看護は、医師の指示に基づいて看護師・PT・OTなどが利用者宅を訪問し、医療的ケア・健康管理・服薬支援・家族支援などを行うサービスです。
ケアプラン作成では以下の点に留意が必要です:
- 医療的観察・処置の必要性
- 服薬・疾患管理の支援
- 在宅療養継続の可否と家族支援
- 終末期支援の有無(ターミナルケア)
第1表:アセスメント・課題分析の文例


本人の意向(例文)
- 「病院に行くのは大変なので、家で療養できるようにしたい。」
- 「服薬の時間がよくわからないので、サポートしてもらえると助かる。」
- 「できるだけ最期まで自宅で過ごしたい。」
- 「点滴や傷の手当ては、専門の人にお願いしたい。」
家族の意向(例文)
- 「病状が悪化しないように、定期的に体調を見てほしい。」
- 「服薬管理が難しいので、訪問時に確認してもらいたい。」
- 「急変があったときの対応に不安があり、看護師が関わってくれると安心。」
- 「看取りに向けて、家族だけでは不安があるので専門職の支援がほしい。」
ケアマネによる課題分析(例文)
- 慢性心不全により呼吸苦が強く、日常生活動作にも影響が出ている。体調変化の早期発見・医療連携のために訪問看護が必要と判断。
- 認知機能の低下により、服薬の自己管理が困難。訪問時の確認・声かけ支援が求められる。
- 家族は在宅での看取りを希望しており、今後の緩和ケア対応に向けて専門職の支援体制構築が必要。
第1表:総合的な援助方針の文例
- 利用者の在宅療養継続を支えるため、医療的管理・服薬支援・家族支援を目的に訪問看護を導入する。
- 訪問看護ステーションと密に連携し、体調の変化を早期に察知し適切な対応を図る。
- 緩和ケア・ターミナル期への対応を含め、本人・家族が安心して在宅生活を継続できる体制を整える。
第2表:ニーズ・長期目標・短期目標・サービス内容の文例


主なニーズの文例
- 体調の急変時に備えて、定期的な健康管理を行いたい。
- 服薬管理に自信がないため、看護師の支援が必要。
- 床ずれ予防のため、体位交換や皮膚状態のチェックをしてほしい。
- 自宅での看取りを希望しており、緩和ケアの支援が必要。
長期目標の文例
- 医療的ケアを受けながら、住み慣れた自宅で穏やかに療養生活を送ることができる。
- 薬の服用が安定し、病状が落ち着いた状態で在宅生活を継続できる。
- 感染症や褥瘡などの合併症を予防しながら在宅で過ごす。
- 家族が安心して看取りを行えるよう、必要なサポートを受けられる。
短期目標の文例(目的別)
健康管理・バイタル確認
- 週2回の訪問で、血圧・脈拍・呼吸状態を確認し、異常時には主治医と連携する体制を構築。
- 呼吸状態を観察し、体調悪化の兆候があれば迅速に対応する。
服薬支援
- 訪問看護師の声かけにより、服薬忘れが週1回以内に減少する。
- 薬の整理・配薬を看護師が確認し、飲み間違いのリスクを減らす。
創傷処置・褥瘡管理
- 褥瘡の状態を定期的に観察し、悪化を防ぐケアを継続。
- 創部の清潔保持と適切な処置により、感染リスクを低減する。
ターミナルケア
- 呼吸苦・疼痛の緩和ケアを通じて、本人の苦痛を軽減する。
- 家族が終末期対応について相談できる体制を整える。
サービス内容の文例
- 週2回訪問し、バイタルチェック・全身状態の観察・服薬状況の確認を行う。
- 必要に応じて主治医へ報告し、状態変化への迅速な対応を図る。
- 皮膚トラブルの予防・創傷処置など、在宅での医療処置を支援。
- ターミナル期においては、疼痛管理や家族支援を含めた緩和ケアを実施。
サービス担当者会議の記録例(要点)


- 看護師より、利用者の全身状態・疾患経過・服薬状況の確認と、今後の支援方針について説明があった。
- 主治医との連携体制についても確認され、緊急時の対応ルールを明確化した。
- 家族からは「訪問看護が入ることで安心できる」「今後の変化に備えて相談したい」との発言あり。
- ケアマネより、ケアプラン上の目標と訪問看護の位置づけを再確認し、サービスの継続に同意を得た。
モニタリング記録の視点(例文)
- 訪問看護開始後、バイタルサインは安定しており、食欲・睡眠も維持されている。看護師より「全身状態は現状維持」との報告あり。
- 服薬確認の際の声かけにより、服薬忘れがほぼなくなった。家族も「指導のおかげで安心できた」とのこと。
- 看取り希望の利用者に対し、看護師より疼痛コントロールの具体的支援が始まり、苦痛の訴えが減少傾向。
- 今後も継続的にモニタリングを行い、状況に応じて主治医との連携を強化していく。
まとめ
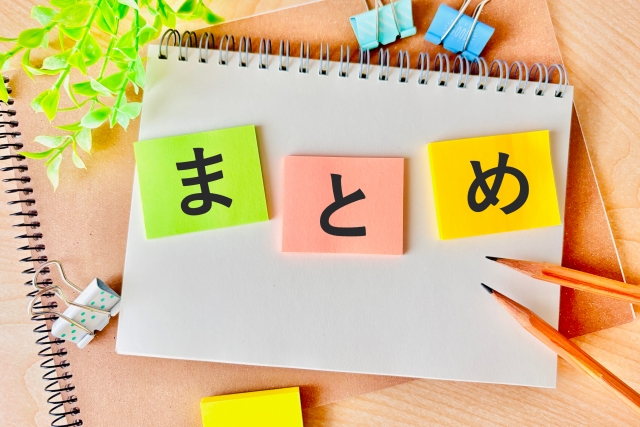
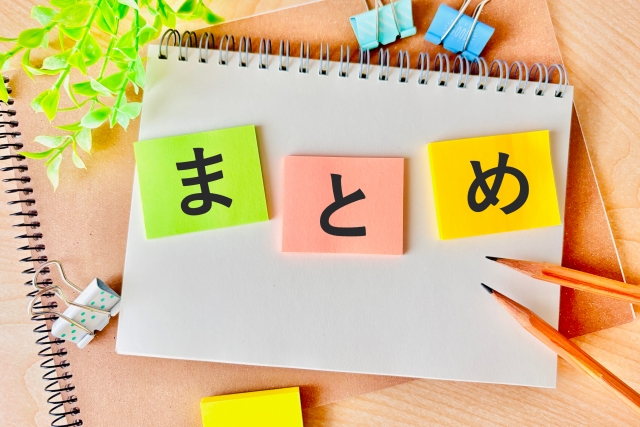
訪問看護を導入するケアプランでは、医療的視点と生活支援のバランスが求められます。
特に疾患管理・服薬支援・緩和ケアなど、具体的な目的に応じた文例を用意しておくと、ケアマネ業務の効率化につながります。
本記事で紹介した第1表・第2表の文例は、現場で即活用できる内容ばかりです。
利用者と家族が安心して在宅療養を継続できるよう、訪問看護の役割を明確にケアプランに反映していきましょう。