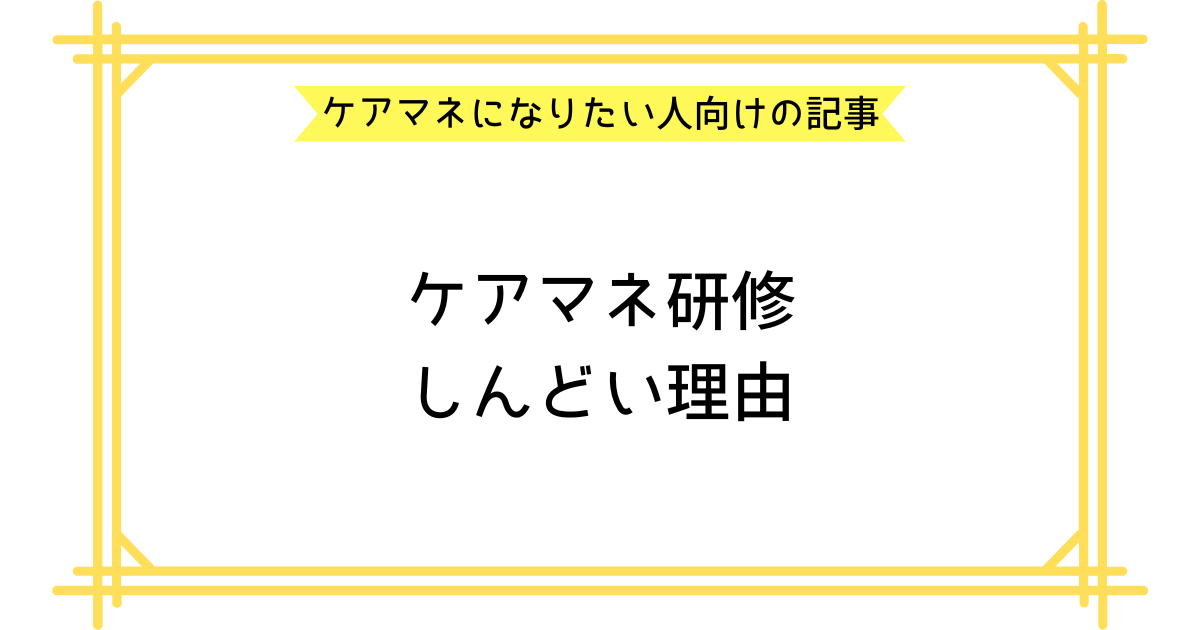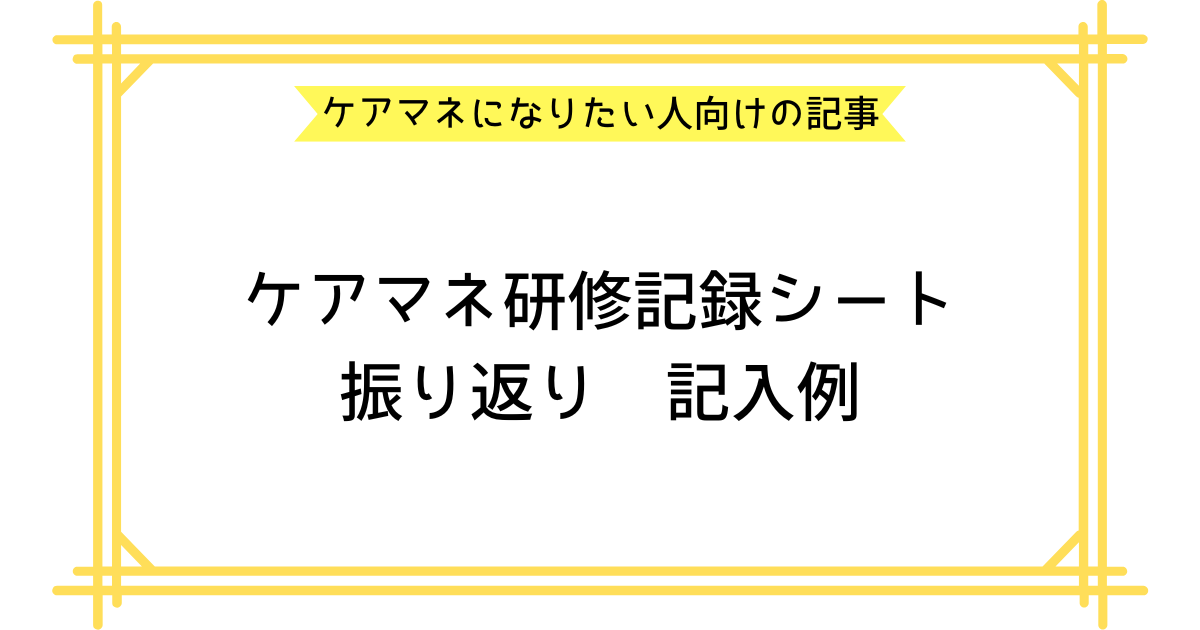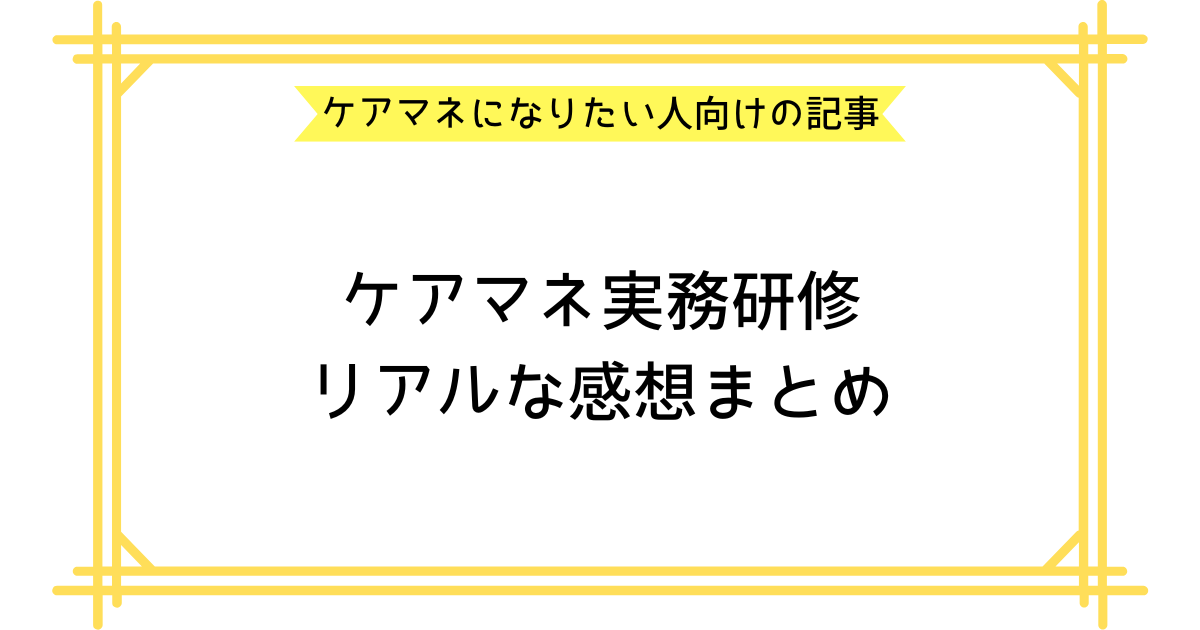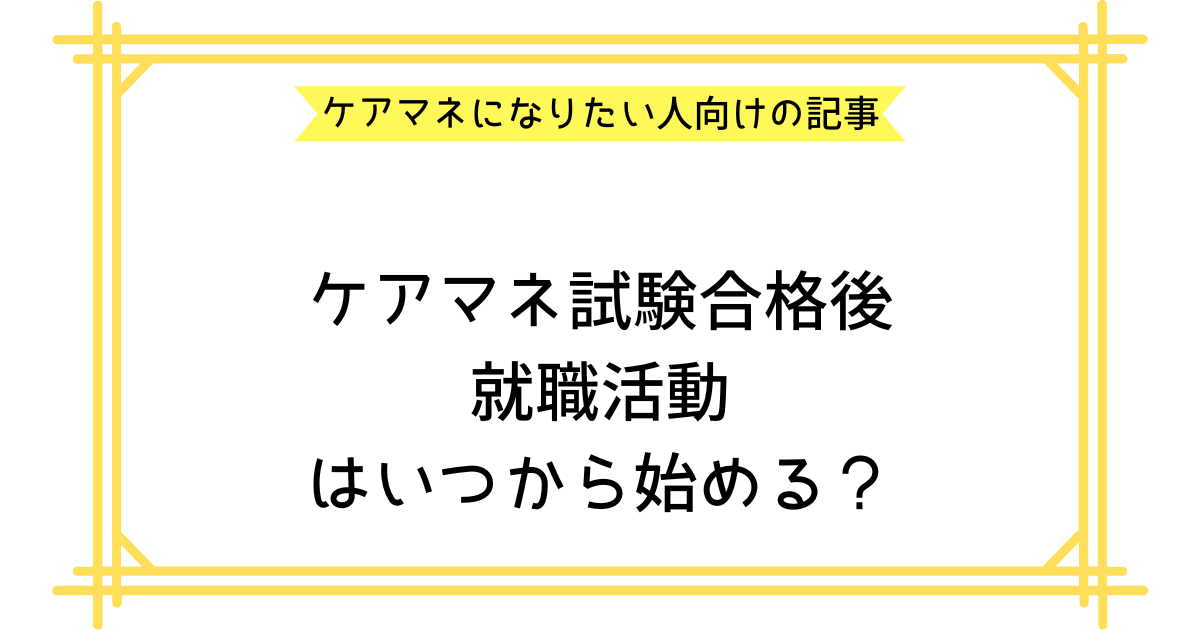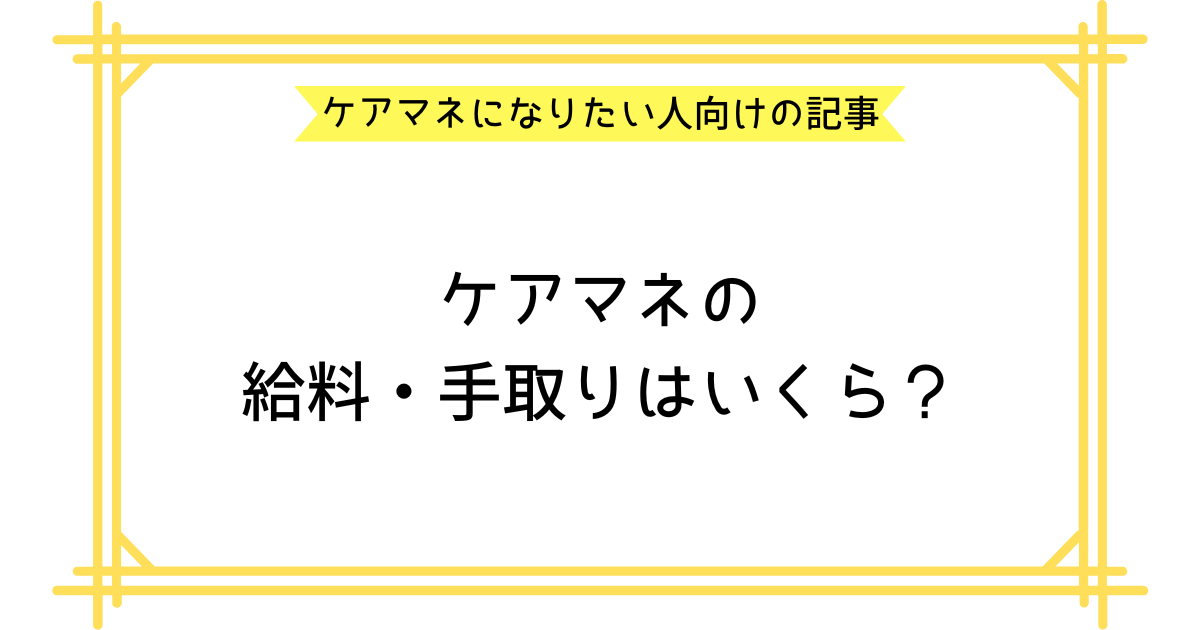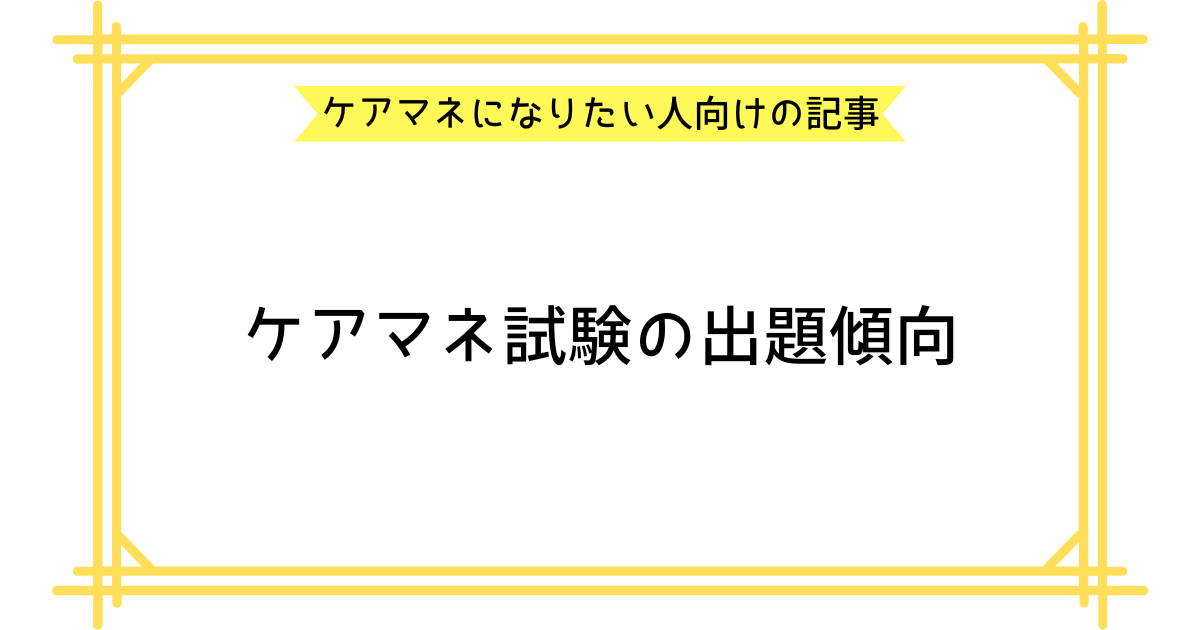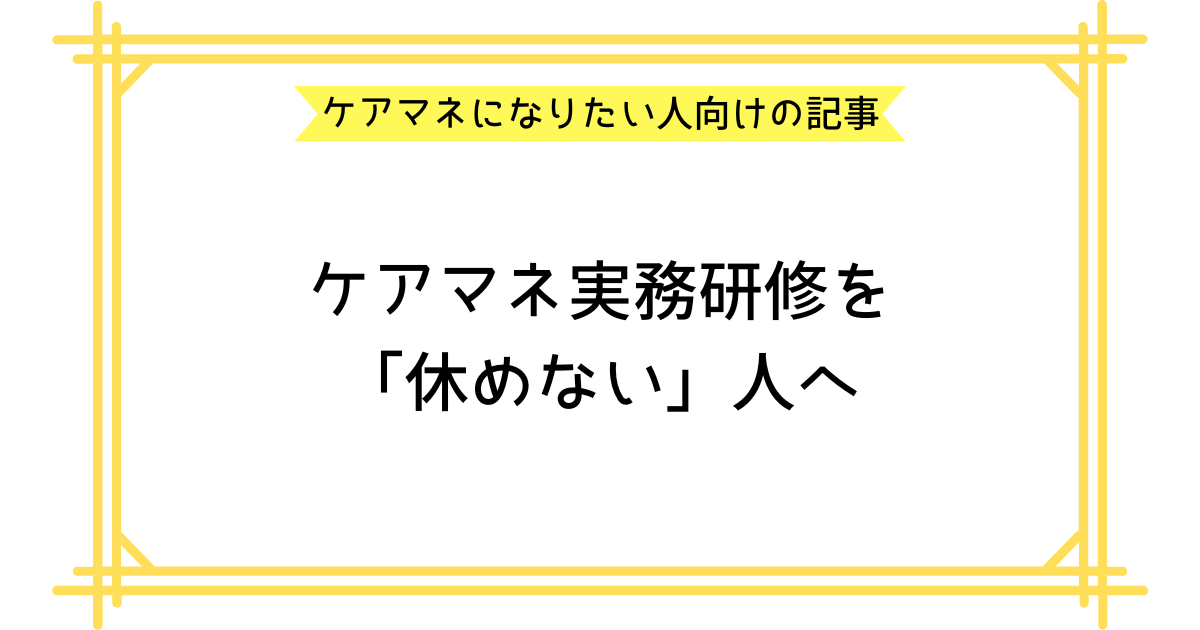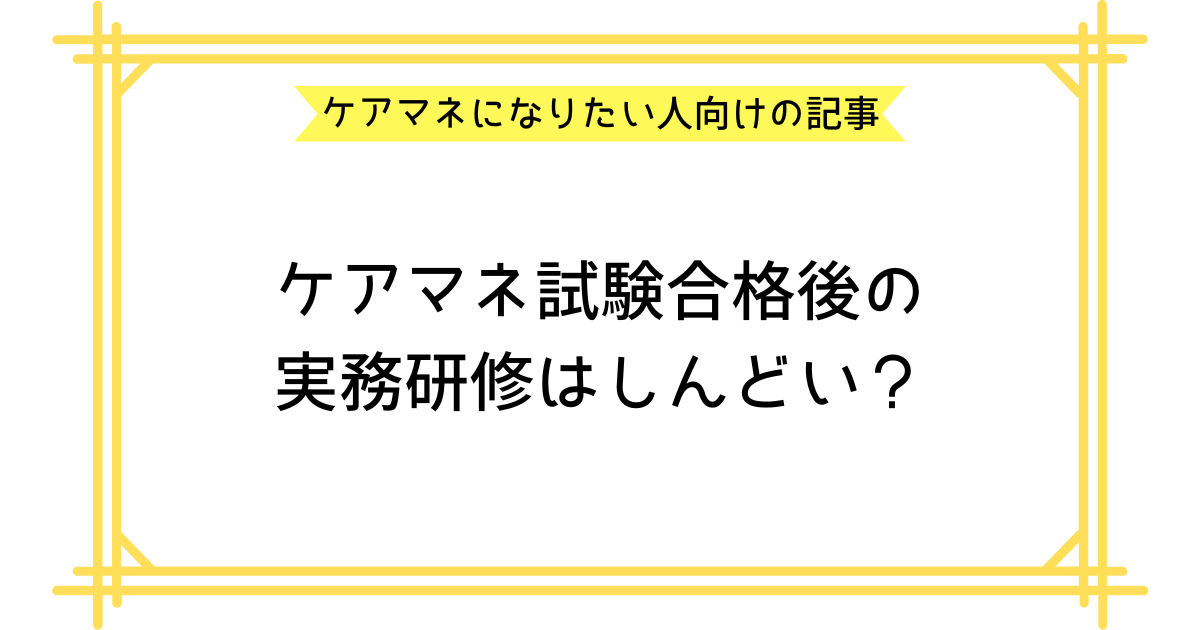ケアマネは車の運転できないと仕事ができない?

ケアマネジャーとして働きたいと思っていても、「運転免許がないと仕事は難しいのでは?」と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
実際にケアマネの求人では「普通自動車免許必須」と記載されていることもあり、「車の運転ができないとケアマネになれないのか?」という疑問を持つのも無理はありません。
本記事では、ケアマネの仕事において運転免許や自動車がどれほど必要なのか、また運転ができない人でも働ける職場の探し方や工夫について詳しく解説します。
車の運転に不安がある方も、ぜひ参考にしてください。
ケアマネの仕事に運転が必要とされる理由とは?
ケアマネジャーは、利用者の自宅を訪問し、生活状況の確認やアセスメント、サービスのモニタリングなどを行うため、外出が多い職種です。特に「居宅ケアマネ」の場合、担当利用者が地域のあちこちに散らばっているため、効率よく訪問するには自動車での移動が非常に便利です。
また、サービス担当者会議や多職種連携のために事業所間を移動する必要があり、時間的制約もある中で、公共交通機関だけでは対応が難しいケースが少なくありません。こうした背景から、多くの事業所では「普通自動車免許(AT限定可)必須」としているところが多いのが現状です。
ただし、これはすべてのケアマネに当てはまるわけではなく、勤務地や勤務形態によって運転の必要性には差があります。
運転できない人でもケアマネとして働けるケースはある?
1. 公共交通機関が整っている都市部の事業所
東京都心部や政令指定都市など、公共交通機関が充実している地域では、車での移動が不要なケースもあります。地下鉄やバスを利用すれば効率よく訪問できるため、運転免許がなくても問題なく勤務できる職場も少なくありません。
また、都市部では自転車や電動自転車での訪問を推奨している事業所もあります。訪問エリアが狭く、移動距離が短い場合には徒歩訪問が可能なこともあり、免許がなくても働ける環境は確実に存在しています。
2. 施設ケアマネや包括支援センター勤務
「特別養護老人ホーム」や「介護老人保健施設」などの入所施設で勤務する「施設ケアマネ」は、利用者が施設内で生活しているため、外出する機会はほとんどありません。そのため、運転ができなくてもまったく支障がないケースが多くあります。
また、地域包括支援センターに勤務する介護予防ケアマネも、訪問頻度が少ないケースがあり、徒歩や自転車で十分に対応できる範囲に業務が限定される場合もあります。
3. 同乗訪問・送迎体制がある職場も
事業所によっては、車の運転ができない職員のために、同行訪問や送迎体制を整えているところもあります。運転手や他の職員が移動をサポートしてくれる体制がある場合、免許なしでも実務を行うことが可能です。
ただし、このような体制がある事業所はまだ少数派であるため、事前の確認や相談が必要です。
運転ができないケアマネが工夫して働く方法
移動手段を確保する
自動車が使えない場合でも、電動自転車や原付バイクを活用することで訪問業務が可能になります。特に都市部では、自転車での移動が業務に取り入れられているケースも多く、天候に左右される面はありますが、十分な代替手段となりえます。
また、カーシェアやレンタカー制度を導入している事業所もあり、免許はあるけれどマイカーがないという方でも対応できる場合があります。
移動時間を効率化したスケジューリング
徒歩や自転車での移動を前提とした場合は、訪問先をエリアごとにまとめてスケジューリングする工夫が必要です。訪問ルートの見直しや、アプリによる地図・ルート管理を使いこなすことで、無理のないスケジュールを組むことが可能です。
職場選びで「運転不要」の条件を明確にする
ハローワークや転職サイトを利用する際には、「運転業務なし」「免許不要」「訪問業務なし」などの条件で検索することで、運転できない方でも働ける求人を見つけやすくなります。面接時には「どのような移動手段が必要か」「マイカー通勤は必須か」などを具体的に確認することが大切です。
まとめ
ケアマネの仕事には車の運転が必要なケースが多いのは事実ですが、「運転できない=ケアマネになれない」わけではありません。都市部や施設勤務、地域包括支援センターなどでは運転が不要な職場もあり、工夫次第で免許がなくても十分に活躍できる可能性があります。
また、自転車や公共交通機関の活用、職場での支援体制、スケジューリングの工夫などで移動手段を補うことも可能です。今後は高齢化社会の進行に伴い、柔軟な勤務体制や多様な働き方が求められるようになるため、運転できないケアマネの活躍の場も確実に広がっていくでしょう。
「車が運転できないから」と諦めるのではなく、自分に合った働き方や職場を見つけて、ケアマネとしての一歩を踏み出してみてください。