ケアマネのなり手がない?ケアマネ不足の主な理由とは?
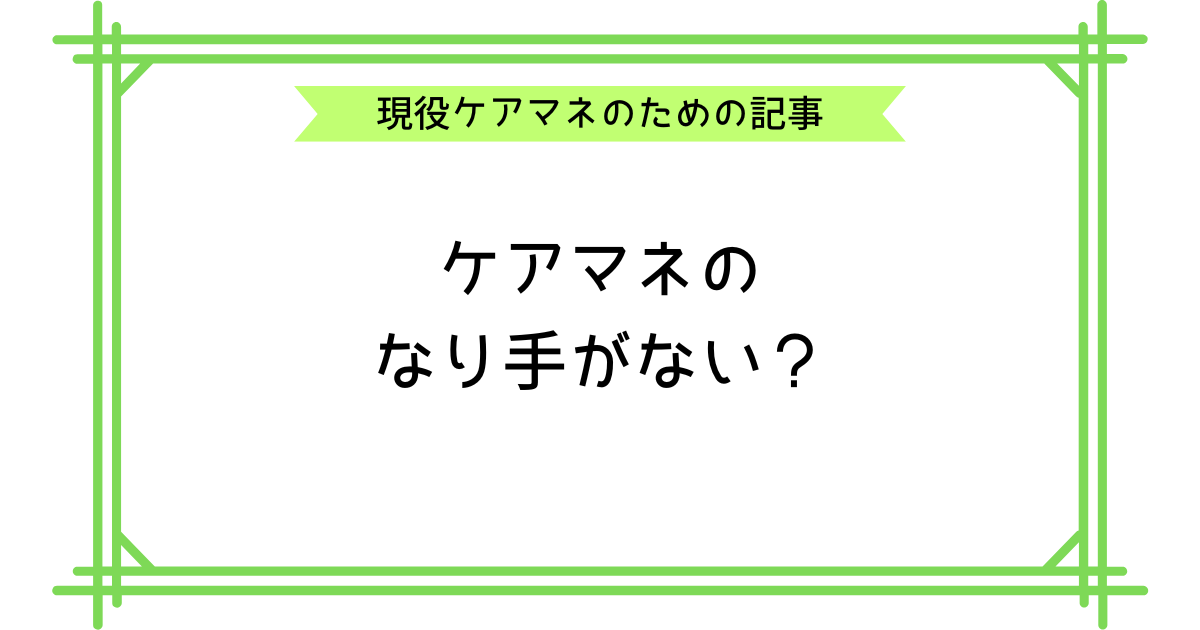
介護業界において「ケアマネのなり手がいない」「ケアマネ不足が深刻」といった声が年々増加しています。
介護支援の中心的な役割を担うケアマネジャー(介護支援専門員)は、高齢化が進む日本において不可欠な存在ですが、なぜその担い手が減少しているのでしょうか?
本記事では、ケアマネのなり手が減っている理由を詳しく解説するとともに、それでもなおケアマネになることで得られるメリットについても紹介します。
介護業界に興味がある方や、今後のキャリアを考えている方はぜひ参考にしてください。
ケアマネのなり手がない主な理由

ケアマネジャーの数が足りない背景には、複数の要因が絡んでいます。
ここでは、主な理由を4つに分けて解説します。
試験の難易度が高く、合格率が低い
介護支援専門員の資格試験は、受験資格が厳しいうえに、出題範囲が広く難易度も高いため、簡単には合格できないと感じる人が多いです。特に医療・福祉・介護の法律や制度に関する問題が多く、暗記だけでなく理解も求められるため、仕事をしながら勉強を進めるのは大きな負担になります。その結果、受験をためらう人が増え、なり手不足につながっています。
責任が重く、精神的な負担が大きい
ケアマネは、利用者や家族の人生に関わる重要な判断を求められる場面が多く、ミスが許されないプレッシャーを感じながら働くことになります。また、多職種との連携や、行政とのやり取りなども必要で、コミュニケーションや調整業務にストレスを感じる人も少なくありません。特に新人ケアマネにとっては、業務の幅広さと責任の重さが心理的なハードルとなっています。
書類業務が多く、業務量が多い
ケアマネの業務は、実際の面談やサービス調整だけでなく、膨大な書類作成や記録業務も含まれます。たとえば、ケアプランの作成や給付管理、モニタリング記録など、多くの文書業務が発生します。こうした「見えない業務」に時間と労力を取られ、現場では「残業が多い」「業務に追われる」といった声が多く聞かれます。業務量の多さが、なり手の減少を後押ししています。
給与が見合わないと感じる人が多い
ケアマネの仕事は高い専門性と責任を伴いますが、そのわりに給与が他の職種に比べて高くないと感じる人が多いです。特に、訪問介護や介護福祉士として働いていた時よりも、ケアマネに転職した後の給与が大きく上がらなかった、むしろ減ったという声もあります。業務量と報酬が見合わないと感じる人が増えることで、ケアマネを目指す意欲が下がっているのです。
ケアマネになるメリット4選

ケアマネのなり手が減っている現状はあるものの、この職業にはやりがいや魅力も数多く存在します。
ここでは、ケアマネになることで得られる代表的なメリットを4つご紹介します。
利用者と深く関わることで得られるやりがい
ケアマネは、利用者の生活をトータルで支える存在として、長期的に関わることができます。サービス導入から日々の変化まで寄り添う中で、利用者や家族から「ありがとう」と感謝される場面が多く、その言葉が日々の励みになります。自分のケアプランで利用者の生活が改善される瞬間に立ち会えるのは、他の職種では得難い感動です。
キャリアアップにつながる
介護職や看護師、社会福祉士などからケアマネへと進むことで、専門職としてのステップアップになります。さらに、主任介護支援専門員の資格を取得すれば、管理職やマネジメントへの道も開けます。実務経験と知識を活かして、より広い視野で介護業界に貢献できるのは大きな魅力です。資格を持つことで転職や独立も有利に進められます。
勤務形態の選択肢が多い
ケアマネは、施設や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなど、さまざまな職場で活躍できます。また、事業所によってはフルタイムだけでなく、パートや時短勤務など柔軟な働き方が可能な場合もあり、子育て中や介護中の人でも続けやすい職種です。ライフステージに応じた働き方ができる点も、大きなメリットのひとつです。
社会的意義の高い仕事である
ケアマネの仕事は、高齢社会において必要不可欠な存在です。行政や医療との連携を通じて、地域包括ケアシステムの一翼を担い、社会貢献度が非常に高い職種です。自分の仕事が社会を支えているという実感が得られることは、大きな誇りとなります。将来的にも需要が続く安定した仕事である点も、安心材料となるでしょう。
まとめ
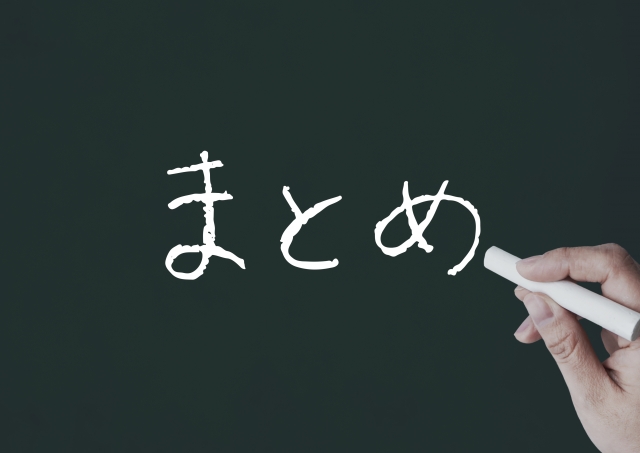
ケアマネのなり手が減少している背景には、試験の難しさや業務量、精神的負担、報酬面の問題など、複数の要因が複雑に絡み合っています。
しかし、その一方で、ケアマネには深いやりがいと社会的意義があり、長く活躍できる専門職としての魅力も多く存在します。
もしあなたが介護業界でのキャリアアップや、より利用者に寄り添った支援を目指すなら、ケアマネジャーという道は十分に検討する価値があります。
課題と魅力を両方理解した上で、自分の未来を見据えた選択をしてみてください。















