ケアマネの一ヶ月の流れを紹介!忙しい時と余裕がある時を解説
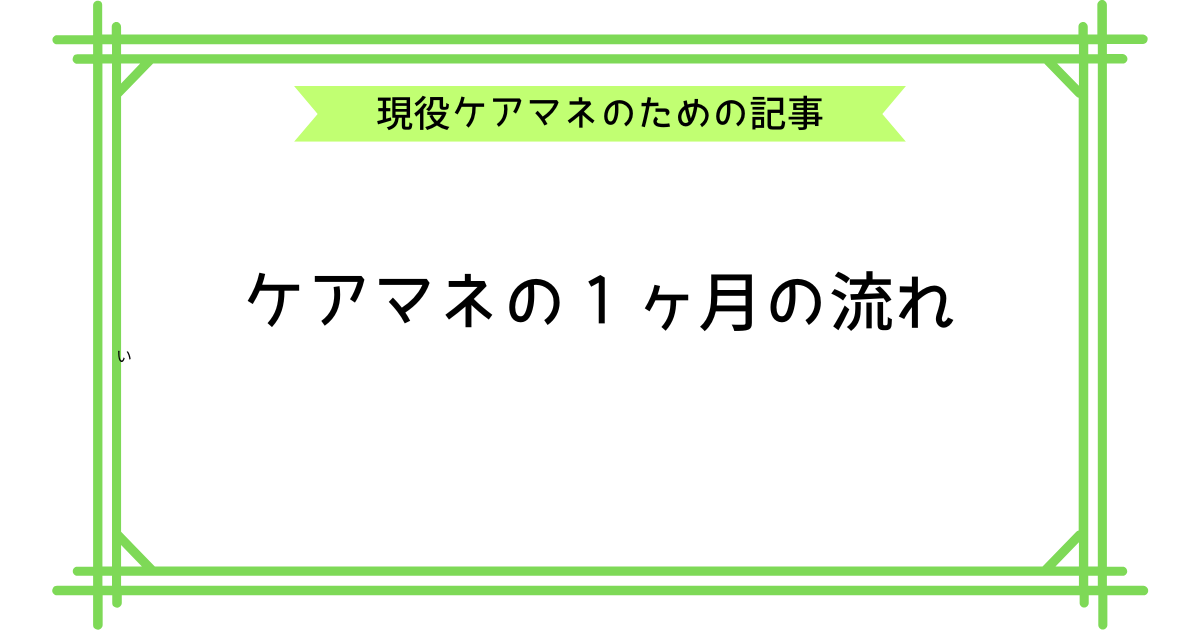
ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事は月単位でのスケジュール管理が重要で、時期によって忙しさに大きな波があります。
「ケアマネはいつが忙しい?」「休みを取りやすいタイミングはある?」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ケアマネの1ヶ月の仕事の流れを時期別に解説し、特に忙しい時期と余裕がある時期、そして休みを取りやすいタイミングについてもわかりやすく紹介します。
これからケアマネを目指す方や現役のケアマネのスケジュール管理に役立つ内容です。
ケアマネの一ヶ月の流れと時期別の仕事内容を紹介

ケアマネジャーの業務は月初・月中・月末でそれぞれ異なる役割があります。
以下で時期ごとに詳しく解説します。
ぜひ業務のメリハリを理解する参考にしてください。
月初(1日~10日頃)
月初はケアマネ業務の中でも特に忙しい時期です。前月に提供されたサービスに基づいて、給付管理(給付票と提供票の作成・提出)を行い、各事業所とのやり取りや確認作業に追われます。また、新しい月に入ったことで利用者へのモニタリング訪問の準備や、月内のスケジュール調整も必要となります。さらに、新規利用者がいる場合は初回訪問やケアプラン作成などの業務が重なるため、通常以上に業務量が増えやすく、残業が発生しやすい時期です。
月中(11日~20日頃)
月中は比較的落ち着いており、モニタリングや担当者会議の開催、認定調査の対応などを中心に業務が進みます。この時期は月初ほどの事務作業の集中がないため、利用者訪問に時間をかけることができる余裕がある時期とも言えます。また、サービス提供に関する課題があれば事業所や医療機関との連携を深める期間でもあります。加えて、書類整理や計画の見直し、勉強会や研修に参加する余裕も持ちやすく、自身のスキルアップにも適したタイミングです。
月後半(21日~25日頃)
月後半になると、翌月に向けた準備が始まります。必要に応じてモニタリング訪問を終わらせ、翌月の予定を調整する期間です。また、新たな課題が発生している場合は、サービス担当者会議を開き、ケアプランの変更や再調整を行います。事業所との連絡や書類の確認、行政とのやり取りなど、再び事務処理も増え始める時期であり、少しずつ忙しさが戻ってくる感覚があります。効率的に動くことで、月末の負担を軽減できます。
月末(26日~月末)
月末は再び忙しさがピークに達する時期です。翌月分のサービス提供票や予定表の作成、ケアプランの見直し・変更、認定更新の手続き対応など、多くの業務が集中します。また、月内に完了しておくべき訪問やモニタリングの確認、記録の締めも必要です。事業所や事務員との連携も多くなるため、時間的にタイトになりがちです。月末のタスクを見越して、月中に余裕をもって準備しておくことが、ケアマネとしての業務負担を軽減するコツです。
ケアマネが休みやすい時期とは?

ケアマネが比較的休みを取りやすいのは、月中(11日〜20日頃)です。
この時期は給付管理の提出が終わり、月末の事務作業もまだ始まっていないため、スケジュールに余裕が生まれやすいのが特徴です。
特に、モニタリングや会議の予定が調整できていれば、1日や半日の休暇を取りやすいタイミングです。
逆に、月初や月末は業務が集中するため、長期の休みは取りづらい傾向にあります。有給を取る場合は、周囲との業務分担や事前の準備が重要となります。
年末年始や夏季休暇のような長期休暇についても、月中を中心にスケジューリングするのが理想的です。
まとめ
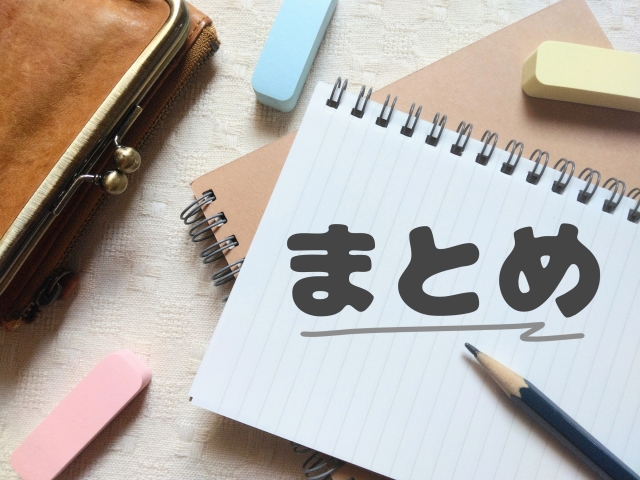
ケアマネの1ヶ月の業務は、月初・月末に事務作業や給付管理が集中し、月中にやや余裕がある構成になっています。
特に月初と月末は事務処理やスケジュール調整が立て込み、繁忙期となるため、あらかじめ計画を立てておくことが業務負担を軽減する鍵です。
一方で、月中は訪問業務や担当者会議などに集中でき、休暇も取りやすい時期となっています。
ケアマネとして働く上では、この月ごとの業務の流れを把握し、メリハリある働き方を意識することが、心身の安定にもつながります。
これからケアマネを目指す方も、実際の現場の1ヶ月をイメージする参考にしてください。















