介護老人保健施設や介護医療院でのケアマネのアセスメントの方法を紹介
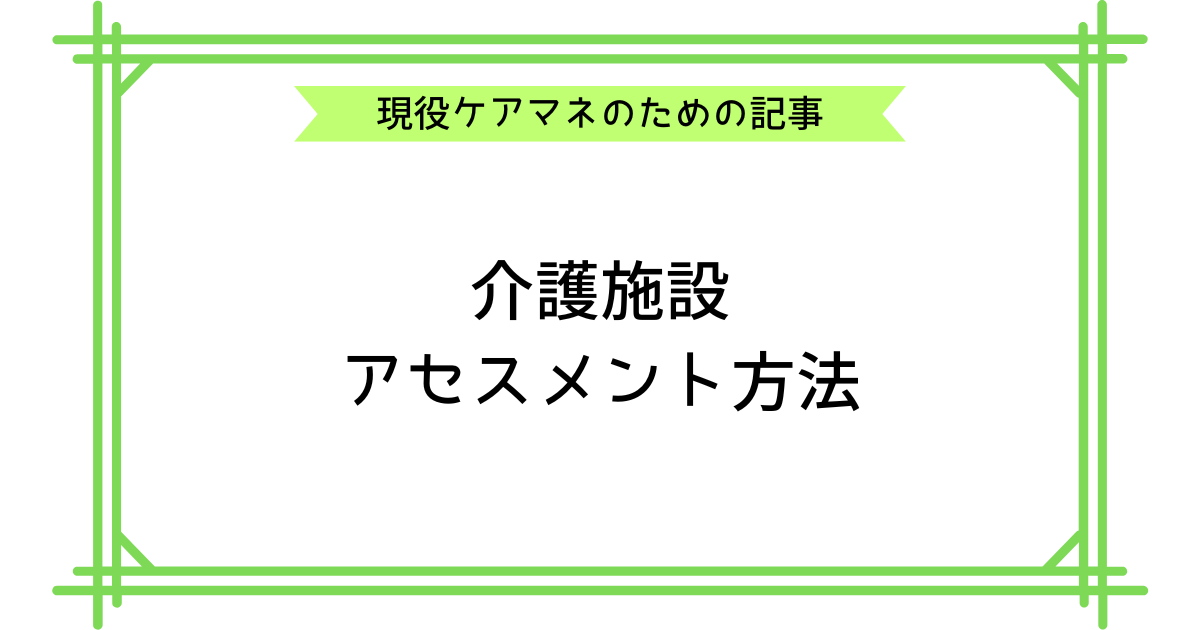
介護老人保健施設(老健)や介護医療院は、医療と介護の両方を提供する施設であり、入所者が在宅復帰を目指す場合や長期療養を継続する場合に重要な役割を担っています。
その中で施設ケアマネジャーは、入所者一人ひとりの心身状態や生活背景を把握し、適切なケアプランを作成するために「アセスメント」を行います。
しかし、在宅のケアマネジャーと比べてアセスメントの視点や方法が異なる点があり、「何を重視すべきか」「どのように情報を集めるのか」に悩むことも少なくありません。
本記事では、老健や介護医療院におけるケアマネのアセスメント方法を具体的に紹介し、現場で活用できる視点を解説します。
介護老人保健施設や介護医療院におけるアセスメントの特徴
老健や介護医療院では、入所者が医療的ケアやリハビリを必要としているケースが多く、アセスメントでは医療職との情報共有が必須です。
例えば、在宅ケアマネのアセスメントが「生活機能の把握」に重点を置くのに対し、施設ケアマネは「医療依存度」「在宅復帰の可能性」「長期療養における生活の質」といった観点を加える必要があります。
さらに、入所直後から退所までの短期間で多職種と連携しながら支援方針を明確にする点も特徴です。
医師・看護師・リハ職・介護職と常に情報を共有し、入所者や家族と目標をすり合わせるプロセスが重視されます。
アセスメントの基本的な流れ
入所前情報の収集
入所前に病院や居宅ケアマネジャー、家族から情報提供を受け、病歴やADL、生活習慣を把握します。特に退院直後の入所では、急性期での治療内容や残された課題を詳細に確認することが重要です。
入所時アセスメント
入所直後に多職種合同でアセスメントを行い、心身機能、認知機能、栄養状態、社会的背景を総合的に評価します。この段階で、在宅復帰の可能性や長期療養の方向性を見極めます。
継続的なモニタリング
入所後は定期的にカンファレンスを行い、アセスメント内容を見直します。状態変化があればその都度更新し、ケアプランに反映させることが必要です。特に老健では在宅復帰支援が目的のため、リハビリの進捗や家族の介護力を重点的に確認します。
アセスメントで重視する視点
医療的視点
介護医療院や老健では、医療的処置が必要な入所者が多いため、服薬状況、褥瘡リスク、酸素療法や経管栄養の有無などを詳細に把握します。医師や看護師と連携しながら医療ニーズを整理することが欠かせません。
リハビリテーション視点
老健では「在宅復帰率」が重要な指標となるため、リハ職からの情報をもとに身体機能やADLの改善可能性を評価します。歩行訓練やADL訓練の到達目標を具体的に設定することが求められます。
生活環境・家族支援の視点
自宅での生活を見据える場合、住環境や家族の介護力を正確に把握する必要があります。家族の支援体制や住宅改修の必要性、福祉用具の導入可否などもアセスメントの重要ポイントです。
本人の意思・希望
医療や介護の専門的評価に加えて、本人の生活意向を尊重することが大切です。「自宅に戻りたい」「できるだけ歩きたい」といった本人の思いを聞き取り、可能な範囲でケアプランに反映させます。
多職種連携によるアセスメントの実際
施設ケアマネのアセスメントは、ケアマネ単独で行うのではなく、多職種による共同作業が前提です。
入所者の心身状態を医師が医学的に評価し、看護師が日常の健康管理を報告、リハ職が身体機能を分析し、介護職が日常生活動作を観察します。
ケアマネはこれらの情報を統合し、本人と家族の意向を調整してケアプランを策定します。
特に老健では在宅復帰支援を意識した「退所前カンファレンス」が重要であり、介護医療院では長期療養に伴う「生活の質向上」を意識したアセスメントが欠かせません。
ケアマネジャーが直面する課題と工夫
情報量の多さと整理の難しさ
医療・介護両面の情報を扱うため、入所時には膨大な情報が集まります。ケアマネは優先順位をつけ、ケアプランに反映させる情報を選別するスキルが求められます。
家族との意思調整
家族の希望と本人の意向が異なる場合もあります。例えば「家族は施設入所継続を希望するが、本人は在宅復帰を望む」ケースなどです。ケアマネは両者の調整役として、現実的な支援方針を導き出す必要があります。
在宅復帰支援の難しさ
老健では「在宅復帰率」が評価指標となるため、医療的ケアが必要な利用者でも在宅復帰を検討しなければならない場面があります。その際には訪問看護や訪問リハとの連携、地域資源の活用が不可欠です。
まとめ
介護老人保健施設や介護医療院におけるケアマネのアセスメントは、医療・介護・リハビリ・生活環境といった幅広い視点を統合し、多職種と連携しながら進める点が特徴です。
在宅復帰を見据えた評価や、長期療養に伴う生活の質向上を意識した支援方針の検討が求められます。
ケアマネジャーは情報を整理し、本人・家族の意向を尊重しながらケアプランに反映させることで、利用者の生活の質を高める役割を担っています。
施設ケアマネとしてアセスメント力を磨くことは、利用者支援の質を高めるだけでなく、自身の専門性向上にも直結します。















