【コピペOK】看取り・ターミナルのケアプラン文例200事例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
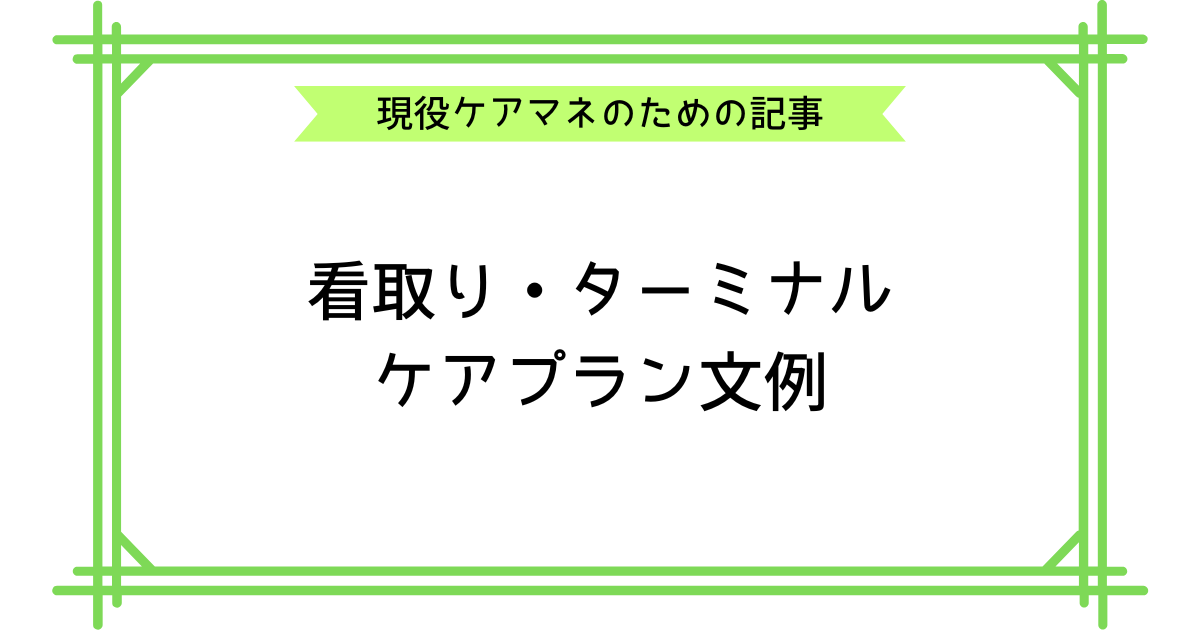
ターミナル期・看取り期のケアプラン作成は、ケアマネジャーにとって最も難しい業務のひとつです。
利用者本人の尊厳を守り、最期まで安心して過ごせるよう支援するためには、医療職・介護職・家族の連携が不可欠です。
しかし実務では、「どんな表現で目標を書けばいいのか」「看取り期にふさわしい文言とは?」と迷う場面が多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、【コピペOK】でそのまま活用できる「看取り・ターミナルのケアプラン文例」を200例まとめて紹介します。
短期目標・長期目標・サービス内容の表現に迷ったときに、ぜひご活用ください。
目次
看取り・ターミナル期のケアプラン作成で意識すべきこと
看取り期やターミナル期は、延命よりも「苦痛の緩和」や「尊厳の保持」が優先されることが多く、ケアプランの表現も通常とは異なります。
たとえば「できるだけ自立を目指す」よりも「安楽に過ごす」「安心して最期を迎える」といった言葉が多用されます。
また、家族への支援や精神的ケアを含める点も特徴です。ケアマネは、医師の方針や本人・家族の意向を踏まえて、文言を柔軟に調整していく必要があります。
長期目標(看取り・ターミナル期のケアプラン)
- 住み慣れた自宅で家族に囲まれ、安楽に最期を迎える。
- 苦痛を最小限に抑え、尊厳を保ちながら生活を継続する。
- 本人の意思を尊重し、希望する場所で最期を過ごすことができる。
- 医療職と介護職が連携し、適切な緩和ケアを継続する。
- 家族の介護負担を軽減しながら、看取りまで支援を続ける。
- 食欲や体力が低下しても、本人らしく過ごせる環境を整える。
- 精神的に安心できる環境の中で、心穏やかに過ごす。
- 苦痛の緩和を優先し、生活の質を保ちながら療養する。
- 家族が本人の意思を理解し、看取りの過程を受け入れられるよう支援する。
- 医療・介護の両面から支援し、本人と家族に安心感を提供する。
- 本人の尊厳を最期まで尊重し、本人らしい時間を過ごす。
- 苦痛がなく、安楽な状態で眠れるよう支援する。
- できる範囲で本人の生活習慣を尊重した療養生活を継続する。
- 家族とともに大切な時間を過ごせるよう支援する。
- 医師の指示に基づき、適切な医療ケアを継続する。
- 本人が不安を抱えず、安心感を持って日々を送れる。
- 最期まで本人らしい表情を保ち、 dignity を守る。
- 家族の意見を取り入れ、納得のいく看取りを実現する。
- 不要な延命治療を行わず、自然な経過を見守る。
- 本人の意思に沿った生活を支援し、尊厳死を目指す。
- 苦痛や不安が軽減され、精神的に落ち着いた状態で過ごす。
- 看護師・医師と連携し、適切な症状緩和を図る。
- 本人の希望に沿った食事や飲水を可能な範囲で支援する。
- 家族が最後まで本人に寄り添えるようサポートする。
- 医療依存度が高くなっても、安楽に過ごせるよう支援する。
- 利用者の価値観を大切にした生活を最期まで保障する。
- 本人が安心できる空間で、平穏に余生を過ごす。
- 苦しみを最小限にし、笑顔で過ごせる時間を持てる。
- 本人の意志決定を尊重し、最期まで意思を反映したケアを行う。
- 在宅での看取りを希望する場合、最後まで継続できるよう調整する。
- 本人の心の安らぎを大切にし、安楽な療養生活を支援する。
- 家族が無理なく介護を継続できる体制を整える。
- 医療処置や介護支援により、症状悪化時も安定して療養できる。
- 苦痛がなく、本人らしい最期を迎えられる。
- 本人の希望に沿い、延命治療を行わず自然な経過を受け入れる。
- 家族と最期まで関わりを持ち、大切な時間を共有する。
- 苦痛をコントロールし、できる限り快適な生活を送る。
- 本人が安心感を持って看取り期を過ごせるよう支援する。
- 家族が本人の意思を理解し、納得感を持って看取りを迎える。
- 医療・介護が一体となり、適切な支援を提供する。
- 本人の人生観を尊重し、価値ある最期を支える。
- 苦痛緩和により、本人が望む生活を実現できる。
- 家族が悔いのない看取りを行えるようサポートする。
- 安らぎを感じながら、最期まで本人らしく過ごす。
- 医療機関や在宅サービスと連携し、安心できる体制を整える。
- 本人の希望に沿ったケアを提供し、尊厳を守る。
- 看取りの過程で本人と家族の不安を軽減する。
- 最期の時まで本人が「自分らしさ」を持って生活する。
- 苦痛や不安を和らげ、穏やかな死を迎えられるよう支援する。
- 家族と共に過ごす時間を大切にし、満足のいく看取りを実現する。
短期目標(看取り・ターミナル期のケアプラン)
- 疼痛コントロールを行い、日中は安楽に過ごせるようにする。
- 呼吸苦が出た際に速やかに対応し、不安を軽減できるようにする。
- 夜間も安心して休めるよう、環境を調整する。
- 食欲低下があっても、好物を少量ずつ口にできるよう支援する。
- 水分補給を可能な範囲で行い、口渇感を和らげる。
- 苦痛時には医師の指示に従い適切に薬を使用できるようにする。
- ベッド上での体位交換を行い、安楽な姿勢を保つ。
- 嘔気・嘔吐の症状がある場合、緩和ケアを優先して対応する。
- 本人の表情が穏やかになる時間を増やす。
- 音楽や会話を取り入れ、リラックスして過ごせる環境を整える。
- 入浴や清拭により清潔を保ち、快適さを維持する。
- 家族が安心して介護できるよう情報を共有する。
- 本人の意思を尊重し、希望に沿った介護を行う。
- 経口摂取が難しい場合も、口腔ケアを継続して行う。
- 苦痛が強まった際には医療職と連携して迅速に対応する。
- 本人の不安を傾聴し、気持ちの安定を図る。
- 家族が不安を抱えた際に相談できる体制を整える。
- 呼吸状態を観察し、異常時は早期に対応する。
- 本人が希望する生活リズムを尊重する。
- 疲労を軽減するため、休息時間を確保する。
- トイレ動作が困難な場合でも dignity を尊重して介助する。
- 本人の好きなものに触れる時間を持つ。
- 苦痛緩和のための医療ケアを継続する。
- 家族が安心して介護に参加できるよう助言を行う。
- 本人が「ありがとう」と言葉にできる時間を増やす。
- 睡眠を妨げないよう夜間のケアを工夫する。
- 家族と一緒に過ごす時間を確保する。
- 本人が不快感を訴えないよう環境を整える。
- 苦痛があるときにすぐ対応できるよう観察を強化する。
- 脱水予防のため、必要な水分を少量ずつ提供する。
- 呼吸が楽になる体位を調整する。
- 苦痛が緩和されるよう、医師の指示に従い薬剤を適切に使用する。
- 本人の希望に沿った生活が送れるよう支援する。
- 家族が介護に自信を持てるよう指導を行う。
- 苦痛の表情を減らし、穏やかな時間を保つ。
- 本人が話したい時に傾聴できる環境を整える。
- 経口摂取ができなくても、口腔内の清潔を維持する。
- 本人がリラックスして過ごせる空間を提供する。
- 家族が安心して過ごせるよう情報を随時共有する。
- 苦痛が最小限に抑えられるよう医療職と連携する。
- 本人の気持ちを尊重し、否定せず受け止める。
- 苦痛が強いときに迅速に医師に連絡できる体制を整える。
- 本人が安楽に呼吸できるよう工夫する。
- 家族の希望を傾聴し、ケアプランに反映する。
- 本人が安心して生活できるよう環境を調整する。
- 家族とともに過ごす時間を増やす工夫をする。
- 苦痛を和らげるための薬剤使用を適切に行う。
- 本人の意思を確認し、可能な範囲で尊重する。
- 安楽な睡眠を確保できるよう支援する。
- 本人が自分らしく過ごせる環境を維持する。
- 家族の負担を軽減できるよう介護方法を提案する。
- 苦痛が緩和されるよう介護職と看護職が連携する。
- 本人が不安を抱かないよう傾聴する。
- 家族が介護を続けられるよう精神的支援を行う。
- 本人の希望を尊重し、最期まで dignified care を行う。
- 苦痛があるときに安心して訴えられる環境を作る。
- 本人が快適に過ごせるようベッド周囲を整える。
- 家族が安心して見守れるよう情報を提供する。
- 苦痛をコントロールし、日中は笑顔で過ごせるよう支援する。
- 本人の表情や仕草から状態を早期に把握する。
- 本人が望む活動をできる限り実現する。
- 苦痛時には医師と速やかに連携して対応する。
- 家族の不安を和らげるため、定期的に声をかける。
- 本人が落ち着いて過ごせるよう環境調整を行う。
- 苦痛が軽減されることで本人が安眠できるよう支援する。
- 本人が最後まで意思表示できるよう傾聴する。
- 苦痛を和らげるマッサージやタッチケアを行う。
- 本人が安心感を持てるよう寄り添う。
- 家族が介護に関わりやすいよう時間を調整する。
- 苦痛緩和を第一に考えたケアを実施する。
- 本人が心地よい環境で過ごせるよう配慮する。
- 苦痛が出ないよう予防的に対応する。
- 家族と一緒に過ごす時間を計画的に設ける。
- 本人の意思を尊重し、無理のない生活を支援する。
- 苦痛や不快感を最小限に抑えるケアを行う。
- 本人が望む生活習慣を可能な範囲で続けられるようにする。
- 苦痛が強くならないよう観察を継続する。
- 家族が安心して本人に接することができるよう助言する。
- 本人が最期まで dignity を保てるよう支援する。
- 苦痛や不安を和らげ、安心して生活できるようにする。
サービス内容文例(看取り・ターミナル期のケアプラン)
- 看護師が定期的に訪問し、バイタル測定と症状緩和を行う。
- 医師の指示に基づき、疼痛コントロールを実施する。
- 看護師が服薬管理を行い、適切なタイミングで投薬を支援する。
- 介護職員が体位交換を行い、安楽な姿勢を維持する。
- 看護師が酸素投与を適切に管理し、呼吸状態を安定させる。
- 介護職員が口腔ケアを行い、口腔内の清潔と安楽を保つ。
- 看護師が皮膚状態を観察し、褥瘡予防の処置を実施する。
- 医師が定期的に往診し、本人と家族に状態を説明する。
- 介護職員が清拭や整容を行い、本人の快適さを維持する。
- 看護師が点滴管理を行い、脱水を予防する。
- 介護職員が排泄介助を行い、 dignity を尊重した支援を行う。
- 看護師が呼吸苦への対応を行い、安楽な呼吸を支援する。
- 介護職員が入浴介助または清拭で清潔保持を行う。
- 看護師が発熱時に迅速に医師へ報告・対応を行う。
- 介護職員が食事介助を行い、可能な範囲で経口摂取を支える。
- 看護師が嘔気や嘔吐への対応を行い、不快感を軽減する。
- 介護職員が就寝時の体位を整え、安眠を支援する。
- 看護師が疼痛緩和のための注射や貼付薬を管理する。
- 介護職員が家族に介護方法を助言し、不安軽減を図る。
- ケアマネが本人と家族にケアプランを説明し、意向を反映する。
- 看護師が呼吸音を確認し、異常があれば早期対応する。
- 介護職員がリネン交換を行い、清潔な環境を整える。
- 看護師が医師と連携し、緩和ケアの方針を共有する。
- 介護職員が環境調整を行い、安楽な空間を提供する。
- 看護師が水分摂取を観察し、必要に応じて補助する。
- 介護職員が会話や傾聴を行い、精神的安定を支援する。
- 看護師が疼痛評価スケールを用いて状態を確認する。
- 介護職員が口腔内の乾燥を予防するため保湿を行う。
- 看護師が緊急時に医師へ連絡し、迅速な対応を取る。
- 介護職員が本人の希望に沿った整容を支援する。
- 看護師が排泄コントロールを観察し、皮膚トラブルを防ぐ。
- 介護職員がベッドサイドでの安楽な体位を工夫する。
- 看護師が在宅医と連携して薬剤の調整を行う。
- 介護職員が眠前の安楽ケアを実施し、安心して休める環境を整える。
- 看護師が不穏時に家族へ状況を説明し安心感を与える。
- 介護職員が本人の好みを尊重した食事介助を行う。
- 看護師が呼吸状態の悪化に備え、酸素や薬剤を準備する。
- 介護職員がベッド周囲を整頓し、安全に過ごせる環境を整える。
- 看護師が服薬効果を評価し、医師と調整を行う。
- 介護職員が本人に声をかけ、安心できる雰囲気を作る。
- 看護師が点滴ラインの管理を行い、感染予防を徹底する。
- 介護職員が家族と一緒にケアを行えるよう支援する。
- 看護師が体調変化をモニタリングし、日々の記録を行う。
- 介護職員が本人に合わせたベッドメイキングを行う。
- 看護師が呼吸苦緩和のため吸引を実施する。
- 介護職員が家族に介助方法を実技で指導する。
- 看護師が疼痛緩和薬の副作用を観察し対応する。
- 介護職員が本人の希望に沿った余暇活動を支援する。
- 看護師が安楽死角度を調整し、呼吸苦を和らげる。
- 介護職員が本人の体調に合わせて介助内容を調整する。
- 看護師が発熱や倦怠感に対応し、苦痛を和らげる。
- 介護職員が排泄介助を行い、羞恥心に配慮する。
- 看護師が不安を訴える本人に寄り添い、精神的安定を図る。
- 介護職員が本人の好みに沿った寝具調整を行う。
- 看護師が緊急時の家族連絡体制を整える。
- 介護職員が本人のペースに合わせた食事介助を行う。
- 看護師が苦痛を軽減する処置を実施する。
- 介護職員が本人の希望に応じて音楽や会話を取り入れる。
- 看護師が薬剤の副作用を観察し、早期に対応する。
- 介護職員が家族と一緒に本人を見守る時間を作る。
- 看護師が酸素飽和度を測定し、状態を記録する。
- 介護職員が本人に合わせたポジショニングを行う。
- 看護師が緩和ケアチームと連携して治療方針を確認する。
- 介護職員が家族にケア状況を説明し、安心感を与える。
- 看護師が本人と家族に今後の症状の見通しを説明する。
- 介護職員が本人が安心できるように声かけを続ける。
- 看護師が疼痛スケールに基づき薬剤投与を行う。
- 介護職員が本人の快適さを第一にケアを提供する。
- 看護師が本人の症状悪化に備えて適切に準備する。
- ケアマネジャーが本人と家族の意向を定期的に確認し、ケアプランを修正する。
まとめ
看取りやターミナル期のケアプランは、本人と家族の尊厳を守りながら最期まで寄り添う支援を反映するものです。
本記事で紹介した【コピペOK】の文例200事例は、現場での文言作成に迷ったときの参考になります。
大切なのは「その人らしさ」を尊重し、一つひとつの言葉に思いを込めることです。
ケアマネジャーとして、本人と家族の安心を支えるケアプラン作成にぜひ役立ててください。















