【コピペOK】腰椎圧迫骨折のケアプラン文例200事例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
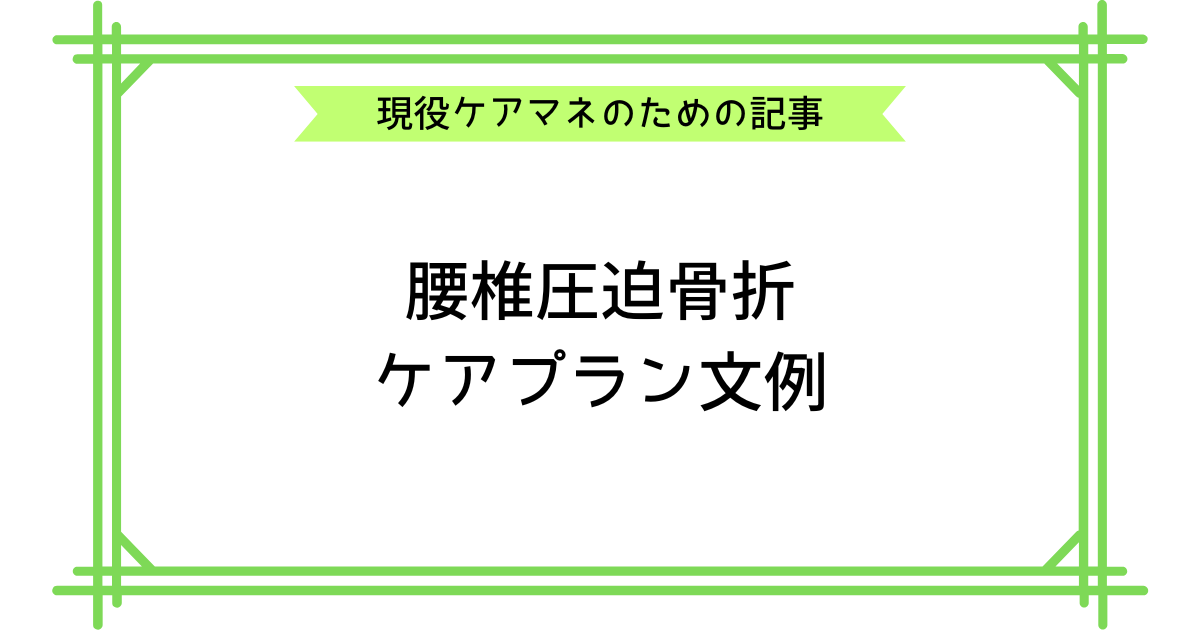
腰椎圧迫骨折は高齢者に多い骨折のひとつで、転倒や骨粗鬆症が原因となるケースが多く見られます。
強い腰痛や動作制限が生じることで、日常生活に大きな影響を与え、要介護状態の悪化につながることも少なくありません。
ケアマネジャーは、骨折後のリハビリ支援、再発予防、生活環境の整備に重点を置いたケアプラン作成が求められます。
この記事では、【コピペOK】で使える腰椎圧迫骨折のケアプラン文例200事例を「長期目標」「短期目標」「サービス内容」に分けて紹介します。
ケアプラン作成時の文言に迷った際に、ぜひ参考にしてください。
目次
長期目標(腰椎圧迫骨折のケアプラン文例)
- 腰椎圧迫骨折後も在宅生活を安心して継続できる。
- 腰痛を軽減し、自立した生活を維持する。
- 再骨折を予防し、安全に生活できる環境を整える。
- リハビリを継続して身体機能を回復する。
- 介助が必要な場面でも dignity を守りながら生活できる。
- 入浴・排泄・食事などの日常生活を自立して行える。
- 本人の希望を尊重し、住み慣れた自宅で生活を続ける。
- 転倒予防を徹底し、骨折の再発を防ぐ。
- 痛みをコントロールし、快適に過ごせる。
- 家族や支援者と協力しながら安心した生活を送る。
- 骨折前の生活にできる限り近づける。
- 栄養を管理し、骨の健康を維持する。
- 外出を継続し、社会参加の機会を持つ。
- 精神的に安定した生活を送る。
- 痛みが軽減し、生活に意欲を持てる。
- 安全に住環境を整え、転倒を予防する。
- 本人の望む生活を実現する。
- 入浴や更衣を安全に行える。
- 再骨折を防ぎ、ADLの低下を予防する。
- 在宅生活を可能な限り継続する。
- 趣味や生きがい活動を続けられる。
- 安心して外出できる。
- 骨粗鬆症治療を継続し、再骨折を防止する。
- 睡眠環境を整え、夜間も安心して過ごせる。
- 本人らしい生活の質を維持する。
- 転倒しにくい動作を身につける。
- 福祉用具を活用して安全に生活できる。
- 本人の不安を軽減する。
- 痛みによる生活制限を最小限にする。
- 家族や地域と交流し孤立を防ぐ。
- 健康状態を維持し、介護度の進行を防ぐ。
- 在宅医療と介護の連携を強化する。
- 不安を和らげ、安心した療養生活を送る。
- 骨折後も dignified life を継続できる。
- 栄養・運動習慣を改善し、再骨折を防止する。
- 本人と家族が安心して暮らせる体制を整える。
- 痛みを和らげ活動範囲を広げる。
- 入浴を安全に行える。
- 生活環境を整備して安全に暮らす。
- 本人の希望を最大限に尊重する。
- 精神的に安定し安心して過ごせる。
- 骨折後の生活を支援し自立を促す。
- 痛みを和らげ、日常生活に取り組む。
- 家族と連携し介護負担を軽減する。
- 住環境を整え再骨折を防ぐ。
- 自宅で安心して療養する。
- 本人が望む生活を支援する。
- 体力低下を防ぎ、活動性を維持する。
- 転倒リスクを回避し安全に生活する。
- 骨折後も在宅生活を継続できるよう支援する。
短期目標(腰椎圧迫骨折のケアプラン文例)
- 痛みを軽減し、安楽に過ごす。
- ベッドからの起き上がりを安全に行う。
- 車椅子からの移乗を介助下で安全に行う。
- 歩行器を使用して安全に移動する。
- 排泄動作を介助下で行う。
- 入浴時に転倒しないよう支援を受ける。
- 毎日水分を摂取し、健康を維持する。
- 食事を自立して摂取する。
- 睡眠環境を整えて安眠する。
- 服薬を忘れずに行う。
- 痛みに合わせて動作を調整する。
- リハビリで体幹を強化する。
- トイレ動作を安全に行う。
- 住環境を整えて転倒を防ぐ。
- 外出練習を安全に行う。
- 家事を一部再開する。
- 清潔を保ち快適に過ごす。
- 痛みを緩和する体位を保持する。
- 更衣を介助下で安全に行う。
- 移動時の不安を軽減する。
- 軽い運動を継続する。
- 呼吸を整えながら動作する。
- 痛みが増強したとき速やかに対応する。
- バイタルを測定して状態を把握する。
- 栄養補助食品を摂取する。
- デイケアでリハビリを受ける。
- 定期的に安否確認を受ける。
- 入浴サービスを利用して清潔を保つ。
- 訪問看護で体調を確認する。
- 福祉用具を適切に利用する。
- 適切な靴を使用して歩行を安定させる。
- ベッドからの立ち上がりを安全に行う。
- 移動時に介助を受ける。
- 夜間の不安を軽減する。
- 趣味を継続して生活に意欲を持つ。
- 家族と連絡を取り安心感を得る。
- 外出を段階的に再開する。
- 配食サービスを利用する。
- 服薬支援を受ける。
- 掃除を支援して住環境を整える。
- 家事の一部を行い自立性を維持する。
- 生活リズムを整える。
- 疲労を感じたら休息を取る。
- 転倒リスクを減らす環境を整える。
- ベッド柵を使用して転落を防ぐ。
- 移乗時に声かけを受けて安心する。
- 痛みが強いとき医師へ相談する。
- 看護師の観察を受ける。
- 外出時にヘルパーが同行する。
- 排泄を安全に行えるよう介助を受ける。
- リハビリで柔軟性を維持する。
- 歩行練習を継続する。
- 医師の診察を定期的に受ける。
- 趣味活動に参加する。
- デイサービスで入浴を行う。
- 夜間も安心して眠る。
- 服薬を継続する。
- バランスの良い食事を摂取する。
- 排泄リズムを整える。
- 不安を訴えたとき傾聴を受ける。
- 転倒防止のため手すりを利用する。
- 運動を継続して体力を維持する。
- 栄養補助を行い健康を保つ。
- 移動時に杖を使用する。
- 室内を整理して安全に過ごす。
- 家族と相談し不安を軽減する。
- 支援者の声かけで安心感を得る。
- 不眠時に医師へ相談する。
- デイケアで生活リハを行う。
- 入浴時に手すりを活用する。
- 訪問リハで機能訓練を受ける。
- 買い物を支援して生活を維持する。
- ゴミ出しを支援して清潔を保つ。
- バイタルを確認する。
- 夜間の照明を工夫して転倒を防ぐ。
- 趣味活動で気分を整える。
- 不安時に相談できる環境を整える。
- 家族と連絡を取り孤独感を軽減する。
- 定期訪問で安否確認を受ける。
- 安心して日常生活を送る。
サービス内容文例(腰椎圧迫骨折のケアプラン文例)
- 訪問介護で掃除・洗濯を行う。
- 配食サービスを利用して栄養を確保する。
- 訪問リハで歩行訓練を行う。
- デイケアで機能訓練を受ける。
- デイサービスで入浴支援を受ける。
- 訪問看護師がバイタル測定を行う。
- 福祉用具を導入して転倒を防ぐ。
- 介護職員が移乗を支援する。
- 医師が往診を行う。
- 看護師が服薬管理を行う。
- デイサービスでレクリエーションに参加する。
- 訪問介護でごみ出しを支援する。
- 訪問リハで筋力訓練を行う。
- 配食サービスを夕食に利用する。
- デイサービスで口腔ケアを行う。
- 訪問看護で疼痛管理を行う。
- ケアマネが定期訪問して状況を確認する。
- 訪問介護で掃除を行い転倒リスクを減らす。
- 医師と看護師が連携して症状を管理する。
- デイサービスで機能訓練を行う。
- 訪問リハで関節可動域訓練を行う。
- 訪問看護で健康相談を行う。
- 配食サービスを昼食に利用する。
- デイケアで生活リハを継続する。
- 訪問介護で買い物支援を行う。
- 福祉用具を調整して安全を確保する。
- デイサービスで趣味活動に参加する。
- 訪問看護師が体調を観察する。
- 訪問リハでバランストレーニングを行う。
- ケアマネがサービス担当者会議を開催する。
- 訪問介護で調理支援を行う。
- デイサービスで入浴介助を受ける。
- 訪問看護で点滴管理を行う。
- 配食サービスを朝食で利用する。
- デイケアで社会参加を継続する。
- 訪問介護で安否確認を行う。
- 医師の往診で状態を確認する。
- 看護師が睡眠状態を観察する。
- 訪問リハで歩行練習を行う。
- デイサービスで趣味活動を行う。
- 訪問看護師が服薬指導を行う。
- 介護職員が体位変換を行う。
- 訪問介護で掃除を行う。
- デイサービスでADL維持を支援する。
- 訪問看護で疼痛コントロールを行う。
- ケアマネが定期モニタリングを行う。
- 訪問介護で洗濯を行う。
- 訪問リハで歩行補助具の指導を行う。
- デイサービスで機能訓練を行う。
- 訪問看護師が状態を記録する。
- 配食サービスを夕食に利用する。
- 訪問介護で調理を行う。
- デイケアで日常動作訓練を行う。
- 訪問リハで家庭内動作練習を行う。
- 看護師が体調急変時に医師と連携する。
- 介護職員が安全に移乗を行う。
- 訪問介護で買い物代行を行う。
- デイサービスで入浴支援を行う。
- 訪問看護で服薬を確認する。
- 配食サービスを利用して栄養を補う。
- ケアマネが本人と家族の意向を確認する。
- 訪問リハで必要動作の練習を行う。
- デイサービスで交流を図る。
- 訪問看護師がバイタルを測定する。
- 訪問介護で掃除を行う。
- デイサービスでレクリエーションを行う。
- 訪問リハで歩行訓練を続ける。
- 訪問看護で症状を観察する。
- 介護職員が安否確認を行う。
- ケアマネがケアプランを定期的に見直す。
まとめ
腰椎圧迫骨折のケアプランでは、「再骨折予防」「疼痛緩和」「生活支援」が特に重要です。
今回紹介した200の【コピペOK】文例を活用すれば、実際のケアプラン作成に迷ったときの大きな助けになります。
利用者の状況に応じて調整しながら、本人の安心と安全を支えるケアプランを作成しましょう。















