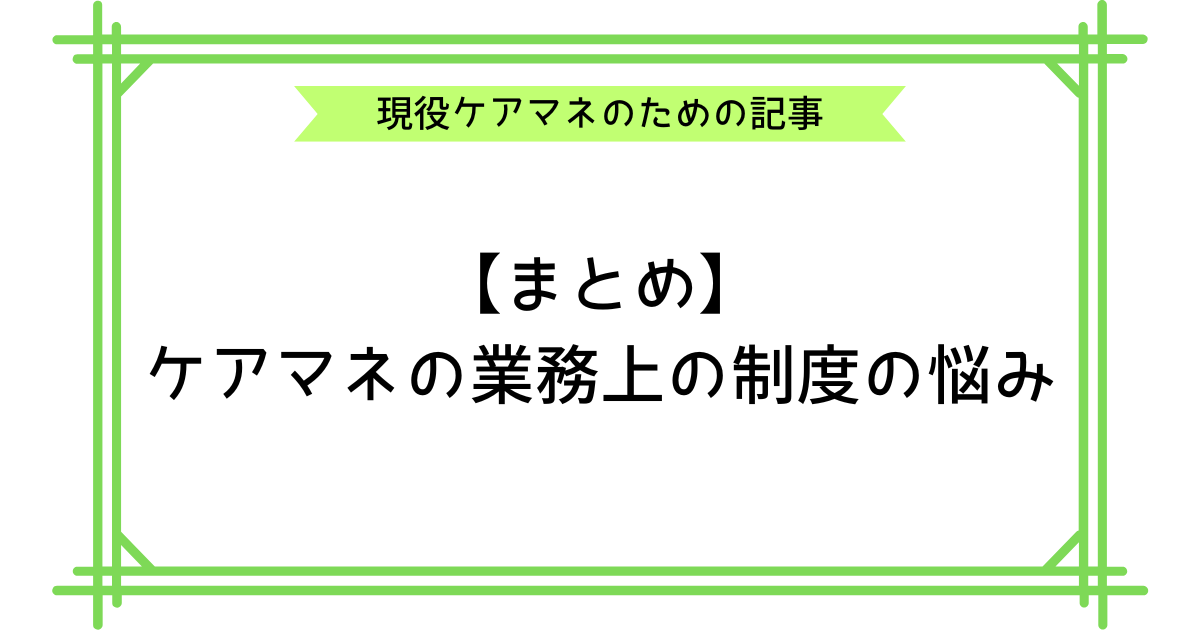ケアマネは担当利用者の預金の引き出しは可能?不可能?良い方法も紹介
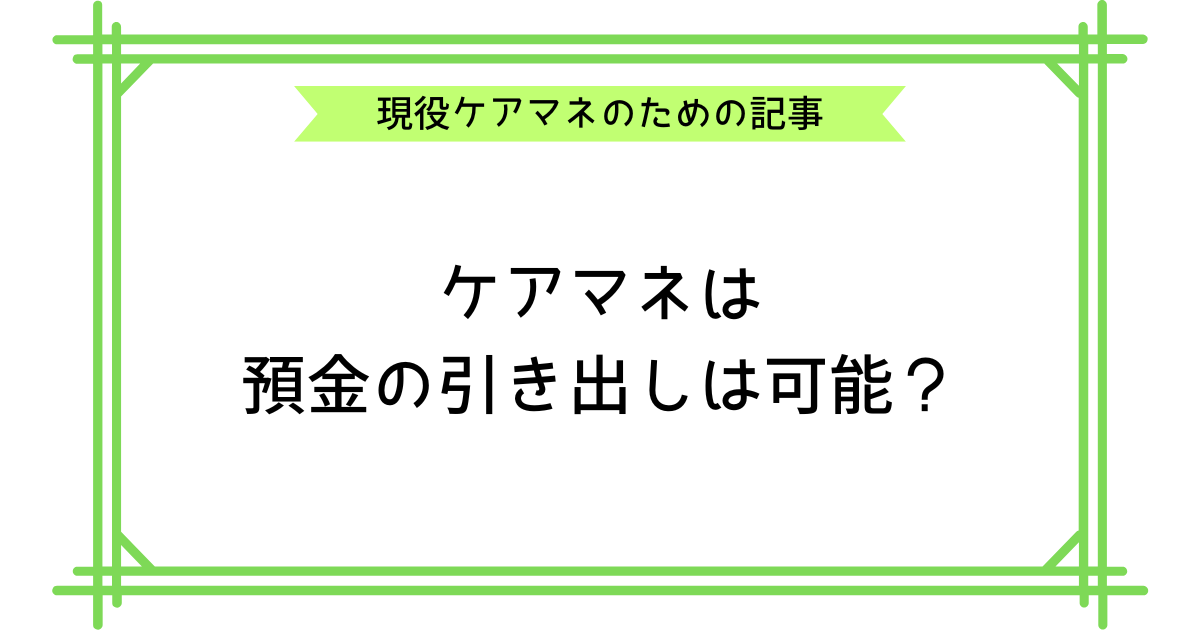
ケアマネジャー(介護支援専門員)は、利用者の生活全般を支える調整役として重要な役割を担っています。
その中で、利用者や家族から「預金の引き出しをお願いできませんか?」と頼まれることがあります。
特に独居高齢者や認知症の方、家族が遠方に住んでいるケースでは、お金の管理や銀行での手続きが大きな課題になります。
しかし、結論から言うと ケアマネが利用者の預金を引き出すことはできません。
法律や制度上の理由があり、ケアマネ自身が金銭管理を行うことは禁じられています。
本記事では、なぜケアマネが預金を扱えないのか、その根拠や背景を詳しく解説するとともに、利用者のお金の管理が必要な場合にどのような代替方法があるのかを紹介します。
ケアマネの業務範囲と金銭管理の違い
ケアマネの業務は介護保険法に基づき「介護サービス計画の作成」「サービス提供事業者との連絡調整」「モニタリング」「給付管理」などが中心です。
あくまで介護サービスの利用を支援する立場であり、金銭の直接的な管理や代行は含まれていません。
一方で預金の引き出しや家計管理は、法律上「財産管理」にあたり、成年後見人や本人、もしくは法的に委任を受けた人のみが可能です。
ケアマネが利用者の預金通帳やキャッシュカードを預かり、銀行から引き出す行為は、業務範囲を逸脱しており不正行為とみなされる可能性 があります。
ケアマネが利用者の預金を引き出せない理由
法律上の制約
ケアマネは介護支援専門員として介護保険制度に基づく支援を行う立場ですが、財産管理の権限は一切付与されていません。銀行での預金引き出しは「本人または法的代理人」でなければ行えないため、ケアマネが代理で行うことはできません。
トラブル防止の観点
もしケアマネが利用者の預金を扱えば、万一お金が紛失したり使途に疑義が出た際に「横領」「不正使用」と疑われるリスクが極めて高いです。利用者・家族との信頼関係を守るためにも、金銭に直接触れないことが大原則です。
保険制度外の行為であるため
預金の引き出しやお金の管理は介護保険サービスではなく、報酬算定もできません。事業所としても業務外のことを行えば、指導や行政処分の対象となる可能性があります。
実際に起きたトラブル事例
現場では「お金を引き出してきてほしい」と頼まれ、善意で対応したケアマネが後にトラブルに巻き込まれるケースも報告されています。
- 預かったお金が紛失し、横領を疑われた
- 利用者の死亡後、相続人から使途を問われ責任問題になった
- 銀行で代理出金をした際に金融機関から不正扱いされた
このように、たとえ利用者や家族からの頼みでも、ケアマネが金銭を扱うことは大きなリスクになります。
預金管理や引き出しが必要な時の代替方法
成年後見制度を活用する
判断能力が低下している高齢者の場合、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう方法があります。後見人には財産管理権限があり、預金の引き出しや生活費の支払いが可能です。
日常生活自立支援事業を利用する
社会福祉協議会が行っている「日常生活自立支援事業」では、福祉サービス利用援助の一環として通帳や印鑑を預かり、公共料金の支払いや日常的な出金の支援を行ってくれます。認知症や軽度の判断力低下がある人に有効な方法です。
銀行の代理人カードや口座サービスを利用する
一部の金融機関では「代理人カード」制度があり、家族や信頼できる人が代理で預金を引き出せる仕組みがあります。ケアマネ自身ではなく、家族や後見人に依頼することで安全に出金が可能です。
家族の協力を得る
遠方の家族であっても、定期的に来訪して手続きする、オンラインバンキングを利用するなどの方法で協力できる場合があります。ケアマネは家族との連携を図り、実際の金銭管理は家族に任せるのが適切です。
ケアマネができる適切な支援とは?
ケアマネはお金を直接扱うことはできませんが、以下のような間接的なサポートは可能です。
- 成年後見制度や日常生活自立支援事業の情報提供・手続き案内
- 金銭管理に関する相談窓口の紹介
- 家族や支援者との調整役としてのサポート
つまり、ケアマネがすべきことは「自分が預金を管理すること」ではなく、利用者にとって安全で法的に問題のない仕組みにつなげること です。
まとめ
ケアマネは担当利用者の預金を引き出すことはできません。
- 法律上の権限がない
- トラブルのリスクが高い
- 介護保険制度の業務範囲外である
これらの理由から、直接お金を扱うのは厳禁です。
しかし、成年後見制度や日常生活自立支援事業、銀行の代理人カードなど、利用者の生活を支える仕組みは整っています。ケアマネはそれらを紹介し、家族や関係機関と連携して利用者の金銭管理を支援する役割を担うべきです。
ケアマネは「お金を扱う人」ではなく「安心できる仕組みへ導く人」。その立場を理解して行動することで、利用者の生活と権利を守ることができます。