【コピペOK】訪問診療・往診に関するケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
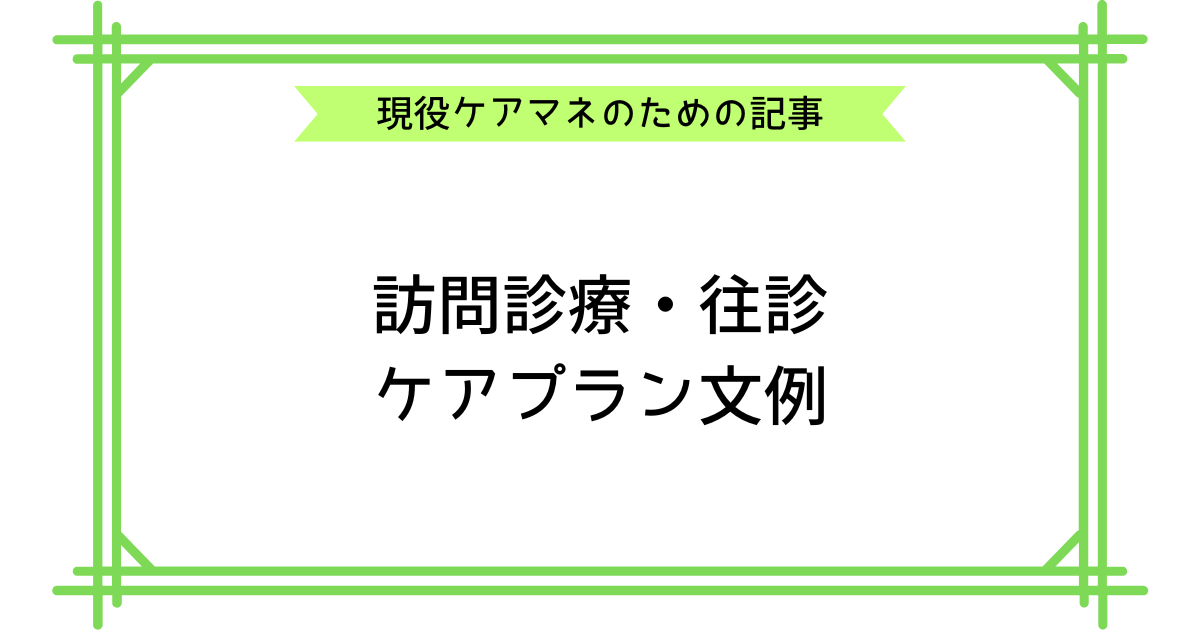
在宅療養を継続するためには、医師が定期的に自宅を訪問して診察や治療を行う「訪問診療」と、急変時に対応する「往診」が重要です。
ケアプランには、訪問診療の目的や往診時の対応を具体的に記載することで、チーム全体が統一した支援を行いやすくなります。
この記事では、実務ですぐに使える訪問診療・往診に関するケアプラン文例を100事例紹介します。
目次
訪問診療・往診に関するケアプラン文例
定期訪問診療に関する文例(1〜25)
- 月2回の訪問診療を受け、全身状態を定期的に確認する。
- 定期的な診察により、持病(高血圧・糖尿病など)の管理を継続する。
- 訪問診療時にバイタルサインを測定し、体調変化を早期に把握する。
- 訪問診療により、薬の処方や調整を受ける。
- 訪問診療で採血検査を行い、健康状態を確認する。
- 医師による訪問診療で、症状悪化の早期発見を図る。
- 訪問診療での診察内容をケアマネに共有し、ケアプランに反映する。
- 訪問診療を通じて、主治医と介護スタッフが情報連携を図る。
- 訪問診療により、自宅での終末期医療を継続できるよう支援する。
- 訪問診療での診察後、必要に応じて他職種とのカンファレンスを実施する。
- 訪問診療で皮膚の観察を行い、褥瘡の予防を徹底する。
- 定期訪問で服薬内容を見直し、副作用を予防する。
- 訪問診療により、慢性疾患の状態を安定的に維持する。
- 訪問診療での指示に基づき、看護師が処置を実施する。
- 訪問診療を通じて、在宅療養生活を継続できるようにする。
- 定期的な診察を受け、急変時の往診体制を整備する。
- 訪問診療で栄養状態を確認し、必要に応じて栄養指導を受ける。
- 訪問診療により、服薬アドヒアランスを高める。
- 定期的な診察でリハビリの必要性を確認する。
- 訪問診療時に家族へ説明を行い、不安を軽減する。
- 訪問診療を継続し、施設入所を回避できるよう支援する。
- 訪問診療により、安心して自宅で療養生活を送れるようにする。
- 訪問診療での診察結果を訪問看護と共有する。
- 訪問診療で、予防接種の実施を行う。
- 定期診察で在宅酸素療法の管理を継続する。
急変時の往診に関する文例(26〜50)
- 発熱時には往診を依頼し、早期対応を図る。
- 呼吸苦が出現した際には往診を受け、適切な処置を行う。
- 意識障害が見られた際には往診を依頼し、医師の判断を仰ぐ。
- 転倒による怪我があった場合、往診を受けて処置する。
- 急な疼痛時に往診を受け、鎮痛薬の調整を行う。
- 嘔吐や下痢が続いた場合、往診で診察を受ける。
- 夜間の体調不良時に往診を依頼し、安心を確保する。
- 急変時に往診を受け、入院の必要性を判断する。
- 往診による点滴治療を受け、体調回復を図る。
- 発作が見られた際には往診で処置を受ける。
- 血圧が異常に高い場合は往診を依頼し、対応を受ける。
- 呼吸状態の悪化時に往診を受け、在宅酸素療法を調整する。
- 体調急変時に往診を依頼し、家族の不安を軽減する。
- 突然の胸痛時に往診を受け、緊急搬送の要否を判断する。
- 発熱時に往診を依頼し、感染症の有無を確認する。
- 便秘や排尿困難が見られた際には往診を依頼する。
- けいれん発作時に往診で対応を受ける。
- 腹痛が強い場合は往診を依頼する。
- 転倒による打撲・骨折が疑われる場合、往診を依頼する。
- 服薬による副作用が出た際に往診を受ける。
- 精神的な混乱が見られた場合、往診で診察を受ける。
- 夜間・休日の急変時に往診を依頼し、速やかに対応する。
- 急な倦怠感が出た場合、往診を受けて原因を確認する。
- 発作後の意識レベル確認を往診で行う。
- 体調不良時に往診を受け、在宅療養の継続を可能にする。
薬剤管理に関する文例(51〜70)
- 訪問診療で処方薬を調整し、副作用を予防する。
- 訪問診療で新しい薬が出た場合、服薬管理を徹底する。
- 薬の飲み忘れを防ぐため、医師と相談し処方形態を工夫する。
- 薬の副作用が疑われた際には、訪問診療時に相談する。
- 薬の服用方法を訪問診療で確認し、正しく内服できるようにする。
- 訪問診療で薬の残数を確認し、過不足がないようにする。
- 定期的に薬の効果を評価し、必要に応じて処方を変更する。
- 薬剤師と連携し、服薬管理の徹底を図る。
- 症状に合わせてPRN薬(頓用薬)を処方してもらう。
- 内服薬の管理方法を家族に説明する。
- 訪問診療でインスリン注射の管理を受ける。
- 在宅酸素療法中の薬の使用について訪問診療で確認する。
- 高齢による多剤併用を見直し、適正処方を実施する。
- 訪問診療で漢方薬の処方を受け、症状緩和を図る。
- 鎮痛薬の使用状況を訪問診療時に確認する。
- 薬の管理方法について家族と医師で情報を共有する。
- 認知症による飲み忘れに対応するため、医師に処方を調整してもらう。
- 貼付薬の副作用について、訪問診療で確認する。
- 薬の内服に拒否がある場合、訪問診療で代替策を検討する。
- 医師・薬剤師と連携し、ポリファーマシーを防ぐ。
終末期ケア・看取りに関する文例(71〜85)
- 訪問診療を通じて、終末期の苦痛を和らげる。
- 医師による訪問診療で、疼痛コントロールを実施する。
- 看取り期に訪問診療を強化し、最期まで自宅で過ごせるよう支援する。
- 訪問診療での指示に基づき、訪問看護が症状緩和を行う。
- 医師の訪問診療により、家族が安心して看取りを行えるようにする。
- 終末期に往診を受け、苦痛を最小限に抑える。
- 看取り期に訪問診療を定期化し、常時体調を観察する。
- 往診で症状に応じた薬剤を処方し、苦痛を緩和する。
- 家族に終末期ケアについて医師から説明してもらう。
- 医師の往診により、延命処置を行わない方針を確認する。
- 訪問診療で本人の意思を確認し、尊厳を保つ。
- 終末期において、訪問診療と訪問看護が連携して支援する。
- 医師の往診により、穏やかな最期を迎えられるようにする。
- 終末期に医師が往診で家族へ助言を行う。
- 訪問診療で看取り期のケアプランを見直す。
家族連携・多職種連携に関する文例(86〜100)
- 訪問診療での診察内容を家族に説明し、理解を深める。
- 家族が安心できるよう、往診時に一緒に説明を受ける。
- 医師の訪問診療で、家族の不安を軽減する。
- 往診に立ち会った家族に症状経過を伝える。
- 訪問診療で医師と看護師が連携し、ケアを統一する。
- 往診時に介護職員と情報を共有し、ケアの一貫性を保つ。
- 医師の訪問診療を通じて、リハビリスタッフと情報交換を行う。
- 薬剤師と医師が訪問診療時に連携し、服薬管理を徹底する。
- 家族が不安な点を訪問診療時に質問できるよう支援する。
- 医師の訪問診療で今後の治療方針を確認する。
- 往診時に緊急連絡体制を確認する。
- 多職種カンファレンスに訪問診療の情報を共有する。
- 医師と訪問看護が往診時に協働し、適切な処置を実施する。
- 家族が希望する看取りの形を、往診時に医師と確認する。
- 訪問診療・往診を通じて、安心して在宅療養を継続できるようにする。
まとめ
訪問診療や往診は、在宅療養を支える大切な医療サービスです。
本記事では、定期診療・急変時対応・薬剤管理・終末期ケア・家族連携と幅広い場面を想定して、100の文例を紹介しました。
そのままコピペしてケアプランに活用できるようにしてあります。















