ケアマネが「疲れた」と感じる理由と対処法|燃え尽きないための工夫とは
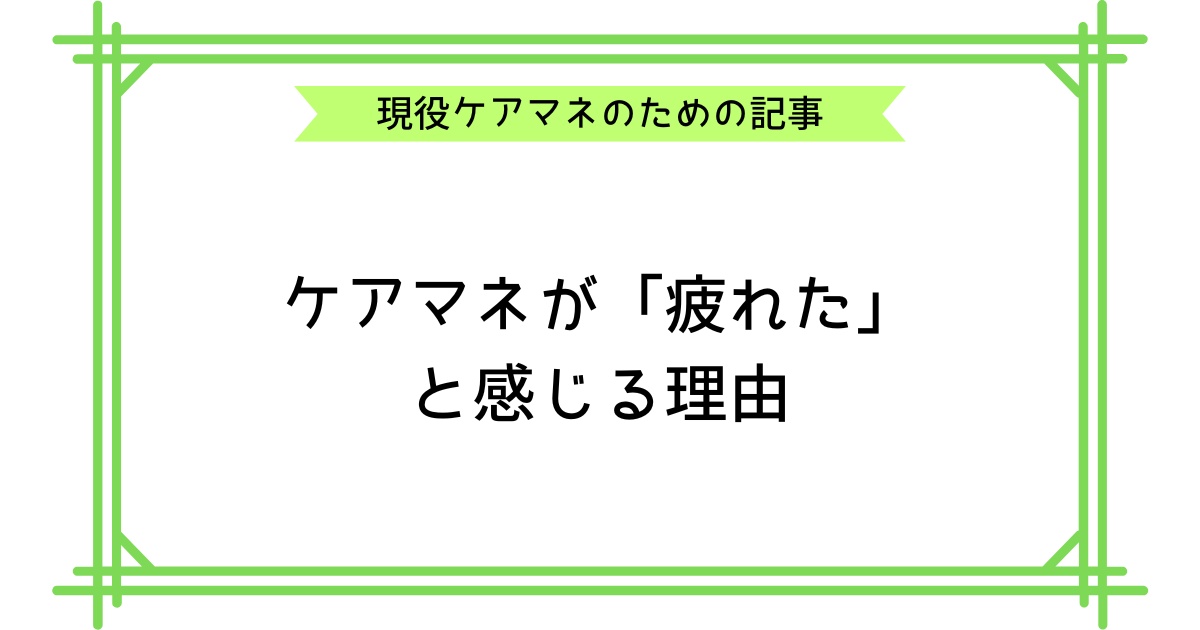
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、利用者のケアプラン作成やサービス調整、家族からの相談対応など多岐にわたる業務を担っています。
責任が重くやりがいのある仕事である一方、「もう疲れた」「限界かもしれない」と感じる人も少なくありません。
本記事では、ケアマネが疲れを感じる背景とその原因、疲れたときの対処法や働き方の工夫を詳しく解説します。
ケアマネが「疲れた」と感じる主な理由
ケアマネは制度上・業務上の特性から、疲労やストレスが蓄積しやすい職種です。
業務量の多さと書類作成の負担
ケアマネの仕事は、ケアプラン作成、モニタリング、給付管理、サービス担当者会議など多岐にわたり、書類作業が膨大です。業務効率化が進まない職場では、残業が常態化し「疲れた」と感じやすくなります。
利用者・家族対応のストレス
利用者本人だけでなく家族からの相談や要望にも応える必要があり、ときには板挟みになることも。感情的なクレーム対応が続くと精神的な疲労が強まります。
人手不足によるプレッシャー
ケアマネ不足が全国的に問題となっており、担当件数が多すぎる事業所もあります。規定の35件を超えるケースを持たされることもあり、心身の負担が増大します。
制度改正や業務範囲拡大
介護保険制度は数年ごとに改正されるため、新しいルールや加算への対応が求められます。制度変更のたびに業務が複雑化し、負担が増えるのも疲労の要因です。
ケアマネが疲れたときの対処法
同僚や上司に相談する
一人で抱え込むとストレスは増す一方です。信頼できる同僚や上司に相談することで、負担の分散や改善策が見えてきます。
業務効率化を意識する
ICTシステムやケアプラン作成ソフトを活用することで、書類作成や情報共有の効率を上げることができます。
担当件数の調整を求める
件数が過剰な場合は、事業所に担当数の見直しをお願いすることも必要です。無理を続けると離職につながってしまいます。
趣味や休養でリフレッシュする
休みの日は仕事を忘れ、趣味や運動でリフレッシュすることが心身の安定につながります。
ケアマネとして働き続けるための工夫
自分のキャリアを見直す
「なぜケアマネを続けるのか」を考え直すことで、モチベーションを取り戻せる場合があります。主任ケアマネや管理職を目指すなど、新しい目標を設定するのも一つの方法です。
転職を視野に入れる
事業所の体制や人間関係によって疲労度は大きく異なります。環境が合わないと感じたら、転職で改善できる場合もあります。ケアマネ資格は需要が高いため、選択肢は豊富です。
他資格とのダブルライセンスを検討する
社会福祉士や看護師、リハ職などとの資格を組み合わせることで、働き方の幅が広がり、疲弊せずにキャリアを続けやすくなります。
まとめ
ケアマネが「疲れた」と感じるのは、業務量の多さや利用者・家族対応のストレス、人手不足や制度改正など複数の要因が重なるためです。
対処法としては、相談・効率化・件数調整・リフレッシュなどが有効であり、長く続けるためにはキャリアの見直しや転職も選択肢となります。
大切なのは「一人で抱え込まないこと」。
ケアマネの専門性は社会に必要とされているからこそ、無理なく働き続ける工夫が求められます。















