ケアマネは嘘つき?そう感じてしまう理由と正しい対応方法
当ページのリンクには広告が含まれています。
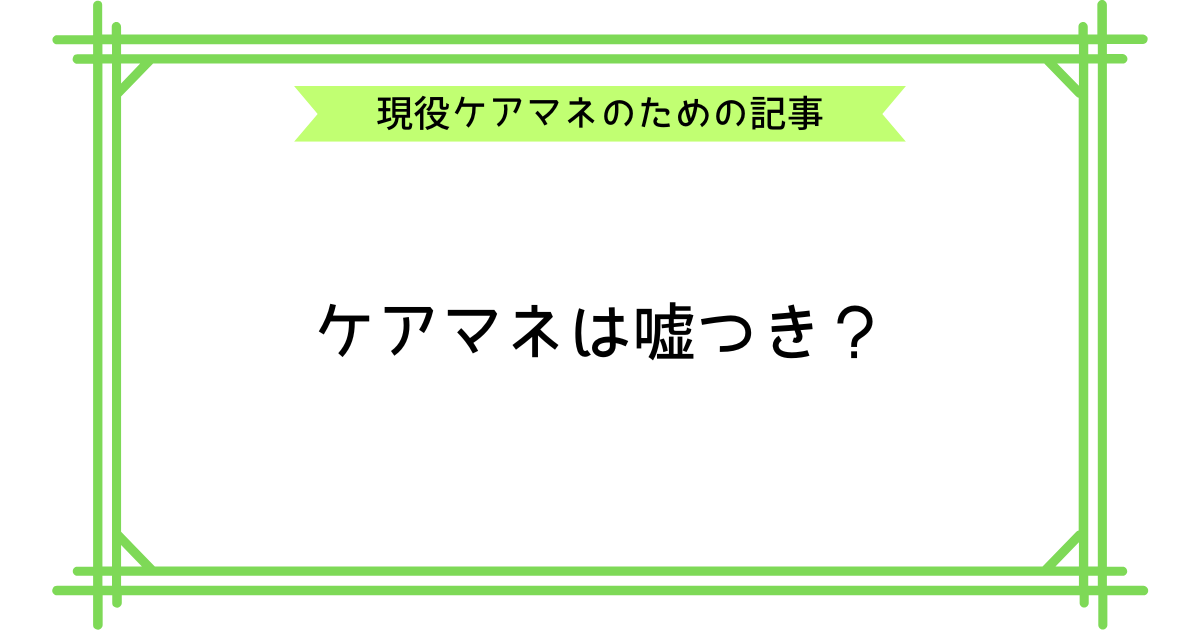
介護サービスを利用する際、ケアマネジャー(介護支援専門員)は利用者や家族にとって一番身近な相談相手です。
しかしインターネット上には「ケアマネは嘘つきだ」「信用できない」といった声も見られます。
果たしてケアマネは本当に嘘をついているのでしょうか。それとも誤解や情報の行き違いなのでしょうか。
この記事では、なぜ「ケアマネ=嘘つき」と感じてしまうのか、その背景と正しい対処法 を解説します。
目次
ケアマネを「嘘つき」と感じる主な理由
1. 説明不足による誤解
- サービス内容や利用回数について説明が不十分
- 制度上できないことを「できます」と誤解させてしまう
- 法改正の影響を十分に伝えていない
2. サービス調整の板挟み
- 利用者と事業所、医師、家族の意向が一致せず、調整の中で話が変わってしまう
- 「昨日はできると言ったのに、今日はできないと言われた」といった矛盾が生じる
3. 忙しさによる対応のずれ
- ケアマネの業務量は多く、連絡ミスや確認不足が起きやすい
- その結果「言ったことと違う」と不信感を持たれることがある
4. 実際に信頼性に欠けるケアマネも存在
- 全員ではないが、中には業務を軽視したり、利用者本位ではなく事業所都合を優先するケアマネもいる
- 「サービスを制限された」「勝手にケアプランを変更された」といった声につながる
ケアマネは本当に「嘘」をついているのか?
多くの場合、ケアマネが意図的に嘘をついているわけではなく、制度の複雑さや説明不足が原因 で誤解が生じています。
介護保険制度は3年ごとに改正され、サービスの基準や加算条件も頻繁に変わります。ケアマネは最新情報をもとに説明しますが、すべてを完璧に伝えることは難しく、誤解が生じやすいのです。
ケアマネに不信感を持ったときの対応方法
1. 説明を再度求める
「なぜできないのか?」「どういう制度上の根拠があるのか?」を確認しましょう。
介護保険法や厚生労働省の基準に基づく説明を受ければ納得できることも多いです。
2. ケアプランに目を通す
ケアプランや利用票・提供票にはサービス内容が明記されています。口頭説明だけでなく、書類で確認すること がトラブル防止につながります。
3. 管理者や地域包括支援センターに相談
どうしても信頼できない場合は、ケアマネの所属する居宅介護支援事業所の管理者や、地域包括支援センターに相談できます。
4. ケアマネを変更する
担当ケアマネを変更することも可能です。信頼できるケアマネと出会うことで状況が大きく改善するケースもあります。
信頼できるケアマネの特徴
- 利用者・家族の意向をきちんと聞いてくれる
- 制度上できないことは「できない理由」を明確に説明してくれる
- サービス事業所や医師と公平に調整してくれる
- トラブルがあっても隠さず共有し、一緒に解決しようとしてくれる
まとめ
「ケアマネは嘘つき」と感じるのは、
- 説明不足
- 情報の食い違い
- 制度の複雑さ
- 一部の不誠実な対応
が原因であることが多いです。
解決のためには、
- 書面での確認
- 制度の根拠を聞く
- 相談窓口の活用
- 担当変更の検討
といったステップを踏むことが大切です。
ケアマネは本来、利用者や家族を支える専門職です。信頼関係を築けるケアマネと出会うことで、安心して介護サービスを利用することができます。















