居宅ケアマネが「辛い」と感じる理由とその対処法を徹底解説
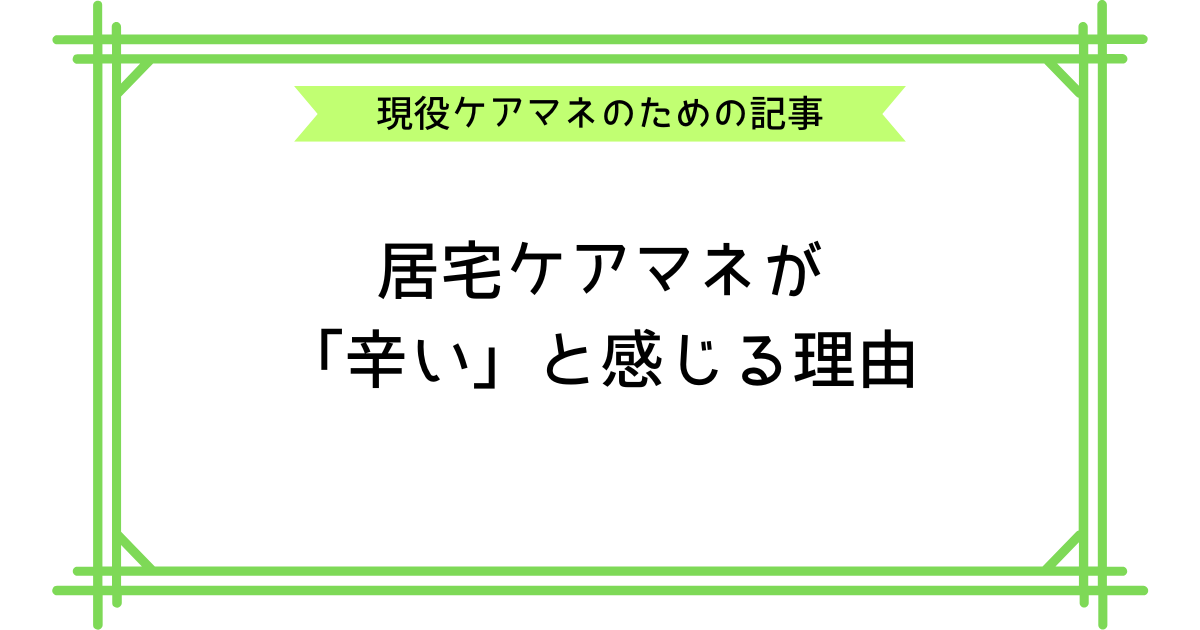
居宅介護支援事業所で働くケアマネジャー(居宅ケアマネ)は、高齢者やその家族を支える重要な存在です。
しかし現場では「仕事が辛い」「もう辞めたい」と感じる声が少なくありません。
利用者・家族・事業所・行政と幅広く関わるため、精神的にも身体的にも負担が大きい職種だからです。
本記事では、居宅ケアマネが辛いと感じる主な理由と背景、具体的な対処法、長く働き続けるための工夫についてわかりやすく解説します。
同じ悩みを抱えるケアマネの方にとって、少しでも参考になるようにまとめました。
居宅ケアマネが「辛い」と感じやすい理由
業務量が多すぎる
居宅ケアマネの最大の悩みは、業務の多さです。アセスメントからケアプラン作成、サービス担当者会議の開催、モニタリング、給付管理、記録、さらに利用者や家族からの相談対応まで幅広い仕事があります。
1人あたりの担当件数は原則35件以内とされていますが、実際にはギリギリの件数を抱えるケースも多く、常に業務に追われる状況になりやすいのです。
利用者・家族からの期待やクレーム
利用者や家族はケアマネに大きな期待を寄せています。その分、**「すぐに対応してほしい」「もっとサービスを増やしてほしい」**といった要望やクレームも日常的に発生します。時には理不尽な怒りをぶつけられることもあり、精神的なストレスの大きな原因となります。
他職種との調整の難しさ
居宅ケアマネは、訪問介護、訪問看護、デイサービス、福祉用具、医師など多職種との連携を担います。しかし、各事業所の方針や考え方は異なり、調整に苦労する場面が多々あります。特にサービス事業所からの囲い込みや断り、医師との情報共有不足などが起こると、板挟みになって辛さを感じやすくなります。
給料が責任に見合わない
ケアマネは大きな責任を負う仕事ですが、給与面では「思ったより安い」と感じる人も少なくありません。特に居宅ケアマネは管理職ではないことが多く、夜間対応などもあるのに給料が上がりにくい点が不満として挙がります。
人間関係のストレス
事業所内での人間関係や上司との関係に悩むケアマネも多いです。特に少人数事業所では人間関係の悪化がダイレクトに仕事の辛さにつながります。孤立感を抱えやすく、**「誰にも相談できない」**状況に追い込まれることもあります。
居宅ケアマネの辛さが深刻化する時期
新人ケアマネの1年目
資格を取得したばかりの新人ケアマネは、制度や加算要件を理解しながら実務を覚えなければならず、知識不足と責任の重さのギャップに苦しむケースが多いです。
繁忙期(モニタリング・給付管理)
月末・月初は給付管理業務が集中するため、通常業務に加えて大きな負担になります。特に利用票や提供票の交付が遅れると事業所全体に影響が出るため、プレッシャーが大きく「この時期は本当に辛い」と感じやすいです。
担当件数が急増した時
人員不足で急に担当件数が増えたり、退職者の分を引き継いだりすると、業務過多で体力的にも精神的にも限界を感じやすくなります。
「居宅ケアマネが辛い」と感じたときの対処法
1. 業務を効率化する
- ICTツールを導入して記録や給付管理を効率化
- スケジュールを「ルーティン化」して業務の見通しを立てる
- テンプレートを活用して文書作成の時間を削減
小さな工夫を積み重ねることで、業務量の負担を軽減できます。
2. 同僚や上司に相談する
辛さを1人で抱え込むと burnout(燃え尽き症候群)につながります。同僚や上司に相談することで、具体的なアドバイスや共感が得られ、気持ちが楽になるケースは少なくありません。
3. 外部の相談窓口を利用する
地域包括支援センターやケアマネ協会、職能団体には相談窓口があります。**「自分の事業所内では解決できない」**と感じたときには、外部の機関に声を上げることも大切です。
4. 担当件数の調整をお願いする
担当件数が多すぎる場合は、管理者に相談して調整してもらうのも一つの手です。制度上は「原則35件以内」とされているため、無理な件数を背負わされている場合は改善を求める権利があります。
5. 転職・環境を変えることも選択肢
どうしても辛さが解消できない場合、転職して職場環境を変えることも一つの解決策です。特に居宅以外にも、施設ケアマネや包括ケアマネ、相談員、または福祉関連の別職種へとキャリアチェンジする人もいます。
居宅ケアマネが長く働き続けるための工夫
ワークライフバランスを意識する
休日は意識的に仕事から離れ、趣味や家族との時間を大切にすることがリフレッシュにつながります。
仲間とのネットワークを作る
地域のケアマネ研修や勉強会に参加することで、同じ立場の仲間とつながれるのは大きな支えになります。「自分だけが辛いのではない」と気づけるだけでも救いになります。
自分のキャリアプランを描く
「主任ケアマネを目指す」「将来は管理者になる」「地域包括で働く」など、キャリアの方向性を描くことで日々の仕事に目的意識を持つことができます。
まとめ
居宅ケアマネが「辛い」と感じる背景には、業務量の多さ・責任の重さ・人間関係・給料面など複数の要因があります。特に新人や担当件数が増えた時期には、精神的・身体的に限界を感じやすいでしょう。
しかし、業務の効率化・相談・環境の見直し・仲間づくりなどによって辛さを軽減することは可能です。どうしても解決が難しい場合は、職場を変えるという選択も前向きな一歩です。
ケアマネジャーは地域で欠かせない存在だからこそ、自分自身の健康と働きやすさを守りながら長く続けられる環境を整えることが大切です。















