ケアマネによるある退職トラブルとは?トラブル対策も解説します!
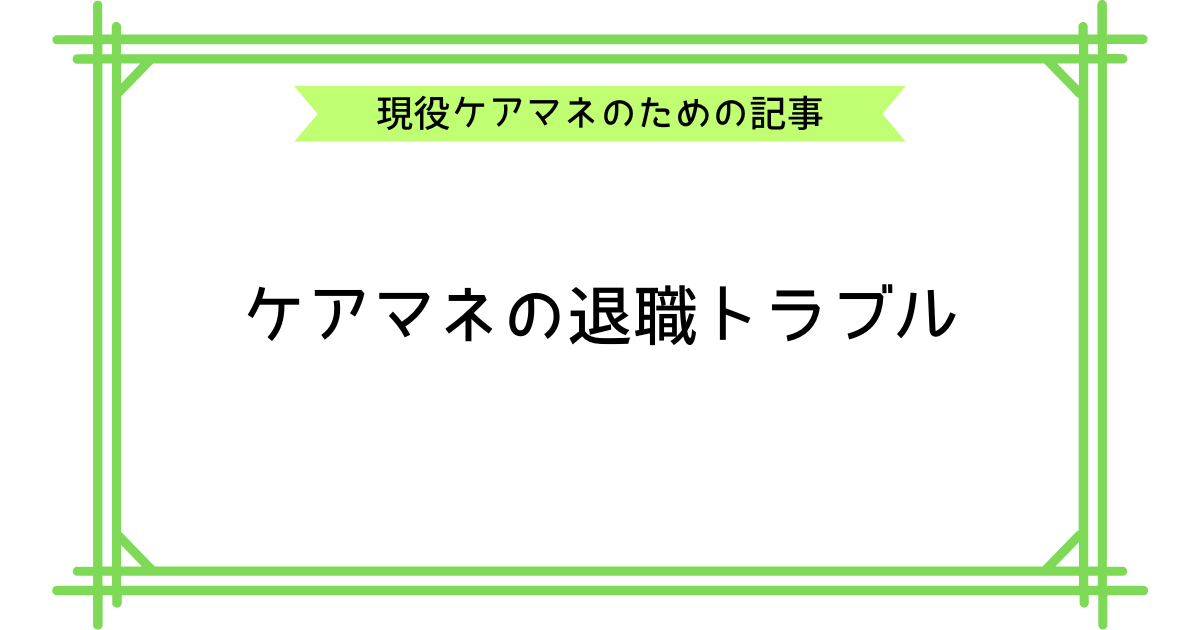
ケアマネジャー(介護支援専門員)の退職は、事業所にとって大きな影響を与える出来事です。
利用者への支援が途切れたり、加算要件が満たせなくなったりと、さまざまなトラブルに発展することもあります。
特に「突然の退職」「引き継ぎ不足」などは、事業所や利用者の信頼を損ねかねません。
本記事では、ケアマネ退職時によくあるトラブルの具体例と、それを未然に防ぐための対策を詳しく解説します。
円満な退職と引き継ぎの参考にしてください。
ケアマネのよくある退職トラブルとは?

1. 引き継ぎ不足による支援の混乱
ケアマネの退職で最も多いのが「引き継ぎ不足」による支援の不備です。利用者の生活に直結するケアプランや事業所との調整が不十分だと、以下のような問題が発生します。
実際に起きがちなトラブル例:
- ケアプランが未完成のまま退職し、モニタリングが滞る
- サービス事業所との連携が取れず、利用者が混乱
- 後任ケアマネが利用者情報を把握できず、支援に支障
2. 事業所が加算要件を満たせなくなる
主任ケアマネが退職すると、「特定事業所加算」や「医療介護連携加算」などの加算取得に支障が出るケースがあります。加算が外れると、事業所の収入にも大きく影響します。
加算関連トラブルの例:
- 急な退職で主任ケアマネ不在 → 特定加算の算定停止
- 実地指導時に「要件不備」と指摘される
- 他のケアマネに負担が集中し、職場環境が悪化
3. 利用者や家族への説明不足による不信感
利用者・家族に退職の説明を十分に行わないと、「急にケアマネがいなくなった」と不安を与え、信頼関係が崩れる原因になります。
こんな声が実際に…:
- 「突然いなくなった。何も聞いていない」
- 「後任が誰かわからない。連絡先もない」
- 「ケアプランの話が止まったまま」
退職理由は伝えにくくても、丁寧な挨拶と情報共有は最低限必要です。
4. 書類の整理・記録が不十分なまま退職
ケアマネ業務には大量の書類が伴います。退職直前になって記録が整理されていないと、後任や管理者が混乱し、実地指導や給付管理に支障が出る可能性があります。
主なリスク:
- モニタリングや担当者会議の記録が未入力
- ケアプランの改定履歴が不明瞭
- 利用者ファイルの整理がされていない
ケアマネ退職時のトラブルを防ぐための対策

1. 退職の意思は最低1ヶ月前に伝える
民法上は2週間前の申し出でも退職は可能ですが、実務的には「最低1ヶ月前」が理想です。早めに伝えることで、事業所側も後任の確保や利用者対応の準備がしやすくなります。
ポイント:
- 所長や管理者に口頭でまず伝える
- 書面で「退職届」を提出(後のトラブル防止に)
- 業務量や担当件数に応じて引き継ぎ計画を立てる
2. 引き継ぎリスト・シートを活用する
利用者ごとに以下のような引き継ぎシートを作成しておくと、後任の負担を軽減でき、利用者支援が継続しやすくなります。
記載内容の例:
- 利用者の基本情報・要介護度・主訴
- サービス内容と事業所との連携状況
- 家族との関係性・注意点
- 今後の支援スケジュール・課題
可能であれば、後任と一緒に利用者宅を訪問する“同行挨拶”も行えるとベストです。
3. 書類・記録の整理を計画的に行う
退職の1〜2週間前には、書類の見直し・整理に取りかかりましょう。特に電子記録システムのメモ欄やファイル内の未記録項目を重点的に確認します。
整理対象の一例:
- ケアプラン(第1・第2表)
- モニタリング記録・担当者会議要点記録
- 利用者ファイル・訪問記録・加算関連書類
管理者や事務担当と連携して、記録の引き継ぎもれを防ぎましょう。
4. 利用者・家族への説明は丁寧に
退職の連絡は、できるだけ直接の面談や電話で伝えるのが基本です。内容としては、「退職する理由(伝えられる範囲で)」「今後の流れ」「後任の紹介」などを含め、利用者の不安を最小限に抑えることが大切です。
退職後にトラブルが発覚するケースもある?
引き継ぎミスや連絡漏れが後任を困らせる
引き継ぎが不十分だった場合、退職後になってから後任から連絡が来ることもあります。「この人の医師情報がない」「加算算定の根拠がわからない」など、引き継ぎ文書の不足や記録の曖昧さが原因になることがあります。
事前対策:
- 「これは重要」と思う情報はメモや別紙で補足しておく
- 後任とのやりとりを可能な限り丁寧に行っておく
- 最終出勤日を明確にしておき、それまでに確認の時間を確保
まとめ

ケアマネの退職は、関係する利用者・家族・事業所すべてに影響を与える重要な出来事です。
引き継ぎ不足や説明不足によって、支援の混乱や加算停止などのトラブルに発展することも少なくありません。
円満な退職を目指すためには、早めの申し出・引き継ぎの準備・書類整理・丁寧な利用者対応が不可欠です。
たとえ辞めるとしても、誠実に最後まで仕事を全うすることが、退職後の信頼や今後のキャリアにもつながります。















