【パクリOK】熱中症・水分摂取のケアプラン文例170事例
当ページのリンクには広告が含まれています。
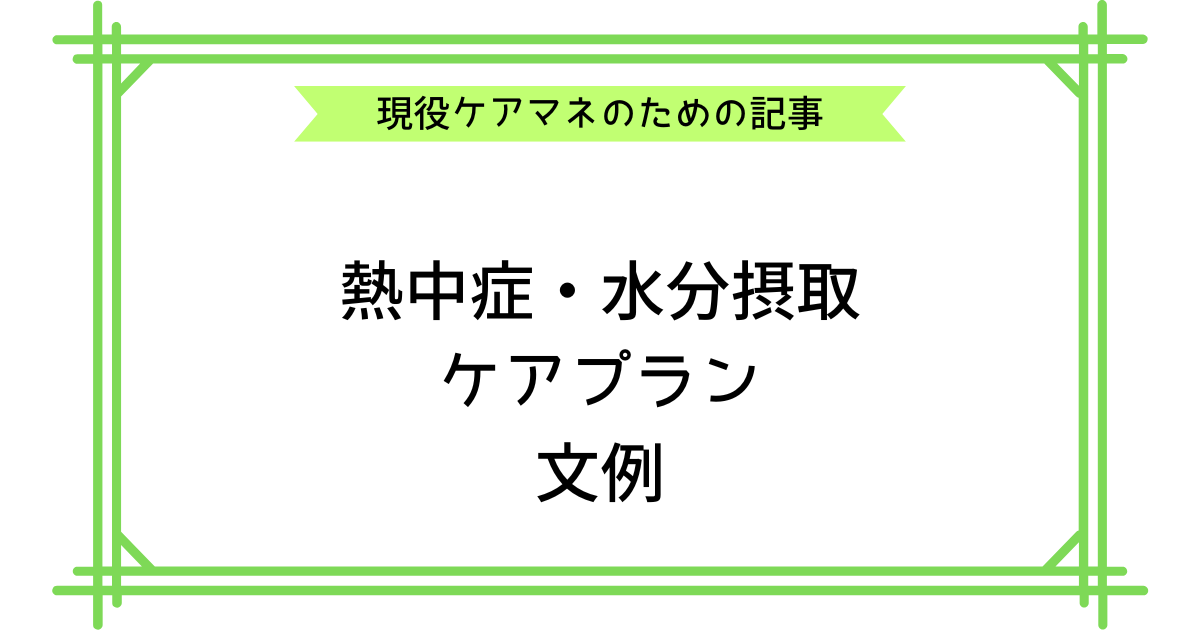
高齢者は体内の水分量が少なく、喉の渇きを感じにくいため、脱水や熱中症のリスクが高くなります。
特に夏季や暖房の効いた冬場には、水分摂取や環境調整をケアプランにしっかりと組み込むこと が重要です。
この記事では、ケアマネジャーや介護職がそのまま活用できる【パクリOK】文例を、長期目標・短期目標・サービス内容の3部構成で170事例 紹介します。
監査対応しやすい表現を意識していますので、現場ですぐにご利用いただけます。
目次
長期目標(熱中症・水分摂取のケアプラン文例)
- 熱中症を予防し、夏季も安心して生活を継続する。
- 適切な水分補給を習慣化し、脱水を防止する。
- 季節を問わず安定した体調で生活できるようにする。
- 水分摂取の習慣を身につけ、健康を維持する。
- 室温調整と飲水管理で熱中症リスクを減らす。
- 家族と協力して水分補給を徹底する。
- 本人が意識的に水分を摂れるようにする。
- 日常生活で脱水症状を起こさない。
- 熱中症の兆候を早期に察知し、重症化を防ぐ。
- 安心して夏を過ごせる生活習慣を確立する。
- 体調変化に応じて柔軟に水分摂取ができるようにする。
- 本人が飲水の大切さを理解し、行動できる。
- 医師の指示に従い、適正な水分管理を継続する。
- 脱水による入院を防ぐ。
- 夏季でも快適に生活できる環境を整える。
- 規則正しい飲水習慣を確立する。
- 本人が安心して過ごせるよう体調管理を支援する。
- 熱中症予防行動を自然に行えるようにする。
- 季節に応じた生活習慣を取り入れる。
- 家族も含めて脱水予防への意識を高める。
- 必要な飲水量を確保し、安定した体調を維持する。
- 水分補給によって排尿や便通を安定させる。
- 日常生活の中で快適に過ごせるよう支援する。
- 脱水による体力低下を防止する。
- 本人の自立を支えながら飲水習慣を身につける。
- 熱中症のリスクを理解し、予防行動を継続する。
- 水分補給で活動量を維持する。
- 室温管理を含めた熱中症予防を徹底する。
- 本人が楽しんで飲水できる環境をつくる。
- 季節ごとに適切な健康管理を行う。
- 夏季の生活リズムを安定させる。
- 熱中症予防を通じて安心できる暮らしを送る。
- 水分補給により薬の副作用を防止する。
- 脱水によるふらつきを防ぐ。
- 本人が納得して水分補給を行う。
- 家族が安心して見守れるようにする。
- 飲水不足による救急搬送を防ぐ。
- 夏季の健康被害を最小限に抑える。
- 適切な水分管理で生活の質を維持する。
- 本人が主体的に飲水できるよう支援する。
- 快適な住環境と水分補給で健康を守る。
- 季節の変化に応じた柔軟なケアを実施する。
- 医療職と連携し、水分摂取を適切に管理する。
- 本人の生活習慣に合わせた予防行動を支援する。
- 脱水予防を通じて転倒リスクを軽減する。
- 熱中症の知識を家族と共有する。
- 毎日の水分補給を無理なく継続する。
- 生活リズムに合わせた飲水を支援する。
- 体調を崩さず安心して夏を過ごせる。
- 水分補給を含めた生活習慣の改善を図る。
短期目標(熱中症・水分摂取のケアプラン文例)
- 1日1200ml以上の飲水を確保する。
- 毎食時にコップ1杯の水分を摂取する。
- 午前と午後に水分補給を行う習慣をつける。
- 就寝前にコップ半分の水を摂取する。
- 起床時に水分補給を行う。
- トイレ後に水分を補給する。
- デイサービスでお茶や水を飲む習慣をつける。
- 水筒を持参し、こまめに水分を摂る。
- 暑い日にはスポーツドリンクを取り入れる。
- バイタル測定時に水分摂取を促す。
- 脱水チェックシートを活用する。
- 口腔ケア後に水分を摂取する。
- 薬服用時に十分な水で内服する。
- アイスやゼリーを活用して水分を摂る。
- デイ利用時に水分提供を確実に行う。
- 外出前にコップ1杯の水分を摂取する。
- 熱中症アラートの日は水分を多めに摂取する。
- 水分補給を見守り、声かけを行う。
- 1日3回以上、排尿の有無を確認する。
- 水分摂取量を日誌に記録する。
- 午前10時と午後3時に水分補給を習慣化する。
- 甘みのある飲料を少量取り入れ飲水意欲を高める。
- 冷たい飲み物と温かい飲み物を状況に応じて選択する。
- 家族の声かけで飲水を促す。
- 脱水サイン(舌の乾燥・尿量減少)を観察する。
- 水分補給を1回100ml以上確保する。
- 水分を摂るたびに褒める声かけを行う。
- 本人が自分で水分を用意できるよう支援する。
- 利用者本人が好きな飲み物を選べるようにする。
- デイでの活動中も定時に水分補給する。
- 外出時は必ずペットボトルを持参する。
- 食事時に汁物を提供し水分摂取を補う。
- 夏場は冷やした飲み物を提供する。
- 水分摂取後の体調を確認する。
- 飲水量を1日ごとに確認し不足時は補う。
- デイ職員が飲水を促す声かけを継続する。
- 水分補給後に笑顔でフィードバックを行う。
- 飲水記録を家族と共有する。
- 冷蔵庫に常に飲料を用意しておく。
- 水分補給をゲーム感覚で習慣化する。
- 水分補給を習慣にするチェック表を活用する。
- 午前・午後のレクリエーション後に必ず水分補給する。
- 服薬前後に必ず水を飲むよう支援する。
- 水分補給後にトイレ誘導を行う。
- 本人が水分補給を思い出せるようメモを活用する。
- 室温調整と合わせて飲水を促す。
- 就寝前の脱水を防ぐために水を用意する。
- 外出後すぐに水分を摂る習慣をつける。
- 一口でも良いのでこまめに飲む習慣を続ける。
- 水分補給を毎日継続し記録に残す。
- デイから帰宅後に水分を補給する。
- 夜間のトイレで目覚めた時に水を飲む。
- 水分補給ができたかどうか職員が記録する。
- 飲水を嫌がる時はゼリーや果物で補う。
- 夏季は1時間ごとに飲水を促す。
- 水分補給ができないときは家族に報告する。
- 外出前後に水分を必ず摂る。
- 体操の前後に水分補給を行う。
- 冷水や麦茶を常備しておく。
- 水分を飲んだらチェックシートに○をつける。
- デイサービス送迎前に飲水を済ませる。
- 外出先での飲水をサポートする。
- 利用者が好むマグカップやコップを用意する。
- 利用者が水分を楽しめる工夫を取り入れる。
- 水分摂取を日課として本人に説明する。
- デイでの飲水回数を増やす。
- 脱水予防のパンフレットを本人・家族に説明する。
- 夏季において冷却タオルと合わせて水分を提供する。
- 食後に必ずコップ1杯の水を飲む。
- 水分摂取の達成度を本人と一緒に確認する。
サービス内容(熱中症・水分摂取のケアプラン文例)
- 訪問介護で飲水の声かけを行う。
- デイサービスで定時に水分を提供する。
- 看護師が脱水兆候を観察する。
- 栄養士が水分摂取メニューを提案する。
- 家族が水分量をチェックシートに記録する。
- 介護職が起床時にコップ1杯の水を提供する。
- 昼食・夕食時に汁物を提供する。
- 水分補給ゼリーを間食に取り入れる。
- 室温調整を行い、快適な環境を保つ。
- 扇風機やエアコンを活用して暑熱対策を行う。
- 訪問介護で就寝前の水分を提供する。
- デイサービスで水分補給ゲームを実施する。
- 配食サービスで水分補給を意識したメニューを提供する。
- 医師の指示に基づき、適正な飲水量を管理する。
- 看護師が服薬時に十分な水分摂取を確認する。
- 家族が水分補給の時間を声かけで促す。
- 訪問介護員が水分を準備し手渡す。
- デイで水分補給の回数をチェックする。
- 栄養士が好みを反映した飲料を提案する。
- 看護師が体重変化を確認し水分量を調整する。
- 家族が冷蔵庫に水分を常備する。
- デイでの活動時に水分を定期提供する。
- 介護職が脱水予防について説明する。
- 看護師が排尿の回数や尿色を確認する。
- デイ職員が活動の合間に水分を提供する。
- 訪問介護で外出前に水分を提供する。
- 看護師が熱中症症状をチェックする。
- 栄養士が経口補水液の活用を助言する。
- デイで水分提供の時間を掲示する。
- 家族が水分チェック表を作成し共有する。
- 訪問介護員が飲水状況を記録する。
- デイ職員が本人に好みの飲料を提供する。
- 看護師が点滴などの医療的水分補給を管理する。
- 介護職が本人の意欲を高める声かけを行う。
- 家族が日中も水分摂取を確認する。
- デイサービスで氷菓子を提供し水分補給を補助する。
- 看護師が服薬と飲水のタイミングを確認する。
- 訪問介護員が夏季の水分補給を徹底する。
- 家族が脱水予防について学ぶ機会を持つ。
- 栄養士が水分補給に適した食品を提案する。
- デイで冷たい飲料を定時に提供する。
- 看護師が脱水リスクのある薬を確認する。
- 介護職が飲水後の安否確認を行う。
- 家族が本人に水分補給を習慣化させる。
- デイ職員が活動後に水分補給を支援する。
- 看護師が血圧測定と合わせて水分管理を行う。
- 訪問介護で外出後に水分を提供する。
- 家族が水分補給に協力し声かけを継続する。
- 栄養士が嗜好を考慮した水分補給方法を提案する。
- ケアマネがモニタリングで水分摂取状況を確認する。
まとめ
熱中症や水分不足は高齢者にとって命に関わるリスクです。
ケアプランに 長期的な目標・短期的な目標・サービス内容を具体的に組み込む ことで、現場のケアがスムーズになり、監査対応でも評価されやすくなります。
今回紹介した【パクリOK】文例170は、そのままコピペして使えるだけでなく、利用者ごとの状況に応じてアレンジしやすい内容になっています。















