居宅介護支援事業所の黒字化するための対策6選!赤字になる理由も紹介
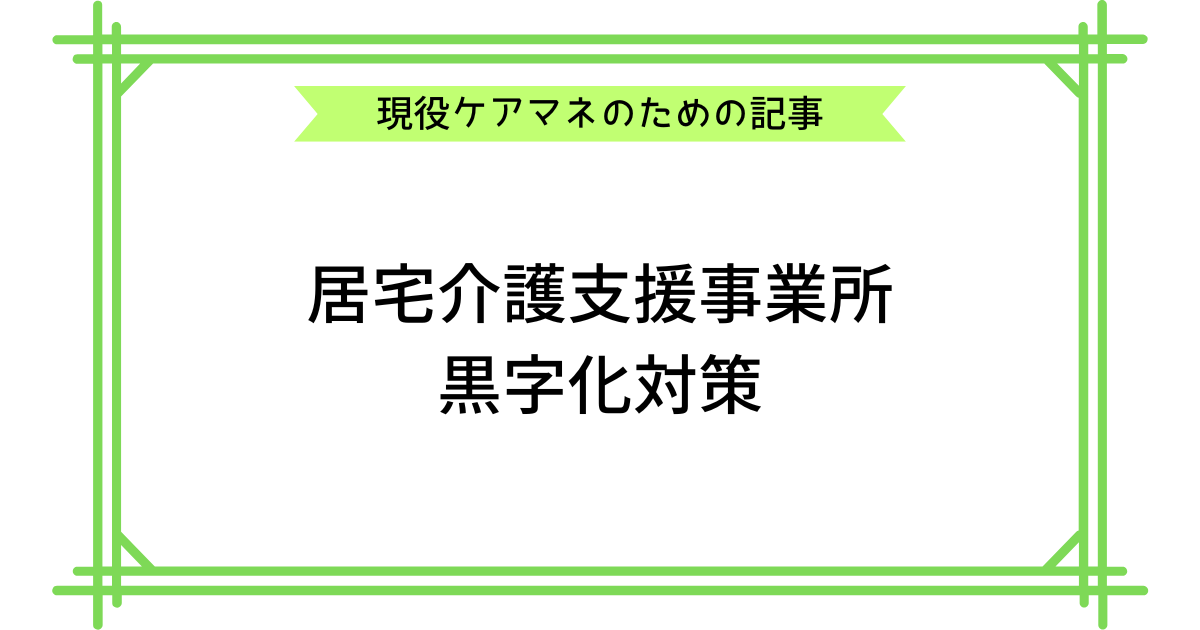
「居宅介護支援事業所を運営しているが赤字続きで困っている」「ケアマネジャーを雇っても収益が伸びない」──そんな悩みを抱える経営者は少なくありません。
居宅介護支援事業所は介護サービスの要として重要な役割を担う一方、報酬が低く赤字に陥りやすい構造を持っています。
しかし、工夫次第で黒字化は十分可能です。
実際に利益を出して安定運営している事業所も多く存在します。
この記事では、居宅介護支援事業所が赤字になりやすい理由を整理し、黒字化を実現するための具体的な対策を6つ紹介します。
経営改善を考える方にとって必ず役立つ内容です。
居宅介護支援事業所が赤字になりやすい理由
報酬単価が低い
居宅介護支援費は、利用者1人あたり月数千円程度しか算定できません。ケアマネが30件担当しても、月に100万円程度の売上しか見込めず、人件費や事務費を差し引けば赤字になる事業所も多いのが現実です。
担当件数が少ない
ケアマネ1人あたりの標準担当件数は35件とされていますが、人材不足や事業規模の問題で20件程度しか確保できない場合もあります。件数不足はそのまま収益不足につながります。
人件費の比率が高い
ケアマネは専門職のため給与水準が比較的高く、人件費が経営を圧迫します。小規模事業所では1人雇うだけで赤字に転落するケースも珍しくありません。
運営効率の悪さ
紙ベースの記録や非効率な業務体制が残っている事業所は、生産性が低く、残業代や人員コストが増えやすくなります。ICT化の遅れも赤字の原因です。
加算取得の不足
特定事業所加算や入院時情報連携加算など、算定できる加算を取っていないと収益機会を逃すことになります。
居宅介護支援事業所を黒字化するための対策6選
1. ケアマネの担当件数を適正化する
黒字化には「ケアマネ1人あたり30〜35件」を安定して担当できる体制づくりが不可欠です。過少件数では赤字、過多件数では質の低下につながるため、業務分担や事務員配置を工夫して適正件数を確保しましょう。
2. 特定事業所加算を取得する
特定事業所加算は人員体制や研修要件を満たすことで算定できます。要件整備には人件費がかかりますが、加算による収入増は大きく、黒字化の柱となります。特に加算Ⅱ・加算Ⅲの取得は多くの事業所で現実的です。
3. ICT・事務員活用で業務効率化する
ケアマネが書類や給付管理に追われすぎると件数を持てません。介護ソフトやクラウドシステムを導入し、事務員に定型業務を任せることで効率を高めれば、ケアマネは本来業務に集中でき、担当件数の増加につながります。
4. 医療・介護機関との連携を強化する
居宅介護支援事業所は「利用者紹介」が収益源ではないものの、地域の医療機関や介護事業所との連携が新規利用者獲得につながります。病院の退院調整部門や地域包括支援センターとの関係づくりは安定した件数確保に直結します。
5. 人材確保と定着を図る
ケアマネ不足は業界全体の課題です。採用コストを抑えるには、既存職員が辞めないように職場環境を整えることが重要です。残業削減、研修支援、柔軟な勤務形態などを整備すれば、人材流出を防ぎ安定した運営が可能になります。
6. 他事業との一体運営を進める
デイサービスや訪問介護などを運営する法人が居宅介護支援を併設すると、利用者紹介や事務作業の分担などで効率化できます。単独居宅は黒字化が難しい傾向がありますが、複合事業であれば相乗効果により経営が安定しやすくなります。
黒字化を実現するための実行ポイント
黒字化のためには単一の対策ではなく、件数確保・加算取得・効率化・人材定着 を総合的に進める必要があります。また「短期的な収益確保」と「長期的な事業継続性」のバランスも重要です。
- すぐにできる施策:加算取得、ICT導入
- 中期的施策:連携強化、人材定着
- 長期的施策:複合事業との一体運営
と段階的に進めれば、赤字体質から脱却し、持続的に黒字を維持できる事業所へと成長できます。
まとめ
居宅介護支援事業所は報酬単価の低さや人材不足から赤字に陥りやすい構造を持っています。
しかし、
- 担当件数の適正化
- 特定事業所加算の取得
- ICTや事務員による効率化
- 地域連携による件数確保
- 人材定着
- 他事業との一体運営
といった施策を組み合わせれば黒字化は十分可能です。
経営改善は一朝一夕にはいきませんが、地道な取り組みを重ねることで「赤字からの脱却」は実現できます。まずは現状の課題を整理し、できるところから改善を始めましょう。















