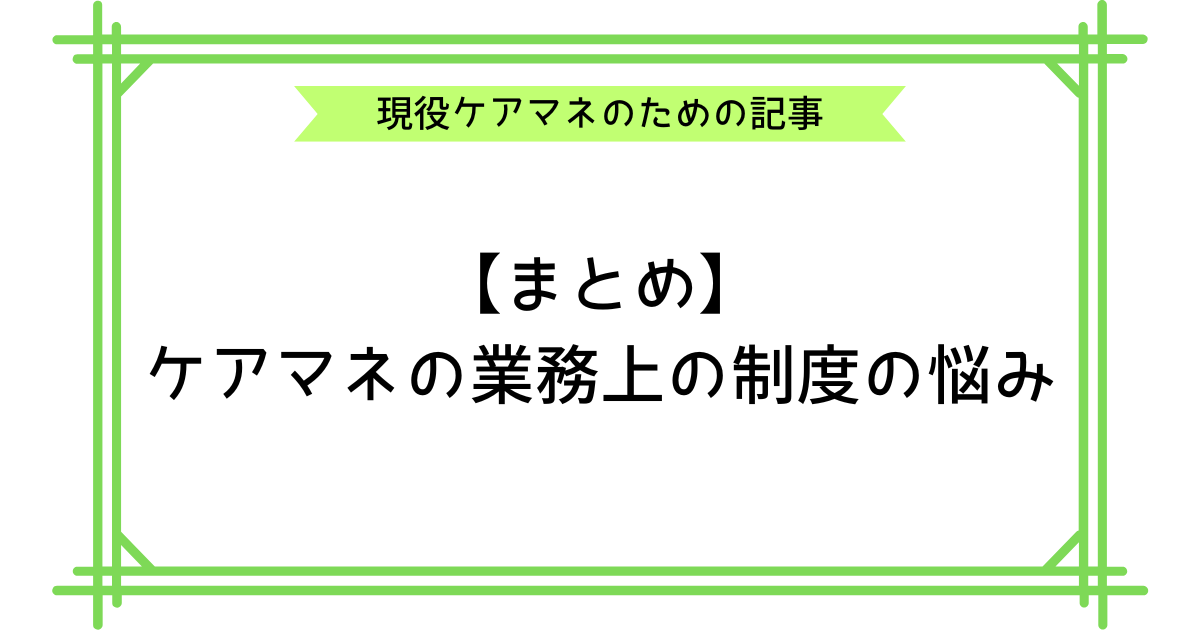居宅介護支援事業所に事務員配置基準はあるのか?
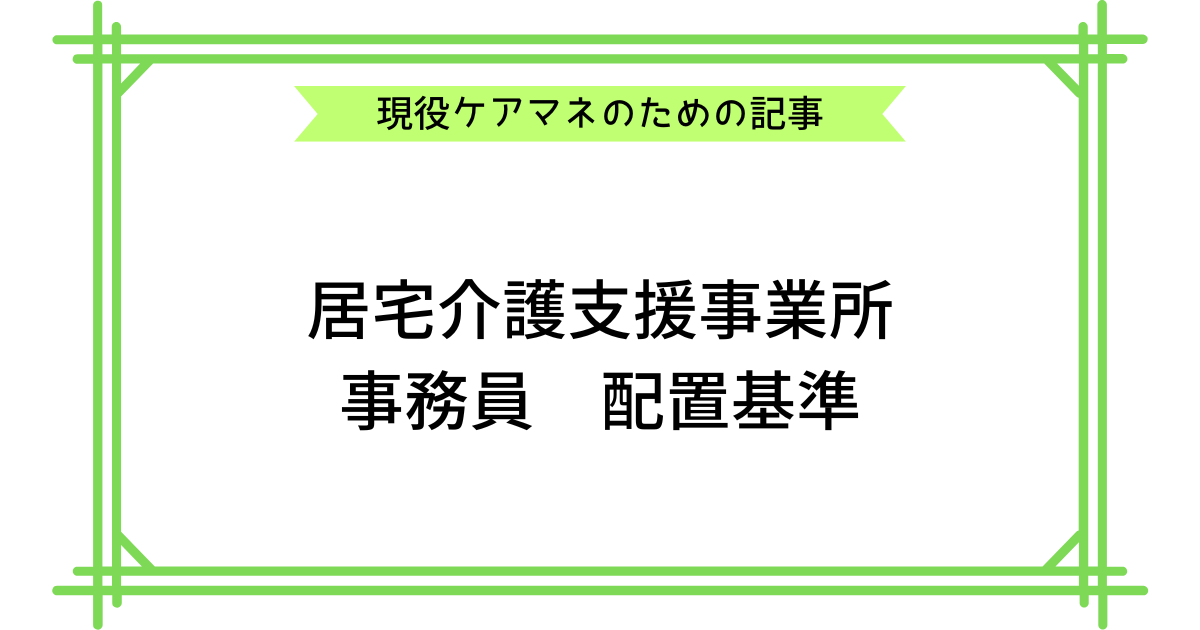
居宅介護支援事業所を運営するうえで欠かせないのが「人員基準」です。
管理者や介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置については明確な基準がありますが、「事務員」についてはどうなのでしょうか。
求人情報などを見ると事務員を配置している事業所も多い一方で、「基準上必要なのか分からない」という声も少なくありません。
本記事では、居宅介護支援事業所における事務員の配置基準について解説するとともに、実際に配置するメリットや注意点についても紹介します。
居宅介護支援事業所の人員基準はどうなっているのか?
介護保険制度に基づく居宅介護支援事業所の人員基準は、主に以下のとおりです。
- 管理者の配置(常勤・ケアマネ資格必須)
- 介護支援専門員(ケアマネジャー)の配置(常勤換算で1人以上、担当件数に応じて複数必要)
この2つが基本であり、法令上「事務員を置かなければならない」という規定はありません。
つまり、事務員の配置は義務付けられていないのが現状です。
事務員に関する配置基準は存在しない
結論から言えば、居宅介護支援事業所において 事務員の配置基準は存在しません。
ケアマネが行う業務(アセスメント・ケアプラン作成・モニタリング・給付管理など)が基準の中心であり、事務員は制度上の必須人員には含まれていないためです。
ただし、事務作業が多い事業所ではケアマネが書類に追われることになり、実務が滞るリスクがあります。
そのため、基準にはなくても「任意で事務員を配置する」事業所が増えているのです。
それでも事務員を配置する事業所が多い理由
書類業務が膨大でケアマネの負担が大きい
居宅介護支援事業所では、ケアプラン(1表・2表・3表)、モニタリング記録、給付管理票、サービス利用票など、膨大な書類を作成・管理する必要があります。さらに監査対応や加算に関する記録整備もあり、ケアマネが事務仕事に時間を取られすぎるのが実情です。
ケアマネが利用者支援に専念できる
事務員を配置することで、ケアマネは本来の専門業務である「アセスメント」や「利用者・家族対応」に専念できます。結果としてサービスの質が向上し、利用者満足度の向上にもつながります。
行政対応や監査に備えやすい
監査や指導の際には書類整備が重要です。事務員が日常的に記録を整理していれば、スムーズに対応でき、ケアマネが一人で追い込まれることを防げます。
法人全体での効率化
法人が複数の事業所を運営している場合、事務員が共通で事務処理を担うことで、効率化やコスト削減にもつながります。
事務員配置のメリットとデメリット
メリット
- ケアマネの事務負担軽減
- 利用者対応やモニタリングの質向上
- 監査対応や給付管理の精度向上
- 法人全体の効率化
デメリット
- 人件費コストが増える
- 小規模事業所では採算が厳しくなる可能性
- ケアマネが事務に慣れている場合、逆に分業で効率が落ちるケースも
小規模事業所と大規模事業所での違い
小規模事業所では、人件費を抑えるために事務員を置かず、ケアマネ自身がすべての事務作業を担うケースが一般的です。
一方、大規模事業所では利用者数が多く、給付管理などの事務量も膨大になるため、複数の事務員を配置しているところもあります。
つまり、事務員の配置は経営規模や事業所の方針によって異なるのが実態です。
ICT活用で事務員の役割を補える場合もある
近年では、クラウド型介護ソフトやICTシステムを導入することで、事務員を配置しなくても業務効率を上げる事業所も増えています。
給付管理やモニタリング記録の自動化が進めば、ケアマネ一人でも事務作業の負担を軽減できるからです。
ただしICT導入にもコストや習熟が必要であり、必ずしも事務員不要になるわけではありません。
まとめ
居宅介護支援事業所において 事務員の配置基準は存在せず、配置は義務ではありません。
しかし、実務上は書類業務や給付管理が膨大であり、事務員を置くことでケアマネの負担を減らし、利用者支援に専念できる体制を整えやすくなります。
- 法的に事務員配置は不要
- 実務上は事務員を配置する事業所が多い
- メリットは業務効率化・質の向上
- デメリットは人件費増加
- 小規模では不在、大規模では複数配置が一般的
事業所運営の方針や規模、財政状況に応じて「事務員を置くかどうか」を判断するのが現実的です。
ICTとの併用も視野に入れながら、ケアマネが本来の専門性を発揮できる環境を整えることが大切だといえるでしょう。