【コピペOK】パーキンソン病のケアプラン文例200事例を紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
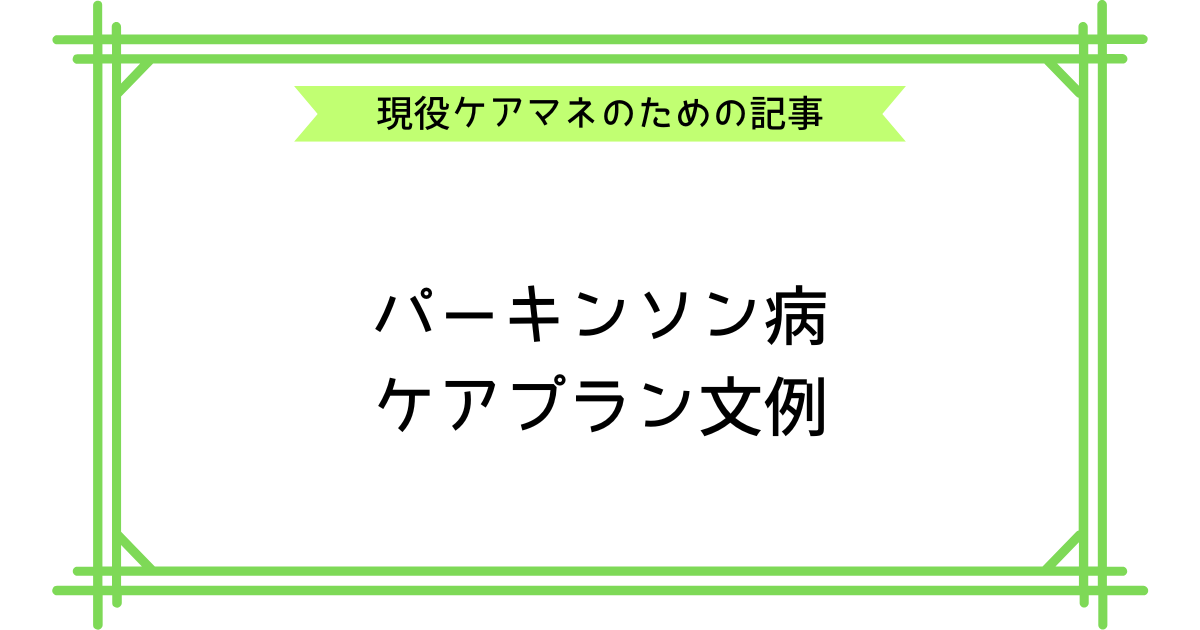
パーキンソン病の利用者に対するケアプラン作成では、運動機能の低下や服薬管理、転倒リスクへの配慮、精神面や家族支援など幅広い観点が求められます。
しかし「文例をどう書けばよいか分からない」と悩むケアマネジャーも少なくありません。
この記事では、パーキンソン病のケアプランに使える【コピペOK】文例200事例をまとめました。
居宅サービス計画の長期目標・短期目標、サービス内容などでそのまま活用できる内容になっています。
目次
パーキンソン病ケアプラン文例【1〜50事例】
- パーキンソン病による動作緩慢により着替えに時間を要するが、訪問介護の支援を受けながら自力で更衣ができるようにする。
- 服薬時間を忘れることがあるため、訪問看護や家族の声かけにより確実に内服できるよう支援する。
- 筋固縮により動作が制限されているが、週2回のデイリハを利用し、関節可動域を維持する。
- バランス能力が低下しているため、歩行補助具を活用し転倒を予防する。
- 生活リズムが乱れやすいため、規則正しい起床・就寝習慣を整えられるよう支援する。
- 入浴時の動作が困難なため、訪問介護の入浴介助を利用し、清潔保持を図る。
- 食事動作に時間を要するが、適切な食器を導入して自力摂取を促す。
- 排泄動作に不安があるため、トイレ環境を整備し、自立排泄を支援する。
- 服薬に伴う副作用や体調変化を訪問看護がモニタリングし、主治医へ報告する。
- 声が小さくなり会話が困難なため、家族やスタッフが傾聴姿勢を持ち、意思疎通を図る。
- 身体の動きが固くなり家事が困難なため、訪問介護で調理・掃除をサポートする。
- デイサービス利用により社会的交流を維持し、閉じこもりを防止する。
- 手の震えにより食事をこぼすことがあるため、スプーンや食器を工夫して自力摂取を支援する。
- 移動時にふらつきがあるため、廊下やトイレに手すりを設置し安全性を高める。
- レビー小体型認知症を合併する可能性があるため、認知面の変化も定期的に評価する。
- 夜間頻尿により転倒リスクが高いため、ポータブルトイレを設置し安全を確保する。
- 家族の介護負担軽減のため、ショートステイを利用し休養を支援する。
- 身体のこわばりにより歩行が困難な時があるため、訪問リハでストレッチを実施する。
- 誤嚥リスクがあるため、訪問看護やSTの指導を受け食形態を工夫する。
- 無動が強くなる時間帯に合わせ、必要なサービスを調整する。
- 食欲低下がみられるため、栄養士の助言を受けて食事内容を工夫する。
- 睡眠障害があり日中の活動に影響しているため、生活リズム調整を図る。
- 意欲低下があるが、趣味活動を継続できるようデイサービスで支援する。
- 不安感が強いため、ケアマネやスタッフが傾聴を行い安心感を提供する。
- 手足の震えにより着替えが遅れるが、更衣動作を練習して自立度を高める。
- 外出意欲を維持するため、週1回は家族と散歩できるよう支援する。
- 服薬管理が複雑なため、一包化された薬を利用し服薬コンプライアンスを高める。
- 体調変化に応じて迅速に医師へ情報提供し、適切な治療につなげる。
- 声量低下により電話対応が困難なため、家族や事務的支援を調整する。
- 食事時にむせることがあるため、嚥下体操を習慣化する。
- バランス機能の低下を補うため、歩行器を導入する。
- トイレまでの移動が困難な場合、ポータブルトイレの使用を支援する。
- 集団活動が苦手だが、少人数グループでのリハ参加を促す。
- 服薬後の副作用が見られる場合は、訪問看護が観察し医師に報告する。
- 家族が介護疲れを訴えているため、レスパイトケアを計画的に導入する。
- 不眠症状に対し、睡眠環境を整えるよう助言する。
- 入浴時に転倒リスクが高いため、浴室マットや手すりを設置する。
- 服薬効果の切れ目に合わせてサービス利用時間を調整する。
- ストレスによる体調変化がみられるため、心理的サポートを取り入れる。
- 車椅子利用となった場合も、自立した生活が継続できるよう住環境を整える。
- 外出時の転倒を予防するため、介護タクシーを利用する。
- 体力低下を防ぐため、デイリハで有酸素運動を導入する。
- 手先の震えが強いため、食具に工夫を加え食事を続けられるようにする。
- 家族への介護指導を行い、安心して支援できるようにする。
- 動作緩慢のため朝の身支度に時間がかかるが、訪問介護のサポートで負担軽減を図る。
- 認知機能低下が進行しつつあるため、生活の中で見守り支援を強化する。
- 食事形態を柔らかめに変更し、嚥下負担を軽減する。
- デイサービスで他利用者との交流を通じ、孤立を防ぐ。
- 排泄時に衣類の着脱が困難なため、介護用衣類を導入する。
- 身体のこわばりが強い朝の時間帯は、介護サービスを重点的に配置する。
- 廃用症候群予防のため、毎日簡単なストレッチを習慣化できるよう訪問リハで支援する。
- 食事のむせ込みを軽減するため、STの指導に基づき食事姿勢を工夫する。
- 家事動作の一部を家族と分担し、本人の自立性を保ちながら生活を継続する。
- 表情の乏しさによるコミュニケーション困難に対し、スタッフが積極的に声掛けを行う。
- 薬効の切れ目で動作が困難な時間帯には、介護サービスを優先的に配置する。
- 転倒防止のため、夜間は足元を照らす照明を設置する。
- 趣味活動を継続することで生活意欲を高めるよう支援する。
- 便秘傾向にあるため、食物繊維や水分摂取を意識した食事内容を工夫する。
- 着替えに時間を要するため、前開き衣類を使用し自立を促す。
- 独居のため安否確認を兼ねて定期的に訪問サービスを導入する。
- 不安発作がみられるため、訪問看護による心理的支援を取り入れる。
- リハビリを通じて歩行距離の維持を目標とする。
- 家族が介護疲れを感じているため、ショートステイを定期的に活用する。
- 誤嚥性肺炎を予防するため、嚥下体操を食前に実施する。
- 在宅生活の継続を目指し、地域包括支援センターと連携する。
- 集団活動に参加し、他利用者と交流できるようデイサービスを利用する。
- 服薬管理アプリを活用して自己管理力を高める。
- 体調変化に応じて柔軟にサービス調整を行えるようケアマネが定期モニタリングを実施する。
- 立ち上がり動作の訓練を継続し、自立度を維持する。
- 家族へパーキンソン病の進行に応じた介護知識を提供する。
- 睡眠障害があるため、就寝前にリラックスできる環境を整備する。
- 服薬の副作用を確認し、主治医に情報を共有する体制を整える。
- 入浴時の動作を安全に行えるよう、浴槽台を導入する。
- 外出時は同行支援を受け、社会参加を継続する。
- 表情筋リハビリを取り入れ、意思疎通を円滑にする。
- 書字困難があるため、代替手段として音声入力やICTを活用する。
- 運動プログラムを継続し、日常生活動作の維持を図る。
- 疲労感が強い場合は活動と休養のバランスを支援する。
- 地域の患者会に参加し、心理的支えを得られるようにする。
- 定期的な家族カンファレンスを行い、介護方針を共有する。
- 歩行時にすくみ足が見られるため、歩行訓練を継続する。
- 食事中の姿勢を調整し、誤嚥を予防する。
- 言葉が出にくいため、ゆっくりとした会話で意思疎通を図る。
- 服薬忘れが生じないようカレンダー管理を導入する。
- 不安定な姿勢での転倒を防ぐため、椅子を安定したものに変更する。
- 入浴拒否が見られる際は、短時間の部分浴から取り入れる。
- 生活リズムが乱れないよう、日中の活動量を増やす。
- 在宅でのリハビリを習慣化し、体力低下を予防する。
- 家族が安心できるよう、介護方法を具体的に指導する。
- 福祉用具を適切に導入し、生活動作を安全に行えるよう支援する。
- デイサービス利用を継続し、社会的孤立を防ぐ。
- 食事の形態を個別に工夫し、栄養状態を維持する。
- 言語訓練を取り入れ、意思疎通力を維持する。
- 服薬後の体調変化を記録し、主治医に報告する。
- 移動の安全性を確保するため、床に滑り止めを設置する。
- 睡眠導入リズムを作り、夜間の不眠を軽減する。
- 家族の介護負担を軽減するため、定期的にデイ利用を調整する。
- 体調悪化時には早期に医療機関と連携できる体制を構築する。
- 音読訓練を取り入れ、発声機能を維持する。
- 外出機会を設け、本人の社会参加意欲を高める。
- 服薬効果の切れ目で動きにくくなる時間帯に、訪問介護を配置して安全を確保する。
- デイリハで歩行訓練を継続し、転倒予防と体力維持を図る。
- 意欲低下が見られるため、本人の趣味を取り入れた活動を支援する。
- 家族が服薬管理をサポートし、飲み忘れや重複を防止する。
- 外出機会を増やし、閉じこもり防止と生活リズムの安定を図る。
- 表情が乏しく意思疎通が難しいため、ジェスチャーやカードを併用する。
- 睡眠障害の改善を目指し、環境調整や生活習慣の見直しを支援する。
- 突然の動作停止(フリーズ)に備え、安全に移動できるよう声かけを行う。
- 入浴動作を安全に行えるよう、浴室に手すりや滑り止めを設置する。
- 栄養不足を防ぐため、食事内容や補助食品を取り入れて調整する。
- 服薬スケジュールを一目で確認できるよう、ピルケースを使用する。
- デイサービスで集団体操に参加し、運動機能と社会性を維持する。
- 家族が介護方法を学び、介助がスムーズにできるよう研修機会を持つ。
- 不安感が強いため、ケアマネが定期的に傾聴を行い安心感を提供する。
- 発声困難に対して、音読訓練や歌唱を取り入れる。
- トイレまでの移動が困難な場合、福祉用具の導入で自立を促す。
- レビー小体型認知症の症状が出た場合に備え、認知機能の評価を継続する。
- 倦怠感が強いときは活動量を調整し、休養を優先できるようにする。
- 定期的に主治医と情報共有し、病状進行に応じたケアを実施する。
- 家族のレスパイトケアとしてショートステイを計画的に利用する。
- 自宅内の段差を解消し、安全な生活環境を整える。
- 在宅酸素や医療機器が導入された場合は、訪問看護と連携して管理する。
- 家族が孤立感を抱かないよう、地域包括支援センターとつなげる。
- 体調に応じてデイサービスの利用日数を柔軟に調整する。
- 体操やストレッチを継続することで、関節のこわばりを軽減する。
- 気分の落ち込みがあるため、精神科医やカウンセリングと連携する。
- 書字困難に対して、代替手段としてタブレット端末を活用する。
- 便秘の改善を目的に、水分摂取を促し下剤の使用を調整する。
- 家族が安心できるよう、緊急時の対応マニュアルを共有する。
- 夜間の転倒防止のため、廊下に人感センサー付きライトを設置する。
- サービス担当者会議で進行状況を共有し、チームで支援方針を確認する。
- 車椅子移動を円滑に行えるよう、住環境の改修を検討する。
- 食欲が低下しているため、少量高栄養の食事を取り入れる。
- 移動時にすくみ足が出た際の声かけ方法を家族に指導する。
- 定期的な理学療法で歩行機能を維持する。
- 趣味活動を継続できるよう、道具や環境を工夫する。
- 家族介護力が低下しているため、訪問介護を増やす。
- 服薬効果の有無を観察し、医師へ早めに情報提供する。
- 社会参加意欲を保つため、地域活動への参加を支援する。
- 不眠が続く場合、医師と連携し投薬や生活習慣改善を検討する。
- 運動障害の進行を予防するため、定期的な体操を習慣化する。
- 食事動作をスムーズにするため、補助具を導入する。
- 認知症を併発した場合にも対応できるよう、見守り支援を強化する。
- 家族が安心して介護を続けられるよう、相談窓口を案内する。
- 会話が減少しているため、意識的にコミュニケーションを図る。
- 移動の安全確保のため、屋内に手すりを増設する。
- 生活意欲を高めるために、本人の役割を家庭内で持たせる。
- 主治医と連携し、薬剤調整を迅速に行えるよう体制を整える。
- デイリハ利用で身体機能の維持と交流機会を確保する。
- 定期的にケアプランを見直し、進行に合わせて柔軟に対応する。
- 呼吸機能の低下がみられる場合、呼吸リハビリを取り入れる。
- 食事介助が必要になった場合でも、本人の自立を尊重して支援する。
- 表情筋を動かす練習を取り入れ、非言語コミュニケーションを促す。
- 介護者が不安を抱かないよう、医療・介護チームで情報共有する。
- 日常生活に支障を来さないよう、必要に応じてヘルパーを導入する。
- 家族がストレスを溜め込まないよう、定期的な相談支援を行う。
- 利用者本人が自分の病状を理解できるよう、分かりやすく説明する。
- 在宅生活の継続を目標に、福祉用具を適切に利用する。
- 社会資源を活用し、生活支援を強化する。
- 動作緩慢が強い場合には、生活動作に十分な時間を確保する。
- 緊急時に備えて、医師やケアマネにすぐ連絡できる体制を整える。
- トイレ動作の自立を支援するため、環境改善を行う。
- 家族の介護負担を軽減するため、介護サービスを複数組み合わせる。
- 移動が不安定な場合は、歩行器や杖を適切に使用する。
- 誤嚥性肺炎予防のため、嚥下リハビリを継続する。
- 本人の希望を尊重し、好きな活動を取り入れる。
- 睡眠の質を改善するため、生活習慣を整えるよう助言する。
- 主治医の診察時に家族も同席し、今後の方針を共有する。
- 安全に外出できるよう、介護タクシーや送迎サービスを利用する。
- 心理的負担を軽減するため、カウンセリングの利用を検討する。
- 家族介護力が不足している場合、地域包括支援センターに相談する。
- 療養上の不安を軽減するため、訪問看護を定期的に導入する。
- 身体活動を維持するため、簡単な体操を日課にする。
- 栄養士の助言を受け、栄養バランスを整える。
- 移動能力に応じてベッドや椅子を調整する。
- 日中の活動量を増やし、夜間の不眠を改善する。
- 表情が乏しいため、声掛けやジェスチャーで意思を汲み取る。
- 家族の不安軽減のため、ケアマネが定期的に状況を確認する。
- 運動機能低下が強い場合、在宅でリハビリを実施する。
- 服薬忘れを防ぐため、ヘルパーによる確認を導入する。
- デイサービスでレクリエーションに参加し、生活意欲を高める。
- 自宅での安全確保のため、段差解消を進める。
- 食事の摂取量を増やすため、好物を取り入れる。
- 不安感を軽減するため、定期的に安心できる声掛けを行う。
- 移動が困難なときは、訪問リハで筋力維持を支援する。
- 家族の介護疲労を防ぐため、ショートステイを活用する。
- 夜間の徘徊がある場合、見守り体制を強化する。
- 医療機関と連携し、進行に応じた治療方針を調整する。
- 日中の活動意欲を高め、生活リズムを安定させる。
- コミュニケーション困難を補うため、会話支援アプリを導入する。
- 緊急時に家族が対応できるよう、連絡先リストを整備する。
- 運動障害の悪化に備え、住宅改修を検討する。
- 自立を尊重し、できる限り本人の力を引き出す。
- ケアマネが定期的に訪問し、サービスの適切性を確認する。
- 福祉用具の使用方法を家族に説明し、安全に活用できるよう支援する。
- デイリハで個別リハを受け、ADLの維持を図る。
- 家族が不安を抱かないよう、介護教室に参加できるよう支援する。
- 本人の生活意欲を高めるため、役割を家庭内で持たせる。
- 定期的な医師の診察で病状進行を確認し、ケアプランを見直す。
- 最期まで自宅での生活を希望しているため、医療・介護チームで在宅療養を支える。















