【コピペOK】ペースメーカーのケアプラン文例を100紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
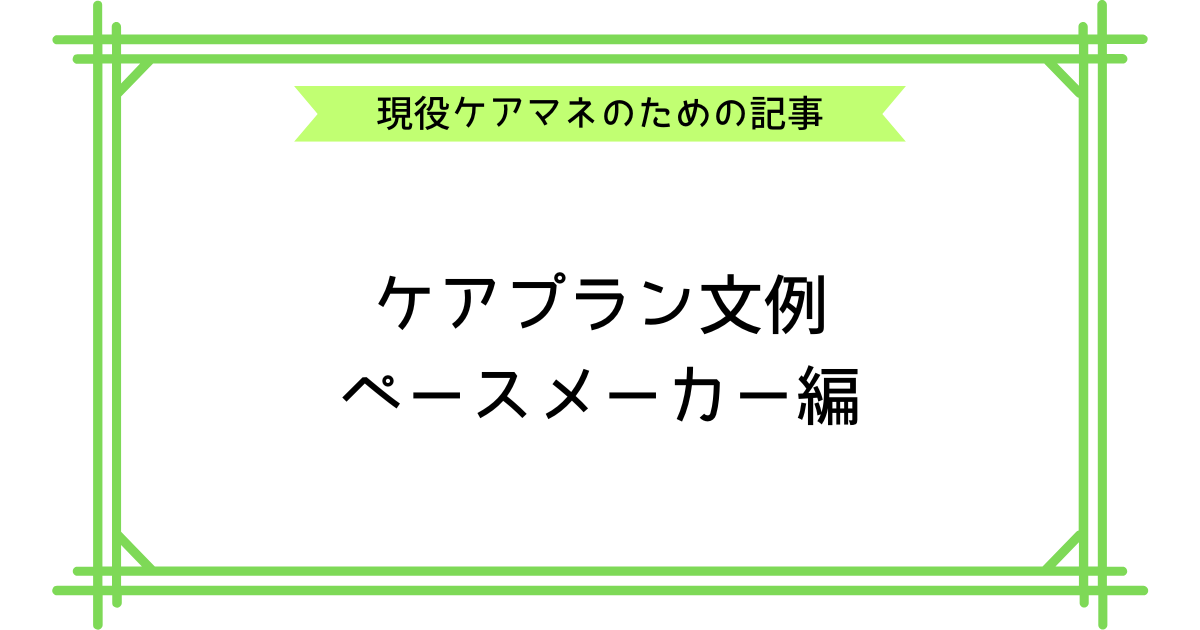
ペースメーカーを植え込んだ利用者のケアプラン作成では、体調観察や安全確保に加えて、日常生活の支援や家族へのサポートも重要です。
しかし「文例をどう書けばいいのか分からない」「安全面をどう表現するのが正しいのか」と悩むケアマネも多いはずです。
この記事では ペースメーカー利用者向けのケアプラン文例を100個 紹介します。
居宅介護支援やサービス担当者会議の準備に、そのままコピー&ペーストして活用いただけます。
目次
ペースメーカーのケアプラン文例100
【体調管理・観察】
- ペースメーカー作動に伴う体調変化を観察し、異常があれば速やかに医師へ報告する。
- バイタルサインを定期的に測定し、動悸・息切れなどの変化を記録する。
- 胸部不快感やめまいの訴えがあった場合、直ちに医療機関へ連絡できる体制を整える。
- 不眠や倦怠感などの症状を本人から聞き取り、訪問看護と情報共有する。
- 浮腫や体重増加が見られた場合は、心不全の兆候として注意し報告する。
- 入浴や運動後の体調を確認し、無理のない生活リズムを整える。
- 発熱や感染症状がある場合は、ペースメーカーへの影響を考慮し医師へ報告する。
- 本人に体調の変化を日誌に記録してもらい、モニタリングに活用する。
- 定期受診の結果を共有し、今後の生活指導に反映する。
- 複数職種で体調情報を共有し、早期発見・早期対応を徹底する。
【服薬管理】
- 不整脈治療薬を確実に内服できるよう、服薬支援を行う。
- 抗凝固薬の副作用(出血・あざ)に注意し、異常時は医師に連絡する。
- 服薬アラームを活用し、飲み忘れを予防する。
- 家族に服薬状況を確認してもらい、ダブルチェック体制をとる。
- 薬の変更があった場合、サービス担当者に迅速に情報共有する。
- 本人に薬の必要性を説明し、服薬意欲を高める。
- 飲み込みに不安がある場合は、訪問看護と連携して服薬支援を行う。
- 副作用と思われる症状を観察し、記録に残す。
- 内服薬と市販薬・サプリメントの飲み合わせに注意するよう助言する。
- 医師の指示を守り、自己判断で服薬を中止しないよう本人へ説明する。
【通院支援】
- ペースメーカー定期点検の通院予定をカレンダーで管理する。
- 通院日の送迎を家族・事業所と調整し、安心して受診できるようにする。
- 通院時に医師からの指示をケアマネが確認し、ケアプランに反映する。
- 病院受診後に薬局での薬受け取りまでを支援する。
- 本人が通院理由を理解できるよう、わかりやすく説明する。
- 通院結果を記録し、家族やサービス担当者に共有する。
- 主治医との連携を密にし、異常時の受診体制を明確にする。
- 訪問看護と通院日程を調整し、医療情報を継続的に共有する。
- 通院への抵抗感を軽減するため、事前に準備物を確認して支援する。
- 定期検査を欠かさないよう、本人に声かけを継続する。
【生活支援】
- 携帯電話は胸から離して使用するよう助言する。
- 電磁調理器やIH使用時は距離を保つよう指導する。
- 重労働を避け、心臓に負担の少ない生活を支援する。
- 日常生活動作を無理なく行えるよう、介護サービスを組み合わせる。
- 睡眠・休養を十分にとり、過労を防ぐ生活習慣を整える。
- 服の着脱を無理なく行えるよう、訪問介護で支援する。
- 買い物や掃除など、心臓に負担のかかる作業は家族と分担する。
- 食事はバランス良く摂取し、塩分や水分を医師の指示に合わせて調整する。
- 本人が可能な範囲で役割を持ち、自立心を保てるようにする。
- 趣味活動を継続できるよう環境を整え、生活の質を高める。
【安全確保】
- 救急搬送先や主治医の連絡先を一覧で掲示する。
- ペースメーカー手帳を常に携帯するよう助言する。
- 災害時の避難計画にペースメーカー利用を考慮する。
- 夜間に体調不良が出た場合、家族が迅速に対応できる体制を整える。
- 外出時は連絡手段を確保し、緊急時に対応できるようにする。
- 自宅の階段・段差に手すりを設置し、転倒リスクを減らす。
- 入浴中の体調急変に備えて家族に見守りを依頼する。
- 緊急時に必要な書類・保険証をまとめて保管する。
- 訪問介護職員が異常を察知した場合の連絡ルートを明確にする。
- 家族に緊急時の対応方法を説明し、安心して生活できるようにする。
【家族支援】
- 家族にペースメーカー管理の注意点を説明する。
- 緊急時の連絡手順を家族に周知する。
- 家族が介護疲れを抱えないよう、ショートステイの利用を提案する。
- 家族とケアマネで情報共有を行い、不安を軽減する。
- 家族が体調変化に気づけるよう、観察ポイントを伝える。
- 家族に服薬管理を協力してもらい、飲み忘れ防止を図る。
- 家族が通院同行できるよう、日程調整を支援する。
- 家族会や地域支援団体を紹介し、孤立を防ぐ。
- 家族の負担が過大な場合、訪問介護を組み合わせて支援する。
- 家族の不安をケアマネが受け止め、相談できる場を確保する。
【リハビリ・運動】
- 医師の許可範囲で、無理のない運動を継続できるよう支援する。
- リハビリ専門職と連携し、歩行訓練を実施する。
- 心臓に負担をかけないストレッチを取り入れる。
- 日常生活動作を維持できるよう運動習慣を整える。
- 運動後の体調を観察し、異常時は医師へ報告する。
- 家族と一緒に軽い散歩を習慣化できるよう支援する。
- 運動内容を本人に理解してもらい、納得して取り組めるようにする。
- 呼吸法を取り入れ、安定した生活活動を支援する。
- 疲労時は休養を優先し、無理のない運動を続ける。
- 訪問リハビリと連携し、在宅でも継続的に訓練を行う。
【心理的支援】
- ペースメーカー植え込みへの不安を傾聴し、安心感を与える。
- 「普通の生活が送れる」ことを説明し、意欲を高める。
- 気分の落ち込みがある場合、訪問看護や主治医に相談する。
- 家族や友人との交流を促し、孤立を防ぐ。
- 趣味活動を継続できるよう支援し、生活意欲を高める。
- 利用者が安心して相談できるよう、ケアマネが定期的に傾聴する。
- 施設利用時も安心できるよう、スタッフに情報を伝える。
- 本人の希望を尊重し、ケアプランに反映する。
- 精神的に不安定なときは、家族と連携して対応する。
- 必要に応じて専門医やカウンセリングを紹介する。
【社会参加・生活の質】
- デイサービスを利用し、社会交流を維持する。
- 地域のサークルや集まりに参加できるよう支援する。
- 施設利用時に安心して活動できるよう、情報を共有する。
- 本人の得意分野を活かし、役割を持てるようにする。
- 季節の行事に参加し、生活の楽しみを持つ。
- 趣味活動を継続できるよう、必要な支援を行う。
- 地域包括支援センターと連携し、生活の場を広げる。
- 外出機会を増やし、閉じこもりを防ぐ。
- 家族との外食や旅行を楽しめるように計画する。
- 本人の希望に沿った余暇活動を支援する。
【将来への見通し】
- 介護度が変化した場合も、継続して生活できるようサービスを調整する。
- 体調悪化時の入院体制を明確にする。
- 今後の生活希望を本人と話し合い、記録に残す。
- 家族と一緒に将来の暮らし方を検討する。
- 介護サービス利用を継続し、在宅生活を支える。
- 定期的にケアプランを見直し、必要な支援を反映する。
- 主治医と情報交換を行い、医療と介護の連携を深める。
- ペースメーカー交換時期に備え、家族と計画を共有する。
- 施設入所が必要になった場合の選択肢を整理しておく。
- 利用者の生活の質を最優先に考え、柔軟にサービス調整を行う。
まとめ
ペースメーカー利用者のケアプランでは、体調管理・服薬・通院・生活支援・安全確保・家族支援・リハビリ・心理的支援・社会参加 など、幅広い支援が必要です。今回紹介した100文例は、そのままコピーしてもアレンジしても使える実践的な内容です。
ケアマネジャーは利用者の安全と安心を第一に考えながら、医師や訪問看護・介護職・家族と連携してケアプランを作成することが重要です。ぜひ日々の業務にご活用ください。















