【コピペOK】歩行器のケアプラン文例を100紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
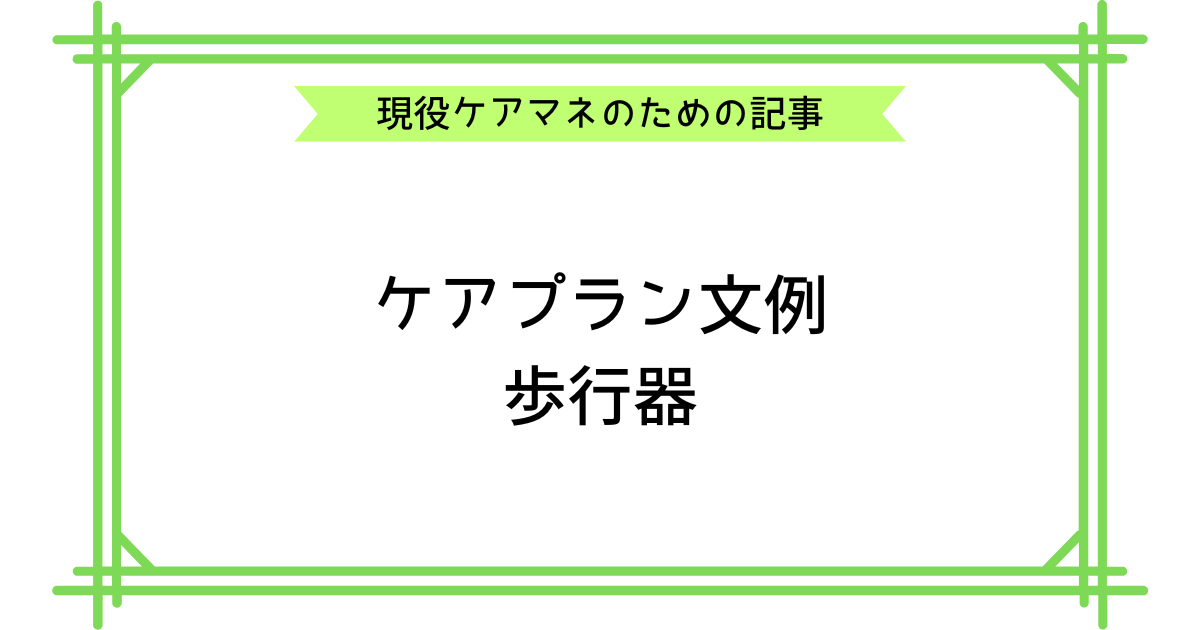
要介護高齢者やリハビリ中の利用者にとって、歩行器は「転倒防止」と「自立支援」を両立する大切な福祉用具です。
しかし、ケアプランに歩行器の使用をどのように落とし込むべきか迷うケアマネジャーも多いのではないでしょうか。
本記事では、歩行器に関するケアプラン文例を100事例 用意しました。
居宅サービス計画書や施設サービス計画書にそのまま使えるように整理しています。
目次
歩行器のケアプラン文例100
【基本的な使用支援】
- 歩行器を使用して安全に歩行できるよう見守りを行う。
- 毎回歩行器を正しく使用できるよう声かけする。
- 使用前にブレーキや高さを確認し、事故を防止する。
- 歩行器を使用して居室から食堂まで安全に移動する。
- 廊下での移動時に歩行器が安定して使えるよう支援する。
- 居室からトイレまでの移動を歩行器で安全に行えるようにする。
- 移動時に無理がないよう、休憩を取りながら歩行器を使用する。
- 歩行器の使用を習慣化し、転倒リスクを減らす。
- 外出時も歩行器を使用して安全を確保する。
- 歩行器を使うタイミングを本人が理解できるように支援する。
【自立支援】
- 歩行器を活用し、自立的に移動できるよう促す。
- 本人の体力に応じて歩行距離を徐々に延ばす。
- 歩行器を使用して短距離から歩行練習を行う。
- トイレ動作まで自立できるよう歩行器で支援する。
- 廊下の往復を繰り返し行い、自立歩行を目指す。
- 食事場所まで歩行器で移動し、自主性を高める。
- レクリエーション参加の際に歩行器での移動を促す。
- 外出時に歩行器を活用し、社会参加を維持する。
- 歩行器使用で本人の成功体験を積み、自信につなげる。
- 本人の希望に応じて歩行器を使い分け、自立を支援する。
【転倒予防】
- 歩行器の使用を徹底し、転倒リスクを軽減する。
- 段差のある場所では職員が付き添い安全を確保する。
- カーペットやマットの段差に注意し、転倒を防ぐ。
- 歩行器が安定するよう床環境を整える。
- 滑りやすい場所ではブレーキ使用を促す。
- 夜間の移動時には照明を確保する。
- 転倒歴があるため、歩行器使用を強く推奨する。
- 濡れた床や浴室内での使用は避け、転倒を防止する。
- 居室内に障害物がないよう環境を整備する。
- 歩行器を使用しても不安定な場合はスタッフが補助する。
【環境整備】
- 居室内を整理整頓し、歩行器で移動しやすくする。
- 廊下に手すりを併用し、歩行器との併用を支援する。
- トイレや浴室前に歩行器を置けるスペースを確保する。
- 施設内の床を清掃し、滑りを防ぐ。
- 居室から共用スペースまでの動線を確保する。
- 利用者ごとに適した歩行器の種類を選定する。
- 高さを調整して本人の身体に合うようにする。
- 車椅子と歩行器を併用できる環境を整える。
- 外出先の段差や階段では別の方法を用意する。
- 歩行器の保管場所を決め、使用時にすぐ取り出せるようにする。
【リハビリ・機能訓練】
- 歩行器を用いた歩行訓練を理学療法士と連携して行う。
- 下肢筋力を強化し、歩行器での移動を安定させる。
- バランス訓練を取り入れ、歩行時の安定性を高める。
- 歩行速度を少しずつ上げ、体力向上を図る。
- 段差昇降練習を行い、外出時の安全性を高める。
- 歩行距離をモニタリングし、目標設定に活用する。
- グループでの歩行訓練を実施し、意欲を高める。
- 理学療法士と連携し、適切な運動プログラムを継続する。
- 歩行器を使用しても疲労が強い場合は休養を優先する。
- 訓練後に成果を共有し、達成感を持てるようにする。
【心理的支援】
- 歩行器の使用に抵抗がある場合は安心できるよう説明する。
- 歩行器使用を前向きに捉えられるよう声かけを行う。
- 成功体験を積み重ねて自信を高める。
- 「一緒に歩きましょう」と声をかけ意欲を引き出す。
- 不安が強いときはそばで付き添いを行う。
- 歩行器の使用に関する本人の気持ちを傾聴する。
- 歩行器を使うことを「リハビリの一部」として説明する。
- 歩行器を使った活動の成果を本人にフィードバックする。
- 本人の希望を尊重し、使用場面を一緒に決める。
- 周囲と比較せず本人のペースを尊重する。
【社会参加】
- 歩行器を使用してレクリエーションに参加できるよう支援する。
- 外出行事に歩行器を持参し、安全に参加できるようにする。
- 食堂での会食に歩行器で移動し、社会交流を促す。
- 歩行器を使用して家族との外出を支援する。
- デイサービスの活動に安心して参加できるよう支援する。
- 利用者同士で歩行器を活用した活動を共有する。
- 地域行事に参加する際、歩行器を活用する。
- 外部ボランティアとの交流に歩行器を活用する。
- 趣味活動に歩行器で安全に参加する。
- 社会参加時の安全対策を職員間で共有する。
【安全確保】
- 歩行器のブレーキ機能を使用前に必ず確認する。
- 歩行器の劣化や破損を定期的に点検する。
- 移動経路に障害物がないよう毎日確認する。
- 居室内に歩行器が転倒しないよう収納スペースを確保する。
- 外出時は職員が付き添い安全を確保する。
- 夜間移動時は照明をつけ、歩行器使用を徹底する。
- 緊急時に対応できるよう歩行器周辺を整理する。
- 食事後の歩行時に転倒しないよう注意する。
- トイレ移動の際に滑り止めマットを使用する。
- 段差解消スロープを設置し、歩行器移動を安全に行う。
【家族支援】
- 家族に歩行器の使用方法を説明する。
- 家族と一緒に歩行練習を行い安心感を与える。
- 家族に転倒リスクを伝え、注意点を共有する。
- 外出時に歩行器を使用できるよう家族へ助言する。
- 家族に歩行器の点検方法を伝える。
- 歩行器使用時の声かけ方法を家族に指導する。
- 家族に歩行器を使った生活の工夫を提案する。
- 歩行器利用で自立が促進されることを家族に説明する。
- 家族と使用場面を相談し、生活に取り入れる。
- 家族が安心して見守れるよう情報提供を行う。
【将来を見据えた支援】
- 定期的に歩行状況を評価し、使用の必要性を見直す。
- 身体機能の変化に合わせて歩行器の種類を検討する。
- 歩行器から杖への移行を目指す場合は医師と相談する。
- 逆に車椅子への移行が必要な場合は早めに準備する。
- 歩行器使用の長期的な効果を記録し、ケアプランに反映する。
- 歩行器を使用しても転倒リスクが高い場合は再評価を行う。
- 利用者本人の目標を尊重し、歩行器の活用方法を調整する。
- 多職種で歩行器使用の効果を検討する。
- 本人の生活の質を最優先に、歩行器の使用を調整する。
- 歩行器を用いて「安心して歩ける生活」を継続できるよう支援する。
まとめ
歩行器のケアプランでは、安全性の確保・転倒予防・自立支援・リハビリ・心理面への配慮・家族連携 が重要です。
今回紹介した100の文例は、実務でそのまま使えるよう汎用性を意識しています。
歩行器は単なる補助具ではなく、利用者の 自立と生活の質(QOL) を高める大切なツールです。
ケアプランにしっかりと反映させ、安心できる生活を支援していきましょう。















