小規模多機能と訪問看護は事業所間契約が必要?制度上のルールを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
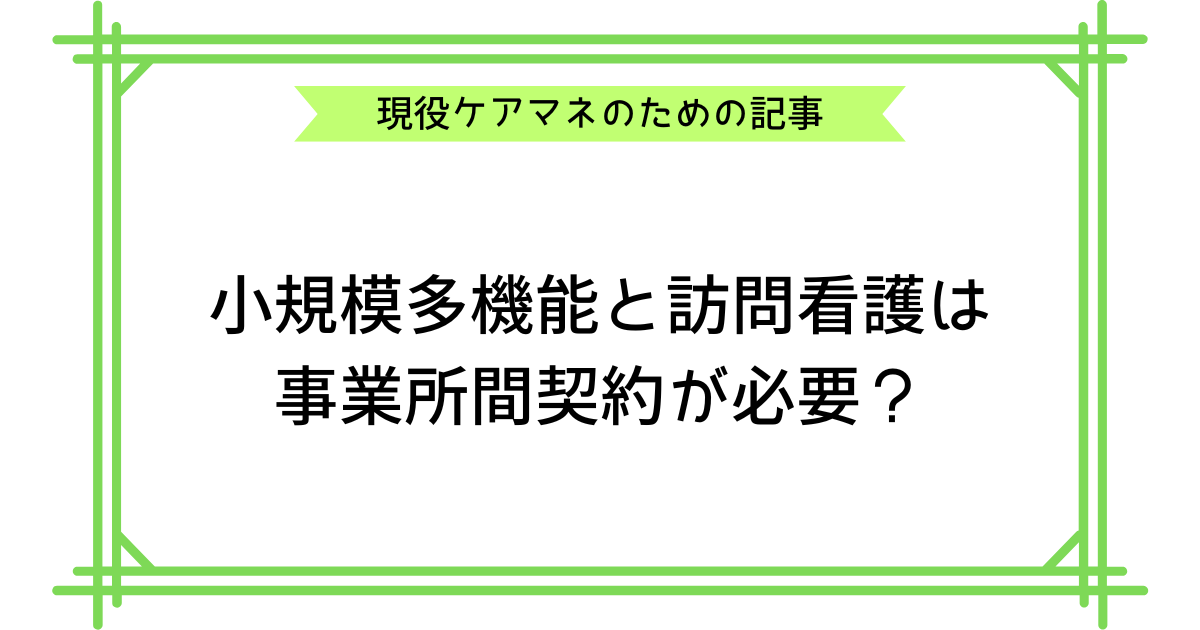
「小規模多機能型居宅介護」は、通い・訪問・泊まりを一体的に提供できる地域密着型サービスです。登録した一つの事業所が包括的に支援を担うため、原則として他の介護保険サービスとの併用はできません。
ただし、医療ニーズが高い方に必要となる「訪問看護」については、例外的に併用が認められています。このときに出てくるのが 「事業所間契約」 という仕組みです。
この記事では、小規模多機能と訪問看護を併用する際に必要となる事業所間契約のルールや手続きについて、制度の根拠を踏まえて詳しく解説します。
目次
小規模多機能型居宅介護の基本ルール
- 地域密着型サービスとして、市町村が指定・運営管理を行う
- 登録した事業所が「通い」「訪問」「泊まり」を包括的に提供
- 包括報酬制(定額制)のため、原則として他の訪問介護や通所介護などは併用できない
つまり、一つの事業所で必要な支援を完結させる仕組みが小規模多機能の特徴です。
訪問看護は例外的に併用可能
小規模多機能の「訪問」は生活援助や介護中心であり、医療的な処置や管理までは対応できません。そのため、医師の指示に基づいて医療的ケアを行う 訪問看護だけは併用が可能とされています。
例:
- 誤嚥性肺炎のリスクがあるため、嚥下機能チェックを訪問看護師が行う
- 在宅酸素や点滴管理が必要で、小規模多機能職員では対応できない
- 終末期ケアにおいて医療的判断・処置が欠かせない
事業所間契約とは?
小規模多機能と訪問看護を併用する場合、利用者が個別に訪問看護ステーションと契約するのではなく、小規模多機能事業所と訪問看護事業所が「事業所間契約」を結ぶ必要があります。
仕組み
- 利用者は小規模多機能と契約しているため、基本的に小規模多機能がサービス提供の窓口となる
- 訪問看護を導入する場合、小規模多機能と訪問看護事業所が契約を結び、サービスを提供
- 利用者本人や家族は、あくまで小規模多機能との契約に基づいてサービスを受ける
契約の目的
- 利用者にとって契約窓口を一本化し、手続きを簡素化する
- 小規模多機能が責任を持って利用者のケアを管理できるようにする
- 介護保険制度上の「包括報酬制」の仕組みを維持する
事業所間契約を結ぶときの流れ
- 医師の指示書に基づき、訪問看護の必要性を確認
- ケアマネジャー(管理者)が訪問看護導入を検討
- 小規模多機能と訪問看護事業所が契約を締結
- サービス担当者会議で方針を共有
- 小規模多機能のケアプランに訪問看護を位置づけ、サービス提供開始
ケアマネジャーが注意すべき点
- 訪問看護導入は「医療的ケアの必要性」が明確であること
- 契約関係は利用者と訪問看護事業所ではなく「小規模多機能と訪問看護事業所」であること
- 利用者・家族に「併用は可能だが、事業所間契約になる」ことを分かりやすく説明する
- サービス担当者会議で小規模多機能と訪問看護の役割分担を明確化する
まとめ
- 小規模多機能型居宅介護は、原則として他サービスと併用不可
- ただし 訪問看護だけは例外的に併用可能
- このとき必要なのが 小規模多機能と訪問看護事業所との「事業所間契約」
- 利用者や家族は小規模多機能との契約一本でサービスを受けられる
制度を正しく理解することで、医療ニーズのある方も安心して小規模多機能を利用できます。ケアマネジャーや事業所は、連携と情報共有を大切にしながら支援を組み立てていくことが求められます。















