小規模多機能型居宅介護における30日ルールとは?ショートステイとの違いを解説
当ページのリンクには広告が含まれています。
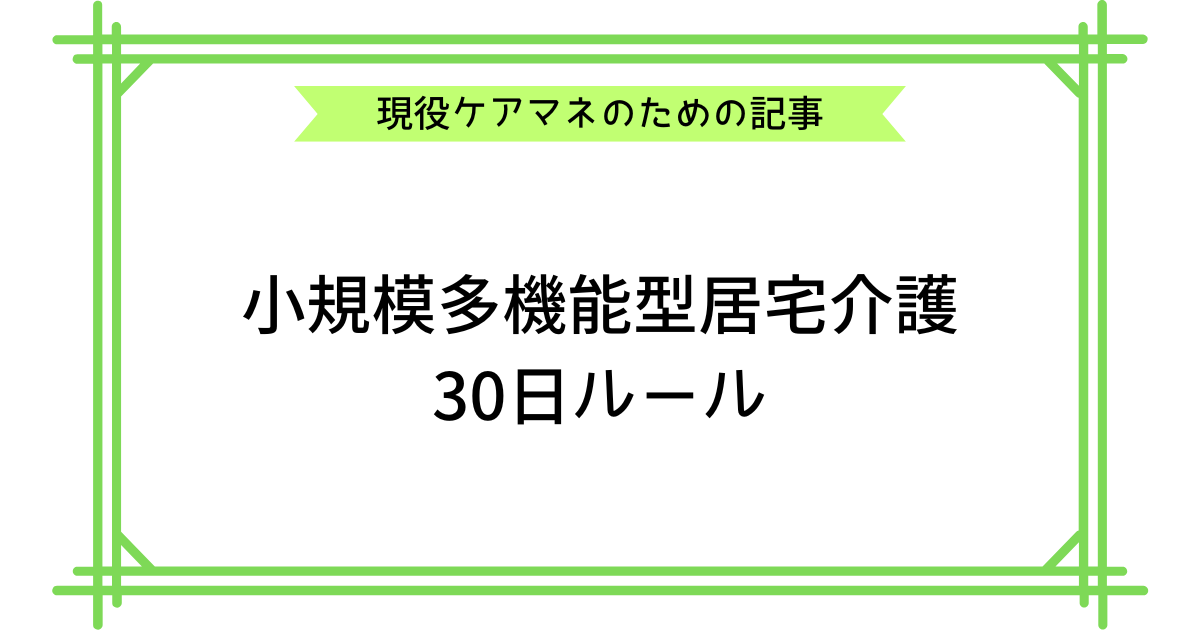
在宅生活を支える地域密着型サービスとして注目される 小規模多機能型居宅介護。
「通い」「訪問」「泊まり」を組み合わせて利用できる柔軟なサービスですが、利用者やご家族からは「ショートステイのように30日ルールがあるのでは?」と質問を受けることもあります。
本記事では、小規模多機能型居宅介護における30日ルールの有無や制度的な位置づけ、ショートステイとの違いをわかりやすく解説します。
目次
そもそも「30日ルール」とは?
ショートステイでの30日制限
介護保険サービスの 短期入所生活介護(ショートステイ) では、
- 原則30日を超えて連続利用できない
- 31日目以降は介護保険では算定できず、自費負担となる場合がある
というルールがあります。
これは「ショートステイはあくまで一時的利用」であり、施設入所の代替とならないようにするための規制です。
小規模多機能型居宅介護に30日ルールはある?
結論から言うと、小規模多機能型居宅介護にはショートステイのような「30日ルール」はありません。
理由
- 小規模多機能は「通い」「訪問」「泊まり」を一体的に提供する包括的なサービス
- 利用者は小規模多機能を「登録」し、月単位の包括報酬で利用する仕組み
- 「泊まり」はショートステイとは異なり、あくまでサービスの一部として位置づけられている
そのため、ショートステイのように「連続30日まで」といった日数制限は制度上設けられていません。
小規模多機能の「泊まり」とショートステイの違い
| 項目 | 小規模多機能の泊まり | ショートステイ(短期入所生活介護) |
|---|---|---|
| 制度区分 | 地域密着型サービス | 施設サービス |
| 利用形態 | 登録利用者限定 | 登録制なし |
| 利用制限 | 原則制限なし | 連続30日まで |
| 料金体系 | 包括報酬(介護度に応じた定額制)+食費・宿泊費実費 | 介護報酬(利用日数ごと)+食費・居住費 |
| 利用目的 | 在宅生活を継続するための柔軟な支援 | 家族のレスパイトや一時的入所 |
| 担当ケアマネ | 事業所専任ケアマネジャー | 居宅介護支援事業所のケアマネ |
注意点:実質的な「長期入所化」は避けるべき
制度上は30日ルールはなくても、以下の点に注意が必要です。
- 小規模多機能は「在宅生活支援」が目的
- 泊まりが長期化すると「施設入所」と見なされ、自治体から指導を受けることもある
- 通い・訪問と組み合わせて、在宅生活を続けられるよう活用することが望ましい
家族が理解しておくべきポイント
- 30日ルールはショートステイ特有の規制
→ 小規模多機能には該当しない。 - 利用は包括報酬制
→ 泊まりを多用しても、基本介護費は定額。ただし食費・宿泊費は別途必要。 - 長期泊まりは相談必須
→ 制度趣旨から外れないよう、事業所・ケアマネと調整する。
まとめ
- ショートステイには「30日ルール」があり、連続利用は30日までが原則。
- 一方、小規模多機能型居宅介護には 30日ルールは存在しない。
- ただし、制度目的は「在宅生活の継続支援」であり、泊まりの長期化は避けるべき。
- 利用計画は事業所のケアマネジャーと相談し、通い・訪問・泊まりをバランスよく組み合わせることが重要。
小規模多機能は、柔軟に在宅生活を支える仕組みとして設計されています。ショートステイとの違いを理解し、安心して使えるようにしておきましょう。
あわせて読みたい

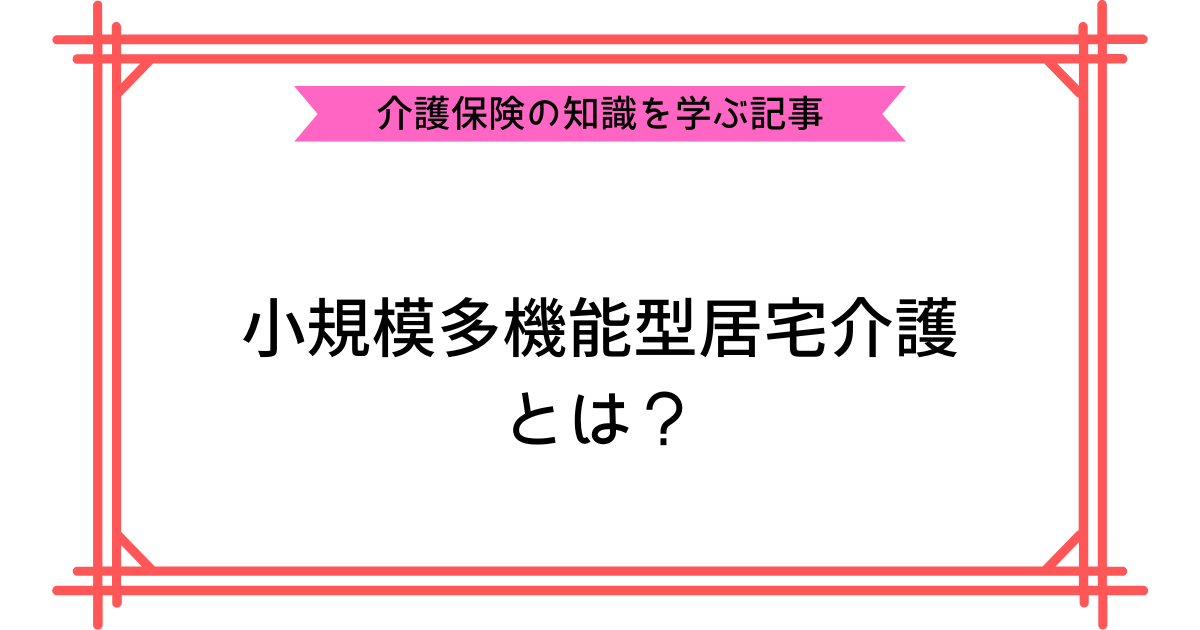
小規模多機能型居宅介護(小多機)とは?わかりやすく解説
介護保険サービスの中には、「訪問介護」「通所介護(デイサービス)」「ショートステイ」といったサービスがよく知られています。しかし、実際の生活では「通い」「訪...















