ケアマネは利用者が亡くなった時に何をするのが正解?
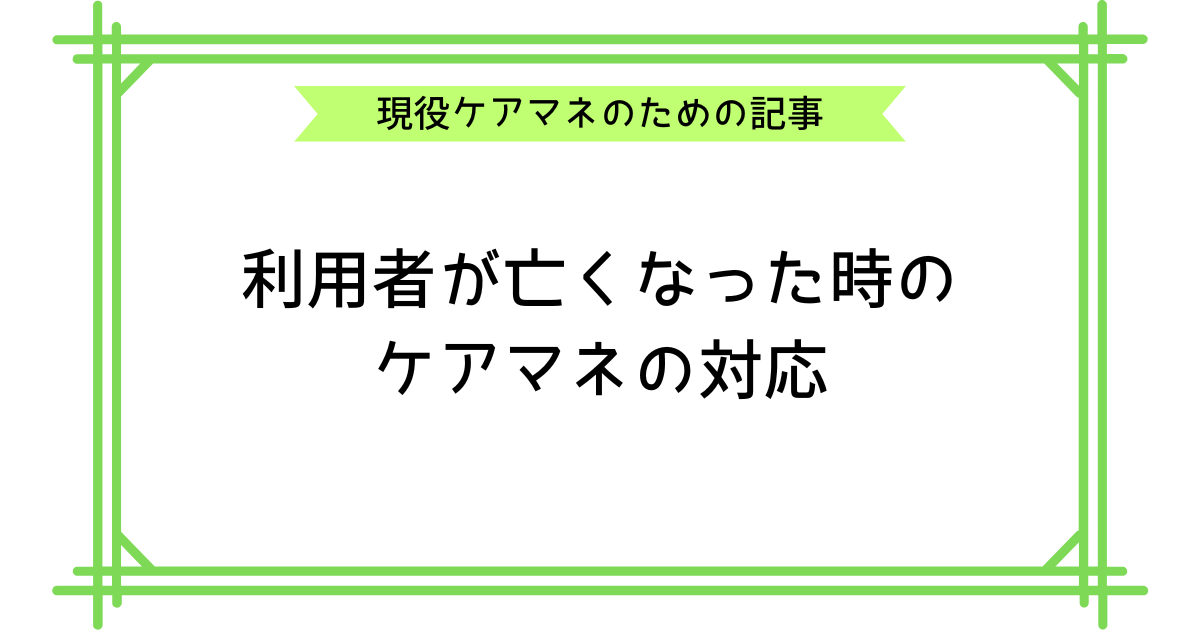
ケアマネージャー(介護支援専門員)として利用者支援を続けている中で、避けられない現実の一つが「利用者の逝去」です。
利用者が亡くなった際には、家族への対応や各種手続きが発生し、何をすべきか迷うことが少なくありません。
悲しみやショックを感じつつも、プロとして冷静に対処しなければならない状況が求められます。
本記事では、ケアマネが利用者が亡くなった際に取るべき正しい対応や流れをわかりやすく解説します。
必要な手続きや家族への対応ポイントを押さえ、スムーズに進められるようにしましょう。
ケアマネが利用者が亡くなった時に取るべき対応とは?

利用者が亡くなった際には、感情的な動揺があっても冷静に対処しなければなりません。
ここでは、具体的な対応手順を解説します。
1. 家族や関係者に事実確認をする
まず、利用者が亡くなったとの連絡を受けた場合、すぐに家族や関係者に事実確認を行いましょう。直接連絡が取れる場合には、亡くなった場所や状況を確認し、誤情報でないかを確かめます。
ポイント
- 連絡者が家族や施設職員かどうかを確認する。
- 亡くなった場所や時刻を詳細に聞き取る。
- 可能であれば、状況を把握しつつ冷静に対応する。
2. 事業所への報告と上司への連絡
利用者が亡くなったことが確認できたら、速やかに事業所や上司に報告します。特に、訪問看護や居宅介護支援事業所など多職種が関わっている場合、情報共有が遅れるとトラブルになることがあります。
報告のポイント
- 亡くなった事実を正確に伝える。
- 事業所全体で対応を共有し、混乱を防ぐ。
- 今後の対応方針を上司と相談する。
3. 他職種や関連機関に情報共有を行う
ケアマネージャーは、多職種連携が重要な役割です。利用者が亡くなった際には、関係機関に対して迅速に情報を共有しましょう。
情報共有先の例
- 訪問介護事業所
- 訪問看護ステーション
- リハビリ職(理学療法士、作業療法士など)
- 地域包括支援センター
- 医療機関(かかりつけ医)
4. 介護サービスの解約手続きと費用精算
利用者が亡くなった場合には、介護サービスを解約し、料金の精算が必要です。特に訪問系サービスが多い場合、解約手続きが遅れるとトラブルにつながるため、速やかに行いましょう。
解約手続きのポイント
- 各サービス提供事業所に解約を連絡する。
- 料金発生の有無を確認し、適切に精算手続きを行う。
- 契約解除届や解約届を速やかに作成する。
5. 家族への丁寧な対応
利用者が亡くなった際には、家族が精神的に大きなショックを受けているため、丁寧な対応が求められます。必要以上に業務的にならず、思いやりを持って接することが大切です。
対応のポイント
- 家族に対してお悔やみの言葉を伝える。
- 必要な手続きについて分かりやすく説明する。
- 葬儀や追悼の場で無理に業務的な話をしない。
ケアマネとしての心得と心構え

利用者が亡くなった際には、感情的になりすぎず冷静な対応が求められます。
しかし、ケアマネ自身も長年支えてきた利用者を失うことに対する悲しみがあり、心の整理が難しいケースも多いでしょう。
そこで、自分の気持ちを整理するためにも、以下のポイントを大切にしましょう。
自己ケアを忘れない
心身の負担が大きくならないよう、自分自身のケアも意識してください。事業所の同僚や上司に気持ちを共有し、無理をしないことが大切です。
メンタルサポートを活用する
特に感情が整理できない場合には、カウンセラーや専門機関を活用することで、心の負担を軽減できます。利用者の死を一人で抱え込まず、適切にケアを受けましょう。
まとめ

ケアマネが利用者が亡くなった際に取るべき対応は、家族や関係者への迅速かつ丁寧な報告と情報共有が基本です。
さらに、サービス解約手続きや費用精算を的確に進め、家族へのフォローも忘れずに行いましょう。
感情的な負担が大きい状況でも、プロとして冷静に対応するために、事前に対応マニュアルを整備しておくことが重要です。
利用者との別れに向き合いながら、プロとしての姿勢を崩さないことが信頼されるケアマネの在り方です。















