【ケアマネがコピペで使える】誤嚥性肺炎のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
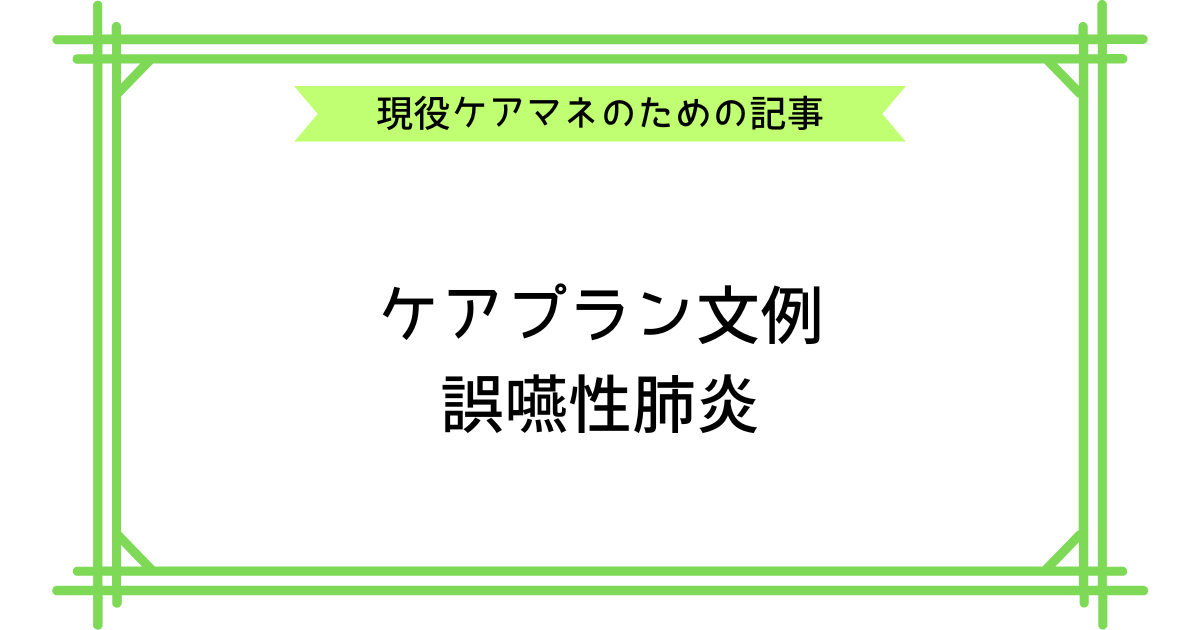
誤嚥性肺炎は、高齢者に多く見られる重大な疾患のひとつです。食べ物や飲み物、唾液などが誤って気道に入ることで発症し、命に関わることも少なくありません。介護現場では「むせが多い」「口腔内が不衛生」「嚥下機能が低下している」といったサインを見逃さず、予防的なケアを行うことが大切です。
ケアマネジャーがケアプランを作成する際には、誤嚥性肺炎のリスクを減らすために、口腔ケア・嚥下訓練・食事姿勢・食形態の調整・服薬管理・医療連携など、多角的な視点を盛り込む必要があります。
本記事では、ケアマネがすぐに使える 「誤嚥性肺炎のケアプラン文例」100事例 を紹介します。各事例は「課題」「目標」「サービス内容」の3要素で整理しています。利用者の状態に応じてコピペ・修正し、ケアプラン作成やモニタリングにお役立てください。
目次
誤嚥性肺炎のケアプラン文例
1.口腔ケア不足による誤嚥リスク
- 課題:口腔内の不衛生が続き、誤嚥性肺炎リスクが高い
- 目標:毎食後に口腔ケアを実施できる
- サービス内容:訪問介護で歯磨き支援、歯科衛生士訪問で指導
2.食事中のむせが多い
- 課題:食事中にむせが多く誤嚥リスクが高い
- 目標:誤嚥なく食事を安全に摂取できる
- サービス内容:STによる嚥下訓練を導入、訪問介護で食事介助
3.不適切な食事姿勢
- 課題:横になったまま食事を摂取している
- 目標:椅子に座り、正しい姿勢で食事できる
- サービス内容:訪問介護で食事時の姿勢を調整し見守り
4.食形態が合っていない
- 課題:硬い食材を摂取し誤嚥している
- 目標:嚥下機能に合わせた食事形態で安全に摂取できる
- サービス内容:STと栄養士が評価し、ソフト食・刻み食に調整
5.服薬時の誤嚥
- 課題:錠剤を飲み込みにくく、誤嚥しやすい
- 目標:服薬補助ゼリーを使用して安全に服薬できる
- サービス内容:訪問介護で服薬介助を実施し、服薬方法を工夫
6.水分摂取時のむせ
- 課題:水分摂取時にむせが頻発する
- 目標:トロミ剤を使用して安全に水分摂取できる
- サービス内容:訪問介護でトロミ調整、STの指導を導入
7.口腔乾燥による誤嚥リスク
- 課題:口腔乾燥が強く誤嚥性肺炎リスクが高い
- 目標:保湿ケアで口腔環境を整えられる
- サービス内容:訪問介護で口腔保湿ジェルを使用、口腔リハビリを実施
8.咳反射の低下
- 課題:咳反射が弱く痰が出せない
- 目標:排痰法を習得し痰を喀出できる
- サービス内容:訪問看護で排痰法を指導、吸引機の導入検討
9.入れ歯不適合による誤嚥
- 課題:義歯が合わず咀嚼不良で誤嚥している
- 目標:適切な義歯で安全に食事できる
- サービス内容:歯科受診を勧め、義歯調整を実施
10.認知症による食事リスク
- 課題:認知症により一気食いして誤嚥しやすい
- 目標:ゆっくりと安全に食事を摂取できる
- サービス内容:訪問介護で見守りながら食事介助、食事ペースを調整
11.食後すぐに横になる習慣
- 課題:食後すぐに横になり逆流・誤嚥リスクが高い
- 目標:食後30分は座位を保持できる
- サービス内容:訪問介護で声かけ、デイサービスで食後リクライニング保持を実施
12.食事量が多すぎる
- 課題:一度に大量に食べてむせや誤嚥がある
- 目標:少量頻回の食事で安全に摂取できる
- サービス内容:栄養士と連携し、少量提供を訪問介護が実施
13.嚥下体操不足
- 課題:嚥下体操を行わず誤嚥リスクが高い
- 目標:毎食前に嚥下体操を実施できる
- サービス内容:STが体操指導、訪問介護が声かけ支援
14.飲み込みに時間がかかる
- 課題:嚥下に時間がかかり途中で誤嚥している
- 目標:時間をかけても安全に飲み込める
- サービス内容:訪問介護が食事中のペースを調整
15.頸部前傾姿勢の保持ができない
- 課題:食事中に頭が後ろに反りやすく誤嚥しやすい
- 目標:顎を引いた姿勢で摂食できる
- サービス内容:訪問介護で姿勢調整、クッションやテーブル高さを調整
16.食事時の集中力低下
- 課題:会話やテレビに気を取られ誤嚥が多い
- 目標:集中して食事を摂取できる
- サービス内容:訪問介護で環境を整え、静かな環境で食事介助
17.嚥下反射が弱い
- 課題:嚥下反射が弱く誤嚥しやすい
- 目標:嚥下反射を高め安全に摂食できる
- サービス内容:STが嚥下リハを指導、訪問看護で継続支援
18.水分摂取不足
- 課題:水分不足で痰が粘調になり誤嚥リスクがある
- 目標:安全に必要な水分を摂取できる
- サービス内容:トロミ調整を行い訪問介護で水分補給を促す
19.痰の貯留
- 課題:痰が喉に貯留し誤嚥しやすい
- 目標:自力で排痰できる
- サービス内容:訪問看護で排痰法を指導、必要時吸引を実施
20.食事介助時のスピードが速い
- 課題:介助者が早く食事を与え誤嚥が多い
- 目標:ゆっくり食事を進められる
- サービス内容:訪問介護で食事介助スピードを調整
21.嚥下リハビリの未実施
- 課題:嚥下訓練を行わず誤嚥リスクが高い
- 目標:ST指導を受けて毎日訓練を実施できる
- サービス内容:週1回ST訪問、日常は訪問介護で声かけ
22.食具の不適切使用
- 課題:スプーンが大きすぎ誤嚥が生じる
- 目標:適切な食具を使用して安全に摂食できる
- サービス内容:OTが食具を選定し、訪問介護で使用指導
23.食事中の姿勢保持が難しい
- 課題:姿勢が崩れて誤嚥が起きやすい
- 目標:姿勢保持具を用いて正しく座位を保てる
- サービス内容:訪問リハで座位保持具を導入、訪問介護が調整
24.嚥下時に唇が閉じられない
- 課題:口から食物が漏れ誤嚥につながる
- 目標:口唇閉鎖を意識できる
- サービス内容:STが口腔体操を指導、訪問介護で実施確認
25.嚥下に必要な筋力低下
- 課題:加齢や疾患で舌や頬の筋力低下
- 目標:口腔リハで嚥下機能を維持
- サービス内容:STがリハを指導、訪問介護で支援
26.誤嚥後の発熱が頻発
- 課題:食事後に発熱し誤嚥性肺炎を繰り返している
- 目標:誤嚥を減らし発熱を予防できる
- サービス内容:訪問看護で健康観察、主治医と連携
27.食事の一口量が大きい
- 課題:大きな一口で誤嚥が多い
- 目標:小さな一口でゆっくり食べられる
- サービス内容:訪問介護で声かけし、スプーン量を調整
28.飲み込み動作が遅い
- 課題:飲み込みが遅く気道に流れやすい
- 目標:時間をかけ安全に飲み込める
- サービス内容:訪問介護で一口ごとに声かけ
29.咀嚼が不十分
- 課題:噛まずに飲み込むため誤嚥しやすい
- 目標:十分に咀嚼してから嚥下できる
- サービス内容:訪問介護で咀嚼確認を行いながら介助
30.認知症による摂食行動異常
- 課題:食べ物を急いで口に入れる
- 目標:安全なペースで摂食できる
- サービス内容:訪問介護で食事時に見守り、声かけ
31.食事中の咳き込み
- 課題:食事中にしばしば咳き込みがある
- 目標:安全に最後まで食事を終えることができる
- サービス内容:訪問介護で食事介助を行い、むせの有無を観察
32.誤嚥後の体調不良
- 課題:誤嚥後に発熱や呼吸苦を繰り返す
- 目標:誤嚥を予防し体調を安定させる
- サービス内容:訪問看護で体温・呼吸状態を観察し、医師へ報告
33.痰の切れが悪い
- 課題:痰が喉に残り誤嚥しやすい
- 目標:自力で痰を喀出できるようになる
- サービス内容:訪問看護で排痰法の指導、必要時に吸引
34.食事形態を本人が拒否
- 課題:嚥下に適した食形態を嫌がり誤嚥する
- 目標:誤嚥リスクを減らしつつ本人が受け入れられる食事を提供
- サービス内容:栄養士と相談しソフト食やゼリー食を工夫
35.姿勢保持が不十分
- 課題:食事中に背中が丸まり誤嚥リスクが高い
- 目標:背筋を伸ばした姿勢で食事できる
- サービス内容:訪問リハで座位保持訓練を実施
36.嚥下に必要な意識が薄い
- 課題:飲み込む意識がなく誤嚥しやすい
- 目標:意識して嚥下動作を行える
- サービス内容:訪問介護で一口ごとに「ごっくん」と声かけ
37.食事介助者の経験不足
- 課題:家族が食事介助に慣れておらず誤嚥が多い
- 目標:正しい介助方法を学び安全に支援できる
- サービス内容:訪問看護が介助方法を家族に指導
38.服薬時の姿勢が悪い
- 課題:寝たまま薬を飲み誤嚥する
- 目標:座位で服薬できる
- サービス内容:訪問介護で服薬時に姿勢を調整
39.夜間の唾液誤嚥
- 課題:夜間の唾液誤嚥で咳き込みが多い
- 目標:就寝時の体位を工夫し誤嚥を減らす
- サービス内容:訪問看護が体位を指導、30度ギャッジアップで就寝
40.義歯の清掃不足
- 課題:義歯清掃が不十分で口腔内細菌が多い
- 目標:毎日清掃し誤嚥性肺炎リスクを下げる
- サービス内容:訪問介護で清掃支援、歯科衛生士の指導導入
41.水分補給の工夫不足
- 課題:水分摂取を避け脱水・誤嚥リスクがある
- 目標:トロミ付き飲料を使い安全に水分補給できる
- サービス内容:訪問介護で調整し提供
42.口腔リハ未実施
- 課題:口腔機能が低下し誤嚥リスクが高い
- 目標:毎日口腔体操を実施できる
- サービス内容:STが指導し訪問介護で声かけ
43.肺炎既往歴がある
- 課題:過去に誤嚥性肺炎を繰り返している
- 目標:再発を予防できる
- サービス内容:訪問看護で健康管理を徹底し医師と連携
44.経口摂取継続の難しさ
- 課題:誤嚥リスクが高く食事継続が困難
- 目標:安全に経口摂取を維持できる
- サービス内容:栄養士・STと連携し嚥下食を導入
45.誤嚥後の対応が遅れる
- 課題:誤嚥後に対応できず体調悪化
- 目標:誤嚥時に迅速な対応ができる
- サービス内容:訪問看護が吸引や呼吸確認を行い家族に指導
46.環境が誤嚥リスクを高めている
- 課題:食事中にテレビや雑音で集中できない
- 目標:落ち着いた環境で安全に食事できる
- サービス内容:訪問介護が環境調整を行う
47.嚥下力の低下が進行
- 課題:嚥下機能が徐々に低下している
- 目標:リハビリで嚥下機能を維持
- サービス内容:STによる嚥下訓練を継続
48.嚥下に関する情報不足
- 課題:家族が嚥下に関する知識不足
- 目標:正しい知識で介助できる
- サービス内容:ケアマネが情報提供、STが家族指導
49.服薬形態が不適切
- 課題:錠剤を砕かずに誤嚥している
- 目標:粉砕やゼリーを使用して安全に服薬できる
- サービス内容:医師・薬剤師と連携し服薬形態を調整
50.日常生活で嚥下意識が低い
- 課題:嚥下を意識せず生活している
- 目標:食事以外でも嚥下意識を持てる
- サービス内容:訪問介護で水分補給時も「ゆっくり飲む」声かけ
51.誤嚥後に自覚がない
- 課題:誤嚥しても自覚せず対応が遅れる
- 目標:誤嚥を認識しすぐに対応できる
- サービス内容:訪問看護でサインの見分け方を指導
52.痰がからんだまま放置
- 課題:痰を飲み込んでしまい誤嚥性肺炎を起こしやすい
- 目標:痰を自力で喀出できる
- サービス内容:排痰練習、吸引機の導入検討
53.間食時のむせ
- 課題:間食時にむせが多い
- 目標:間食も安全に摂取できる
- サービス内容:トロミ飲料やソフト菓子を選定
54.食事介助時の一口量が多い
- 課題:介助者が大きな一口で与えるため誤嚥が起きる
- 目標:小さな一口で介助できる
- サービス内容:訪問介護で一口量を調整
55.嚥下力の低下で食欲減退
- 課題:食べづらさから食欲が低下している
- 目標:嚥下しやすい食事を工夫して摂取量を増やす
- サービス内容:栄養士と連携してメニュー調整
56.口腔乾燥の放置
- 課題:口腔乾燥を放置し誤嚥リスク増大
- 目標:口腔保湿を習慣化できる
- サービス内容:口腔保湿ジェルを使用し訪問介護で声かけ
57.食事中の姿勢が傾く
- 課題:体幹保持が弱く食事中に体が傾く
- 目標:姿勢を安定して食事を行える
- サービス内容:訪問リハで座位保持具を導入
58.食事中の疲労
- 課題:食事中に疲れて誤嚥が増える
- 目標:短時間で安全に食事を終えられる
- サービス内容:少量提供で回数を増やし対応
59.嚥下時の咳反射が弱い
- 課題:誤嚥しても咳が出にくい
- 目標:咳反射を高められる
- サービス内容:STによる嚥下リハを導入
60.服薬時の不安
- 課題:薬を飲むときに毎回むせる
- 目標:安心して服薬できる
- サービス内容:服薬補助ゼリーを使用
61.口腔ケアの習慣化不足
- 課題:口腔ケアを忘れることがある
- 目標:毎食後に必ず実施できる
- サービス内容:訪問介護で声かけ、歯科衛生士の指導
62.口腔機能訓練不足
- 課題:舌や頬の筋力が低下
- 目標:口腔体操を毎日行える
- サービス内容:STの指導で実施
63.食事のペースが早い
- 課題:急いで食べ誤嚥が増える
- 目標:ゆっくり食事をとれる
- サービス内容:訪問介護で一口ごとに声かけ
64.飲み込みのタイミングが遅れる
- 課題:飲み込む前に気道に入る
- 目標:嚥下タイミングを合わせられる
- サービス内容:STが嚥下訓練を実施
65.発声が弱い
- 課題:声が弱く嚥下筋も低下
- 目標:発声練習で嚥下力を高める
- サービス内容:STが発声訓練を導入
66.口腔内残渣
- 課題:食後に口腔内に食べかすが残る
- 目標:食後に残渣をなくせる
- サービス内容:食後の口腔ケアを徹底
67.水分摂取の工夫不足
- 課題:水分不足により痰が増えて誤嚥
- 目標:安全に水分補給できる
- サービス内容:トロミをつけた飲料を使用
68.体位変換不足
- 課題:寝たきりで体位が変えられず誤嚥が増える
- 目標:適切な体位で誤嚥を防ぐ
- サービス内容:訪問介護で体位変換を実施
69.栄養不足
- 課題:嚥下障害で栄養が取れていない
- 目標:誤嚥なく必要な栄養を摂取できる
- サービス内容:栄養士が嚥下食を調整
70.食欲不振
- 課題:食欲低下で食事量が少ない
- 目標:安全な嚥下で食欲を回復できる
- サービス内容:STと栄養士が連携して工夫
71.嚥下機能評価不足
- 課題:嚥下機能の評価が十分でない
- 目標:正確に評価して適切な対応を取れる
- サービス内容:STによるVF検査依頼
72.食事形態の見直し不足
- 課題:本人の嚥下機能に合っていない
- 目標:適切な形態に変更できる
- サービス内容:刻み食からソフト食に変更
73.家族の知識不足
- 課題:家族が誤嚥対策を知らない
- 目標:家族が正しい知識を持てる
- サービス内容:ケアマネが情報提供
74.排痰力低下
- 課題:痰を出せず誤嚥性肺炎を起こす
- 目標:呼吸リハで痰を喀出できる
- サービス内容:訪問看護で呼吸法を指導
75.呼吸機能低下
- 課題:呼吸が浅く誤嚥リスクが増大
- 目標:呼吸リハで肺活量を維持できる
- サービス内容:訪問リハが呼吸訓練を実施
76.就寝中の誤嚥
- 課題:夜間唾液誤嚥が多い
- 目標:就寝体位を工夫して防ぐ
- サービス内容:30度ギャッジアップで就寝
77.誤嚥後のケア不足
- 課題:誤嚥後の口腔ケアができていない
- 目標:誤嚥後に必ずケアを実施できる
- サービス内容:訪問介護で清掃
78.服薬形態が適さない
- 課題:薬が飲み込みにくい
- 目標:服薬形態を調整できる
- サービス内容:薬剤師と連携し粉薬に変更
79.唾液分泌低下
- 課題:口腔乾燥で誤嚥リスク増大
- 目標:唾液腺マッサージで改善
- サービス内容:訪問介護が実施
80.リハビリ未実施
- 課題:嚥下機能維持のリハが不足
- 目標:毎日継続できる
- サービス内容:STがプログラムを指導
81.一気食い
- 課題:急いで食べて誤嚥しやすい
- 目標:少量ずつ食べられる
- サービス内容:訪問介護で食事ペースを調整
82.口腔機能訓練未実施
- 課題:舌・唇の筋力が低下
- 目標:毎日訓練を実施できる
- サービス内容:STが舌体操を指導
83.姿勢補助具未使用
- 課題:椅子が合わず姿勢が崩れる
- 目標:姿勢補助具を活用できる
- サービス内容:OTが調整
84.嚥下訓練の継続困難
- 課題:継続できず効果が出ない
- 目標:毎日少しずつ実施できる
- サービス内容:訪問介護で声かけ
85.誤嚥性肺炎の再発予防
- 課題:繰り返し肺炎を発症
- 目標:再発を防ぐ
- サービス内容:口腔ケア徹底、嚥下訓練
86.食事中の注意不足
- 課題:会話しながら食べて誤嚥する
- 目標:集中して食事できる
- サービス内容:環境整備、声かけ
87.痰吸引体制不足
- 課題:痰が多く吸引体制が整っていない
- 目標:必要時に吸引できる
- サービス内容:訪問看護で吸引実施
88.看取り期の誤嚥リスク
- 課題:終末期で誤嚥が頻発
- 目標:苦痛なく過ごせる
- サービス内容:医師・訪問看護と連携しケア
89.誤嚥後の体位調整不足
- 課題:誤嚥後に横になる
- 目標:誤嚥時に適切な体位を取れる
- サービス内容:訪問看護が指導
90.食後のうがい不足
- 課題:食後に口腔残渣が多い
- 目標:必ずうがいを実施できる
- サービス内容:訪問介護で支援
91.発熱時の対応不足
- 課題:誤嚥後に発熱しても対応が遅れる
- 目標:すぐに医師へ相談できる
- サービス内容:訪問看護で観察と連携
92.抗菌薬使用の管理不足
- 課題:抗菌薬の服薬管理が不十分
- 目標:正しく内服できる
- サービス内容:訪問看護で服薬確認
93.家族の介助スキル不足
- 課題:家族が介助に慣れていない
- 目標:正しい介助方法を習得できる
- サービス内容:STと訪問看護が指導
94.経管栄養の誤嚥リスク
- 課題:経管栄養後に逆流しやすい
- 目標:安全に栄養投与できる
- サービス内容:訪問看護で体位指導
95.食事環境が不適切
- 課題:暗い・狭い環境で誤嚥が起きやすい
- 目標:明るく安全な環境で食事できる
- サービス内容:環境を整備
96.認知症による拒食
- 課題:食事を拒否して誤嚥しやすい
- 目標:少量でも安全に摂取できる
- サービス内容:本人の好みを取り入れ工夫
97.咽頭残留の多さ
- 課題:飲み込んでも食物が咽頭に残る
- 目標:残留を減らし誤嚥を防ぐ
- サービス内容:嚥下後に空嚥下を促す
98.咳嗽力低下
- 課題:咳が弱く誤嚥時に排出できない
- 目標:咳嗽力を高められる
- サービス内容:呼吸リハを導入
99.医療連携不足
- 課題:医師や歯科との連携不足でリスク管理が不十分
- 目標:医療と連携して誤嚥予防を行える
- サービス内容:ケアマネが連絡体制を整備
100.総合的な誤嚥予防
- 課題:誤嚥リスクが複合的に存在
- 目標:包括的に誤嚥性肺炎を予防できる
- サービス内容:口腔ケア・嚥下訓練・栄養調整を多職種で実施
まとめ
誤嚥性肺炎は、高齢者にとって非常に身近で重大なリスクです。
嚥下機能の低下、口腔内の不衛生、不適切な食事姿勢や食形態など、原因は多岐にわたります。ケアマネジャーは、誤嚥リスクを見極め、予防策を盛り込んだケアプランを立案することが重要です。
今回紹介した100事例は、口腔ケア・嚥下訓練・食事支援・環境調整・医療連携など、幅広い視点を網羅しています。
実際の利用者の状態に合わせて組み合わせ・修正しながら、日々のケアプラン作成にご活用ください。















