【ケアマネがコピペで使える】離床のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
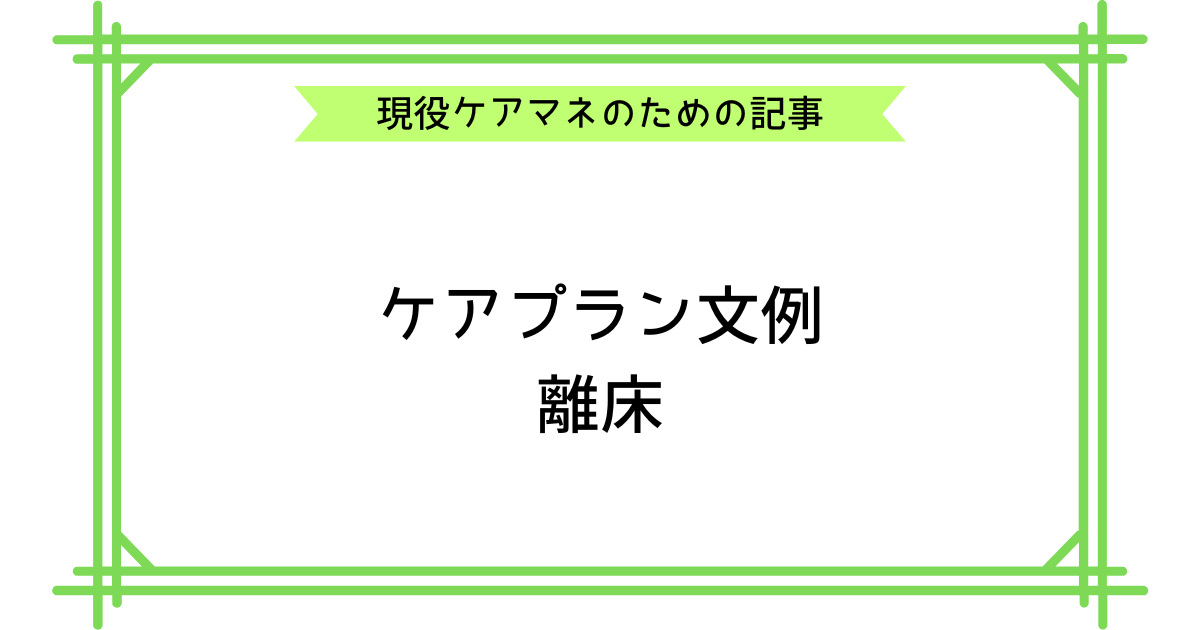
高齢者の生活において「離床」は非常に重要なテーマです。ベッド上での生活が長く続くと、筋力低下や褥瘡、廃用症候群を招きやすく、生活の質が低下してしまいます。そのため、ケアマネジャーは利用者が安全かつ意欲的に離床できるように、適切なケアプランを立てる必要があります。
本記事では、実際にケアプラン作成に役立つ「離床の文例」を100事例まとめました。
状況別に分類しているため、そのままコピー&ペーストして使えるだけでなく、利用者の状態に合わせたアレンジにも役立ちます。
目次
離床習慣の定着を目的とした文例
- 毎朝決まった時間に離床し、生活リズムを整える。
- 起床後はベッド上で安静にせず、椅子に移乗して朝食をとる習慣をつける。
- 昼食時は必ず食卓で座位をとり、離床機会を増やす。
- 昼寝はベッドではなくリクライニングチェアで行い、長時間臥床を避ける。
- 午前と午後にそれぞれ1回以上、ベッドから離れる時間を設ける。
- 季節ごとの生活行事に合わせて離床時間を確保し、生活意欲を高める。
- 家族訪問時には必ず居間に出て交流を図る。
- 毎日一定時間、テレビを居間で視聴し離床習慣をつける。
- 日課として新聞を居間で読む時間を設定し、ベッドから離れる習慣を持つ。
- ラジオ体操を行うことで自然に離床を促す。
- 食後の休憩はベッドではなく椅子で行うようにする。
- 孫や家族と交流する時間は必ず居間で過ごし、離床を促進する。
- デイサービス参加日の朝は早めに離床し、準備を整える。
- 医療職の訪問時は離床して対応する習慣を持つ。
- 訪問リハビリの前には必ず椅子に移乗して準備する。
- 自宅での趣味活動(編み物・書道等)を机で行い、自然に離床できるようにする。
- ペットの世話をする時間を設け、離床のきっかけとする。
- 来客があった際はベッドから起き上がり、リビングで応対する。
- 季節の変化に応じて庭やベランダに出る習慣をつける。
- 睡眠と覚醒のリズムを保つため、日中は積極的に離床時間を確保する。
身体機能維持・向上を目的とした文例
- 毎日一定時間、離床して歩行練習を行う。
- 車椅子に移乗し、居室内を自走する機会を設ける。
- ベッドから椅子への移乗動作を繰り返し練習し、下肢筋力を維持する。
- 離床時に上肢運動を取り入れ、筋力低下を予防する。
- デイサービスでの機能訓練に合わせ、在宅でも離床機会を増やす。
- 毎日10分以上の座位保持を行い、体幹の安定性を養う。
- 足こぎ車椅子を活用して、離床中の運動量を増やす。
- ベランダに出て太陽光を浴び、骨粗鬆症予防を図る。
- 起床後のストレッチを椅子に座って行い、柔軟性を維持する。
- 離床後に歩行器を用いた短距離歩行を習慣化する。
- 車椅子で屋外に出て、近隣を散歩する機会を設ける。
- 離床時間にセラバンドを活用し、筋力維持訓練を行う。
- 起立保持を数分間行い、立位耐久性を高める。
- 離床して掃除などの家事を取り入れ、活動性を高める。
- リハビリ用ペダル運動を離床時に実施する。
- 離床時間に体操DVDを利用して自主訓練を行う。
- 屋外でガーデニングを行い、自然な形で離床機会を作る。
- 季節の野菜を庭で収穫する作業を離床時間に取り入れる。
- 離床時間に座位で歌を歌い、呼吸機能を維持する。
- 機能訓練士の助言をもとに、自主トレーニングを離床時に実践する。
精神面・意欲向上を目的とした文例
- 離床時間に好きな音楽を聴き、気分転換を図る。
- 趣味活動をベッド外で行うことで生活意欲を高める。
- 離床時に家族と会話をする時間を設け、孤独感を軽減する。
- 孫と遊ぶ時間を居間で過ごし、自然に離床できる環境をつくる。
- 離床時間に塗り絵や折り紙を行い、楽しみながら活動量を増やす。
- テレビで好きなドラマを居間で視聴する習慣を持つ。
- 離床時にペットと触れ合い、気持ちの安定を図る。
- 家族と一緒にお茶を飲む時間を椅子で過ごすようにする。
- 離床して庭の花を眺め、リラックスできる時間を持つ。
- 離床時間に趣味の写真整理を行うことで楽しみを感じる。
- 季節ごとのイベント(節分・花見など)を離床して参加する。
- 離床時間にボードゲームを楽しみ、社会的交流を促す。
- 近隣住民との交流を居間で行い、社会参加を支援する。
- 離床時に電話やタブレットを使い、友人と交流する。
- 外出準備を離床の動機づけとして活用する。
- 離床して家族の食卓に加わり、食事を一緒に楽しむ。
- 離床して家族と映画鑑賞を行い、共有時間を増やす。
- 季節の行事(七夕・お盆・お正月)に合わせて離床機会を作る。
- 離床中に地域活動(自治会・集会所行事)に参加する。
- 離床を通じて「できることが増えた」と実感し、自信を回復する。
安全確保・転倒予防を目的とした文例
- 介助者と共に離床し、転倒リスクを最小限に抑える。
- 離床時に手すりを使用して安全に移動する。
- 車椅子への移乗時に介助を行い、事故を防ぐ。
- 離床時間は床に滑り止めマットを敷いて安全を確保する。
- 夜間の離床はセンサーライトを設置し、転倒を防止する。
- 離床時にポータブルトイレを利用し、移動距離を短縮する。
- 介助者の声かけでゆっくり離床する習慣を持つ。
- 離床直後にふらつきがないか確認し、転倒防止につなげる。
- ベッドからの立ち上がり時は歩行器を使用する。
- 離床の際に血圧測定を行い、体調を確認する。
- 急な起き上がりを避け、段階的に離床動作を行う。
- 離床時にサポートベルトを活用し、介助者の負担を軽減する。
- 安全に離床できるよう、介助者が常に見守りを行う。
- 離床後すぐに立ち上がらず、数分間座位を保持する。
- 転倒歴を踏まえて、離床時間は常に見守りを強化する。
- 離床時はナースコールを使用して介助を依頼する習慣をつける。
- 移動前に足元の障害物を取り除き、安全な離床環境を整える。
- 離床に合わせて福祉用具(スロープ・手すり)を適切に使用する。
- 離床時にはリハビリパンツを使用し、トイレ動作をスムーズにする。
- 転倒不安を軽減するため、安心できる介助体制で離床を支援する。
在宅生活継続・介護負担軽減を目的とした文例
- 離床習慣を確立し、自宅での生活継続を支援する。
- 離床時に自分でできる動作を増やし、介護負担を軽減する。
- 食事や排泄を離床して行うことで、介助量を減らす。
- 離床時間に自主的に水分補給を行い、介助依存を防ぐ。
- 離床をきっかけに身だしなみを整え、生活意欲を高める。
- ベッドから離れて生活する時間を増やし、介護時間を短縮する。
- 離床後に着替えを自立して行い、介護負担を減らす。
- 離床して排泄動作を行うことで、オムツ依存を軽減する。
- 離床時間に服薬を行い、服薬管理を容易にする。
- 離床時間を利用して訪問リハビリを受けやすくする。
- 離床習慣を持つことで、デイサービス利用時にスムーズに対応できる。
- 離床時間に入浴準備を行い、介助効率を高める。
- ベッド上生活からの移行を進め、在宅療養を継続できるようにする。
- 離床習慣を確立することで、介護者の精神的負担を軽減する。
- 離床時に家族と食事を共にすることで、介護意欲を支える。
- 離床時間を活用して、買い物や来客対応を自立して行えるようにする。
- 離床をきっかけに自宅内での役割(片付け・趣味活動)を担う。
- 離床機会を増やすことで、介助量を削減し家族の時間を確保する。
- 離床習慣を持ち続けることで、施設入所を先延ばしにする。
- 本人の希望を尊重し、離床を通じて「自分らしい生活」を継続できるようにする。
まとめ
離床は単なる「起き上がる動作」ではなく、生活リズムの維持、身体機能の保持、社会参加、介護負担軽減など多くの意味を持っています。
本記事で紹介した100の文例は、利用者の状態や目的に応じて活用できるように幅広く構成しました。
ケアマネジャーの皆さんは、そのままコピペしながらも必要に応じて修正し、利用者一人ひとりに合わせたケアプランに仕上げてください。















