【ケアマネがコピペで使える】糖尿病のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
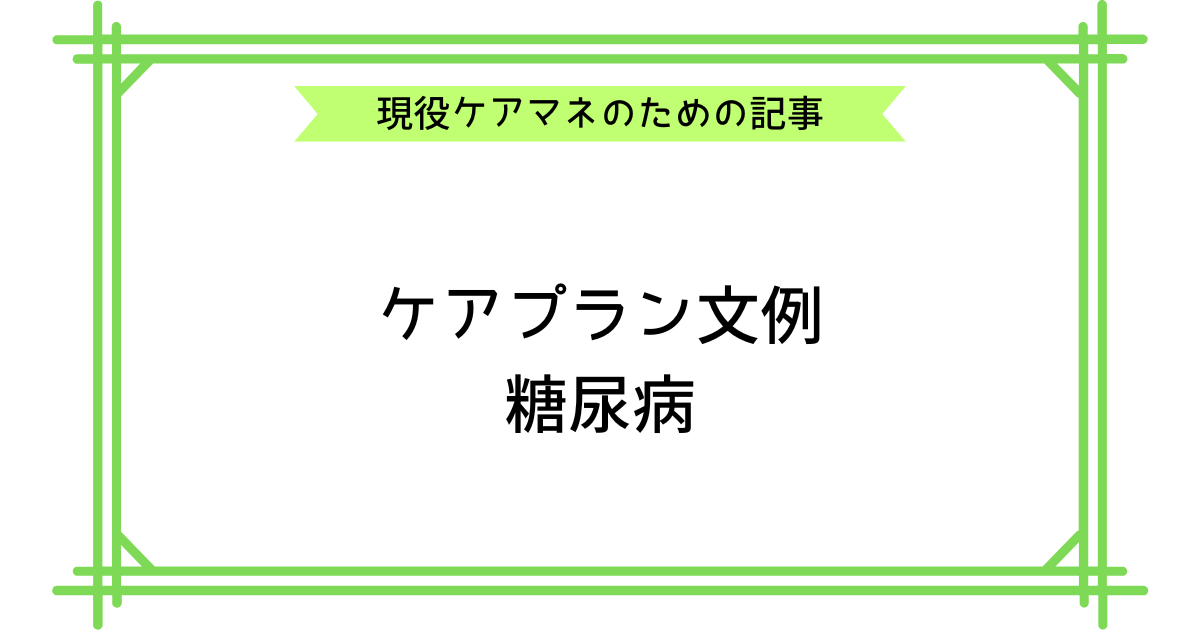
糖尿病は生活習慣と深く関わる慢性疾患であり、適切な自己管理が欠かせません。
食事・運動・服薬・血糖コントロールのいずれかが崩れると、合併症や入院リスクにつながります。
そのためケアマネジャーは、利用者が「自宅で安心して糖尿病管理を継続できるように支援するケアプラン」を作成する必要があります。
本記事では、糖尿病を抱える方の在宅生活支援に役立つケアプラン文例を 100事例 紹介します。
「食事管理」「服薬・インスリン管理」「運動・生活習慣」「体調管理・合併症予防」「家族支援・社会資源活用」の5つに分けていますので、そのままコピペするだけで活用でき、状況に応じてアレンジもしやすい構成になっています。
目次
食事管理に関する文例
- 管理栄養士の指導をもとに、糖尿病食を実践する。
- 塩分・糖分を控えた食事を継続し、血糖コントロールを図る。
- 家族と協力して、バランスの取れた食事を準備する。
- 食事時間を一定に保ち、血糖値の安定を目指す。
- 適正な摂取カロリーを守れるよう、食事量を調整する。
- 外食時にも糖尿病対応メニューを選べるよう支援する。
- 食後の高血糖を防ぐため、食事の栄養バランスを見直す。
- 血糖値の変動を抑えるため、間食を制限する。
- 甘味料や低糖食品を活用し、ストレスなく継続できる食事を心がける。
- 毎日の食事内容を記録し、振り返りに活かす。
- 家族に糖尿病食の調理方法を学んでもらい、協力体制を作る。
- 野菜を多く取り入れ、食物繊維を意識した食生活を送る。
- 食後は軽い運動を取り入れ、血糖値上昇を抑える。
- 季節の食材を取り入れ、食事を楽しみながら管理する。
- 食事療法への意欲を高めるため、定期的に成果を確認する。
- 水分は無糖の飲料を選び、糖分摂取を制限する。
- 血糖値コントロールに適した食器や計量器を活用する。
- 医師や栄養士と連携し、食事管理を継続できるようにする。
- 家族と一緒に健康的な食生活を楽しむことで、継続を図る。
- 血糖コントロールを優先した食事療法を習慣化する。
服薬・インスリン管理に関する文例
- 医師の指示通りに経口薬を服薬できるよう支援する。
- 服薬忘れを防ぐため、服薬カレンダーを使用する。
- 家族と連携し、服薬状況を毎日確認する。
- インスリン注射を自己管理できるよう、看護師が指導する。
- インスリン注射のタイミングを忘れないよう、生活リズムを整える。
- 注射部位の皮膚トラブルを予防するため、部位をローテーションする。
- 低血糖発作時の対応について、本人と家族が理解する。
- 血糖測定を習慣化し、服薬や注射管理に活かす。
- インスリン保存方法を理解し、適切に管理する。
- 薬の飲み忘れがあった際は、速やかに医師に相談する。
- 看護師の訪問時に服薬管理を確認し、継続できるようにする。
- 内服薬とインスリンの併用管理をサポートする。
- 服薬を確実に行うため、声かけやリマインダーを活用する。
- 家族がインスリン手技を理解し、見守りできるようにする。
- 医師の指示変更に応じて、服薬計画を見直す。
- インスリン注射の自己操作が困難な場合は、訪問看護を導入する。
- 血糖コントロールが乱れた場合は、服薬状況を確認する。
- 副作用や異常があれば速やかに医師へ報告する。
- 医療職と連携し、服薬管理の習慣化を支援する。
- インスリン・服薬管理を通じて、安定した在宅生活を継続する。
運動・生活習慣に関する文例
- 毎日30分程度のウォーキングを習慣化する。
- 医師の指示に基づき、無理のない運動を継続する。
- 日常生活に家事動作を取り入れ、活動量を増やす。
- 離床時間を増やし、廃用症候群を予防する。
- 筋力維持のため、簡単な体操を日課とする。
- 食後の軽い散歩を取り入れ、血糖コントロールを図る。
- 睡眠リズムを整え、生活習慣を安定させる。
- ストレス軽減のため、趣味や交流を継続する。
- 家族と一緒に運動し、楽しみながら継続できる環境を作る。
- 医師の指導を受け、運動強度を調整する。
- 在宅リハビリを活用し、身体機能を維持する。
- 外出の機会を増やし、活動量を確保する。
- 無理のない運動を継続し、生活習慣病予防を図る。
- 季節に応じた運動を取り入れ、生活意欲を高める。
- 水分補給を工夫しながら、運動を安全に行う。
- 着替えや身だしなみを整える習慣を持ち、生活リズムを保つ。
- 日中は活動的に過ごし、夜間の睡眠を促進する。
- 運動を生活習慣に組み込み、無理なく継続できるようにする。
- 家族と協力して運動計画を立てる。
- 運動習慣を通じて、血糖コントロールを安定させる。
体調管理・合併症予防に関する文例
- 血糖測定を定期的に行い、変化を記録する。
- 定期通院を欠かさず、医師の管理下で治療を継続する。
- 足病変の予防のため、毎日足の観察を行う。
- 爪切りや足の清潔保持を徹底し、感染を防ぐ。
- 視力低下に備え、定期的に眼科受診を行う。
- 神経障害の有無を確認し、生活上の安全を確保する。
- 高血圧・脂質異常の併存症管理を行う。
- 感染症予防のため、手洗いやマスクを徹底する。
- 体調変化があった際は、早めに医師へ報告する。
- 定期的な血液検査を受け、合併症の早期発見に努める。
- 低血糖時に備えてブドウ糖を常備する。
- 高血糖が続いた場合は、受診を検討する。
- 感染症流行期には外出を控え、体調維持を優先する。
- 体調に応じて介護サービスの利用時間を柔軟に調整する。
- 医師の治療方針を家族と共有し、体調管理に活かす。
- 合併症リスクに応じたケアを多職種で検討する。
- 定期的にバイタルチェックを行い、変化に早期対応する。
- インフルエンザワクチンなど予防接種を適切に受ける。
- 定期健診を継続し、早期発見・早期対応につなげる。
- 合併症予防を意識し、日常生活に工夫を取り入れる。
家族支援・社会資源活用に関する文例
- 家族に糖尿病管理の基礎知識を伝え、協力体制を作る。
- 家族と共に食事制限を実践し、支援体制を整える。
- 家族が服薬管理を見守れるようにする。
- 家族がインスリン手技を理解できるよう指導を受ける。
- 家族と一緒に血糖測定の記録を確認する。
- 医師や栄養士と家族が情報共有できるよう調整する。
- 介護サービスを組み合わせ、家族介護の負担を軽減する。
- ショートステイを活用し、家族の休養を確保する。
- 家族が安心して介護できるよう、医療職と連携を図る。
- ケアマネが調整役となり、家族の相談に応じる。
- 糖尿病患者会やサポートグループを紹介する。
- 医療費助成制度の利用について説明する。
- 訪問看護を導入し、在宅での療養を支援する。
- デイサービスを利用し、生活リズムを整える。
- 家族会議を通じて、支援体制を定期的に見直す。
- 多職種連携で在宅療養を支える仕組みを作る。
- 家族が糖尿病に対して不安を抱かないよう、相談体制を整える。
- 医療・介護サービスの併用で、在宅生活を継続する。
- 社会資源を活用し、経済的負担を軽減する。
- 家族と本人が安心して生活できるよう、ケアチームで支援する。
まとめ
糖尿病のケアプランは、食事・服薬・運動・体調管理・家族支援といった多方面に配慮する必要があります。
今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーが実際のプラン作成でそのままコピペして使えるよう整理しました。
利用者一人ひとりの生活背景や医師の治療方針に合わせ、文例を組み合わせて活用してください。
ケアマネが的確な支援を行うことで、利用者の血糖コントロールや生活の質が大きく向上します。















