【ケアマネがコピペで使える】高次脳機能障害のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
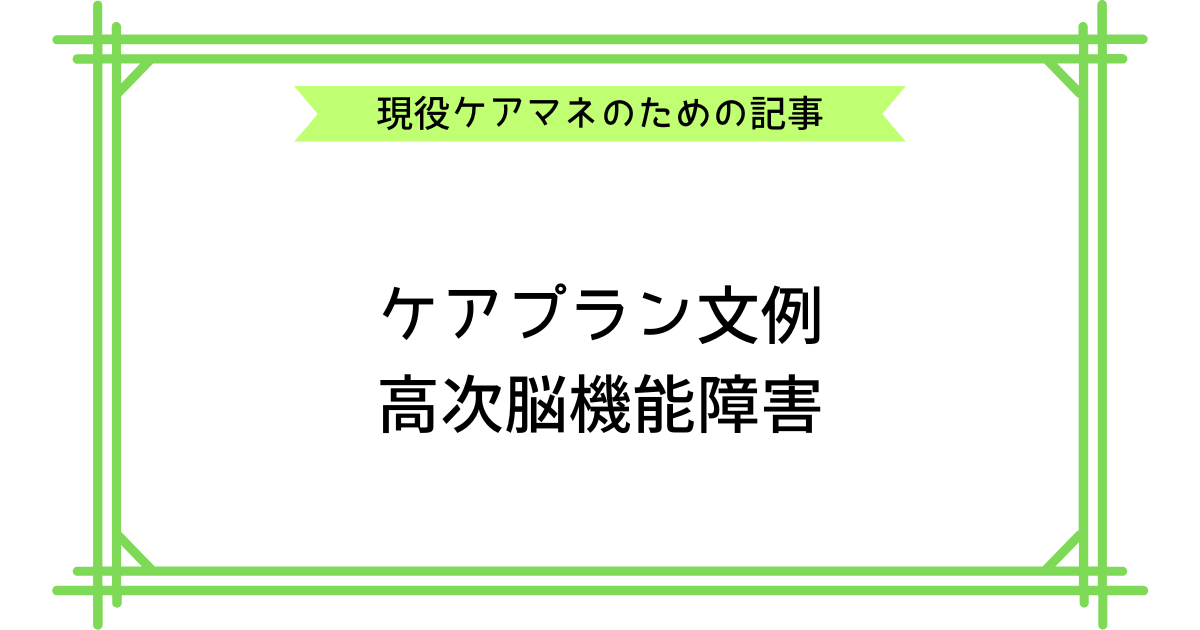
高次脳機能障害は、交通事故・脳梗塞・脳出血などによる脳損傷の後に起こることが多く、記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害など、多岐にわたる症状が現れます。身体機能が回復していても、認知や行動の障害によって日常生活や社会生活に大きな支障をきたすため、介護・福祉・医療の連携が重要です。
ケアマネジャーは、利用者本人の自立支援だけでなく、家族支援や社会資源の活用も含めた包括的なケアプランを作成する必要があります。
本記事では、現場ですぐに活用できる「高次脳機能障害のケアプラン文例」を 100事例 紹介します。目的別に分類していますので、そのままコピー&ペーストして使えるだけでなく、利用者の状態に応じてアレンジしやすい構成となっています。
目次
記憶障害への支援に関する文例
- 日課をホワイトボードに書き出し、視覚的に確認できるようにする。
- 毎朝予定を家族と一緒に確認し、記憶を補完する。
- スマートフォンやメモ帳を活用して予定を記録する習慣を持つ。
- 薬の飲み忘れ防止のため、服薬カレンダーを使用する。
- 買い物リストを作成し、忘れ物を防止する。
- デイサービス利用日をカレンダーに書き込み、視覚的に覚える。
- 予定を繰り返し声かけし、記憶を補助する。
- 写真や絵を用いた手順表を作成し、動作を思い出せるようにする。
- 通院日を家族と一緒に確認し、受診忘れを防ぐ。
- 食事や排泄などの生活リズムを固定し、習慣化で記憶を補う。
- 服薬支援アプリを導入し、服薬忘れを減らす。
- 家族が毎日一度予定を確認し、記憶障害を補助する。
- メモリーノートを持ち歩き、記録する習慣を持つ。
- 日課を繰り返すことで、記憶定着を促す。
- 約束事は必ずメモを残し、確認する習慣をつける。
- 電話対応時には内容を紙に書き残す。
- 重要事項は掲示板に貼り、本人と家族が共有する。
- 日記を書く習慣を持ち、生活を振り返りやすくする。
- 視覚的に理解できるよう、色分けしたメモを使用する。
- 記憶障害に合わせ、繰り返し説明を行い安心感を与える。
注意障害への支援に関する文例
- 作業は一度に複数行わず、一つずつ区切って行う。
- 集中できる時間を短く設定し、休憩を挟む。
- 騒音やテレビを消し、静かな環境で作業する。
- 食事中は会話を控え、注意を食事に集中できるようにする。
- 外出時は付き添いをつけ、安全に行動できるようにする。
- 複雑な作業は職員や家族が補助する。
- 注意が散漫になった際には、声かけで切り替えを行う。
- 家事動作は短時間に区切り、完遂を促す。
- デイサービスでは静かな席に案内する。
- 運転など危険を伴う行為は控える。
- 説明は短く明確に行う。
- 注意力が低下しやすいため、誤飲や火の取り扱いを避ける。
- 危険物や刃物は本人の手の届かない場所に置く。
- 転倒リスクを減らすため、動線上の障害物を取り除く。
- 買い物や金銭管理は家族が同行する。
- 複数の予定を同日に入れず、一つに絞る。
- 課題を小分けにし、達成感を得られるようにする。
- 注意障害による事故を防ぐため、火気使用を制限する。
- 課題終了後には必ず確認作業を行う。
- 本人の集中力に応じて、活動内容を調整する。
遂行機能障害への支援に関する文例
- 家事は手順書に従って行い、段階的に支援する。
- 料理は簡単な作業に分けて実施する。
- 洗濯は家族が下準備を行い、本人は干す作業のみ行う。
- ゴミ出しを決まった時間に行い、習慣化する。
- 課題を小さなステップに分け、達成感を持たせる。
- 本人に合わせ、家事の一部を担当できるよう調整する。
- 作業開始時には声かけを行い、実行を促す。
- 予定をリスト化し、順番に取り組めるよう支援する。
- 一つの作業を終えてから次の作業に移るよう促す。
- デイケアでの活動を通じて遂行機能の訓練を行う。
- 買い物リストを作り、必要な物を選べるよう支援する。
- 課題を実行できた際は肯定的にフィードバックする。
- 予定表を活用し、活動の見通しを持たせる。
- 課題をやり遂げた達成感を日記に残す。
- 家族と役割分担し、簡単な作業を本人に任せる。
- 洗濯や片付けなどの家事を、毎日繰り返し練習する。
- 遂行機能障害に応じて、活動を短時間で完了できるよう調整する。
- 本人が混乱した際には、再度手順を説明する。
- 作業手順をイラストや写真で提示する。
- 遂行機能を補うため、介助者が最初と最後を確認する。
社会的行動障害への支援に関する文例
- 感情の起伏が激しい場合は、落ち着ける環境を整える。
- 衝動的な発言に対しては否定せず、受け止めて対応する。
- 社会的ルールを繰り返し伝え、行動の安定を図る。
- 集団活動に参加する際は、少人数から始める。
- デイサービス職員が仲介し、交流を支援する。
- 周囲とのトラブルが起きた際は、速やかに介入する。
- 社会的行動障害を理解した家族や職員が支援する。
- 暴言や拒否があった場合も冷静に対応する。
- 本人が安心できる人間関係を維持する。
- 他者との会話は短時間で行う。
- トラブルが起きた場合、振り返りを一緒に行う。
- 余暇活動を通じて社会的行動を練習する。
- 本人に合った役割を与え、達成感を得られるようにする。
- デイサービスでの行動観察を行い、計画に反映する。
- 環境を整備し、刺激を減らして落ち着いて過ごせるようにする。
- 社会性を高めるため、家族との交流を意識する。
- 問題行動が生じた際は原因を分析し、対応を検討する。
- 周囲に障害特性を説明し、理解を深めてもらう。
- 本人の感情を尊重し、無理のない社会参加を支援する。
- 社会的行動障害に配慮し、本人が安心して過ごせる場を提供する。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に高次脳機能障害の特徴を理解してもらう。
- 家族に対応方法を説明し、安心して介護できるよう支援する。
- 家族会議を開き、役割分担を確認する。
- 家族に心理的サポートを行い、介護負担を軽減する。
- 介護疲れを防ぐため、ショートステイを活用する。
- 外部サービスを導入し、家族介護の負担を減らす。
- 家族に記録方法を伝え、行動変化を把握できるようにする。
- 家族の不安に応じて、多職種連携でサポートする。
- 環境を整理整頓し、混乱を防ぐ。
- 危険物を片付け、安全な環境を整える。
- 予定表や掲示物を見やすい場所に設置する。
- 生活リズムを家族と共有し、一貫性を持たせる。
- 家族に相談窓口を紹介する。
- 医師・看護師・リハ職と連携し、家族への説明を行う。
- 家族が安心できるよう、緊急連絡体制を整える。
- 環境調整を繰り返し行い、本人に合った生活環境を作る。
- 地域資源を活用し、家族の負担を軽減する。
- 本人と家族が共に安心して過ごせる環境を整える。
- 家族の介護負担を定期的に確認し、支援計画を見直す。
- 本人と家族の生活の質を高めることを目標に、ケアプランを実施する。
まとめ
高次脳機能障害は、身体的な障害が軽度でも日常生活に大きな影響を与えます。そのため、ケアプランには 記憶障害・注意障害・遂行機能障害・社会的行動障害・家族支援 といった幅広い観点が必要です。
本記事で紹介した100の文例は、ケアマネジャーが実際のプラン作成にそのまま活用できる形式になっています。利用者の障害特性や生活背景に合わせて組み合わせることで、より実効性の高いケアプランを作成することが可能です。















