【ケアマネがコピペで使える】心疾患のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
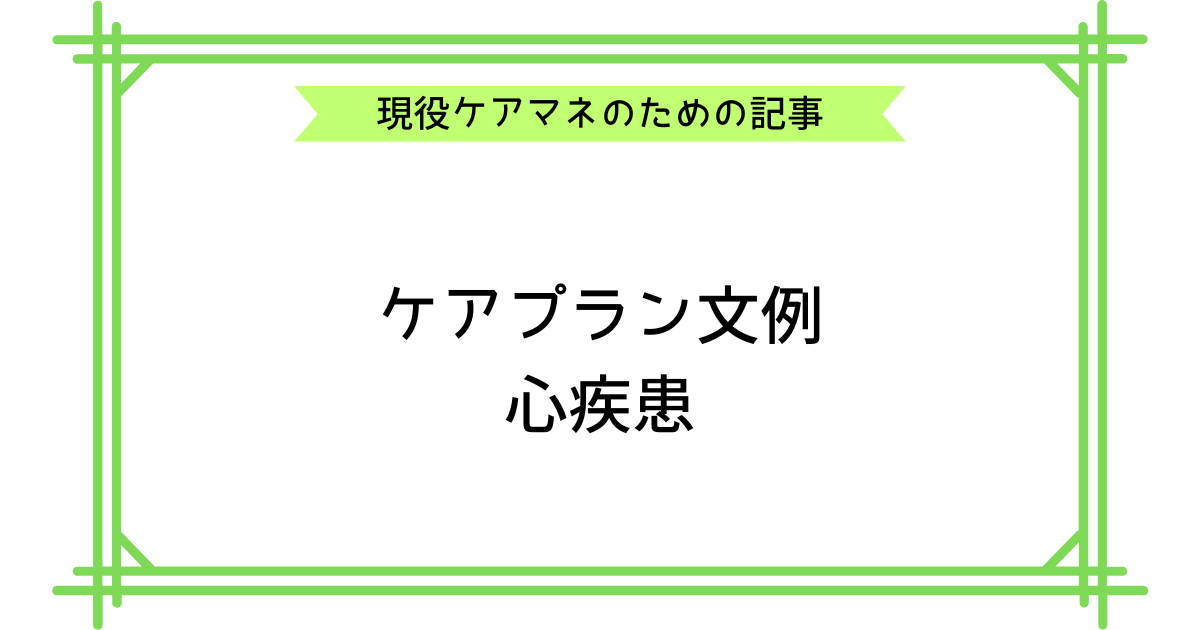
心疾患(心不全・心筋梗塞・狭心症・不整脈など)は、高齢者の在宅生活において頻繁に見られる病態です。
症状が安定していても急変リスクが高く、生活全般に細やかな支援が必要となります。
ケアマネジャーは、 症状の観察・服薬管理・生活習慣の調整・家族支援 をバランスよく盛り込んだケアプランを立てることが重要です。
本記事では、心疾患を持つ方へのケアプラン文例を 100事例 紹介します。分類ごとにまとめていますので、コピー&ペーストして活用しやすく、利用者の状態に合わせたアレンジも容易です。
目次
症状管理に関する文例
- 毎日の血圧・脈拍測定を習慣化し、記録する。
- 体重を毎日測定し、心不全の兆候を早期に発見する。
- 呼吸苦が出現した場合は安静を保ち、医師へ報告する。
- 浮腫の有無を観察し、変化があれば記録する。
- 労作時の息切れを確認し、活動量を調整する。
- 夜間の呼吸困難がないか観察する。
- 胸痛が出現した場合はすぐに医師に連絡する。
- 脈の不整を感じたら、家族が医師へ報告する。
- 急激な体重増加があれば受診を促す。
- 倦怠感が強い場合は活動を控え、休養を優先する。
- 咳や痰の増加を確認し、呼吸状態の悪化に注意する。
- 服薬後の副作用や異常を観察する。
- 発作時に対応できるよう、救急搬送体制を確認する。
- バイタル測定結果を訪問看護師と共有する。
- 血圧が高値の時は塩分摂取状況を確認する。
- 医師の診察時に症状を正確に伝えられるよう記録を整理する。
- 自覚症状を本人に聞き取り、日誌に残す。
- 心不全の増悪兆候を家族と共有する。
- 動悸が続いた場合は早めの受診につなげる。
- 症状の観察を通じて、安定した生活を継続できるよう支援する。
日常生活支援に関する文例
- 活動と休養のバランスを取り、無理のない生活を行う。
- 睡眠環境を整え、夜間の安眠を促す。
- 階段昇降は家族が付き添い、安全を確保する。
- 入浴は短時間とし、体調に応じて清拭に切り替える。
- 更衣動作は休憩を挟みながら行う。
- 排泄時のいきみを避けるよう配慮する。
- 栄養バランスを考慮し、心疾患に適した食事を提供する。
- 食塩制限を意識した調理を行う。
- 水分制限を守れるよう、家族と協力する。
- 食事は少量頻回とし、胃部への負担を軽減する。
- 安静を保てるよう、ベッド周囲を整備する。
- 転倒防止のため、動線上の障害物を整理する。
- 室温を一定に保ち、体調悪化を防ぐ。
- 家事の負担を軽減するため、訪問介護を利用する。
- 外出は体調に応じて短時間にとどめる。
- 呼吸苦が強い場合は体位を工夫し、安楽な姿勢をとる。
- 疲労をためないよう、活動スケジュールを調整する。
- 食事内容を日誌に記録し、栄養士と共有する。
- 家族と協力して減塩レシピを工夫する。
- 日常生活の支援を通じて、安定した在宅生活を維持する。
服薬・通院支援に関する文例
- 医師の指示通りに服薬を継続する。
- 服薬カレンダーを使用し、飲み忘れを防ぐ。
- 家族が服薬状況を毎日確認する。
- 通院日をカレンダーに記録し、受診忘れを防ぐ。
- 通院には家族が付き添い、診察内容を共有する。
- 医師の説明を家族と一緒に聞き、理解を深める。
- 服薬後に体調変化があれば、速やかに報告する。
- 内服薬の残量を確認し、切らさないようにする。
- 服薬と食事のタイミングを整える。
- 複数の薬を飲む際は、薬剤師の指導を受ける。
- 訪問看護師が服薬確認を行う。
- 家族と連携し、服薬を習慣化する。
- 通院前に症状やバイタルを整理して持参する。
- 医師の指示変更があれば、すぐに共有する。
- 医療職と連携し、服薬の副作用に対応する。
- 受診後の指示を家族と確認し、生活に反映する。
- 医師の指示に従い、予防的薬を継続する。
- 通院が困難な場合は、訪問診療を検討する。
- 服薬支援を通じて、再発予防につなげる。
- 医療連携を強化し、継続的に治療を行う。
再発予防・生活習慣改善に関する文例
- 禁煙を継続し、心疾患の悪化を防ぐ。
- 飲酒を控え、心臓への負担を軽減する。
- 適正体重を維持できるよう支援する。
- 栄養士と連携し、心疾患に適した食事を継続する。
- 水分・塩分制限を守れるよう、記録をつける。
- 運動療法を医師の指示に基づき実施する。
- 軽い運動を日課に取り入れる。
- 無理のない範囲でウォーキングを行う。
- 睡眠時間を十分に確保する。
- ストレスを減らすため、趣味や交流を取り入れる。
- 過労を避け、休養を優先する。
- 季節ごとの体調変化に注意する。
- 高血圧や糖尿病の併存症管理を徹底する。
- 定期健診を継続し、再発予防につなげる。
- 水分管理を本人と家族が一緒に行う。
- 毎日の体調変化を記録する。
- 食事・運動・服薬を総合的に管理する。
- 健康意識を高めるため、情報をわかりやすく提供する。
- 本人に合った生活習慣改善を継続する。
- 再発予防を意識した生活全体を支援する。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に心疾患の特徴を説明し、理解を深める。
- 家族と一緒に血圧・体重測定を行う。
- 家族に服薬の重要性を説明する。
- 家族会議を開き、介護方針を共有する。
- 緊急時の対応方法を家族に伝える。
- 家族の介護負担を軽減するため、訪問介護を導入する。
- 家族の疲労を考慮し、ショートステイを利用する。
- 家族が安心して介護できるよう、医療職と連携する。
- 家族に日常生活上の注意点を説明する。
- 家族に水分・塩分制限の工夫を伝える。
- 室温・湿度を適切に保つよう家族と共有する。
- 寝室を静かで安定した環境に整える。
- 手すりを設置し、転倒リスクを減らす。
- 家族に体調変化のサインを学んでもらう。
- 家族が安心できるよう、定期的に相談時間を設ける。
- 多職種と連携し、家族の不安を軽減する。
- 家族に介護知識を提供し、安心して支援できる体制を作る。
- 緊急連絡体制を整備し、家族と共有する。
- 家族支援を通じて、在宅生活の継続を可能にする。
- 本人と家族が安心して暮らせるよう、包括的に支援する。
まとめ
心疾患のケアプランでは、 症状観察・服薬管理・生活支援・再発予防・家族支援 の観点をバランスよく取り入れることが大切です。今回紹介した100の文例は、ケアマネジャーが実際のケアプラン作成にそのままコピペして使えるよう整理しました。
利用者と家族の状況に応じて文例を組み合わせることで、安心して在宅生活を継続できるケアプランを立てることが可能です。















