【ケアマネがコピペで使える】脊髄小脳変性症のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
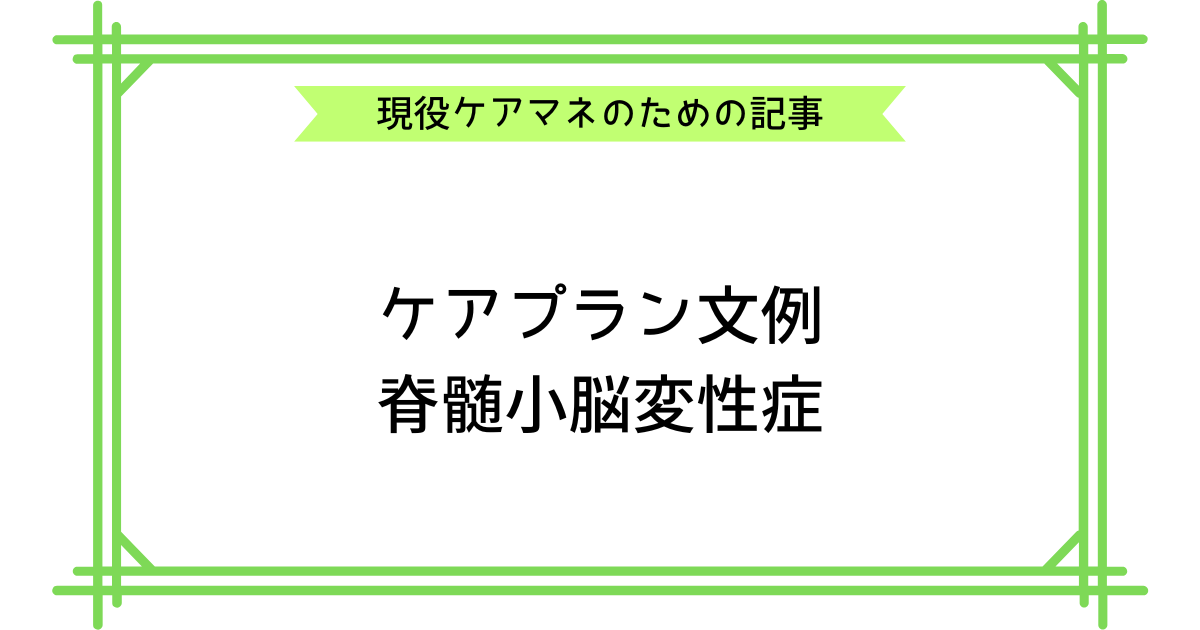
脊髄小脳変性症は進行性の神経難病で、運動失調や歩行障害、言語障害、嚥下障害など多岐にわたる症状が見られます。進行に伴い、自立生活が難しくなりやすく、介護・リハビリ・医療の多職種連携が欠かせません。
ケアマネジャーは、運動機能の維持、生活動作の工夫、コミュニケーションや嚥下支援、家族の介護負担軽減を意識したケアプランを立案する必要があります。
本記事では、脊髄小脳変性症を持つ方へのケアプラン文例を 100事例 紹介します。コピー&ペーストで使えるように整理しましたので、現場ですぐ活用できます。
目次
運動機能支援に関する文例
- 理学療法士の指導に基づき、歩行訓練を継続する。
- 転倒防止のため、歩行器や杖を活用する。
- バランス訓練を日課とし、運動失調の進行を遅らせる。
- 下肢筋力を維持するため、ストレッチを行う。
- 上肢協調運動を取り入れ、巧緻性を高める。
- 座位保持練習を通じて体幹の安定性を確保する。
- デイケアでのリハビリに参加し、体力維持を図る。
- 移乗動作の訓練を行い、自立度を高める。
- 電動車椅子を導入し、移動範囲を広げる。
- 在宅リハビリを取り入れ、運動習慣を継続する。
- 運動後に疲労が強い場合は休養を優先する。
- 体幹強化体操を行い、姿勢保持を支援する。
- 歩行補助具の調整を定期的に行う。
- 立ち上がり訓練を継続し、自立動作を支援する。
- リハビリを通じて生活動作への意欲を高める。
- 運動機能の変化を記録し、計画に反映する。
- 介助量を調整しながら、自立度を尊重する。
- 運動に取り組む時間を固定し、習慣化を図る。
- 疲労が強い日は介助を増やし、無理のない範囲で活動する。
- 安全を最優先にし、転倒リスクを減らしたリハビリを行う。
日常生活動作の工夫に関する文例
- 食事動作を補助し、自助具を活用して自立を支援する。
- 入浴は介助と福祉用具を組み合わせ、安全に行う。
- 排泄動作にポータブルトイレを活用し、移動負担を減らす。
- ベッドからの起き上がりを支援する。
- 衣類は着脱しやすいものを選ぶ。
- キッチンでの家事は椅子を用いて行えるようにする。
- 歯磨きや洗顔は座位で行い、転倒を防ぐ。
- 移動経路を整理し、つまずきやすい物を取り除く。
- 浴室に手すりを設置し、安全性を確保する。
- 生活動作を小分けに行い、疲労を減らす。
- 室内に段差解消スロープを設置する。
- ベッド周囲を整理整頓し、起居動作を安全に行う。
- 介助を受けながらも本人の自立部分を尊重する。
- トイレへの動線を短縮し、排泄の自立を支援する。
- 食事は姿勢を安定させ、誤嚥を防ぐ。
- 清潔保持を目的に、定期的な清拭を行う。
- 就寝環境を整え、夜間の移動を安全にする。
- 座位での作業を増やし、生活意欲を維持する。
- 在宅生活を快適に続けられるよう生活動線を見直す。
- 活動量を調整し、体力に合わせた日課を作る。
言語・嚥下支援に関する文例
- 言語療法士の指導を受け、発声訓練を行う。
- ゆっくりと発話できるよう、会話環境を整える。
- 家族が口元を見て会話することで理解を助ける。
- コミュニケーションボードを導入する。
- スマートフォンやタブレットを使い文字で意思疎通を行う。
- 嚥下訓練を継続し、誤嚥を予防する。
- 食事形態をペースト食やソフト食に調整する。
- 水分はトロミをつけて提供する。
- 食事中は姿勢を整え、誤嚥を防止する。
- 食後は30分間座位を保つ。
- 咳やむせ込みが続く場合は医師に報告する。
- 嚥下機能の変化を定期的に評価する。
- 必要に応じて胃瘻造設について説明を受ける。
- 言語療法士のアドバイスを家族と共有する。
- 会話時は静かな環境を選び、聞き取りやすくする。
- 声が出にくい場合は筆談を併用する。
- 食事に時間を十分に取り、焦らず摂取できるよう支援する。
- 嚥下体操を日課とする。
- 飲み込みに注意し、少量ずつ摂取する。
- コミュニケーション手段を複数確保し、孤立を防ぐ。
心理・社会参加支援に関する文例
- 趣味活動を継続し、生活意欲を維持する。
- デイサービスに参加し、社会的交流を持つ。
- 孫や家族との時間を増やし、孤立を防ぐ。
- 気分の落ち込みに対して傾聴を行う。
- 不安を和らげるため、カウンセリングを導入する。
- 外出の機会を作り、生活に変化を与える。
- 季節の行事に参加できるよう支援する。
- 本人の意思を尊重し、生活の選択権を大切にする。
- 気分転換に音楽や読書を取り入れる。
- 同じ疾患を持つ人との交流機会を作る。
- 家族と一緒に旅行や外出を計画する。
- デイケアでの活動を通じて役割を担う。
- ストレスを軽減できるよう、生活環境を整える。
- 笑顔で接する時間を増やし、安心感を与える。
- 利用者が望む活動を可能な範囲で実現する。
- 季節ごとのイベントに合わせた活動を計画する。
- 日記や記録をつけ、生活の振り返りを行う。
- 家族や友人と電話やビデオ通話で交流する。
- 精神的支援を通じて、不安感を軽減する。
- 社会参加を通じて、QOLを向上させる。
家族支援・環境整備に関する文例
- 家族に脊髄小脳変性症の特徴を説明する。
- 家族が介助方法を学び、安心して介護できるようにする。
- 家族会議を開き、介護体制を共有する。
- 介護負担を軽減するため、訪問介護を導入する。
- ショートステイを活用し、家族の休養を確保する。
- 家族にリハビリ方法を説明し、家庭で実践できるよう支援する。
- 緊急時の対応方法を家族と共有する。
- 家族の心理的負担を軽減するため、相談に応じる。
- 家族の介護疲れを見える化し、外部サービスを導入する。
- 住宅改修を行い、バリアフリー環境を整備する。
- 室内に手すりを設置し、安全に移動できるようにする。
- 浴室やトイレの環境を整え、介助しやすい空間にする。
- ベッドや車椅子を適切に調整する。
- 移動スペースを確保し、事故を防ぐ。
- 照明を明るくし、転倒リスクを減らす。
- 福祉用具のレンタルを活用する。
- 家族が相談できる窓口を紹介する。
- 医療・介護サービスを組み合わせ、在宅生活を継続する。
- 家族支援を通じて、介護負担を軽減する。
- 本人と家族が安心して暮らせるよう、包括的に支援する。
まとめ
脊髄小脳変性症は進行性で治療が難しい疾患ですが、ケアマネジャーが 運動機能支援・生活動作工夫・嚥下と言語の支援・心理ケア・家族支援 をバランスよく取り入れたプランを立てることで、利用者の生活の質を大きく高めることが可能です。
今回紹介した100の文例は、現場でそのまま活用できる形式に整理しました。利用者の状態や希望に合わせて組み合わせ、実効性の高いケアプランを作成してください。















