【コピペOK】要介護3のケアプラン文例を100事例紹介
当ページのリンクには広告が含まれています。
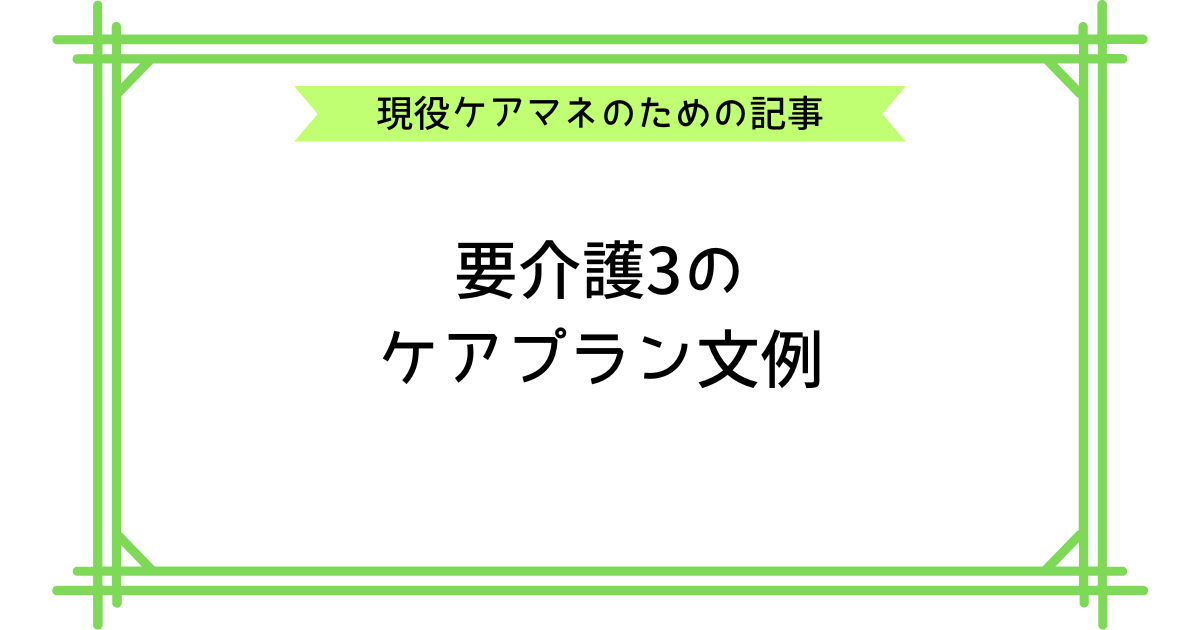
要介護3は、日常生活全般に中度の介助が必要な状態を指します。
歩行や排泄、入浴、食事といった基本的な生活動作の多くに支援が求められるほか、認知症を併発している場合も少なくありません。
ケアマネジャーがプランを作成する際、利用者ごとに異なる生活背景や身体状況に合わせて計画を立てる必要があります。
そこで本記事では、要介護3の利用者に対応したケアプラン文例を100事例 用意しました。
カテゴリ別に整理し、コピペして使える形で紹介します。現場でのケアプラン作成や新人ケアマネジャーの参考資料として活用してください。
目次
要介護3のケアプラン文例
移動・歩行支援
- 室内での移動が不安定で転倒リスクが高いため、歩行器を導入し、介助と見守りを組み合わせながら安全に歩行できるよう支援する。
- 廊下やトイレまでの移動に時間を要するため、手すりを設置し、転倒を防止しながら自立的な移動を促す。
- 外出時には車椅子を使用し、介助者と共に安全に移動できるよう支援することで、社会参加の機会を維持する。
- ベッドからの起き上がり時にふらつきが見られるため、介助を行い、安定した動作で立ち上がれるよう支援する。
- 屋外歩行は困難であるが、屋内では伝い歩きが可能であるため、家具の配置を工夫して安全に移動できる環境を整備する。
- 段差昇降が困難であるため、スロープを設置し、介助により安全に通行できるように支援する。
- 車椅子からベッドや椅子への移乗が不安定であるため、介助方法を統一し、安心して移乗できるように支援する。
- 夜間のトイレ移動で転倒の危険があるため、動線に夜間照明を設置し、安全を確保する。
- 移動中に疲労が強いため、こまめに休憩をとりながら、体力に応じて活動できるよう支援する。
- 屋内外での転倒リスクを軽減するため、段差やカーペットの巻き込みを排除し、環境を整える。
- 狭い場所での方向転換が困難なため、車椅子を使用する場面では広さを確保し、安全な移動を行えるように支援する。
- 移動に時間がかかるため、訪問介護時にスケジュールを調整し、無理なく行動できるよう配慮する。
- トイレや食堂など生活の主要な動線に重点的に手すりを設置し、自立的な移動を促す。
- ベッドサイドに立ち上がり補助具を設置し、起立動作をスムーズにできるよう支援する。
- 歩行器使用時に姿勢が前傾しやすいため、体幹を支える補助を行い、安全性を確保する。
- 歩行練習を日課に取り入れ、体力や筋力を維持できるように支援する。
- 車椅子での生活が中心となっているため、段差解消とスロープ設置により生活範囲を拡大する。
- 通院時は送迎サービスを利用し、安全に病院へ通えるよう支援する。
- 転倒後の恐怖心が強いため、安心感を与える声かけを行い、自信を持って歩行できるよう支援する。
- 季節の変化や体調に合わせて歩行距離を調整し、無理なく活動を継続できるようにする。
排泄支援
- トイレまでの移動が不安定なため、定時のトイレ誘導を行い、失禁を予防する。
- 夜間の排泄はポータブルトイレを使用し、転倒防止と安心した排泄を支援する。
- 尿意の訴えが弱いため、時間を決めて声かけを行い、排泄リズムを整える。
- 排泄後の処理に時間を要するため、介助を行い清潔を保持できるように支援する。
- 下着や衣類の着脱が困難であるため、前開きタイプを使用し、排泄動作を簡便化する。
- 便秘がちであるため、水分摂取や排便習慣を整える支援を行う。
- トイレ内での姿勢保持が困難であるため、手すりを設置して安全な動作を確保する。
- 排泄に不安を感じているため、安心できるようにプライバシーを尊重しながら介助を行う。
- 夜間の頻尿に対応するため、ベッド近くにポータブルトイレを設置し、転倒リスクを減らす。
- オムツ使用時も定期的に交換し、皮膚トラブルが発生しないように支援する。
- 下痢や軟便の際にはこまめに排泄介助を行い、清潔保持を徹底する。
- 排尿のコントロールが難しいため、失禁パッドを適切に使用し、生活の安心を支える。
- 膀胱留置カテーテルを使用しているため、感染予防に配慮し、衛生的な管理を行う。
- 排泄の失敗で羞恥心を持たないよう、否定せず受容的に対応する。
- トイレへの移動に時間がかかるため、早めの声かけを行い、余裕を持って排泄行動ができるように支援する。
- 便秘解消のため、食事や運動を取り入れ、自然な排便が促されるよう支援する。
- 排泄中の転倒を防ぐため、トイレ内に緊急コールを設置し、安心して利用できる環境を整える。
- 排泄後の手洗い動作をサポートし、清潔保持を徹底する。
- 下衣の操作が困難なため、簡易的な衣服を準備し、排泄を自立的に行えるようにする。
- 家族と協力し、夜間排泄時のサポート体制を整え、介護者の負担軽減を図る。
入浴・清潔保持
- 入浴時に立位保持が不安定なため、介助を行い、転倒防止に配慮しながら清潔保持を支援する。
- 浴槽への出入りが困難であるため、シャワーチェアを使用し、安全に全身を洗えるよう支援する。
- 入浴が難しい日には清拭を行い、皮膚の清潔を維持できるようにする。
- 皮膚の乾燥が強く見られるため、入浴後に保湿剤を使用し、スキンケアを徹底する。
- 浴室での転倒リスクがあるため、滑り止めマットを設置し、安全な環境を整備する。
- 入浴への意欲が低下しているため、本人の好みを尊重しながら声かけを行い、入浴習慣を維持する。
- 長時間の入浴が困難なため、短時間で効率的に清潔保持ができるように介助を工夫する。
- 浴室の温度差によるヒートショックを予防するため、入浴前に浴室を暖めておく。
- 入浴時に衣服の着脱が難しいため、介助を行い、安心して入浴できるよう支援する。
- 髪や頭皮の汚れが目立つため、週数回は洗髪を実施し、爽快感を得られるよう支援する。
- 爪切りや整髪など身だしなみを整え、清潔感を維持できるよう支援する。
- 入浴後に疲労感が強い場合は、ベッドで十分な休養をとれるよう配慮する。
- 入浴中の会話や交流を通じてリラックス効果を高め、生活の楽しみを感じられるよう支援する。
- 入浴拒否が見られる際は無理に促さず、足浴や部分清拭から取り入れ、徐々に習慣化を図る。
- 皮膚疾患の治療中であるため、医師の指示に基づいて洗浄方法を工夫し、悪化を予防する。
- 入浴後に衣服をすぐに着用できるよう、着替えを事前に準備し、動作の負担を軽減する。
- 水分摂取を入浴前後に促し、脱水予防を行う。
- 入浴中の表情や体調変化を観察し、異常があればすぐに対応できるようにする。
- 季節に応じて入浴頻度を調整し、本人が快適に過ごせるよう支援する。
- 入浴や清潔保持を通じて自己肯定感を高め、生活の質を維持できるよう支援する。
食事・栄養
- 咀嚼力が低下しているため、やわらかい食事形態を準備し、自立的に食事を摂取できるよう支援する。
- 誤嚥のリスクがあるため、食事中は座位保持を徹底し、見守りを行う。
- 食欲が低下しているため、栄養補助食品を取り入れ、必要な栄養を確保する。
- 水分摂取が不足しがちなため、こまめに声かけを行い、脱水を予防する。
- 食事中の集中力が続かないため、落ち着いた環境で食事できるように配慮する。
- 嚥下機能が低下しているため、とろみをつけた飲み物を提供し、安全に摂取できるよう支援する。
- 食事の際にスプーン操作が困難であるため、持ちやすい福祉用具を導入し、自立支援を行う。
- 偏食が見られるため、好みに合わせた献立を工夫し、栄養バランスを整える。
- 体重減少があるため、定期的に体重測定を行い、栄養状態を確認する。
- 食事中にむせが見られるため、少量ずつ摂取するよう支援する。
- 嚥下体操を食前に行い、誤嚥リスクを軽減する。
- 食欲不振が強い場合は、少量多回の食事を取り入れ、無理なく摂取できるよう支援する。
- 食事中に疲れやすいため、休憩を挟みながらゆっくり摂取できるようにする。
- 本人の嗜好を尊重し、楽しみながら食事できるよう工夫する。
- 家族とも食事を共にできる機会を増やし、生活意欲を高める。
認知症・行動心理症状
- 徘徊傾向があるため、居室や玄関の環境を工夫し、安全を確保する。
- 不安や焦燥感が強い場合は、傾聴を行い、安心できる環境を整える。
- 昼夜逆転が見られるため、日中の活動量を増やし、夜間の安眠につなげる。
- 記憶障害により混乱が見られるため、予定をカレンダーやホワイトボードに書き出して支援する。
- 食事や排泄を拒否する場合には、本人の意思を尊重しながら根気強く声かけを行う。
- 怒りっぽさが目立つため、刺激を避け、穏やかな対応を心がける。
- 同じ質問を繰り返すことが多いため、否定せずに落ち着いた口調で応答する。
- 孤独感を強く感じているため、会話や交流の機会を増やし、安心感を持てるようにする。
- 物盗られ妄想が見られるため、物品の管理を工夫し、家族と情報共有する。
- 入浴や排泄に抵抗がある場合は、好みや習慣を尊重し、安心して受け入れられるよう支援する。
- 認知症による焦燥感を和らげるため、音楽療法やレクリエーションを取り入れる。
- 突発的な興奮が見られる場合は、静かな環境に移動し、安心できる時間を持てるようにする。
- 日課を習慣化させることで、混乱を減らし、安定した生活が送れるよう支援する。
- 記憶障害による不安が強いため、家族写真や馴染みの品を身近に置き、安心感を得られるようにする。
- 家族との交流時間を増やし、本人が安心できる環境を維持する。
社会参加・生活意欲
- デイサービスを定期的に利用し、社会交流を通じて生活意欲を維持できるよう支援する。
- 本人の趣味活動(編み物や園芸など)を続けられるように環境を整える。
- 季節の行事や地域活動に参加し、生活の楽しみを持てるように支援する。
- 短時間の外出を取り入れ、社会とのつながりを保てるようにする。
- 家族と一緒に買い物や食事に出かけられるよう、外出支援を行う。
- 日常の役割を持てるように、簡単な家事(洗濯物たたみ等)を取り入れる。
- 地域の交流会やサロン活動に参加し、孤立を防ぐ。
- 自分でできる範囲の作業を増やし、達成感を持てるように支援する。
- 定期的な会話や交流を通じて、生活に張り合いを持たせる。
- 本人の希望を尊重し、自立した生活を続けながら生きがいを感じられるように支援する。
まとめ|要介護3のケアプラン文例は「安全確保」と「自立支援」の両立がカギ
要介護3は、日常生活の多くで介助が必要となる一方、自立できる部分も残されています。ケアプラン作成では「できることを活かしつつ、安全を確保する」ことが重要です。
本記事で紹介した 100のケアプラン文例 は、居宅介護支援や施設介護の現場ですぐに使える内容になっています。利用者一人ひとりの生活背景に合わせて調整し、質の高いケアプラン作成に役立ててください。















