老健施設のケアマネと支援相談員の線引きとは?役割の違いと連携のポイントを解説
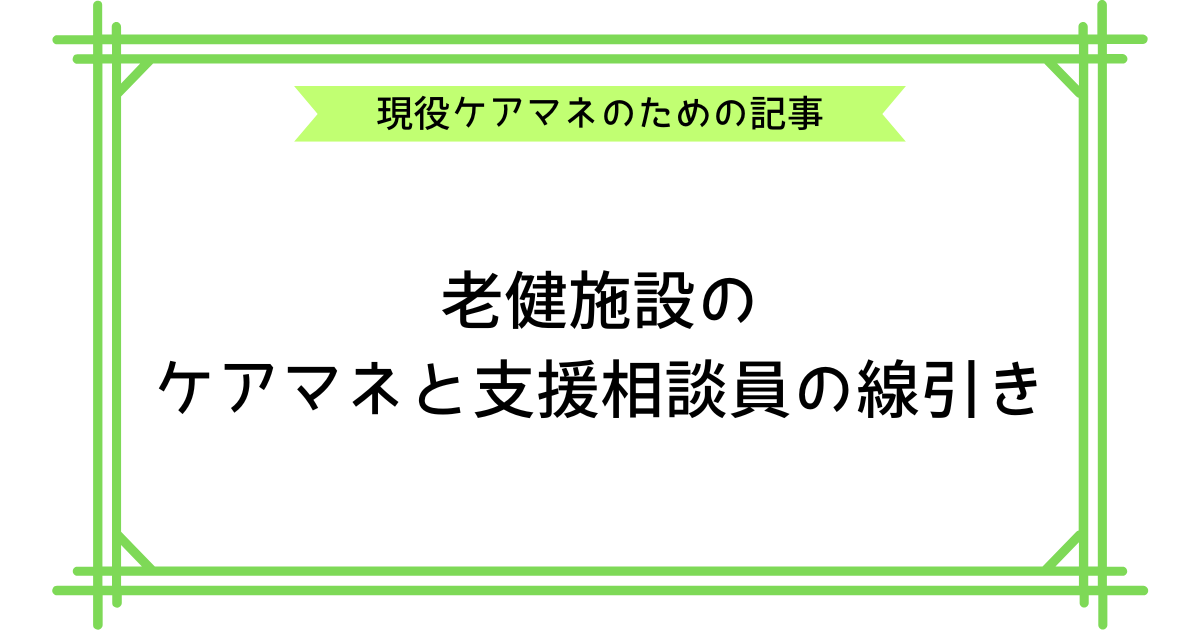
介護老人保健施設(老健)では、「ケアマネ」と「支援相談員」がそれぞれの立場で入所者を支援しています。
しかし、現場では「どこまでがケアマネの仕事?」「支援相談員がやってもいい範囲は?」といった線引きに迷うことも多いのではないでしょうか。
この記事では、老健施設におけるケアマネと支援相談員の役割の違い、業務範囲の線引き、そしてスムーズな連携方法について詳しく解説します。
そもそも老健(介護老人保健施設)とは
老健は、病院と在宅の中間に位置する「在宅復帰を目的としたリハビリ施設」です。
医師・看護師・リハ職・ケアマネ・支援相談員など、多職種が連携して利用者の生活を支えます。
主な役割は次の通りです。
・医療的管理のもとでリハビリを行う
・在宅復帰を目指した介護・生活支援を提供
・在宅サービスや家族への引継ぎ支援
この中で、ケアマネと支援相談員は特に「入退所支援」「生活支援」「家族対応」で関わることが多く、役割が重なりやすい職種です。
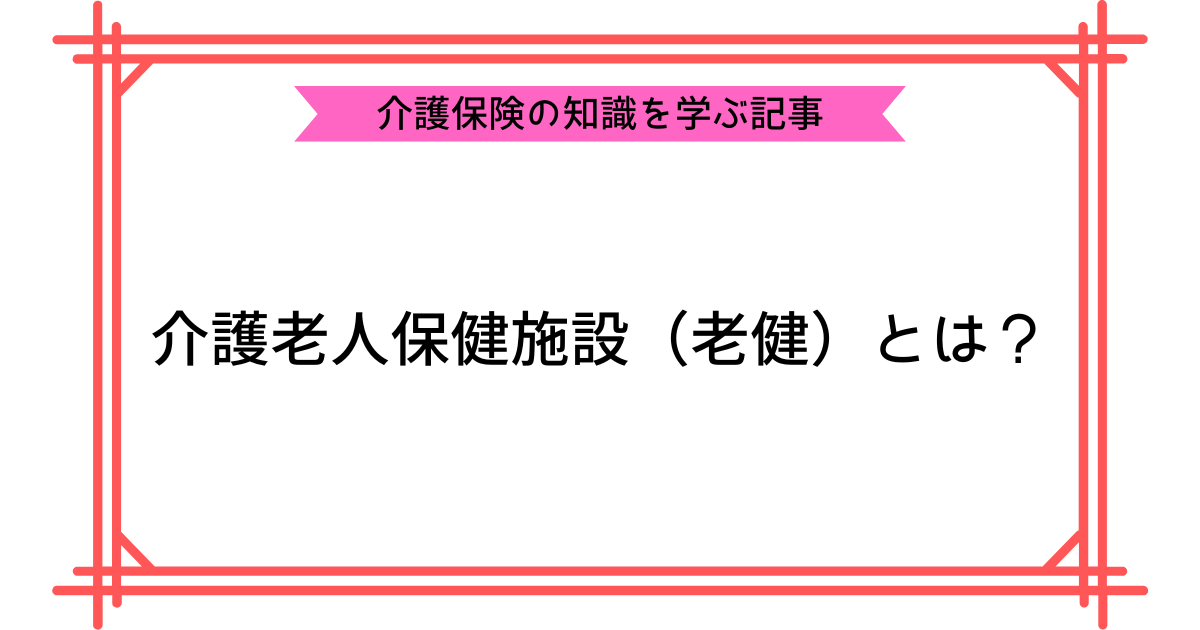
老健ケアマネの役割と業務内容
老健施設のケアマネは、「施設サービス計画(ケアプラン)」を作成する専門職です。
介護保険法に基づき、入所者一人ひとりの状態や目標に合わせて支援内容を調整します。
主な業務内容は以下の通りです。
・アセスメント(利用者の心身・生活状況の把握)
・施設サービス計画書(第1〜3表)の作成
・サービス担当者会議の開催・記録
・モニタリング・再アセスメント
・在宅復帰支援のための目標設定・調整
・退所後の在宅支援事業所との連携
ケアマネは、チームの中心として「計画の立案・評価・調整」を担う役割を持っています。
そのため、記録や会議などの文書業務が多く、利用者や家族と深く関わりながら全体の方向性を管理します。
支援相談員の役割と業務内容
支援相談員は、老健施設における利用者・家族との相談窓口であり、地域や関係機関との調整役も担います。
入所前から退所後までの「利用全体の流れ」を支えるポジションです。
主な業務内容は以下の通りです。
・入所相談、見学対応、入所調整
・入所時の契約・説明・家族対応
・退所支援(在宅・他施設への連絡・調整)
・行政・医療機関・ケアマネとの連絡窓口
・苦情対応や利用者の生活相談
・地域連携・広報活動
つまり支援相談員は、利用者や家族と施設をつなぐ「相談窓口担当」です。
生活面や心理面の相談、入退所調整など、ケアマネよりも広い範囲で人間関係や環境面の調整を担います。
ケアマネと支援相談員の線引き(業務範囲の違い)
現場で混同されやすい業務を中心に、明確な線引きを整理すると以下のようになります。
| 業務項目 | ケアマネ(介護支援専門員) | 支援相談員 |
|---|---|---|
| アセスメント | 介護保険上の要件に基づき実施(心身・生活状況の把握) | 入所前後の生活背景・家庭環境の聞き取り |
| ケアプラン作成 | 施設サービス計画書(第1〜3表)の作成・見直し | プラン内容を家族に説明・同意取得補助 |
| 会議の開催 | サービス担当者会議を主催 | 会議日程調整・資料配布・記録補助 |
| 入所調整 | 基本的には支援相談員が中心 | 必要に応じてアセスメントの観点から参加 |
| 家族対応 | ケア内容に関する説明・評価報告 | 契約・生活相談・退所支援・苦情対応など広範囲 |
| 在宅復帰支援 | ケアプランの目標設定・リハビリ連携 | 他事業所・家族との退所調整窓口 |
| 地域連携 | サービス調整中心 | 医療・包括・行政など外部連携中心 |
簡単に言えば、
ケアマネ=「計画・評価・制度的な管理」
支援相談員=「人と人をつなぐ実務的な調整」
という違いがあります。
実際の現場で起こりやすい「線引きのあいまいさ」
現場では、利用者や家族からの相談がどちらに届くかで混乱することも少なくありません。
例えば次のようなケースです。
・家族から「退所後の在宅サービスはどうなるか」と相談された
・「〇〇さんのデイサービス利用を検討したい」と要望があった
・「リハビリ内容をもう少し増やしてほしい」との希望を受けた
これらの対応は、
・支援相談員が一次対応(内容を把握)
・ケアマネが計画調整・サービス見直しを実施
という流れが基本です。
つまり、支援相談員が「窓口対応」し、ケアマネが「計画に反映させる」ことが正しい連携の形です。
ケアマネと支援相談員が連携するためのポイント
- 業務分担を明文化する
施設内で「誰がどこまで対応するか」を明確にし、マニュアルや役割表を作成しておくことが大切です。 - 情報共有をこまめに行う
家族対応や退所支援など、両者が関わる業務は必ず申し送り・共有ノートで記録を残します。 - 利用者・家族への説明を一元化する
ケアマネと相談員が別々に説明すると混乱を招くため、内容を整理して伝えます。 - 「制度対応」と「生活支援」を分けて考える
ケアマネは介護保険制度上の手続き、支援相談員は生活・心理・地域連携を担当と整理しておくと、トラブルが減ります。
線引きが曖昧なまま起こりやすいトラブル例
・家族が「誰に相談すればいいのかわからない」と混乱する
・同じ内容を二重に説明してしまい、信頼を失う
・退所調整時にケアマネと相談員の意見が食い違う
・担当責任の所在が不明確になり、苦情につながる
これらの多くは、役割の共有不足と情報伝達のズレが原因です。
定期的に職種間カンファレンスを行い、情報のすり合わせを行うことで防ぐことができます。
まとめ
老健施設では、ケアマネと支援相談員の役割は明確に異なりますが、目的は共通しています。
どちらも「利用者の在宅復帰と生活の安定」を支えるために存在しており、役割を分けつつも連携して動くことが求められます。
線引きを意識することは大切ですが、最終的に大切なのは「情報の共有」と「チームとしての一体感」です。
お互いの専門性を尊重し、利用者・家族にとって分かりやすい支援体制をつくることが、質の高い老健ケアにつながります。















